軽トラのラジオをつけると
――七色のカンバスに、裸の黒人が、無数の円を塗っている。無数の円は、しだいに模様を呈し始める。雨が降り出すと、黒人はしだいに、猫になってゆく。カンバスはなにになってゆくか?……
これに賀谷が答えようとしたので、三人はあわてて賀谷の口をふさいだ。賀谷はハッと我に返り、運転に疲れ過ぎていたと反省した。
賀谷のみならずみんな座り続けのために疲労困憊していた。ここらでいったん「尻休め」しようと、偶然前へ停まったクリーニング屋の店先に求人広告が貼られていたので、穂野と八代井がその場で就職し、やがて高価なスーツやドレスを持って戻って来た。お尻も回復していたので、またぎゅう詰めになって座席に座った。
走り出した軽トラの中では、みんなぴったりサイズの合ったフォーマルな装いであった。
街道の名前が二つ変わるころ、ガソリンがなくなり、近くにガソリンスタンドはないという標識を読むと、たまたまそこを歩いていたひじょうに小柄な浮浪者へデコ軽トラを譲った。浮浪者は女子たちの着ているドレスもくれなければ譲り受けないと言ったので、四人は晴れ着も譲った。
歩いていると街道が運送業者の職場にさしかかり、にわかに騒がしくなったので道を逸れて住宅街に入った。家々の間隔がたいへん長く、平屋ばかりで空がたいそう広かった。住宅ではなさそうなドーム型の建物がやたらと目についた。
ひんぱんに《ルパナヨオ》のための看板があったけれど、ルパナヨオというのが「諸事情によるやむなしの放浪者」、あるいは「当地の慣習に疎く、そのことが当人の危険につながり得る人」を意味する語句であることはしばらくわからなかった。それが方言なのか外来語なのかは最後まで不明であった。
看板にいわく、ドーム型の建物は降灰時の避難会館なのだった。気流の関係で周囲一帯は遠方の数十の火山が噴いた灰の集結地となっており、ちょうどそれを読んでいる時に鳴り響いた耳に心地よいメロディは降灰警報のサイレンなのだった。
知明と賀谷が、この時看板を読まなかったら灰は飛んで来なかったのではなかろうかと議論するのはずっと後日のことだった。
四人は最寄りの会館に駆け込んだ。
ドーム型の壁から天井一面に幻想的な空が描かれて、見事な量感の雲の陰から様々の幻獣が覗いていた。画家のサインが壁の下方の隅に書かれていたが、そのミドルネームがたいそう卑猥な駄洒落になる落書きが書き加えられていた。
会館は公園の上に建てられたらしく、一面の芝生は枯れていたけれど噴水の池やブランコやジャングルジムがあって、あちこちに避難中の子どもが取りついていた。
数人の悪童たちが「水飲み場のな――給水タンクにな――下剤を入れて来たぜ」と話しているのを小耳にはさんだ。降灰警報は継続しており、悪童たちは便所に注目していた。時間が経つにつれて避難者が増え、水飲み場を数人が使用したが、そのうちにちらほらと便所に行き始めた。
ショルダーバッグを提げたサラリーマンふうの男性が便所へ駆け込むと、悪童の一人がついて入った。あのおっさんがショルダーバッグを扉の裏に掛けるかどうかだなと、知明と賀谷が話していると間もなく悪童はショルダーバッグを持って出て来た。そのまま仲間たちと降灰のピークに達した薄青い世界へ駆け出て行った。
少し遅れてサラリーマンふうの男性が出て来た。下腹をさすりながら、しばし迷って、しかしショルダーバッグを取り返すべく、これも降灰の薄青い世界に駆け出て行った。
四人は水を飲まないようにして、隅に固まって座っていた。
やがて便所には悲惨な行列が出来た。
ふたたび一帯に響き渡るオルゴールを合図に人々は表へ出た。四人は、ずんぐりしたお爺さんから話を聞いている最中だったが――「近ごろはこの一帯も衰弱してな、なにもかもが廃れてしもうた。昔、都市の資産家どもの実験で、多額の援助を受けた流れ者たちが集まって、なにもない平野から出発して町を作ったんだ。だからルパナヨオには優しいのさ。ともあれ開拓の苦労は並大抵ではなかった。それでも日本一幅の広い国道を敷いてからは大いに栄えたものでな、数々の偉人を近代史に送り出したものだった。今では亜細亜中の灰を集めるだけで、この土地を新たに踏む人間も君たちのようなルパナヨオばかりさ。それでも私はね、」――オルゴールを聞くなりお爺さんをそこに残して外へ駆け出た。
太陽はそれほど傾いていなかったけれど、灰のためにあたかも真っ赤な夕映え空だった。ストライキ中のイミニアンがすなわち忙しく労働しているトラックが通りかかったから、四人はヒッチハイクして乗せてもらった。
けれども賀谷が運転手と剣呑な雰囲気になり、降灰区域を過ぎてすぐに降ろしてもらった。
空は晴れ渡り、ぬぐったような青だった。降灰区域は、入る時には気がつかなかったけれど、出る時にはでかでかとした忠告の看板が目についた。誰しも入る時には気がつかないのではなかろうかと、知明と賀谷が議論するのはずっと後日のことだった。
たいへん幅広な街道を歩いて行った。運搬業者の職場が遠のいて閑散としていた。
やにわに現れたサーフショップと釣具店のあいだに大きな古着屋があったので、学生服もずいぶんボロになっていた四人は立ち止まり、しかしけっきょくは、そのまま通り過ぎた。
垢や土埃は安心すると知明が打ち明けると、みんな賛同した。
フェンスを乗り越えて茂みの中に、なんの用途か円形にアスファルトの敷かれた清潔な箇所があったから、そこに今夜の陣を張った。
ウィンナーだのトウモロコシだの焼いて夕食を済ませ、そのまま焚き火を見つめていた。
賀谷が、我々ルパナヨオがいつかなにかのはずみで帰郷した暁には、もう学業には戻れまいから、そん時ゃみんなで商売でもやろうと言った。
――そうだなァ、地球に火災保険をかける保険屋でもやるか。全焼した場合のみ支払う約束でな、一人くらい契約者は出ると思うぜ。大金持ちの酔狂が一人いりゃァ、俺たちみんななんとか食ってけるんだ。どうだい知明。
賀谷は目をきらきらさせて、頭の中で考えていることの端々に、自分でうなずいていた。
――保険会社を起こす資金源だけどな、著作権だか特許権だかがある今のうちにやらんと。新しい柄を考案するなんてどうだ。閃きだけで億万長者になれる仕組みは、この世にまだ残ってるんだから、それで汗を流さない手はないぜ。
つまりドットとかチェックとかアーガイルとかな、それくらいのレベルの新しい柄を考案してアパレル業界に売るんだ――そうだなあ模様は瓢藤に考えさせよう。数学の天才だから柄にも強そうだ。なあ知明、いい案だろう……?
翌朝、西へ向かって歩いていると汚い手書きの看板が立っていた。苦心して読んでみるに、今しがた歩いて来た道はかならずなにか物を落とす道である、と書かれてあった。
みんな持ち物をまさぐったけれどなにをなくした気配もなかった。かならずなにか物を落とす上に落とした物を忘れるのだろうか? 先達が落として忘れた物がなにか落ちていたわけでもなかったが。
前方にじっと目を凝らすと、ずいぶん先にも同じ看板があるらしい。四人は持ち物を大事に抱えて歩いた。けっきょく看板は五つあり、通過し終えた四人は毎度なにを落とした様子もなく、ふり返って確認する限りでもなにか落ちている様子はなかった。
ネオイミニズムに耽って一切の文明の利器を排しつつ歩いていたけれど、ある時知明が衝動的にタクシーを停めた。他の三人もまた同じ衝動の内部にあったので知明が動かなくとも誰かが同じタクシーを停めていたはずだとは後日判明したことであった。
然らばその場合、最後に動いたはずなのは誰で、世の発明者は誰を押しのけて発明者になり、人類はなにを押しのけてここまで来、世界はなにを押しのけて存在し、物の限度はなにを押しのけて斯く在るのかと議論するのはさらに後日の明け方の夢であった。
停まったタクシーからドライバーが降り、後部座席の扉を開いて女子たちと賀谷を乗せ、知明に助手席の扉を開けた。客が乗り込むと丁寧に閉め、後ろから回って運転席へ戻るそのあいだに知明はシフトレバーのとなりへ束にして留めてある紙幣を下から数枚引っこ抜いた。運転席に座ったドライバーにすべて渡して長距離運転をお願いするとひじょうに喜んで発車した。
よさそうな枝道があったところで《棗椰子街道》を離れ、どことも知れない鄙びた土地へ向かってもらった。
途中から道がずっと満開な蔓薔薇の茂るアーチに囲まれていると思うと、急に途切れた。さてはどなたか皇族様のおん地所であらっしゃったのかしらとドライバーは独りごちた。
山道が切れて町に出、また山道に入り、町に出、山道に入りをくり返すうちに、もうじき一種の突き当たりに行き着きますよとドライバーが言った。
彼は常田さんといって、よくしゃべる人で、ここまで来るあいだに四人とはすっかり打ち解けていた。かなり開けっぴろげな身の上話や、仕事柄遭遇する珍妙な出来事を問わず語りにしゃべりつつ、時おりラジオをいじくっていたと思うととつぜん音量を上げた。
大音量のサイケデリックトランスミュージックに合わせて、一同、車が浮くほど跳ねながら、制限速度を大幅に超えて飛ばして行った。
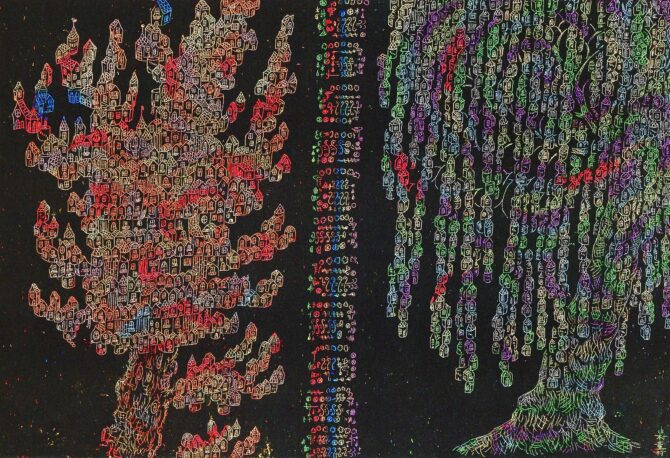
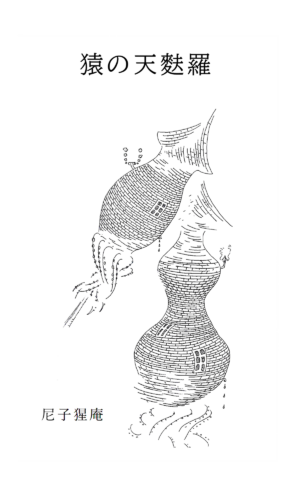











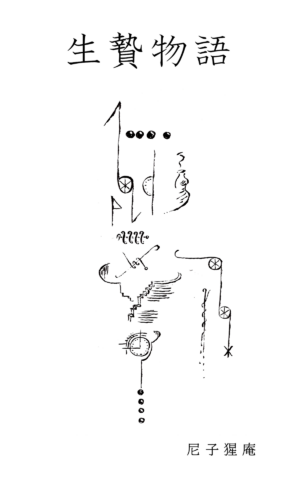










"猿の天麩羅 5"へのコメント 0件