眠りに落ちかけるたび、水平に流れて来た丸太が滝に至り垂直の龍と変ずるに際して発するゴリリの響きが、耳の底というよりも頭の深部から鳴る。輾転反側の布団を遂にめくって沈思す、残すところはあとわずか、余は、暗夜に灯火失い、なまなかにもせよ蘇生せしめられた感受性の、震えおののき、喚き散らすを放擲し、どこかに存すると願われてやまぬ、心頭滅却せられた究極理性もてすべてにともかく納得し、ありのままを自ら望み直し、果てしない独善的の主観のうちに、しか信ずる世界のかたちへ改竄するを急がねばならぬ。
今から天道是か非かなんぞ言うてはおれぬ。天は自ら助くる者を助く、身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ、断じて行えば鬼神も之を避く、何でもいいが、そういう勇ましい言語印象をのべつ幕無しくり返し、固く固く縫いつけん。薬缶道心の冷めやすさも追っつかぬ間断なさで初発心時便成正覚々々々々々々々々、だらだら刻み込む自己催眠をば開始する。
煙草やら酒やら持ち込んで、余が幼い時分に逝去した、もうほぼ記憶にもない祖父が普請道楽に建てた離れの茶寮に籠もり、掛け軸やら茶器やら値打ちもわからぬ古美術に囲まれた明窓浄机に千思万考。
昔々、祖父の祖父くらいに医者がいて、自身不治の病にかかり、間がな隙がなモルヒネを打ちながらほくほく死んで行ったと聞く、真偽は不明なれど、その霊薬の残りあらばと時おり虚しく探したりなんぞしながら結跏趺坐して坐禅瞑想。
無念無想の地獄おだやかならず、気の乱れに大なるめまい覚えて逃れ、けっきょく脂にえがき氷にちりばむ言語迷妄へと追いやられて、しかし甚だ不完全な翻訳法である言語を用いて諸相を見んとする不毛でも、愚も愚を守れば愚ならずで、馬鹿と鋏は使いよう、愚者も一得とやら、長者の万灯より貧者の一灯とやら、やれるだけやらっしゃれ、どのみち救いのない末法に何をぬかそうが罪もあらざるなり安心々々と、空虚・卑屈の頼もしさ。
ここに至って思想の貴賤は死との折り合いの如何ですべてかたがつく。ほんらい死にゆく者とまだ生きる者の真理は違う。生きたい者と嫌々生きざるを得ぬ者の真理も違う。死にたい者と嫌々死なざるを得ぬ者の真理も違う。しかしここに至って違いなんぞは何でもない。これまで余が身内に流入し堆積して来た一切の観念は死を巧妙に度外視する卑賤の思想であった。そこにじつは奥ゆかしい死との語らいが秘められていたとしても我が凡才にはわからぬ、もはや無用の長物なり。せめて供養に思念の香を立つる願以此功徳。
信仰の貴賤も然り。花盗人は風流のうちと、あちこち空き巣に入っては、古今東西ちゃんぽんの、玉石混交極まりない教義の煩瑣な断片が山となって門に刻まれたるは盲亀の浮木、道に散りばめられたるは優曇華の花、人生字を識るは憂患の始めとやらのどん詰まり、げに不潔なスラムを形成しておるが、これも無用となりき願以此功徳。
ふたたびモルヒネを探して、畳を上げて床板を外し、泥まみれになって掘るうちに確かな手ごたえ。しかし地下から出土したのはそう言えば聞いたことがあった桃山時代のものとかいう驚くべき古豪の梅干しであった。わりに古からぬ箱をぶち割れば、中におざるはあまりにとしふりて魂も宿り尽くし、化け果てたような壺の沈黙。固く結んである縄をぶち切って蓋を開ければ、果たせるかな淀みに淀んだ薄闇の底に石のようなものが重なっていた。相当の価値を呈するやもしれぬ先祖伝来の家宝であった。ちょうど催していたことであるから小便漬けにしておいて元通り埋めておく。我がこんじきの体液のぬくもりにさぞかし大地があたたまるであろう。しばし排尿後の下腹部の灼熱に悶え、完全に治まりはせぬまでもせめて弱まるのを待つ。
世界中の誰も余を知らぬことが余を最大の人物にする。郷内に余を知らぬ者のないことが余を最大の人物にする。いずれ郷外の者が余を知る未来が来るであろうか、一切の過去を暴く技術が発明されて? すべての死者の証言が集められ、往時の様子が黄泉の川面に映されて? そんな未来が来るならば今この時も見られているわけだ。しかし見ておる未来の有象無象よ、たといどんな大人物でもすべて余より年下だ。然れば余について偉そうに何を宣うこともここに禁ず。未来に生きる若輩どもは左様心得て口を閉ざせ。同時に人類の年齢で勘定するならば、過去のすべての偉人も余より年下だ。誰の教えに反しようとしゃらくさいばかりだ。
時至りてこの茶寮をば楽虚洞と名づく。今朝のらっきょうの香が舌から取れぬので。然れば余は楽虚洞主人と号せらるべきなり。
楽虚洞の名を捨つ。さあ鳥のまさに死なんとするその鳴くや哀し。しかし、もうほろほろと心の自然な響きに聞き入っておりたいけれども時間がない。人のまさに死なんとするその言や善し。しかし間に合わなんだ。余がまだ気づかぬ、しか望むものを、急ぎ発明しなければならぬ。
生存それ自体への欲望はさておいて、死欲、確かにそのすがたを余は見尽くした。その息吹を肺腑の破裂せんばかりに嗅がされた。しかしこいつはいつも「今この瞬間の決行」を要求するばかりで、奉祀への絶対的待機という状況には一向に役立たなんだ。(待機ほど生命力の要るものはない。)(待機ほど救済せられ得ぬものはない。)ほんらい強力な味方であるはずが、たいへんな邪魔立てをすらして来た。今すぐに死ねぬのならば死にとうないとまで、それ(死欲)はいつだって裏切るのであった。こんなものは検討にも値せぬ、考えて損した、捨てん捨てん。
しょせんどのように転ぼうが落つれば同じ谷川の水、しかし転ぶまでの暇つぶしがいるのだ。文明が。自己催眠・自家洗脳に励むよりないのだ、よし失敗してももう一度あのぼんやりした夢遊病的の境地に帰るための起爆剤にはなるであろう。巧遅は拙速に如かず、早くふたたびぼんやりせんけりゃならぬ。できぬなら理想的なる真実を一つ自ら創造し、それに帰依するのほかはない。
つまり死が生のオルガスムスであるという事実のほかに真理は一つとしてないという真理である。この思いつきは生まれて来る前の、魂が霊界にあった時分からの想起だ。今しもここいらに併存している幽冥界からの。創造したのではなく思い出したのだ。
さて死がオルガスムスであるために、生と謂うは、余すなわち魂と、妻すなわち肉体との布団の中の暗中模索なのであった。
それなので生に凝る(=苦しむ)ほど死は甘美なものとなる。苦しみのあまり魂の奇形となった場合はその限りにあらず。
死の訪れを、我慢に我慢を重ねて引き延ばせば引き延ばすほど甘美なものとなる。いたずらに引き延ばし過ぎて感覚の潮が引いた頃合いに当たればその限りにあらず。
認識を太うしてじっくり味わい、気分を高め、感覚を練磨するほど甘美なものとなる。あまり耽って感覚の満ち干の幅を狭めるような鈍麻があればその限りにあらず。あちこちの認識に無節操に手をつけて病気をもらい、膿血の混じるような場合も然り。
死を忌避し蔑視し無視し続けたインポテンツには不意討ちの不快感しかともなわぬ。穢れた夢精のごとく去る。
性急に突入してもまたたいそう淡白なことだ。もったいなきことこの上なし。
死の前には万人が処女であり、死は生者の誰しもに破瓜であるから甘美では原則あり得ず、然るがゆえに前以てよくよく自ら習練を積むことが肝要なり。なでさするくらいでは足らず、代替物を用いて膜を破き切っておらねばならぬ。純潔の窮屈を広げ切っておらねばならぬ。その点、我が精神疾患の、のべつ幕無しに反復された自覚症状や時おりの大発作は文句なしの嫁入り道具、たびたびの気絶に黒光りした我が魂のホトは、いつ襲い来るやもしれない至高の強姦魔を前に何の恐れもなし。
左様の思惟に充血する脳天あたかも勃起した頭部のごとし、なかなか鎮静せぬさまあたかも持続勃起症のごとし、丸太の激突したドタマから余は勢いよく射精するであろう、大気中の諸精霊は大いに孕めかし!
つひにゆく道とはかねて聞きしかど
きのふけふとは思はざりしを
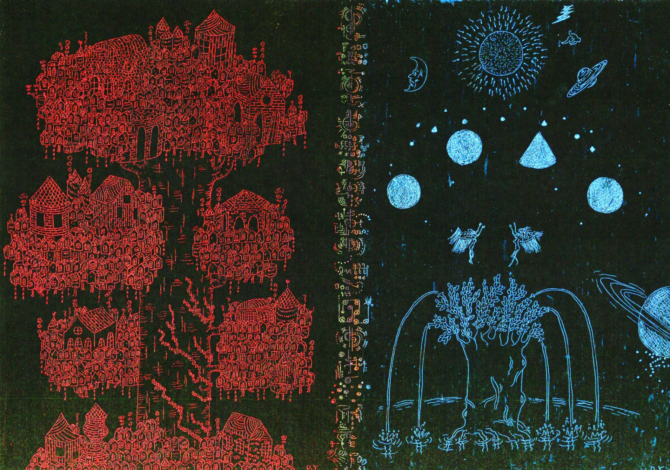
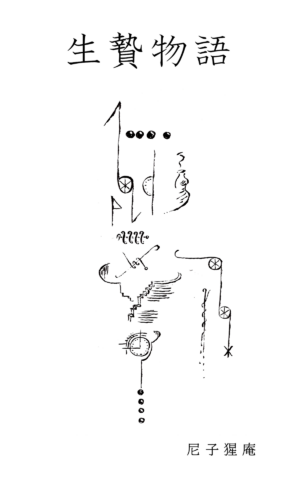











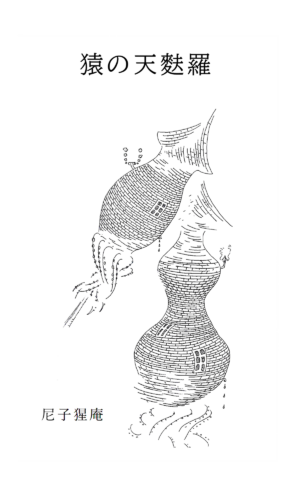










"生贄物語 6(完)"へのコメント 0件