一箱十二粒入りのチョコレート。私は残り少ない人生をこれに委ねることにした。
決まりごとは単純だ。以後、私が一度蔑まれる度に一粒チョコレートを食べる。なんでも構わない、汚物を見るような目で見られたり、辛辣な言葉をかけられたり、あるいはすれ違いざまにわざと肩にぶつかってきた、とかでもいい。とにかく私がこれまでに投げつけられてきた侮辱や悪意や敵意のようなものが再び向けられたなら、それが私の命を減らすということだ。
逆に、もし万が一――ほんとうに万が一の話だけれども――私に優しい言葉をかけたり親切にする人がいた場合はチョコレートを一粒その人にあげる。
そうして、最後のチョコレートがなくなったとき、私は自ら命を絶つ。
そう決めたのは十二月初めのある寒い夜のことだった。
私は期間限定パッケージと印刷された洒落た箱から透明フィルムを剥がすと、最初の一粒を取り出して口に含んだ。寒さに固くなったチョコレートはごくゆっくりと溶けていく。甘い。
十二月の最初の月曜日、眠りから覚めて布団から這い出て昨夜からコップに注ぎっぱなしだった水道水で喉を湿らせて、次にやったことがチョコレートを食べることだった。もちろん一人暮らしの私は今日まだ人に会っていないし、そもそも昨日このチョコレートを近所のコンビニで買って以降誰とも顔を合わせていない。
なのになぜ私はチョコレートを食べているのか。
私は、たぶん私という人間が好きだった。でも現実の自分の姿が、あり方が、なれの果てが、自分を好きな自分を満足させるようなものでは到底なく、そのことを許せないという気持が折に触れて育っていった。
その、歪んだ自尊心がざわざわと茂っていくのを刈り取る作業が私には必要だった。でも作業は苦痛を伴うものだった。「こんな簡単なことがどうしてできないの?」となじられる度に、「トロトロ歩いてんじゃねえよ」とせかされる度に、「あなたと居るとこっちまで暗くなるわ」と嘆息される度に、そいつは私の胸の中でちくちくとざわめいて皮膚の裏側を引っかき始め、ついには喉元のあたりを突き破って出てきそうになる。
「やめて」と私はそれを抑えこもうとする。「私がいなくなってあげるから、もう勘弁して」
ゆうべ私が決心をして、自宅近くのいつものコンビニに入り、一箱十二粒入りのチョコレートを買ったのは偶然ではなかったということだ。あばた面の店員はぞんざいな手つきでバーコードを読み取り、レジに表示された金額を顎で示す。私が入店してからここまでひとことも喋っていない。
「Suicaで」
私が言うとさらに何も言わず、レジを操作する。
「……っすか」
はっとして顔を上げるが店員はレジに目を落としたままだ。大事なところが聞きとれなかった私が「え?」と声をだすと、彼はレジ横に貼りだされた掲示を黙って指差す。
『レジ袋は有料になりました。一枚三円』
たったそれだけのことを伝えるのに言葉を使うのも億劫なくらい、私は面倒な存在なのだ。知ってたけど。
「いらないです」
私は会計を済ませ、チョコレートの箱をトートバッグに放り込むとコンビニを出た。
そういうわけで私は今こうしてチョコレートを食べている。目が覚めてからあばた面のコンビニ店員の顔ばかりが脳裏に浮かんで、やっぱりあれは一回分に相当するんだと改めて思った。私の命の十二分の一が、そうして呆気なく消えた。
底冷えのする部屋の中で私はのろのろと着替えを始めた。
今日はバイトの日だった。なんのことはない軽作業の仕事だったが、それでも今の私には気が重い。一日働いていればトラブルの十や二十は軽くあるだろう。つまり普通にバイトをやっているだけで、私の命は今日のうちに尽きる公算が大なのである。
その身も蓋もない見通しのせいか、袖を通した肌着の冷たさのせいか、私は大きく身震いした。極寒の洗面所で冷え切った化粧品はまったく意のままにならず、幼児の落書きの方がまだマシだと自信を持って言えるくらいのメイクが完成した。まあいいか、どうせ今日死ぬのだから、と私は頓着せずに身支度を続ける。
駅に着いたとき、バッグの中にチョコレートがあるのをもう一度確認した。実はさっきアパートを出たとき、チョコレートを忘れたことに気づいて取りに戻ったのだ。危ないところだった。これを忘れたら今日一日が台無しになってしまう。バッグの口を閉めながらエスカレーターに乗ろうとした。それがまずかった。
どんっ、と後ろから押された。
Bluetoothイヤホンを着けた若い男が大股で私の横を追い越し、エスカレーターを上っていった。故意に押したというより、追い抜きざまにぶつかったという感じだったが、私はあからさまな悪意を感じた。前のめりによろけた拍子に閉まりかけのバッグの口から期間限定パッケージと印刷されたチョコレートの箱が飛び出す。慌てて手を伸ばすが、それは空しく宙を掻き、箱はエスカレーターのステップに豪快にぶつかって、その中身をぶちまけた。
あああー、と思わず声が出る。
箱がステップの上をもんどりうってチョコレートを吐きながら転がるのをスローモーションのように見ていた。箱を拾い上げると、中にはもう二粒しか残っていない。エスカレーターが終端に到達し、私はステップが吸い込まれていくところに黒い綿埃と一緒になってカラカラと回る九粒のチョコレートを見ながらエスカレーターを降りた。
あんなになってはもう食べられないし人にもあげられない。私は、今日死ぬとはいってもあれを食べられるかどうかはまた別の問題なのだ、ということが分かったのが何だか可笑しかった。
「あなた、大丈夫?」
背後から話しかけられて私はびくっとした。振り返ると、五十絡みの女が私の顔を覗き込んでいる。
「え、大丈夫……です」
どうやらエスカレーターでの一部始終を見ていたらしい。彼女は男が去って行った方角に目をやって言った。
「人にぶつかっといてなんだろうね、謝るどころか振り向きもしなかったわよ」
いかにも正義感丸出しの世話焼きおばさんといった風情だった。バイト先にいる柴崎というおばさんとなんとなく似ていた。もっとも似ているのは見た目だけで、柴崎は世話焼きでも親切でもない。
「あなた、怪我はなかった?」
「いえ、大丈夫です」
私はバイトに遅れそうなので時計を確認しておばさんに礼を言った。頭を下げたときにバッグの中のチョコレートのことを思い出した。まさかの万一が訪れたのだ。
「あ、これいかがですか」
私はチョコレートの箱を取り出すと、最後の二粒のうち一つを差し出した。
「チョコレートです」
そう言って引きつった笑顔を作ろうとしたが、それはただの引きつった能面にしかならなかった。私の顔はとうの昔に感情を表現する機能を喪失していた。おそらくそれが彼女の警戒を惹起したのだろう。おばさんは急に真顔になって、声のトーンを低めた。
「まあっ、落ちたチョコレートなんて食べられるわけないじゃない!」彼女が一気に二メートルくらい身を引いて私から離れたような気がした。「人が心配してるのに、なんて子かしら!」
おばさんは吐き捨てるように言って足早に去っていった。そうじゃないのに。私は口ごもった。あなたが親切だったからあげようとしたのに、とおばさんの背中に念じてみたが何も起きない。それにこれは落ちたチョコレートじゃない。落ちたチョコレートはさっきのエスカレーターの終点で黒い綿埃と一緒にカラカラ踊っている。これは箱に残されたたった二粒のうちのひとつなんだよ、と思うと泣きそうになる。私は私の命の残り半分をくれてやろうとしているのに、そんなもの無価値だと言われている気分になった。
「やっぱりそうなのね」
私は呟くと、おばさんにあげようとしていたチョコレートを口に含んだ。








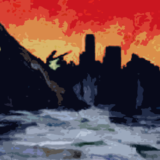

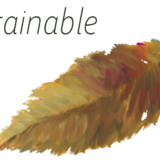



















"CCD(前編)"へのコメント 0件