「ベランダ」
共用通路から戻って、部屋の、厚い金属製の軽量素材の部屋の扉を開けると、ちょうど奥の突き当りに患者用ラジオが乗っている棚が置いてあるのが見える。奥に行くまでの廊下は狭く、片側がキッチンになっていて、水垢のついた流しが大口を開いている。もう片側にはハクション、ティキティキ、はくしょん、ティキティキ、はくしょん、トイレの扉がある。その扉の上下は切り取られていて、外からなかで何をしてるのかすぐ分かるようになっている。自殺防止、あるいはトイレの穴に手あたり次第、衣類、布、トイレットペーパーを詰め込んで意図的に汚物と水をあふれさせてしまう輩防止となっている。それならば各部屋でなく共用トイレにしてしまえばよいのに。キッチン・トイレのドアに挟まれた細い廊下を抜けると、ベッドが置かれている。白く塗装された金属製ベッドのマット、患者が自分で週一回取り換える、糊のきいたシーツ、枕カバー、純白が目に眩しい。部屋の壁は扉と同じ素材、金属でできている。小銭か何かで傷つけた跡は塗りなおされている。横を向くと、今さっき入って来た扉の位置からは死角となっている壁にクローゼットがあって、荷物が入っている。そして窓がある所と思しきところ、窓はないが、窓際と呼ばれるであろう側には小机があり、患者用パソコンが置かれている。古いがきちんと動く。チリチリチリチリ。室温が低いとそんな音が鳴る。……
いつもタコ部屋大ホールの片隅には、設計士の仙人がいる。髪も髭も長く白髪交じりで、眼鏡をかけていて、誰とも口をきいたことがないのだ。自分は、それはそれでいいらしく、タコ部屋ホールのカレンダーの月が替わると、用済みになった前月の紙を取って、それを糊のようなものでつなげて大きな一枚紙にしている。それで設計している。家をだ。僕はそばのテーブルに座って、口から首を絞められたネズミの断末魔みたいなか細い声を絞り出すとともによだれを時々吹きながら(言っとくと僕がだ。僕は病人だからね)、その様子を観察している。まあ、それもある日を境にやめてしまったけれど。この仙人に僕ははじめ尊敬の念すら抱いていたのだ。というのもホールの隅に自分の荷物のすべてを固めて、そこからほとんどその場を動かなかったので、その集中力にぞっこん参ってしまったのだ。当然、飯も配膳してもらっていた。もちろんその中にはカップ入りのヨーグルトもあった。彼はこれをうまく利用した。その利用の仕方、それで僕はもう十分だと思えた。といっても何のことだろうと思うからちょっと前の話でもしようか。……
なにかをじっくり考えたい時、少しの疑問も恐れず自分は今まさに考えているんだって思いたい時は、眼下の中庭を見つめていればいい。気球大の目が舐める。僕の目が僕を含めた景色を舐める。今では本当に気球大ってわけじゃない。そんなものこの船内のどこにも狭すぎてぎちぎちである。だがそういうこと、ぎちぎちの圧迫感ってこと。僕らが感じているのは。眼下の中庭ってのはもちろん、どこにも存在しない。この船のどこに中庭がある? でもそれは心に描くんだ。でも上手く描けても、踵で九十度回れ右して、ベランダを歩き出すのは難しい。気付けば現実に歩き出していて、現実の個室や現実の廊下や現実の大ホールの壁に現実にぶつかり、ぶつかったことも気づかずまだ現実に壁に歩き続けるから。ただし、もしも完璧なベランダを想像できたとしたら、現実には歩いたりしない
でも、ベランダの中でどうあがいてもその横断の果てに地平線は待っていやしない。なぜならベランダとは区切られたそういうものだからだ。せいぜいゆっくり端から端へ三十歩で、歩き始めに背中に触れた鉄柵と同じ、だが確実に反対側のといえる鉄柵に到着するだろう。そう、いくら作り物でも、ベランダはこの船から出られないのと同じく、すべて鉄柵で覆われている。閉鎖病棟と呼べよう
そしたらとにかく鉄柵の向こうを見つめればいい。ただし、上はなるべく見ないこと。そこにも無数に横切る鉄柵があって、その向こうの抜けるような嘘の空を見るのは吐き気を催すから。引力が逆さまに作用して、嘘っぱちの空に落っこちそうになって、頭上の柵に体が押し付けられそうな気分になるから。本物の空はやっぱり見えない。薬のせいだ。本物の空に該当する部分は鏡。口を開けて見上げる僕らが映っている。でもなにかを考えたければそこに来ればいい。そこは鉄柵に覆われたベランダなんだ。僕は時折、本当は猫が来てくれれば楽しいと思ってる。猫なら鉄柵の間をすり抜けられるし、かわいいし……。はっくしょん、はくしょん。僕は猫アレルギーなんだ。共同猫ってやつだな
けれども僕は朝食の時間が終わったあと、すぐにはベランダに出なかった。最近の食事の時間の僕の席は、タコ部屋大ホールの、開け放たれた共同夢であるベランダのサッシのすぐそばだったので、共同夢台風がついさっき通り過ぎたばかりで、まだわずかに蒸すような暑さがそこに残ったままなのを、肌で感じとっていた。だからベランダはまだ雨に濡れていると思ったから出なかった。僕の他にも、ベランダに出た入院患者はいなかった。僕らはこのベランダを病人用ベランダとは言わない。言うだけむなしくなるのがおちだ。とにかくベランダは無人のはずだった
いや、いや、一人だけいた。僕が食後の温かいお茶を個室で飲んでいた時、中年特有のがっしりした、小さな佐合(さわい)の背中が僕らの共同夢サッシを通り抜けていったのを僕は見ていた気がした
その巨大な顔を密着させんとばかりに相手に近づけて話しかける癖のある佐合は、今朝の、僕が呼ぶところの朝食前の「なんでもない時間」、いつもとはまるっきり別人のようにおとなしかった。タコ部屋大ホールの、佐合のいるところだけ、まるで空気がへこんでしまっているかのようだった。酸素さえも薄そうだった。普段のすぐかっとなる騒がしさとは程遠く、顔も小さく見えた。だから僕は少しのあいだ佐合を遠くの席から見つめていたのだった。その時の佐合の姿はどこか、忘れ去られた空っぽの犬小屋を連想させた。狂犬病ワクチンを打ってもらえず、人を信用せず、通りすがりの幼児を噛んでしまって保健所に連れてかれてしまった居住者のいた経緯のある、いまは空っぽの犬小屋。でもなぜだか朝食のあとでは、佐合のしょんぼりした様子のことをすっかり忘れてしまっていたので、彼がベランダに出ていったことも、おぼろげな記憶として留められたていどだった
ベランダは僕にとって大事な場所だった。ぶらぶらカウガールのある、タコ部屋大ホールの、行ったことがない看護師たちのテリトリへ続く出入口は大きな伸縮性の鉄柵で覆われていて、その圧倒的な閉塞感を催す病棟内では、たまに息が苦しくなるのだった。僕らのベランダは夜間以外解放されていたが、月は見えなかった。星空も見えなかった。なぜならさっきも言ったけれど空はないから。そこはただのベランダだったから。毎朝定時を過ぎてもサッシの鍵が閉まったままだと、みんな頭が息苦しくなった。そのたび、看護師か介護士を呼び止めるのだった
「今日ハべらんだハ開放サレナイノデスカ?」と。……
そのたび僕らはいつも、またやってしまったと思うのだった。これでは僕らはまるで声をあげて駄々をこねて泣いているみたいじゃないかと、慌てて口をつぐむのだった。だが僕らは、僕はなぜだかそれを抑えることがどうしてもできないのだった。そしてそんな時は決まって、屈辱的なことに医師の回診があり、具合を心配されるのだった。にやにや笑いを向けられながら。ティキティキ。そしてようやくベランダを開放する薬が貰えるのだ
だからといって僕はベランダよりさらに先の外に出たいというわけでもなかった。外に出ることはできなかった。外に出るという想像力が足りなかった、あるいは足りなくさせられていた。そしてやっぱり一番というべきかベランダというものこそが、結局のところ鉄柵に囲われた、でも外に出られる唯一の場所なのであった
だがベランダは一人になりたい時、今、自分は一人なんだと錯覚でもいいから思いたい時にはもってこいの場所だった。もしも一人でベランダの壁の出っ張りに腰掛けていて、誰かが僕の隣に僕と同じポーズで腰掛けて――なぜ病人は同じ姿勢を取りたがるのだろう? 左右対称、相手と同じ姿勢、真似。安心するのか――顔を覗き込んできたりし始めても、気づかない振りをしていれば、そのうち立ち去ってくれる、そういう場所なんだ(猫がいればもっといいと僕は再び思う。はくしょん)
この船内で完璧に一人になれるのはそこしかないのだ。個室にいて、別段、うるさく話し掛けてくる者もほとんどいないのだが、両隣の会話は聴こえてくるし、一人部屋と言っても、それでも病棟内はどこへ行っても誰かがいる気がする。時々、僕はそれが嫌になる
この病棟には二十年も三十年も暮らしている入院患者もざらではないことを、日々のなかで僕は知ることとなった。学校から上がるとそれからはずっとそこにいて、生活している者がいることを、本人たちに直接聞いたのではないが、折々の様子で自然と知った
彼らの半数はタコ部屋第ホールでぶらぶらカウガールを見て過ごすことが多かった
僕はあまりテレビを見るために行くことは少なく、周囲をこっそり観察するほうが好きなのだったが、彼らは本当に日がな一日中、ぶらぶらカウガールを見ている。そして彼らはそんな僕よりも案外、外の世界に近い。なぜなら彼らの見ているぶらぶらカウガールは、個室にある病人用テレビよりも、あなたたちが普段見ているテレビに、近かったから。本来ならば病人用テレビ放送など、あってはならないのだ。だがそれではあまりに刺激が強すぎる。だが病人もテレビが見たい。その折衷案が個室にのみ病人用のものを取り付けるということ。だからみんな、部屋の低刺激には飽きてタコ部屋大ホールに来ているのだろう
病人向けドラマ……
病人向けニュース……
病人向けコマーシャル……
でも大ホールでは外で見られているのとほとんど同じ放送が流れている。あなたが見ているテレビと同じ。閉鎖された場所で、外に出られない病人の僕らが、あなたがご飯を食べたり、仕事へ行く前に新聞を読んだり、帰宅していつものルーティーンで、癖で、リモコンの電源ボタンを押して「ながら見」しているようなテレビと同じものを、真剣に見つめている。これって不思議だと思わないか
時代劇。スポーツ中継。外の様々なニュース。もしくは『期間(・・)限定(・・)!・秋のきのこ(・・・)のデミグラス・ハンバーグセット!』というようなコマーシャル。夜の九時には消灯だが、それまでは彼らはみんなで、広々とした床に各々、寝そべったり胡坐をかいたり、壁に寄りかかったりして、自分のポジションをわずかにも動かず陣取って、船の揺れの影響を受けないつくりの、天井からぶら下がった大きなぶらぶらカウガールの画面を見て過ごす
期間限定・秋のきのこのデミグラス・ハンバーグについてもう少し語ろうか。前にも語ったから、それともやめておこうか。きのこといえば秋だが、この時は夏の終わりであったと思う。暦の上、カレンダーではそうだ。でも寒い海域を航行していたかもしれない。病棟内はエアコンが静かに唸っていたし、季節を感じるのは難しい。ベランダに出れば話は別だが、鉄柵の向こうの景色はどうも嘘っぽい。期間限定を、そのままの意味と捉えるのもここでは難しい。ここでは期間という言葉はないに等しく、限定自体されてもいない。あるいは期間も限定も永遠に完璧なのだ。つまりもっと他のことが限定されているのだが、それにもだんだんと何も感じなくなってくる。だからこそ、僕らは期間限定をいつまでも掴み取れずに、それらが萎縮した頭の中を通過していくのをゆっくりと感じるだけなのだ。ああそうだ、そういったデミグラスハンバーグを食べたければ、一か八かここの管理栄養士さんにでも頼んでみればいい。食事の時間、まれではあったが病院の献立を決めている栄養士のおばさんがやってくる。何をしに来ているのかは定かではない。もしかしたら病人好きなのかも。慈愛。うんきっとそうだ。そうでなければもっとへんてこりんな、不親切な献立表を組むだろうからね。古参の患者の中でも活気のある者たちはその姿を認めると、「栄養士さん、毎週フライドポテトにして!」「茶碗蒸し、食べたい!」「グラタン。グラタンをお願いしまあす!」と声をあげて嘆願する。それが通ることははたしてなかったように思えるが。とにかく、テレビを見て、期間限定・秋のきのこのデミグラス・ハンバーグセットを食べたがる患者が実際どれだけいるのかは知らない。……
佐合という患者と、佐合メモなるもののことを知ったのはここで目覚めて、大ホールに出るようになって間もない頃のことだった。ここへやってきた僕に、最初に一番長く話しかけてきたのが佐合だった。彼は僕に、自宅の電話番号と住所を教えてくれといった。この人は一体全体、何を言うんだろうと思ったが、とっさに僕は考えを巡らし、教えなかった。今は思い出せない、といってはぐらかした。もしこのような場所でなかったら、そんなやり方は不自然極まりなかったろうが、ここはそれがまかり通る場所だったので(もちろん一か八かやってみてわかったことだったが)、僕は彼を上手くかわすことができた。「おう、思い出したら教えてくれよな」とぼろぼろの折りたみ式の自作のメモ帳に僕の名前だけ書き留めてあとは去っていった。あとになって看護師から、佐合はメモ魔だから注意するようにと教えられた
僕のあとに新しい入院患者が来た時も、電話番号と住所を尋ねていたのを見掛けたことがあった。見事ぼろぼろのメモ帳に新たなデータを収めることに成功したこともあったし、偶然看護師が通りかかり、追い払われたこともあった。「あーあ、なんだよう、こっちがなにしたってんだよう」佐合はそのたびにぶつぶついいながら、赤い顔をむっつりさせてカウガールを見に去っていった。彼が廊下を行く姿は、まるで顔が歩いているみたいだな、と僕は思った。佐合は背が低く、顔がとにかく大きかった。はたして彼が今後、まあ僕も含めて、外の世界に出られるかはわからないが、住所や電話番号がもとで、退院したあとでトラブルが起こることが多々ありそうだと思った。でも佐合が外に出たがっているのかはわからなかった。ここにいるほかの患者たちもそうだ。彼らはどうしたいのだろうか。……
周囲を見ると、なんだか僕らは廃墟の窓辺に置き去りにされた、白い腹の魚の浮いている水槽みたいなものだなと思えた。そこへ時折誰かがやってきて、蒸発した分の水を補給してくれているだけなのかもしれないと思わせた。その誰かというのは、あるいはそれこそ低刺激な病人用テレビ放送であって、あるいは病人用本であって、睡眠薬であって、下剤であって、あるいは食事であって、その他薬剤であって、診断ミスであって、患者同士だけでなく患者と看護師同士の金の貸し借りの利率の素早い計算であったり、もしかしたらあるいは期間限定・秋のきのこのデミグラスに刺激されるぼんやりとした枯渇であった。もっともこの中で病人用本を選ぶのは、ほとんど誰もいなかったが
古い記憶や淀んだ意識はやがて、注ぎ足された水で薄まりはするが、必ずわずかには維持され続ける。なかには均等に薄まらずに、原液が部分々々に残ったり薄まりすぎたり、それがために奇妙な影を思考や外見や行動に落としている者もいるのだが。とにかくそんな印象を僕はもっていた
閉鎖病棟には常に、歯磨き粉と大便が合わさった匂いが充満している
僕はそれが別に嫌ではなかった。月に二、三度の強制麻酔でいつの間にか眠らされて目が覚めて改めて廊下に出た時などにしか、臭いなとは感じなかった。すぐに鼻は慣れるのだった。廊下で年寄りが大便を漏らした時なんかを除いては。そういう場合は間接的っていうか、直接的だから。ティキティキ
僕は今、タコ部屋大ホールにいた。しかしなかなか思考に集中できなかった。ぼんやりともできなかった、部屋を眺めまわした。部屋にはびっしりと十五台の机が並べて置かれており、僕は一番後ろの、壁際にいたので、そこから大部屋全体が見渡せた。カウガールから一番遠い位置だ。午後のなにもない時間――一日のうちの二度目の「なんでもない時間」――だったので、椅子に座ったり椅子のあいだの地べたに座ったり、机をベッドのようにして寝ていたり、大半は真剣にカウガールを見ていたが、休んでいる人たちが多かった。あと一時間半もすれば夕食で、そのあとまた三度目の「なんでもない時間」があって、薬の時間があって、就寝となる。僕は知らぬうちに向こう側の机を見ていた。シーツを敷いてタコ部屋の机の一つをベッドにした佐合の寝床だった。性格に似合わず几帳面にベッドメイクされていた。そこが今は空っぽだった
視線を戻し、自分の隣の、部屋の隅の机のほうを向いた。そこにはもう何年も髭にも頭髪にも手を入れてないであろう、白髪混じりの仙人のような爺さんの患者が、今日もいつもどおりに大きな紙を広げてその上に身体をかがめているのが目に入った
この患者は毎日、来る日も来る日も、月替わりに不要になったカレンダーを何枚かくっつけて大きくした紙の裏を使って、家の設計図を毎月書いているのだが、盗み見る限りでもそれがどうしたことか玄人並みなのだ。この患者は、世捨て人のようなその風貌と、一月掛けて何度も何度も消しゴムで消しては手直しを入れるその営みと、さらには誰とも口をきかず、唸り声かゼスチュアでしかコミュニケーションをとらないその態度に、ある種の気高さを感じさせるのだが、この人はひょっとしたらここへ入る前は本当に、腕のある設計士だったのかもしれないと僕は考えていた。ティッシュの箱の厚紙を使った自作の定規にちびた鉛筆。この患者の書き上げた家々は、これから先、現実に形になることはないだろうし、「自分はこのことにだけかかずらわっていられれば、自分のいる場所なんてどこだっていい」とその姿そのものがそう物語っているようだったのでなんだか安心して見ていられた。いや、それももう昔の話だ
今では微塵も思わないが、少し前に一度だけ、この爺さんと話がしてみたくなったことがあった。珍しく人に話しかけたくなったのは、爺さんの気高い、孤高の印象があったからだ。あとは安心感と
その時は僕は本当に爺さんに挨拶でもしてみようかと思ったのだ。だがその直前で、その欲求は遮られた。初めて見る光景だったが、ある痩せぎすの患者が現れて、爺さんの隣に腰かけたからだった。爺さんに友達がいるとは思わなかったので僕は少々驚いた。友達という言葉がこの場所で当てはまるのかは置いておいて。その患者は口があまりきけぬのか、「どうも」というように手を動かして、なにやら合図をし、両手の指で丸を作っている。そして鉛筆を見せた。それに対し爺さんも「ぐわー」と答えた。「ぐわー」僕はその一部始終を見ていたのだが、爺さんは「ぐわー」と頷いたあと、自分の机の陰――爺さんは部屋の隅をねぐらにしていたのでいろいろ物を隠すことができたので――そこからヨーグルトの容器を一つ取り出してきた。僕はそれを見て「きゅー?」と息を漏らした。実は爺さんの設計に使っている紙を繋げるためには、ヨーグルトを糊代わりに使っているのだった。だが僕はそのことは知っていた。こうしてヨーグルトは食べずにとっておくらしい。まるで囚人だなと思ったこともあったが。ヨーグルトは蓋を開けておいて、少し乾かしておくと、べたべたしてきて糊として使えるらしい。ティキティキ。糊を売店で買わないで、身の周りのものを利用するという何か病的な信念があるのだろう。紙だってカレンダーの裏紙だもんね。そして、今取り出してきたヨーグルトの容器、今度は、それを何に使うのだろうと僕はこっそり見ていた。そのやってきた患者は容器を受け取った。蓋が少し開いている
おもむろに患者は蓋を引っぺがしてそれをひっくり返した。ああ、こぼれるよう! だが……、その中から出てきたものは……、僕には最初、石鹸かなにかに見えた。石鹸? 手のひらの中の黄色く半透明の、硬そうな樹脂のようなもの。大きさは、そう、紙カップを一回り小さくしたくらい。少し考えてから僕は答えに辿り着いた
「あれはヨーグルトだ。乾燥して半ば水分の飛んだヨーグルトの成れの果てだ!」
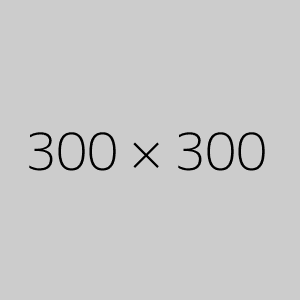























"第二章"へのコメント 0件