最後の蝉がうるさかった。とりわけ例年より元気だというわけでもないけれど、やたら耳につく。夏になるたび必ず訪れる風物、世界のどっしりとした自律神経、今年も来たかと頼もしゅうなくはない。しかし余は今年でおさらばと、我が死後にも続くどっしりに惜別の感慨は、蝉を呼び水には、もひとつ湧かぬ。
蝉といえば幼い時分、取り巻きになる前の友人どもと、交尾中のをつまみ上げて、いたずらごころもなくただ二匹が変に引っ付いておるからむしろ親切心で引き離したら、ぞんがい長い生殖器(?)がぬるぬると出て来てズルリと垂れた。悲鳴を上げて放り投げ、一目散に逃げた。それは殺すよりも恐ろしい気味悪さであった。そういうものが生殖だと観ぜられた。生きるということと遊離して、それは存するような。滅私的の繁栄意志や、快楽的の死欲やというよりも、もっと単純に暴力的な、不必要に醜悪な。生殖は捕食にまさる生物への呪いで、こいつが死と踊り狂うておるのが浮き世の真像、その他余分の生活や人生はすべてゴミなりと虚しゅうなって、空っぽに呆けた気分あたかも蝉の抜け殻のごとし、背中の切れ目をかするくぐもった風音をつらつら聞いておる我が身は殻の内にあるのか外にあるのか、斯様な体感は羽化でないと言えるであろうか、蝉とはつまり余にとってそういう存在であった。
いやな想起のために汚く濡れた気分をお返ししようにも、引き取ってくれる風物もなし。悪いのは余のほうで、四方を山川に囲まれた田舎町に育ちながら、余は自然の風物にずいぶん無関心で来た。これが見納めの最後の四季にも触手の縮こまった感受性は濁った水底で委縮したひだひだがかすかに痺れておるばかり。何かにしんみり感ずる器官は不明なる心理的の防衛作用のエビや小魚につつき散らされてちょぼちょぼになり果てた。
このちょぼちょぼに代わってがんばる器官が感受性を以て任ずる言語思考だ、これが世にいわゆる不感症だ、そんな言語思考に組み立てられた情感が述べて申さく、おのが生命も早晩この風物に混じるのであるからして、風物への不感は不感症にあらず、自他の境界の消滅なり。相撲大会以降、自然の万物に漂う霊気をおのずから認識し、前以てそこへ同化されたのだ、その上もはや余分を感じないまでのことだと宣う。風景自体は風景を眺めぬゆえ、もはや風物たる余は風物に感性の動かぬも道理、下手な感慨はむしろ人為の虚言と、そういう言語踊りを述べ立てる、その強大な説得力は、無数の常套句から成る人工情感の、一億現代人を渡り歩く狡猾さだ、我が現代人の内部からはしかと見あらわすこともかなわぬ大黒幕だ。
まあ一理あるように思わないでもない。どう思い返しても相撲大会以前から無関心であったことを考えたところで、供物は誕生の瞬間より決まっていた宿命でなくもあるまい。一方通行と実感せられるばかりな時間のうちに、あとになって初めてかたちを成すが、鋳型は天孫降臨の時分にとうから安置せられていた、余のような真正の供物は生まれた時から人間でありかつ自然でもあったのであろう。
イキハジが逃げたために十歳の冬には奉祀が見られなんだ。身代わりの祖母に行われた奉祀は密儀めいて、村議会の老人たちしか立ち会わなかった。
二十歳の冬に因幡さんで初めて奉祀を見た。その時にはすでに強制せられていた放蕩のため急速にぼやけ始めていた心が、瀕死といえどもまだかろうじて生きておった感受性が一気に澄んだ。そう記憶している。この記憶にしかし反応を示す感受性は、今やっぱり壊死しておるけれども。
自分は十年後に死ぬと実感してからの日々はむしろたいそう幸福であったと記憶している。壊死しておるにつき往時の胸中を正確になぞり返すこと能わずといえども、余には充分に確かである。夜半が多かったか、しかしいつでもどこでも予告なしに襲い来る錯乱、神経発作、前後不覚、離人、おしなべてそののちふたたび回復した自意識はげに冴え渡っていた。生まれ直していた。嗚呼おれは今初めてようやくきちんと存在したという気がした。この経験を持たぬ人は半身だけが生きているわけだと思った。これを幸福であったというのである。自己紛失と邂逅の日々に、不安・恐怖・懊悩・煩悶のたぐいは魂の輪郭を濃ゆうしてくれる厳しくも優しい慈父的作用であった。
その澄み渡った感受性をふたたび然るべく濁らすまでが骨だった。錯乱の内部においては永遠の苦痛、過去の壊滅、通り過ぎては包括的の大幸福、この反復の最も豪儀に隆盛していた頃、今にして思えば二十二、三くらいであったか、父としばしば滝へ通っていた。夜になってから人目を避けて。本番に取り乱さぬための予行演習であった。
大会以前からコッソリ行われていたことではあった。その時はまったく平気で、珍しく面白く、平生寡黙で不愛想な父と出かけるのも楽しみであった。それがじっさい供物の役を射止め、宿命が受粉してからは、ただ通うだけでなくだんだん予行演習の観を呈し出したが、それも淡々としたものであったし、身の引き締まる誇らしさだけであった。取り巻きどもと日頃忍び込んで遊んでいることを隠している可笑しみもあった。
しかし二十歳にしてようやく奉祀を目の当たり見てからの滝は、いやそれから二、三年の潜伏期間を経てからの滝は、血の幻臭がこびりつき、冥府の悪臭が漂い、轟々たる水音に明らかな人間の悲鳴が混じり、ある日とつぜん滝壺に足を浸けることもままならず、心臓が喉までせり上がり、父に引きずられて行く道すがらに気絶すること一度ならず……。
我ながら情けない、何をしとるか、小学生時分にもできていたことぞ、足を運ぶだけでいいのだ、滝へ向かい、硬くて重い水の柱を頭と肩でぶち割って割り込み、篠突く銃弾の鈍痛に耐えて馬鹿のように立っているだけでいいのだ、あとは自分ですることではない、向こうからやって来る、すべてつつがなく確実に手続きしてくれる、とりわけ供物のそれは一瞬で過ぎ去り、祝福のうちに終わるものだから、しかもまだまだ遠い未来のことなのだから、今は何も考えることはないのだ、足を運んでそこへ立つ行動だけすればよいのだ、これは訓練ですらない、あんな未来はじっさいには来ないと、左様胸中に無限反復し、知らず知らず枝を切って根を枯らすのたくらみ、何ぼか功を奏して、次第々々に慣れては行った。
習慣の法力で以て毎夜通った。勢いがつくと昼間にも行った。父は収穫を控えた畑もほっぽらかして余に付き添うた。完全に惰性になるまで入り浸った。重篤なる中毒になれかしと祈りつつ。やがて滝に立つことは遂に本能の欲望にも肯われたと信ぜられた。
遂に我ら父子は人間に勝利せりと思われた、矢先のこと、とつぜん家から出られなくなる。滝へ向かわなくとも出られなかった。めまいに天地がひっくり返り、星の引力と遠心力は拮抗を失い、肺は密封され、右往左往するうちにまたぞろ気絶、以降癖がついたごとく気絶々々の毎日に時刻もわからず、はて飯は食うたろうか用は足したろうか。
それを父は引きずり出し、卒倒すれば背負って滝まで通った。放り込まれて水中に沈む余は、気絶したまま無意識に息を詰め、溺れることもなくたゆたっていた。抵抗しようにも方法を思いつかぬ。気魄においてはるかに上回る父の手にむんずと掴まれて、振りほどくことなぞ頭によぎりもせぬ。気づけば滝までたどり着き、絶え間ない水の鈍器に殴打せらるるまにまに突っ立っていた。これを延々くり返すうちにふたたび神経は錯乱やら卒倒やらの怪演をぴたりとやめた。この「ふたたび」と「ぴたりと」は悪夢の中において何度もくり返されたが、ある時とうとう、どんな重病人でさえある程度は蘇生し得る最低限の神経まで滅却せられたのだと、左様何ものかが滅却せられつつ宣うて跡を濁さず消えた。
爾来完全にぼんやりし、すべてが平気になった。平気になったと言ってもやっぱり脳髄は不浄の肉であるから時には旧套の残滓を見せたけれども、煩悩の死骸の譫言が垂れ流されているだけだった。固定せられたものの反復こそゆいいつ確かに善なるものであった。余に職業があるとすれば予行演習の反復がそれであった。余に生まれて来た意味があるとすれば予行演習の反復がそれであった。滝の霊気を吸収するためでなく、穢れを浄めるためでなく、ただ行為に慣れるためだけの予行演習であった。慣れればどうなるかといえば、よりいっそう予行演習に励むことができるというためだけの予行演習であった。
ここまで来ればかえっていっそう気を引き締めんけりゃ泳ぎ上手は川で死ぬと、あたかも毎度々々が一回限りの真剣勝負、千丈の堤も蟻の穴より崩るると、一年じゅう間断なく行われたけれども、何といっても神髄は冬であった。
真冬の滝は悪意と敵意に満ちている。圧倒的な無関心に閉ざされている。深夜の水は頭蓋なんぞ最初の殴打で軽く貫通する。肌なんぞ一瞬で消滅し、脊髄は覚束なき電気になる。一切の感覚を失してのち、ぴんぴん響く何かだけ残る。ただおのれに肉体のあることを恨む。おのが魂の存在を異物的に体感する尋常ならざる主観、そちらへの移住、ふだんは自覚できぬたぐいのそれは魂であった。しかし不完全だ。そのいわれや如何。壊れたみたいに震えながら滝に打たれるうちに明らめられて、何が明らめられたかは知らねど、ただただ肉体と地上との癒着が憎い、気を失いたい、何が魂、何が冥府、いっそ魂もろともきれいさっぱり死後それ自体とも刺し違えて道連れに消えたいが、意識はこじ開けられ続ける。あまりに重たい水の殴打に、どれだけ電気が炸裂し、暗闇のはずがピカピカ眩しくとも、倒れてしまいたいそのまま溶けてしまいたいのに足は独立し、絶命から逃走せん逃走せんと力み、意志と乖離して踏ん張り続け、何かにスイッチを押され続けていつまで経っても気絶させてはくれないのであった。
これはさすがにもう大丈夫そうだ、過ぎたるは何とやら、急いては何とやら、またぞろ変にひっくり返ってもナンだしと、予行演習の分量は徐々に控えられ、間隔は広まり、もはや二月三月隔てても平気であると確認すること数回を経て、今年は軽く二度しか行われなんだが、あのがむしゃらに励んでいた日々に死ななかったことがつくづく不思議であった。父が余の精神的凍傷をどのようにあたためたか覚えていないが――それは愛情よりも効果の問題で以て、叱咤一本槍よりも優しくあたためたのには違いないが――それとも父もまた憑かれたごとくであったのか?――それとも一切は村議会の監督のもとに行われていたのか、我が脈拍や血圧は克明に記録されていて?――心臓発作なり肺炎なりでポックリ逝かれておれば今頃、ポックリ逝かれておればなんぞと願わずに済んだものを。
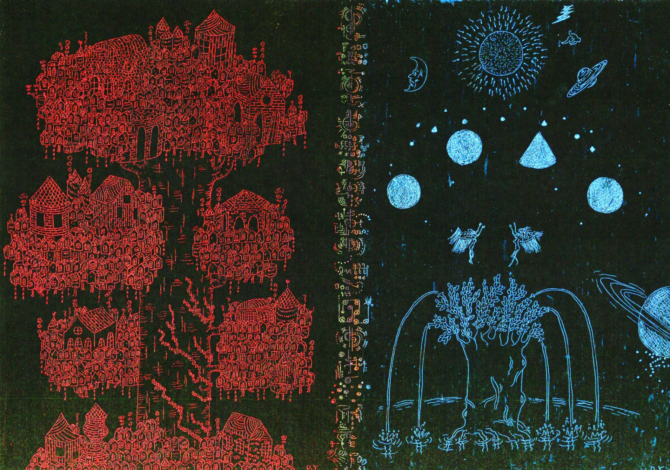
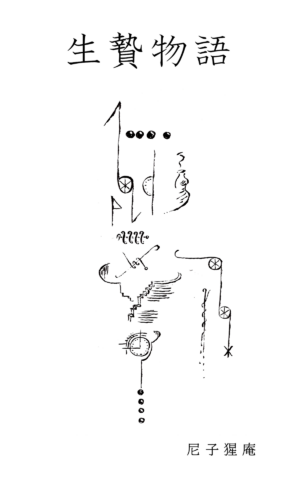











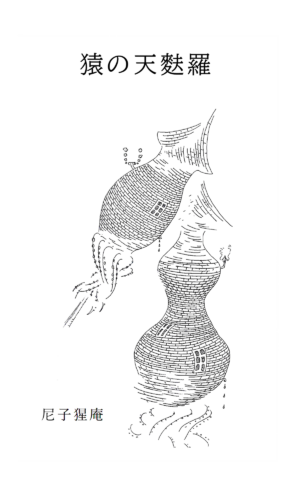










"生贄物語 2"へのコメント 0件