みんなでテレビを見ていた。半田のノートパソコンでYouTubeを見ることもあるけれど、たいがいテレビだった。保健所の殺処分を回避しようとする運動が悲鳴を上げていた。
その施設は送られて来た犬でごった返していた。ぎゅう詰めの檻の中で病気が蔓延していた。血便が床を塗りたくっていた。関係者は疲弊し切っていた。報道のカメラは神のようにじっと目だけを向けていた。
今は別の家族が住んでいる、前の家で飼っていた犬は、一家の崩壊に際して飼い続けられなくなった。父が奈良に老夫婦の里親を見つけたと言って連れて行った。母と姉と私が移り住んだ借家へ、「つつがなく受け渡した」と報告に来た。
小六の時、父の金を盗んだ。クラスメイトに手伝ってもらって使い果たした。手伝ってもらったために露顕して学校で問題になったが盗んでないと言い張った。問い詰める教師は私が目を見つめて話すために「嘘ついとる人間は目を逸らすもんや」と信じた。
財布にはち切れんばかりだったピン札が借金であったと知るのはのちだった。家の電話線は抜かれ、セダンが家の前に停まっていた。学校から帰って来ると「お父さんどこ?」と聞かれた。本当に知らなかった。夜中に執拗に玄関をノックされた。尖ったドライバーを持ってバス停まで姉を迎えに行っていたのもまだ小六だった。爾来私たちきょうだいは電話の音やインターホンや、とりわけノックが今でもこわい。
私の小学六年はまた、弱い者いじめをした時期でもあった。学生時代には養護学校の教師を目指していた母の教育で、灰谷健次郎を読んでいた。そして、なぜかそうなった。
隣のクラスの担任のまだ若造な教師から情熱的に叱られたのなんぞよりも、養護学級の先生のおじさんが叱らず、ただ寂しそうな笑みを浮かべたのが耐えられなかった。この学校で好きだと思う人間はこの人と図工の先生だけだった。
末っ子の私は「ぼくは誰をいじめたらいいの」と母に聞いたらしい。いかにも可哀相だが、そこで殺しておかなければならなかった。
罰は受けた。私自身、もっとひどい目に遭ったこと。おのれがそういう存在であるということ。もっと悪い奴が罰を受けていないということ。来世では虫に生まれるかもしれないこと。時効はないこと。
今からでも投獄してくれれば贖い得るのに自首したとしても逮捕はしてくれないこと。謝罪もできないこと。
鬱病。パニック障害。罰は受けた。しかし主観的の私的な罰だ。勝手に受けたものだ。本当の罰はこれから受けるだろう。
母が諸々の返済を終え、他市のマンションに引っ越して、友人たちとは疎遠になった。
そのマンションで、私と母は同じ朝に、飼い切れなかった犬の夢を見た。私は、ひたすらなでている夢。母は、玄関に訪ねて来た彼女が焼けて子犬になる夢。その夢を見た頃、生きていれば十六才くらいだった。この朝私と母は、そうか、あの子死んだんやと言い合ったが、真相はわからぬ。父が見つけた奈良の里親とやらに私たちは会っていなかった。
今テレビに映っている犬たちはいつまでも貰い手が出なかった。私の犬は、生きていれば今では二十二、三才くらいか。いずれにせよ、もう確実にいないだろう。
あの時真実では父がどこに連れて行ったにせよ、私は死んだら彼女に会いたい。許してくれるのだろう。再会を痛ましいほど嬉しがるんだろう。ちぎれんばかりに尻尾を振るんだろう。犬はそうだ。世界中で犬だけだ。犬が人間の最大の罪だ。
いつかテレビで、かつて飼った犬たちのお墓を作っていて、自分もそこに眠るつもりだと言っている人がいた。ここで私の多動児の名残は即座に、あの世で飼い犬たちに八つ裂きにされるその人を想像するが、誓ってそんなことは考えるのもイヤなのだ。保育所時分、虫封じをされても治らなんだ自傷癖だ。思考はうるさ過ぎる。時にはとても耐え切れぬ。
今、保健所から送られて来る犬たちの、たくさんの痛ましい吠え声を聞いていてあまりに寒い。みんな黙って見つめていた。
やがて欧米に比べて遅れている慈善精神というような吠え声だった。我々の沈黙がそれだ。しかしこれは遅れているのか。舶来の饒舌が合わないだけではないのか。じゃあ何が合うのか。無常。かむながら言挙げせぬこと。ただ不浄なる黄泉を思い、死をただ歎き、ただ悲しむこと。寡黙。
現に今テレビを見ている若い我々も、何か口ごもらしめられるものがある。あんがい誰でも、外ではあれやこれやと言う人も、家ではこんなものではないのか。善し悪しはわからぬが好悪はハッキリしている。あんまりしゃべるな。然り、もっと黙って欲しい。助けずに歎いて欲しい。いやそう言葉にすればまた激しく違うけれども。私の時はほっといてくれと願う。そういうかたちで激しく助けて欲しい。いざその段に臨んだ未来の私が前言撤回していたら、もうその他人をどうこうして欲しいと願う権利はないけれども。
あふれ返る犬たちの解決を悪魔にゆだねざるを得なくなる時を先延ばしし続けるのが天下の義務だ。我々は穴蔵の中で、善意や救済に究極の慈愛が合致する時を待つ。平和的に人口が激減する時を待つ。私の寿命が間に合わなければ悲しいし、その時よりもあとに生まれて来たかった。
解決が悪魔にゆだねられた場合は言うまでもなく食料化だ。スウィフトにダブリンかエディンバラかの(本も捨てて来たからこんな簡単な確認ももうできぬ。)生まれ過ぎる貧民の子を食料にする考察があった。むろん駄法螺だ。神々のためのユーモアのようなことだ。こういったたぐいのブラックユーモアが純粋な本音になる時が来るであろうか。来ればぜひとも参加して、力の限り敗北し、炎に包まれて「やったよママ、世界一だ!」と叫びながら爆発したい。しかしこの圧倒的な最期、『白熱』(1949)のジェームズ・キャグニーのような絶対的なママを私はまだ持たぬ。
摘出せられた母が臓器を執刀の医学生から見せられ、長々と説明を受けた三十分後に喫茶店でオムライスを食べていた私の心は死んでいる。多めに飲んでいた薬に昏睡させられながら心はどこかで悲鳴を上げていたろうか。私の中の少年は子ども時代の墓の中から両手を突き出してぶるぶる震わせていたろうか。
しかし私はオムライスを食べた。行動の予定を決めねば外出できず、決められていたものへ機械的に従った結果だとしても。そして母親の子宮と卵巣の死骸を見ながら何の懐かしさも覚えなんだことは解剖学の誤謬を明らめていた。
(まだ犬の吠え声は続いている。)
スウィフトの晩年発狂と駄法螺との関係はあろうか。あるなら私の魂はそこにどっぷり浴している。口にすべきでないことを言い過ぎたし、これからも言うに違いないので。一緒にテレビを見ている連中はどうか。穴蔵の変人どもは。
(言語中枢が痙攣しているばかりだ。好きにさせるのが最も早い脱出法だ。)穴蔵の変人どもと言ったか。ここな二人の女流作家は、書き溜めたものの膨大さに祟られて、実る前に腐り、咲く前にしぼみ、もはや新作が書けなくなっていた。
じつに十余年に及ぶ挑戦歴で、二人合わせて応募数は百作を超えた。長編・中編・短編の割合で言えば3・4・3くらいだそうな。ショートショートや童話などの掌編を入れれば百五十を超える。それでもやめる踏ん切りがつかぬのは、なまじ二次予選、三次予選、そして二度までも最終選考に残ったことが呪いになった。しかも一度目がごく初期であったことが奥部まで刺さった。予選突破は全体の一割に満たなかったが、それで充分呪われ得た。
応募してから結果がわかるまで何ヶ月もかかるために、常に何か応募している状態で、落選したとしても、常に次の結果待ちだったということが呪いになった。そうこうするうちに常識の範囲を外れていたが、ここまでやる人間は少なかろうことと、ここまでやって駄目なら駄目だろうことを身にこたえて弁えながらやり続ける悟達感のようなものが、逆怨みも焦りも抜け落ちたものが、何かに化けやしないかという期待がないでもなかった。
受賞するには倍率が何百倍から何千倍で、二人の挑戦の手数では五十歳までやったと勘定しても十数回生まれ変わらなければ受賞できない計算だった。かくも絶望的な文学賞応募一本槍というやり方で、百を超えた応募というのも正確には百作を意味しはせず、以前に落ちた作品を推敲し直して再挑戦というのも多いけれど、ああこのテーマ、このアイデア、このトリック、この描写、この構成、この結末、この台詞、このしぐさ、このキャラクターは既にあの作品に書いたからなと、まだ発表もしていない過去作に邪魔されて、時に経たれるうちに話題作なんかで未発表の自作の骨子が先を越されると暗殺されたようなものであった。












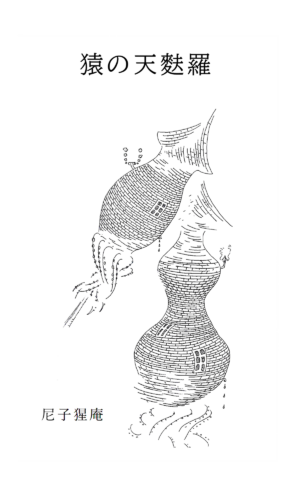
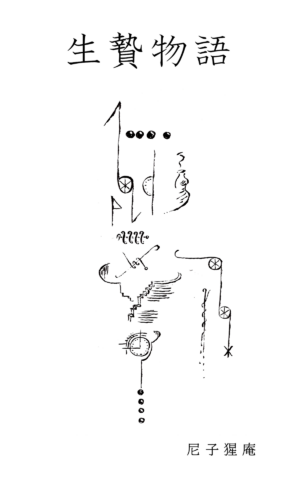










"ホルマリン・チルドレン 7"へのコメント 0件