我々は床だけできた山の隠れ家を忘れたように暮らしていた。
危うく思い出しそうになると、別の夢想に逸らす。たとえば山の中に、二人で両側から幹を抱えて手が届くかどうかという大木(名前は不明。図鑑で調べかけてやめた。)があるのだったが、あの幹にアーチ型の扉をつける。そしたらあとは木が自力で、内部に家を作るから。時々見に行って、幹に窓がついていたら住み頃だ。煙突まで出ていたら急がねば、それ以上放置すると人まで住み出すものな。――云々。
アルコールがのさばり過ぎないよう監視することに、我々は労力のほとんどを割いていた。
私は白状すればこのたび住宅街に帰って来るまでの十余年緩慢な酒浸りだった。初期には鬱病の症状が絡んで小便に行けなくなり、ぱんぱんだった尿意もやがて消滅し、夕方に熱湯のような血尿がちょっとだけ出て、それをくり返すうちに慢性前立腺炎を得た。下半身の疼痛と激しい不快感が出ているあいだは飲酒は大敵だったけれど、しかし呼吸器を踏みつけにして来る気鬱が装填するものと、何をさせられるかわからない脊椎の深部のやかましさを回避するには起きてすぐ枕元の夕べの残りの焼酎を飲み干すしかなかった。
眠っているあいだに覚えのない行動をしていたとあとで姉や母から聞いた。
この十余年の八割がたが夕方まで二日酔いで、たまに残らない朝などは洗面所の鏡で白目の白さにぎょっとした。強くもない肝臓にアルコールは寄生虫になっていた。
何度かやめた。すると世界は澄み渡り、夜にはそわそわと膝などさすり、頭はうるさく、悪夢におののき、眠れず、目を閉じ続けて気絶するように寝て、飛び起きれば前後不覚で家の中を歩き、五日と続かずふたたび飲むと世界は優しく、何も気にならなくなり、やがてまた二日酔いが苦痛になり、どうにもならなくなってやめる決意をしても、二日酔いはすぐに抜けるわけではなく、その晩飲まずに寝た翌朝まで「やめる」のスタートは切られない、この決意の成立の遅さに耐えられずにけっきょく習慣で飲んでいた。
八歳のバーベキューパーティーで飲んだ缶ビールが始まりか。もっと幼い頃からお正月のおとそは好きだったが。時々こっそり飲んでいた。中学二年だったか体育祭の朝にも緊張をやわらげるために冷蔵庫にあった白ワインを一杯だけ引っかけて行った。酒臭さなどはバレなかったが、リレーのアンカーだったのに「何か遅かったな」と言われた。
この十余年、やめた期間の最長は二週間ほどだった。合計は一月に満たなんだ。今もけっきょく私だけ何も食べず初っ端から蒸留酒を飲んでいる。せめて薄めて温めて。これがのさばらぬための監視に満身力を込めていた。貴崎さんより濁っていた。彼女のはほとんどスタイルに過ぎなかったと判明していた。むろん誰も指摘はしなかったけれども。
無為徒食の二日酔いほど純粋な苦しみはなかった。おのが卑小さと向かい合うよりほかにすることのない、誰のためでもなく、それ自体で存在する、愚者の真剣な労働であった。
近頃の我々は、一つ山を隔てた隣町の喫茶店などで、頭を寄せ合って、練られもしない計画を練ろうとしていた。せめて計画を練ろうとする気分を、全力で生ぜしめ、慎重に長引かせていた。
そのようなことをしているあいだは、学生や、おばさん連など、人生に今たまたまトラブルのない人たちからの迫害を恐れた。迫害されているところを想像し、その無邪気な悪魔たちに罪の重さを教えてあげる。あのなァ、そんなことをして、もしも我々が、今にも死にゆく親の最期の手続きを相談しているきょうだいだったらどうするのか。ェえ? そんなつもりはなかったでは済まへんぞと、そういうことを考えて、現れもしない外敵をいっそう悪人にした。そうしている限り我々は、親の最期を相談するように真剣であり得た。
メダカはあれからまた二尾死んでいた。放置されるほうがよいらしかった。我々は気づかれないようにカーテンの隙間から見下ろして眺め、申しわけないように餌をやった。
庭の按排は半田が意外にやった。植物の世話にも詳しいから聞けば、半田の実家のベランダには鉢植えが多数あり、虫も湧く。ある時彼がリビングに腹這ってぼんやりと眺めていたら、鉢植えに生じて育った一匹の蠅が手すりの向こうの空へ決然と旅立った。彼は大いに感激した。かの虫は絶命の危険を惜しげなく自由に賭した。ウン十億年生きて来ていまだに死を避けられぬ生物の不思議は、この世がどこかの星の罪びとの送られて来る刑務所ないし天上世界の罪びとが落ちて来る地獄の証明なりと思い至らしめられるものであったが、かの虫の勇気と喜びはその事実を一笑にふす軽さであったと。
以上の説明が植物の世話の詳しさとどうつながるのか私には遂に不明であった。
その半田がそちこちに太陽電池パネルのついたランタンみたようなものを挿し込むやら吊り下げるやらして置いている。通販で買うたとか。けっこう安いねんで。なるほど夜になれば青や七色に光ったが、三時間もすればずいぶんか弱い。それで半田は太陽電池パネルに虫眼鏡を固定して太陽光を強化すると言ったけれど実行はされなかった。せいぜいこまめに拭いていた。夜中のトイレに行き会えば、あんがい貴崎さんや庄原も、リビングにしゃがんで、かろうじて点いている灯りを見ていたりした。
洗面所には女性たちの化粧水や乳液が置かれ、開閉式の鏡の裏にはT字カミソリ等が置かれていた。トイレには蓋つきの小さなゴミ箱が置かれ、風呂場の石ケンには常時半田の髪がめり込み、庄原の歯ブラシはいつも乾いていた。
こんな無為の我々も時には世間並に、世間一般の模倣をしなければならぬ、それで健常世界の流行から添加物ノイローゼを摂取して、無農薬の玄米を炊いていた。するとある日米びつに穀象虫が湧いていた。床に置くと、いじいじ歩いていた。みんなで眺めた。こめくい虫や。こいつか。うちらはあんたか。こんなんか、俺たちは。しゃあないやっちゃな。
体によいもの体によいものと、囚人たちの健康をおもんぱかった安からぬ食費、あるいは通販で、あるいは庄原の車で以て彼方此方から買い求め、小便などしょっちゅう大根やアスパラガスの匂いがしていた。前の人の残り香すらなかなか弱からぬものだった。
漬物に究極の栄養食を押し付けてきゅうりの浅漬けが常備せられた。一度炊飯器の予約の押し忘れで米が炊かれていなかった時、ライ麦コッペパンに挟んでみてから浅漬けホットドッグなるものがちょっとだけ流行した。
川野さんがあんがいゲラで、強いて笑わせ続ければかなり長く笑った。両手で顔をおおい、遂には机に突っ伏して、音量上は極めて静かに、まっ赤になって笑うのだった。












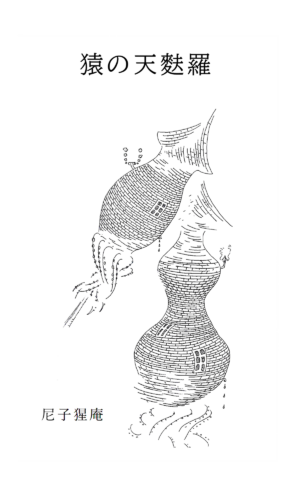
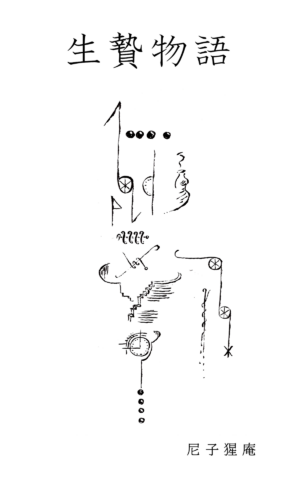










"ホルマリン・チルドレン 6"へのコメント 0件