熱が出た。四十度まで上がって、三日で治った。頭の中の塊も心臓の瘤も取れないが、これは以前の状態に戻っただけのことだ。菌だとか免疫力だとかいうよりも、安定剤を急にやめた副作用による熱であると、四十度へ達した時に観ぜられた。
病院には行かなかった。かぜ薬も飲まなかった。十代の終わり頃タミフルでおかしくなって以来、かぜ薬のたぐいがイヤだった。正座してわけのわからぬことを姉にまくし立てたらしいのは覚えていないが、その手前までは覚えている。まず口の中に物を詰め込まれたような感覚があり、次いで頭の中が父親の怒鳴り声から始まって世界中の叫び声で充満し、胸のざわつきが際限なくふくらんで激しく肉体を動かさずにはいられない、だいたいそういうことだった。
この錯乱、じつはがんらい持病めいたものであったのが、タミフルで大きに誘発せられて、しかしそれ以来かえって治まってはいるのである。劇薬として退治したかのように。
あるいは心理的の問題で、あの症状は無意識下にタミフルと接着せられ、飲まなければ出て来ないと思い込んでいるだけかもしれぬけれども――嗚呼しかし、これはそんなふうに見破ってしまったらば、逆さまの精神分析に、かえって錯乱を戻すかもしれぬ。
そもそも想起というものはそれ自体が怖い。幼少期の記憶は、古いものでは二、三歳頃か、父親が炊飯器を叩きつけているものだとか、廊下に置いたビー玉が勢いよく転がるマンションの傾き、六歳阪神淡路大震災の悲鳴、いや何よりも十歳交通事故の瞬間の、どうしても思い出せない記憶というものが地雷のように眠っているのだ。ヘタに歩き回って踏んづければ、どれくらい吹き飛ばされるかわかったものではないのである。
うつるから来ないほうがいいと言ったけれど、みんなうちにずっといた。おもにリビングで静かにしていた。私は部屋で寝ていて、一度も降りて行かなかった。
何だかやたら掃除機をかけなければと思った。じっさい実家にいた頃よりもよほどかけていた。おもに、床に落ちている長い髪が気になって。貴崎さんのだったら、よいというわけではないけれども、まあよかったところが、庄原の可能性もあったので。庄原がイヤというわけではなかったけれども、貴崎さんではない庄原というのは耐えがたくて。
布団も干したかった。布団を干すという文化がないらしく、女性二人の布団も私が干していた。あんたが潔癖過ぎるだけよとなじられたけれど、取り込んだ布団に二人は顔をうずめてくんくん嗅ぎ、「お日さまの匂いがするわァ」と言っていた。
食事は、川野さんが作ってくれていたようだが、なぜか必ず庄原が持って来た。どのようなやり取りがあったのか知れないけれど、来るのは彼だけだった。
「きつないか」と言った。
「あァ大丈夫。むしろ四十度超えてから、めっちゃラクでな」
「それヤバいんとちゃうんか」
そう言って笑っていた。
「何かふっとマシになってな、治りよったわと思ったら四十度超えとった。――まあいわゆる神経不安がどっか行って、それでラクやねんわ」
庄原はわかると言った。やはり彼も同じクチなのだった。その話をした。庄原は薬を一度も飲んでいなかった。病院なんか行ったら病人になる。それに病院なんか、治ったら毎日でも行ったる。行かれへんから病人なんや。そう言った。私もよく考えることだが、私のは通院し続けるための逆説の呪文のようなものだった。庄原は有言実行で、言ったのは今が初めてだから不言実行で、つまりは言霊のさきわう国の人だった。
私も本当は庄原のようだった。医学への不信ではない。診察はありがたい。しかしいわゆる心の病を治すというのは、人格の改造かもしれぬ。それは準殺人かもしれぬ。魂のことを考えるならあるいは殺人より恐ろしい。そんなことを任せるのはお医者さまに気の毒だ。恋人だとか、そういう存在にしか任せようがない。もしくは自分だ。自分だったらどういう結果になっても人のせいにできない笑いがある。決して可笑しくはないけれど、それだからこそ笑いにすがるのほかはないものがある。
最初の強烈な印象がだんだん失墜していた庄原にもふたたび上昇して来るものがあった。
つまるところ私と庄原は一勝一敗である。世間からの敗北の中での引き分けである。
私の理屈では世間と我々も引き分けにできるが――無為徒食は世人には純粋の苦痛でしかない事実を以て――この理屈の所有を以てただちに庄原からもう一勝を積めるかもしれぬ。
嗚呼こんな戯れ言もひとえに熱の賜物であるが、こうした自嘲も熱の賜物だから言うまい。この分別。これ熱への一勝である。
庄原に見つめられていると、大型の飼い猫にでも見つめられている気がした。これの前では病気になってはならぬのだと思われた。弱っているところを見せたら噛み殺されてしまう。いくら懐かれていても。犬とは違う。
「――……お前は疲れとんや」
庄原はそう言って、じっと座っていた。優しかった。壁に飾ってある絵など見ても、何も言わなかったが。半田の絵だったのだが。飾ってくれと言われて、ほんまに飾ったんかと言われた、画用紙にシャーペンの抽象的細密画で、よくもまあこんなに細かく描くと思う秀作なのだが。
それから思い出話であった。小学五年の頃、担任の暴力女教師と対決した。私は反抗と挑発をくり返して頭を叩かれ喉を突かれ髪を引っ張られ、ちょうど足首を剥離骨折していたギプスを蹴って回られる、なるたけ多く打たせるノーガード戦法であった。
ゴンタの友人も廊下に引っ張り出されてタイマンで叱られると、いくらゴンタでも泣いたけれど、私は何をしても泣かなかったためにことさら許せないらしかった。「何やその目は」。これはこの女教師に限らず、小中高とほかの先生たちにも、または兄にもバイト先のコチンピラにもしばしば言われたが、どんな目なのか自分ではいまだにわからぬ。ともあれ打たせるだけ打たせる戦法は少々功を奏し過ぎ、ほかの生徒が学校に行けなくなって体罰が発覚、どこかへ飛ばされて行った。
暴力女教師は追放された。あの暴力はしかし私が過剰に引き出し過ぎたものでもあった。あまりに容易く人の職を奪える人道的権力、被害者のシンボルとして結果的に扇動した後味の悪さ。












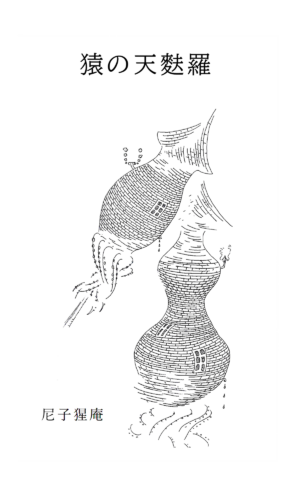
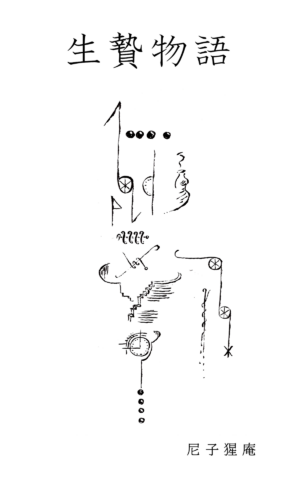










"ホルマリン・チルドレン 8"へのコメント 0件