庄原が、父親に掛け合って、ワンボックスカーの後部座席をゴッソリなくして来た。運転中、後ろの連中は捕まるものが少なくて少々難儀したけれど、車を停めると、そこは膝を伸ばしてくつろげる空間だった。世間から隠れながら移動できる洞穴であった。
助手席はいつも私だった。この特権は私が家を提供しているからで、後ろの連中から不平は起こらなかった。またいざという時に運転を代われ得るのが私だけだったこともあるけれど、その場合は無免許運転になるために最後の手段である。
庄原の車であちこちへ行った。
山奥のダムや、山中の何か巨大な洋風建築の廃墟や、山裾の高級住宅街などに無駄に停めては、自然や富裕層の閑寂の中を歩き回った。無計画に山路をずうっと歩いて行って、長々と引き返して来たりした。
その前を通り過ぎた時、ある学習塾がなくなっていることに、私はひそかに反応していた。この塾からは小六の頃、他校の生徒から異文化が入って来て、けっこう危険な遊びが流行った。ある方法で、三、四人がかりで一人を、一瞬で気絶させるという遊びだった。立ったまま鼾をかく者や、寝言を言う者もあった。適性があるのか私は気絶できなかったが、外国に行ったと言う者もあった。
ある日、クラスメイトの一人が立ったままの気絶で、まっすぐ顔面から倒れ、救急車で運ばれて先生に露顕した。塾にも抗議が行った。その後十七年ばかり経っているから、それでつぶれたわけでもなかろうが。
その遊びを当時何と呼んでいたか忘れた。庄原は覚えているかもしれないけれど、昔の話が快いか不明だったので聞かなかった。
だいたいは車から降りず、我らが住宅街を色々な地点から眺め、起こりそうもない事件を探したり、平穏な家々を眺めて、知っていればそのお宅の噂や、そこで巻き起こったこしらえごとのエピソードを思ったりしながら駄菓子を食べていた。
やがて庄原の父親が――どこまで事情を把握しているのかは定かではないが――車を庄原に譲った。もう退職されていて、夫婦用の小さな車を購入されたということだった。
親の庇護の厚さと角度は、あるいは庄原が最も強いらしかった。
ある日、広い車内で、もうはばかることなく男たちがタバコを吸い、女性たちが黙って窓を下げている時、半田が言い出した。我々に何かできることはないかと。
それは社会復帰のことではなかった。もっと簡易な社会参加、損得のない善意の行為。神への奉仕という概念も、ヒューマニズムも絡まず、すなわちボランティアでもなく――我々がそんなものを考えれば、活動している人々への愚弄だ。そんな悪いことは誰もしたくなかった――もっと、暇を持て余した貴族のように、純粋の善意にふけること――我々は悪意を持つ気力がもはやなかった――ができぬものかと。
わからぬではない。カーク・ダグラス演ずるゴッホ(1956)が情熱も行動力もあるのに結果としての怠け者になり果てたのち本格的に絵を描き始めた、そのただ描き始めたということに関して弟テオに「仕事を見つけた」と喜々として手紙に書いていた。あれだ。おのが命と正気を賭けて「機関車のように」激しく取り組みようがあるか否かだ。あるわけないと自覚しているだけいくらかマシで、マシなだけにかえって救いようがない事実をいかに一蹴し得るかだ。正しい生き方は常に困難なほうを選ぶことと見つけ、善にも悪にも染まらぬ行動の死骸を断乎脱出することだ。ここまで言えば完全にかけ離れた。そう言った途端そもそもかけ離れるも糞もなくなった。
我々の熱意は外部とくっきり遮断された車内にのみ固く充満する霊気であった。半田もまたおのが意見を極めて下手に、不明瞭に語ったために、かえって全員、言わんとすることはわかっていた。それから抽象的の話が、あわや具体的の話へと移行しそうになるたび、大地に墜落しようとするところを我々は全力で引き返し、虚空へ帰すことに努めた。
トラブっている人物限定の子ども教室を半田が提案する。即座には墜落しそうになかったので、誰も急いで引き返さずに聞いた。
同じマンションにどうやら不登校児童がいる。これを学校生活に戻すのが最終目的だが、その過程は深甚である。一緒に遊び、共に悩み、旅にも出、最後には、俺たちみたいにはなるなと言って去るのだそうだ。
そろそろ引き返さねばならぬので、しかし親が嫌がるだろうねと結論した。善の霊体は地上で肉体に入り込んだが最後、現実状況の中でどうしようもなく死んでしまうのが人類永遠の空転だ。かくして安全に虚空へ帰って行った。
やっぱりボランティアだ。神への奉仕にしてヒューマニズムだ。それで考えるほど老人介護の需要にしか行き着き得なかった。
我々が会社を立ち上げて自由にやる案。金をかき集める手段は立ち上げてから考えるとして、しかしどこまでも向こうの都合に沿わねばなるまい。向こうの健康状態と生理現象がすべてだ。その苛酷、緩慢、醜悪、無際限。死別しかない達成のかたち。ここの根本的の解決に悪魔的秘密結社の必要を唱え出す頃、虚空の飛翔は急速にぼやけ始める。
じっさいは墜落もしない。ここに至って、元々何も飛んではいない。
しかし誰も落胆していなかった。牢獄から逃れられたように清々しかった。このようにして我々は何度でも出所し、脱獄し、逃げおおせた。
家の庭にメダカが来た。火鉢の中で、一尾十円のヒメダカが十尾、砂利の上を、マツモのあいだをつんつん泳いでいた。
レイアウトを相談して、浮子を一本浮かせておいた。半田が水中ビデオカメラを手に入れると豪語した。それええね、火鉢だけやなくって、近所の川やため池にも毎朝設置しに行って、晩に飲みながら見ようよ。けれども、水中ビデオカメラはけっきょく手に入らなかったし、みんな忘れたのでもあるまいが、誰も指摘はしなかった。
メダカを改良して食って行けないかと半田が言った。それは直接のお金の話、現実の地上と肉体に関係する、真面目な社会復帰の話であった。
山のダムには野生化したグッピーが群れなして泳いでいたが、その中に、背筋が青く光ったメダカがいた。半田があんがい詳しくて――何年か熱帯魚を飼っていたそうな――あれはみゆきという種類だと言った。あれをすくって、繁殖させて、そっから始めるのはどうや。何やったらマスとかサケみたいに、いったん海の生け簀で育てるのに成功したら巨大メダカも夢やないでえ。
それで画像検索しまくって、メダカの改良種を調べた。とんでもない高価なものもあった。いくらかは奇形にしか見えなんだ。我々は頭を寄せ合って熱心に見た。名前も凄くて楊貴妃、オロチ、秀吉、琥珀透明鱗ヒカリダルマ、毘沙門天、夜桜、深海、若草ラメ、鬱金歌舞伎――けっきょく普通のかたちのアルビノがええな。
「でも、うちのヒメダカたちが一番かわいい」
そう川野さんが言った。貴崎さんも同意した。
二人ともこの家を近頃「うち」と呼ぶ。
玲衣子さんがまた話を聞いて駆けつけて来た。謎に秘められていたのが遂に登場した庄原を見にやって来たのだった。
実物を見てからは何やらむんむん匂うかのようであった。こんなに露骨かと思った。同じものが貴崎さんにも潜んでいて、それが原因のいじめ被害であったろうか。美貌は女人のグループでは君臨しそうなものを、いや確かに君臨していたはずであったが、それが謀反に遭ってけっきょくこうまで持続的に蹴落とされたというのはあらためて凄かった。
あまりに早く我々はまたログハウスへ招待されていた。
旦那さんは相変わらず嬉しそうに貴崎さんを近くに寄せた。貴崎さんの気持ちは不明であった。旦那さんは庄原を見て「神童が増えとる」と言った。
やがて貴崎さんはあからさまに旦那さんを嫌がって離れたが、旦那さんはその反応も嬉しいらしかった。
玲衣子さんは庄原を近くに置いた。それで判明することには前回は少なからず私の席だった。嫉妬に蘇生を感じるかと思ってさぐったけれど、嫉妬らしいものがなかった。ふたたび強い欠陥をただ感ずるばかりだった。
半田がつらそうだった。堪え切れずにどうにかなるのではないかと案ぜられたが、どうにかなれるまでの生命力がないらしかった。












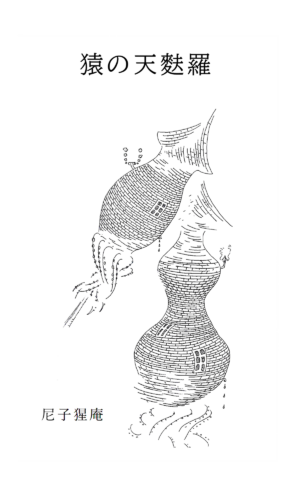
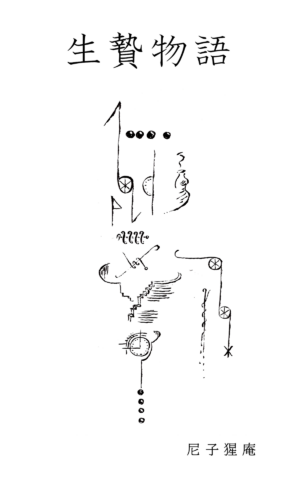










"ホルマリン・チルドレン 5"へのコメント 0件