一章・失われた語り部を求めて
古びたビデオテープのヘッドに舌をあてて、精神を集中する。読み取ったイメージが頭に浮かぶ。唸り声を上げた黒い平面はかすかに白んで、それからJOJOに色づき始める。もう少し。でも、赤味がかったままだ。色調の狂った彼女は緑色の肌をしている。しかも、まったくの無音。どうやら、このテープは破損しているみたいだ。完全に舐め取ることができない。
それでもいくつか読み取れることはある。コメンテーターは……滝川オバステルだ。たぶん、深夜の超長寿番組『NEWS JAPON』だろう。
画面が切り替わる。タカ派として人気を集めた前東京都知事のインタビューらしい。不機嫌そうなその話しぶりからすると、たぶん、テロ対策のための治安維持強化について主張しているんだろう。でも、音が出ないから、正確な意味が取れない。
画面が切り替わる。9・11の映像。続いてバリ島爆破テロの映像。さらに、ロンドン連続爆破テロの映像。恐怖を煽り立てるためのお決まりのシークエンスだ。
画面が切り替わる。車がゆっくりと走っている。歩道を歩いているカップルの女が、いまにもキスをしようとしている恋人そっちのけで車に見惚れる。音の出ない画面で見るスローモーションはなんだかくすぐったい。これは……プジョー206クーペだ。ただのCM。こんなでも、なにか重要な記録ということになるんだろうか?
テープの巻き戻るような音。少しの間。再び、ざわざわと鳴る。質の悪い録音機を空気が撫ぜる音だ。録音自体は続いているみたいだけど、意味のある音はまったく入っていない。
どうやら、このテープを読みつづけるのは無意味らしい。ぼくは古びたビデオテープから長い舌を離し、ひとまず「舌読み」を終える。
他のテープをざっと舐めても、内容はほとんど同じみたいだ。たぶん、テロ関連のニュース映像を撮り貯めたものばかりだろう。ラベルは貼っていないけど、たぶんそうだと思う。全部、五年以上前の映像ばっかりだ。
九〇年代式の古い洋室の中をもう一度見回す。白を基調にした、フローリング張りの清潔なワンルームだ。縦に長くて、しかも両側の壁あたりに荷物が散らばっているから、なんだか通り道みたいで落ち着かない。清潔で、ひっそりとしていて、誰かの住んでいた気配はない。でも、ドアノブあたりにはぬくもりのようなものも残っている。「舐念法」を試す価値はあるかもしれない。どうだろう、ちょっと微妙だ。体調もすぐれない。「三十六式」を使うだけの体力は残っていないと思う。まあいい。探索の方法は他にいくらでもある……。
「まあいい。探索の方法は他にいくられもある……」
と、ぼくは思ったことをそのまま口に出す。
冷蔵庫を開ける。新製品のとうもろこしビール、百円のオレンジワイン、ヌード枝豆、レンジDE焼魚、ヨーグルト豆腐……安く酔うためのものだけが揃っている。封を切られたヨーグルト豆腐は少し乾いているが、問題はなさそうだ。食べてみる。間違いない。ヨーグルトの味がする。
しばらくたって、口の中から腐臭がする。アロロロ! そういや電気は止められていたんだ! かれこれ一ヶ月は腐りっぱなしだったのに、ぼくはなんで食べてしまったんだろう! 流しへヨーグルト豆腐を吐き出す! 不健康な黄色のチーズ片がぼくに「こんにちは」を言う!
ところで、とぼくは口を拭いながら考える。なぜ彼は豪華な宿舎があるというのに、こんな貧乏くさいアパートを借りていたんだろう。彼は有能な特殊能力者集団「○者」の中でもさらに特別な「語り部」だ。宿舎以外に家を持つにしたって、フリーヶ丘あたりに住むことも簡単だった。それとも、なにかどうしようもない事情があって、こんな寂しい下宿を潜伏先にしていたのだろうか?
ぼくは「どうしようもない」という語の突きつける切なさにオモラシしそうになりながら、大家から借りた彼の部屋の鍵を手の平にもてあそぶ。その合鍵には、町の合鍵屋さん「ミスターミニット」のトレードマークである男のイラストが書いてあって、失踪した男の部屋で見る絵としては、和みすぎる。おい、おまえ、笑ってんじゃねえよ……ぼくの囁き声に男は微笑を返す。というか、もともと笑っている。
ところで、ぼくは辺りを見回す。
この部屋にはCD、MD、MO、フラッシュメモリー、カセットテープ、ビデオテープ……と記録媒体はたあくさんある。それなのに、まったく奇妙なことなんだけれど、再生装置がない。テレビもビデオもHDDプレイヤーもない。DENONのコンポもあるにはあるが、アンプとスピーカーだけで、ラジオしか聞けない。パソコンもデジカメもない。再生装置を持っていったか、盗まれたか……それともまさか、ぼくの「舌読み」をあてにして記録したのか? 一応、再生装置があったらしいと思わせるもの、たとえばAVケーブルなんかがそこいらにたくさん散らばってはいるんだけど……ところで、ぼくは長らく、「AVケーブル」をいやらしい棘のついた鞭かなにかと勘違いしていた。
とにかく、もうちょっと「舌読み」をしてみよう。ビデオを取り、ヘッドからテープを引っぱり出して舐める。でも、舌先にピリリと電気の走ったような違和感を覚える。「舌読み」のやりすぎだ。舌細胞の動きがてんでばらばらで、上手にうねるのは無理そうだ。どうやら、「舐念法」もできそうにない。さっきやらないでよかった! やってたら死んでたろう。
「さっきやらないれよかった! やってたら死んれたろう」
と、ぼくは思ったことをそのまま口に出す。
ところで、いまのぼくに読めそうなメディアは文字通り「読めるもの」、たとえば……そう、ノートだ。
ほとんどのノートはビデオテープの管理に使われているが、何冊かは彼が語り部としての仕事に使う台本の草稿用だったみたいだ。草稿ノートの表紙にはそれぞれタイトルがふられている。そのうち、『ジャンボジャッポン黎明記~耳クソねちゃねちゃ族VS耳クソぱさぱさ族~』というタイトルが目に入る。たしか、さる高名な自称哲学者の日本史研究論文によると、日本の先住民族は本州から追い出されて南と北に散ったため、両者には遺伝的共通点があるという。このノートはそれを「語り直し」用に脚本化したものだろう。彼とはそんなに任務の話をしないけれど、この文書のことだけは小耳には挟んでいた。それが今、ここにあるわけだ。
一ページ目を開く。
デッカイドウに住む一族とチッサナワに住む一族には奇妙な共通点があるという。
彼等は共に酒に強い。
彼等は共に肌が浅黒い。
彼等は共に二重瞼である。
彼等は共に眉毛が濃い。
彼等は共に耳クソがねちゃねちゃである……。
ノートを閉じる。それしか書いていない。字が汚いし、期待していたほどの内容でもない。もっとも、語り部である彼が「語り直し」をすれば、それを聞いた者は語られた内容を信じることになるから、長々と論理立てて説明する必要もないんだろう……。
別の一冊、『アバランチ』と銘打たれたジャポニカの「じゆうちょう」を開く。罫線の無い白紙に大きな字で三行に渡り、「ゆっくり/自分のチンポで/一歩ずつ」と書いてある。それも、一ページ目、いきなりだ。
彼は字が汚いから、それはむしろ、「自分のテンポで」と書かれているのかもしれない。でも、彼が下ネタを書かないという確証はどこにもない。ぼくにはそれが「チンポ」なのか、それとも「テンポ」の書き損じなのか、区別がつかない。ただ、もしも「チンポ」なのだとしたら、彼が「一歩ずつ」を見逃すはずはなく、「インポずつ」と駄洒落を重ねるはずなんだけれど。
わからない。なにもかもが。これは語り部としての仕事なのか、単なる趣味か、それとも、狂ってしまったのか……。
「終わったかい?」
人生の深い悲哀をユーモアで包んだような声。振り向くと、玄関の壁に寄りかかる大家の姿が真夏の逆光でシルエットとなっている。ずんぐりとした体型をのぞき、すべてがハードボイルドだ。
「いえ、まらこれといった証拠は……」
「証拠ねえ」と、大家はシルエットのまま入ってくる。「見つからなければ、失踪としては成功ってことだな」
「そうなんれすが……ぼくも見つけないことには困るんれす」
「自殺志願者かね?」
「いくらなんれも、それはないと思います。れも、そうならないためにも、早く見つけないろ」
シルエットは笑う。
「そうだが、もしも自殺じゃなければ、詩人だな。完全な失踪なんて、詩人の仕事以外の何物でもない。そうだろ? ぜひ一度、お目にかかりたいもんだ……おっと」
大家のシルエットは上がりかまちにつまずく。まるで人生そのものにつまずいたとでもいうような、ため息混じりの苦笑が聞こえる。
「完全な失踪は見ることなんてできないな」と、シルエットは続ける。「太陽や死がそうであるように」
「そうれすね。れも、完全な失踪が自殺じゃないことを祈りますよ」
シルエットはぼくをじっと観察している。そして、「自分のチンポで?」と訝しげに声を立てる。アロロロ! ぼくは慌ててノートを隠す。
「これはぼくんじゃないれすよ、シャイ谷の書いたものれ……」
「ああ、そう。それならいいんだが。子供じみているな」
表情の見えないシルエットはとても寛大で、完璧なハードボイルドの高みからぼくを見下ろす。「これはテンポです」などと言い訳することはできない。逃げ出したいような気持ちになる。
「あの、ここにあるものをみんな持ち出していいれしょうか?」
「みんな? なんのために?」
「持ち帰って、じっくり読みたいんれす。ちょっと読みきれないれすし、同僚の失踪はやっぱり大事件れすから」
シルエットは少し考え込む。ぼくは彼がハードボイルドらしい無頓着を発揮して、店子の持ち物を他人任せにすることを願う。でも、シルエットは言う。
「駄目だな。そいつはできない」
「なぜ? 身元なら明かしたれしょう」
「忘れ物だけが、その人間のすべてだからさ」
その言葉と共に日が沈んだらしい。玄関から差し込んでいた逆光が消え、大家をシルエットから解き放つ。そこには完璧にハードボイルドな笑顔が浮かび上がり……アロロロ! 違う! 普通のオッサンだ! 辛子色のトレーナーを着ている。それはあまりにダサいので、辛子入りのトレーナー(綿80%・辛子20%)であってもおかしくないくらいだ。
あろ? それどころか……大家の額に緩やかな放物線を描く生え際は左右対称じゃなくて、微妙にズレている。決して富士額だからじゃない。それはでっち上げに頼ったツケ、人造悲劇だ。
「HG?」
と、ぼくは思わずからかい混じりのドイツ語を漏らす。その一言で大家は自分のカツラが致命的な「あっち向いてホイ」をしていることに気付く。大家自身、気付いてはいるが直すに直せない、そんな微妙な心境を人類史上かつてなかった表情で表し、急におどおどした態度に変わる。ぼくは彼のハードボイルドが、逆光のまやかしだったと気付く。
「お願いしますよ」と、話題を変えなかったのはぼくの優しさだ。「こんなもの取っれおいらって、なんにもならないれしょう? あなたが法的責任を問われるころはありません。ほら、これがライセンスれす」
ぼくが差し出した○者のIDカードを、大家は両手で受け取り、じっと見つめる。たぶんそこに「国家認定捜査官」の文字を見留めたはずだけれど、大家の顔はますます曇る。
「しかし、最近はプライバシーとかがうるさいし、もしも訴えられたら……。私なんてほら、ただの大家だから」
そう言って、大家は泣き出しそうになる。ひどく弱っているようだ。ぼくはこのままシャイ谷の遺留品について話をつづけようと思ったが、自分の中のサディストを押さえつけることができない。
「なんれ?」
と、ぼくは嘲笑を浮かべる。大家はというと、金魚のように口をぱくぱくとさせている。彼は静かな心理戦の末に、自分の秘密がなんとか――傷だらけではあっても――生き残るようにと願っているらしい。
一体、誰かのHGを見過ごすのは優しさだろうか? イエス、と人は言うだろう。HGはHGであることによってすでに裁かれているのだから。しかし、HGが偽りによって非HGのフリをするなら、それを徹底的に隠しとおすことこそHG側の礼儀ではないだろうか? まして、カツラを右向け右させるという無様なミスを犯しておきながら、相手の憐れみに居直るなんて、HGの風上にも置けない。大家の淡い期待は叶わないだろう。ぼくはそういう厚かましさを好まないし、なにより、思ったことをそのまま口に出す癖がある。不毛の頭皮は理不尽な正直さによって完膚なきまでに白日の元に露されるだろう。
「なんれ権限がないんれすか。あなたは大家れしょう?」と言ってから、ぼくはゆっくりとつけ加える。「それとも、HGだかられすか?」
「そんな、まさか、そんなことを言うなんて」
と、大家は口から泡を吹く。
「正直は美徳れすよ」
ぼくはそう言うと、大家の頭を優しく撫で、カツラを外す。母親が赤子のおしめを脱がすように、優しく。大家の頭は思ったよりもすべすべとしている。
「ほら、綺麗な頭皮をしてるじゃないれすか。隠さない方がいいれすよ」
偽りの髪を失った大家は、奪われた者の手つきで額を覆う。はじめは恥じらいをどうしようもないという様子だけれど、頭皮に感じる風や正直者のみが受けられるあの暖かい視線のせいで、表情はJOJOにほぐれる。古い皮を脱いだ爬虫類のように柔らかい顔になる。
「わかったよ」と、大家は言う。「この部屋のものは持って行くなりなんなり、好きに使うといい。その合鍵はしばらくの間、君に預けるよ。責任は私が持つ」
「ありがろうございます」
ぼくはロンズデールのボストンバッグに入るだけのメディアを詰めると、大家に「さよなら」を言う。
「君、名前は?」
大家に呼び止められ、振り向く。さっきとは位置関係が逆転している。たぶん、大家から見たぼくの姿は、真夏の逆光のためにシルエットだけとなっているはずだ。
「さっきIDカードを見せたれしょう」
「違うよ、あれは職業名だろう? 私は本名が知りたいんだよ」
「他に本名なんれありませんよ。それがぼくの持っている唯一の名前れす」
「へえ! そうかい!」と、大家は戸惑う。「変わった名前だねえ」
こんなことは慣れっこだ。ぼくはにやっと笑う。大家もぎこちない微笑みを返す。
「それじゃ、さようなら、探索者!」
大家はその言葉を繰り返す。まるで、名前を呼ぶことでぼく個人の特性が立ち昇ってくるとでもいうように。でも、うまくいかないみたいだ。ぼくはその反復が止まないうちにドアを占める。ドアはかちゃりと、秘め事めいた音を立てる。カッコいい!
☆
フリーヶ丘の宿舎の部屋で、ボストンバッグを開ける。持ち帰ったメディアは膨大な量だ。「舌読み」はそんなに楽ではないから、すべてを読み終えるには、すごく時間がかかるだろう。
適当に一つのメディアを取る。CD。幸い、デジタルデータなら、磁気テープよりは読み取るのが簡単だ、アナログはゴチャゴチャしすぎる。
制作時期はかなり古いみたいだ。ラベルには『お菓子考』と銘打たれている。シャイ谷の声ではあるけれど、「私」がそのままシャイ谷を指すかどうかは不明。他人の論文を語り直しただけかもしれない。
傑作揃いのブルボン「袋ビスケット」シリーズから四天王を選ぶとしたら、三つがすぐに決まるということに異論はないだろう。
まず、コクのあるビスケットをホワイトチョコで優しく包んだ「ホワイトロリータ」。続いて、かすかなレモンの香りで食欲をそそる「バームロール」。そして、折り重なったパイ生地の割れる音が繊細な「ルマンド」。
しかし、ここからが問題だ。「ラテショコラ」、「チョコリエール」、「レーズンサンド」、「ソフスイート」、「ルーベラ」……候補は多いが、どれも決め手にかける。
異論反論はあるだろうが、私はあえて「レーズンサンド」を推したい。というのは、他がほとんどチョコ菓子であるのに、これだけはレーズンというフルーツが入り、栄養学的見地からもバランスが取れるからだ。個性的であればよいというよりも、四天王を並べて見たときのバランスを大事にすべきではないだろうか。
その点、明治製菓のバランスを欠いた商品ラインナップといったら!
私は先日、「クッキーinアポロ」を開けた。フタの裏には「アポロのフチのギザギザは何個あるでしょう?」と書いてあった。私はクソ真面目にも、アポロを指に持ち、熱心に数えた。数えている間にも、チョコレートが融けて指がベタベタになる。それでも、私は十七という数字を数え上げた。
答えは箱の底に書いてあるらしかった。私はアポロをすべて平らげ、箱の底を見た。十八山だと書いてあった。
起点を指で押さえておかなかったから、間違えたのだろうか? ともかくも少し不愉快になり、箱を閉じようとすると、ベロを固定する部分の切れ込みの下に、「買ってくれてありがとう。」と書いてあるのを見つけた。
「売女が!」
私はそう叫び、箱をゴミ箱に叩きつけた。空になった箱は、思ったよりも大きな音を立てた……。
しかし、そうは言っても、お菓子がわが国の主要産業となることは間違いない。
他にCDから読み取れるのは、お菓子の商品名の羅列と紹介。そして最後に合計金額と消費税、買った店の名前、日付が読み上げられる。レシートの代わりだろうか? ○者はその特殊能力を発揮するため、血中インシュリン濃度を上げておかなくちゃならない。そのために大量のお菓子が必要だったと思えなくもないけれど、それをあえてメディアに残す意味はあるんだろうか、しかも日記みたいな文章とともに? なにかを意図していたのか、それとも狂気か?
ところで、シャイ谷キメ朗は単なる○者ではない。語り部であり、それと同時に、哲学者でもある。
中華料理屋を訪れ、「ここの小籠包うまいよ」と言ったら、「え、三段論法?」と冗談の気配すら見せずに聞き返してきて、そのままほうっておいたら店長の議論力を確かめるために論争を吹っかけてしまう――それほどの哲学者だ。その彼が、いきなり『お菓子考』という論考を物するという可能性もなくはない。語り部としての仕事の一つかもしれない。どちらとも取れる、ということだ。
「ろちらとも取れるということら」
と、ぼくは思ったことをそのまま口に出す。
ところで、『お菓子考』と銘打たれた「語り」入りCDの最後部、レシートの読み上げらしいところを参考にすると、二つの重要事項がわかる。
まず一つ目、買い物は「お菓子の町おか」というチェーンのディスカウント菓子屋でなされたということ。支店名までは言われなかったが、シャイ谷がひそかに借りていた下宿の近く、東京都川底区台風ヶ淵の駅前に一店舗ある。たぶん、そこのことだろう。
そして二つ目、買い物は総額で十二万飛んで八円だということ。一品がたかだか百円程度の店でそれだけ買うということは、店員の印象に深く刻まれているにちがいない。
ちなみに、買い物をした日付はシャイ谷が任務をしなくなった日の数日前である。失踪するにあたっての食料としたという可能性は大きい。食料を用意して自殺するというのもありそうにないから、たぶん、どっか遠いところに出かけたのだろう。それならそれで一安心だ。探索者のぼくにかかれば、遠いところに行った人間の後を追うほど楽なことはないのだから。
ぼくはすぐさま「お菓子の町おか」の台風ヶ淵支店に向かう。
その店は台風ヶ淵駅前の雑然とした商店街にある。お菓子が山と積まれた店先には、それなりに有名なメーカーの商品が一箱三十円ぐらいの捨て値で売られている。もっとも、賞味期限が切れる寸前の商品や、季節外れの季節限定商品ばかりである。
「ああ、あのお客さんね。覚えてるよ。一、二ヶ月前に届けたよ。名前は忘れちゃったけれど」と、忙しげにレジを打ちながら、店員のおばさんは答える。六本の束になった前髪はカールさせてあり、植物のおしべを思わせる。力がこもりすぎ、かえって人を怯えさせる類の笑顔。
「普段はそういうことしないのよ。あんまり注文が多いもんだから、店長命令でね」
「そうれすか。じゃあ、彼の家まれ届けたんれすか」
「そうよ、私が2tトラック転がしてね」
「支払いはこういうカーロれした?」
と、ぼくは○者に配布されるクレジットカードを見せる。
「いえ、現金だったわ」
「そうれすか、おかしいな……こんなころ聞くのもアレれすが、彼の生活は苦しそうれしたか?」
「さあ」
と、おばさんはまったく興味なさげにお菓子をレジ打ちし続ける。店内は狭くって、まるでウナギの寝床だ。列になった買い物客たちは苛立たしげに舌打ちをする。といってもほとんど全部が女だから、ぼくが本気を出せば全員KOできるのだ、こちとら仕事だ、文句があるならかかってこいや!
「かかってこいや!」
と、ぼくは思ったことをそのまま口に出す。アロロロ! しまった! でも、大丈夫。店内の客はみんなドン引きになっているため、ほんとうにかかってくる人はいない。
ところで、ぼくは調査のためにも、おばさんの注意を惹かねばならない。
「彼は特殊な仕事についれるから、現金は持っれないはずなんれすが……」
「そう? 万札でドンと渡してくれたわよ」
「万札? そんなはずないらあ!」
「なによ、じゃああんた、私が嘘ついてるっていうの!」
ぼくには思っていることをバカ正直に言語化する癖があり、それがレジのおばさんを苛立たせる。おばさんはレジを打ち終えて空になった買い物カゴをぼくの頭にかぶせると、バーコードリーダーの赤光線でぼくの目を狙い打つ。
「ちょっと……勘弁してくらさいよ。すいませんれした」
「できないね! あんた、私が泥棒だって疑ったろう? 許せないよ!」
「そんなの被害妄想ら! やめれ下さいよ!」
ぼくは執拗なレーザー攻撃を避けながら、おばさんの髪型を誉めまくる。JOJOにおばさんの怒りは収まり、「欧陽菲菲みたいれすよ」という誉め言葉が決着をつける。おばさんは使い慣れた銃をしまうように、バーコードリーダーを下げる。
「ああ、わかるかい? これ、なかなか気付かない人多いのよ。あんた、わかる人だね」
「ええ。わかりますよ。絶妙なバランスれすよね。ケープを何本使ったらそうなるんれすか?」
おばさんは指を三本たて、ショッキングピンクの唇で投げキッスをする。ぼくは一口ゲロを軽く飲み込む。
「それで、彼はろんな様子れした? 暗そうれしたか? 思い詰めらり……」
「明るくていい子だったわよ」と、おばさんは再びお菓子のレジ打ちを始めながら言う。「でも、変わった服着てたわね」
「変わった服? おかしいら、彼はいつも全裸なんらが……」
「そんな人いないわよ、いくら真夏でも。いたら私、逃げ帰ってるもの」
「いや、ほんとうなんれすよ。彼は絶対に服を着ないんれす。御世話になった人の葬式れも、裸に黒ネクタイれ行くんれすよ」
「そんなわけないでしょ。捕まるわ」
「ほんとれすってば。そのときはネクタイの剣先れ股間を隠して乗り切ったんれすから」
おばさんは怒ったらしく、ふたたびバーコードリーダーの赤光線をぼくの目に向ける。アロロロ! なんて怒りっぽいんだ!
「すいません、すいません……じゃあ、ろんな服を着てたんれすか?」
おばさんは彼女のスゴイ銃を下げ、満足げな笑みを浮かべる。
「こんなよ。真っ白い奴。腕が動かないから、支払いには苦労したけどね」
そう言って、おばさんは自分の身体を抱きしめるような格好をする。そう、それはまさにあの瘋癲病院の重症患者が着させられる拘束衣だ。
「拘束衣……? 鼻頭ら!」
ぼくはあの狂人の名前を思い出し、あいつがシャイ谷の失踪に関わっていたことを痛感して嫉妬に悶える。
「くそっ、あのガイキチめ! 病院にいたんじゃないのか!」
ぼくは駆け出す。おばさんが呼び止める。
「あんた、名前は?」
「探索者!」
ぼくはそう言い残し、官給セグウェイにバルルンと電源を入れる。原理的には一輪車と同じでも、リミッターを外してあるセグウェイは、古いバイクのような音を立てて、おばさんを置き去りにする。ぼくは自分がハードボイルドな探偵になったような気分になる。

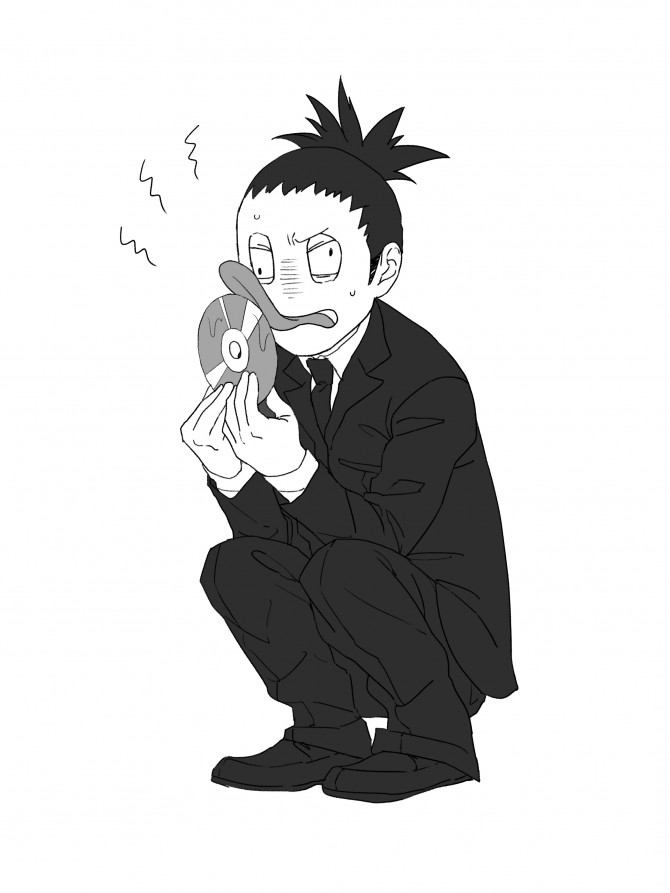
























"ちっさめろん(2)"へのコメント 0件