エアコンの設定温度を四度下げた。一度ではどうしようもなく、二度でも効果が見込めなかったので四度下げたのだった。雨も降らず蒸し暑い日が続いていた。中学校は長期休みに入り、夏も盛りとなっていた。暑いのは苦手だ。何もかもが面倒になる。ギラついた日差しの下とクーラーの効き過ぎた室内の往復で体調も芳しくない。だからと言って今日が普段よりも特別に暑いというわけではなかった。暑いは暑い。毎日暑い。そろそろ地球も太陽系のハビタブルゾーンからはみ出してしまうのではないかと心配してしまうくらいに。しかしこの室内に限って言えば、温暖化の原因はもっと個人的な話であった。つまり、今ぼくの目の前で苛立っているよく日に焼けた新参者二人のことだ。
彼らと比べると古参ということになる洋次郎がエアコンの駆動音に反応して一瞬頭を持ち上げるが、目の前の二人から目をそらすようにすぐペンを動かし始める。ぼくは彼がいつものように口を動かさぬまま文句の視線をこちらへ向ける前に小さなブランケットを手渡した。洋次郎は夏でも長袖の服を着ている細身で色白の寒がりだった。
ぼくの個人塾には学習机が四つある。それらは小学校の給食の時間のように向かい合わせにくっつけられて置かれている。これまで洋次郎がここへ通ってくる日は生徒が彼一人だったので、ホワイトボードに向かうように彼が座りぼくはその前が指定席だった。今日は僕らの背にホワイトボードがあり、目の前には運動部を引退したばかりの少年が二人座っている。日焼けでズルムケになった顔には汗が滲み出していて、カラフルな半袖シャツをさらにたくし上げノースリーブにした彼らの幼さの残る二の腕は小麦色どころか焦げ茶色と呼ぶべきだろう。二人のシャツはどちらもヨーロッパのサッカークラブのユニフォームだった。肘にまだ生々しい擦り傷があるのが浩介、ひとつ数式を書くたびに頬にできた真新しいニキビを触らずにはいられないのが雅彦。そんな特徴は限定的なものであって彼らのことを説明するにはもう少し普遍的な点を並び立てるべきだが、それはこの物語に関係のないことなので省略する。
この塾はいわゆる進学塾ではない。どちらかといえば学校の勉強についていけない子供達に向けて開かれている。もちろんよくできる子が来てもいいのだが、それなら明確なノウハウと情報の蓄積があるメジャーな進学塾を勧めることにしているので、今通ってくれている生徒はやはり学校教育が苦手だという子供が多い。洋次郎にしても初めはアルファベットから教えなければならず、それを覚えこませるのにも一ヶ月を要した。そして次のことを教えれば前に覚えたことをすっかり忘れてしまうので、なかなか根気が必要だった。そんな彼も今では学校のテストで平均点を取ることができるようになった。しかしどうやら彼にはぴったり平均点を取るという才能があるようで、近頃は成績の伸び悩みに苦しんでいる。三年生の夏休み、周りが高校受験へ向けて本格的に勉強を始める今後が心配だが、ここまでできればそろそろ普通の進学塾に通ってもいいんじゃないというようなことを冗談で仄めかしてみてもうちへ通いたいと言ってくれることは素直に嬉しい。だからもう少し力になってやりたいものだ。新入塾者の二人を洋次郎と同じ曜日に受け入れたのは、それが彼のカンフル剤にでもなってくれればいいと思った部分もある。勉強は一人でするものだが、やはり周りで同じように励んでいるライバルがいることはぼく自身も刺激になった経験があるから。しかし洋次郎はどうだろうか。本人も母親もあまり周りを気にしたり影響を受けたりするタイプではないと言っていたので集中を乱すだけになる恐れもあったが、どうやらそれなりに意識はしているみたいだ。もちろん彼がそれを態度に表すことはない。ただこの春から彼を見ているぼくには装われたその無関心が手に取るようにわかり愛しくもある。人間とは不思議なものだ。本人にさえわからないことが他人には丸見えだったりすることがあるのだから。特に子供は素直で可愛らしい。大人の装いはいやらしくて鼻につくので苦手だ。そしてみんながみんな何かしらの演技をしなければならないこの社会も苦手だった。それでも塾協会やその他交流会に参加するにつれ、それぞれがそれぞれの大切なもののために日々を生きているようなことがようやく少しわかり始めた。厭世的な大学生だった僕も少しは成長できたのだろうか。良くも悪くも。いつまでも子供のままでいたいものだが、それを許されるような才能はなかった。それはぼくの悪い言い訳でしかないのだが。そもそも何について大人や子供などと言って区別しているのか。自分が気に入らないものだけを見て全体をこうだと決めつけていたぼくが一番子供だったのだろう。そうは言っても、綺麗なものだけを見て生きていければどれだけ心地よいことか。そんなことを言った時は友人に「おまえは薄っぺらな人間だ」とボロクソに罵られたのだが。その友人が言うには今の子供たちは大切に育てられすぎているらしい。できるだけ失敗を経験しないように大事に大事に世に送り出され、そして自分では何も考えられない子供のままの大人ができあがるのだとか。大切なことを何も知らないまま。もちろんそんな人ばかりではないだろう。それに自分で何も考えなくてもよい社会になれば、それはそれで幸せなのではないか。もちろんそれを受け入れられるほど社会が発展していればの話だが。幸い日本では多くの人が明日のパンを心配する必要があるわけではなく、ぼんやりしていてもそれなりに生きていける。努力するのが恥ずかしく、一生懸命に生きるのが難しい社会になったなんて言っても、それは言い訳でしかない。現に一生懸命生産性のある日々を送っている人がいるのだし。ようは人目を憚らず夢中になれるものに出会うことができていないのだろう。規定された中でやることをやっていれば生きていけるのだから。そんなことを話すぼくらだって、結局迷子で何も見つけられていないのだけれど。
話が逸れた。酒の席での何も成し遂げていない若造の薄っぺらな会話なんてどうでもいい。それに今の子たちはぼくなんかよりもよっぽど頭を使い真剣に生きているような気がする。情報が溢れた世界に小さい頃から慣れている彼らはより現実的に自分の将来を設計しているように思えるのだ。ぼくみたいに何もしない夢想家よりもよっぽど大人。むしろ教えられることの方が多いくらいで申し訳ない。そんなことよりも、とぼくは時計を見上げた。あと五分で時間だ。今回のテストは夏休み前の数学のテスト問題を数字だけ変えたものなのでどれも解き方を教わっているはず。運動部の二人はともかく洋次郎にはそれなりに詳しく解説し直したので高得点を期待したい。そんな彼はもう解き終わって膝の上で毛布をぎゅっと握りしめたまま無表情で俯いている。ちゃんと時間いっぱい確認してくれているのだろうか。計算ミスの多い彼には解き終わってもしっかりと確認することを何度も言っている。洋次郎の頭がコクンと落ちて引き上げられた。なんてことだ、目を開けたまま居眠りをしていたに違いない。
タイマーが鳴った。しかし運動部の二人はそれが聞こえないかのようにペンを動かし続ける。やる気はあるんだな、と感心してから「はいそこまでー」と僕は二人の頭に広げた手のひらを置いた。それでも二人はしばらくペンを動かしていたが、無言で頭に手を置き続ける初対面の大人に観念したのかやがて照れ臭そうにペンを机に転がした。
「おつかれさま。自信は?」
「ご覧の通り」
そう言って自嘲気味に自分の答案を振ってみせる浩介。雅彦は見覚えがある問題が解けそうで解けなかったのが悔しいのかじっと答案を睨みつけている。やっぱり運動部は負けず嫌いだなと少し期待を抱いて二人に赤ペンを渡した。洋次郎は自分のペン入れから以前僕があげた赤ペンを取り出して採点の準備をする。
「じゃあさっそく問一から見てこっか」
「自分でやんの?」
「そうだよー。不正なしやからな。シャーペンしまっとこっか」
「えーめんどくさ」
そう言いながらも素直に従う二人。ああだこうだ文句は垂れるが拒絶はしない。事前に親から聞いていたよりも随分とやりやすい。それから一つずつ解説しながら答え合わせをしていくが、途中で集中力が切れることもなかった。たぶんこの二人は問題がわからないのではなく、そもそも知らないのだろう。因数分解ひとつ解くにしてもどうしてそうなるのか積極的に尋ねてくれる。僕は黙々と採点をする洋次郎に心の中で、こいつらは伸びるぞ、と言ってやった。その時彼は何も感じずにいられるだろうか?
「とりあえずこんなもんかな。さて、何点になった?」
それぞれが問題ごとの点数を足し合わせることに集中し、しばらく教室内はクーラーの音だけが響いていた。やがて計算が終わった浩介が隣の雅彦の答案を覗き込もうとするが、彼は机に体を被せて隠してしまう。
「なんだよ見せろよ」
「合計出たらな。おまえ何点だった?」
「まさが言ったら教える」
洋次郎は目に掛かる重たい前髪の影からそんな二人をじっと見ていた。羨ましいのだろうか。煩わしいのだろうか。僕はそっと彼の点数を覗き見て微笑んだ。八十九点。頑張ったじゃないか。まあ、先週じっくり解説したばかりだからそれくらいは期待していたのだが。今回は裏切らなかったな。しかし間違えたものがことごとく計算ミスだ。もったいない。解き方的にはどれも正しいので新参者二人に満点を突きつけることもできたのに。
「できたー?」
「ちょっと待って」
「おせーよ」
「うるせ、おまえが邪魔するからだろ」
二人の前で洋次郎は微動だにせず座っている。この環境は彼に少し酷だろうか。少しは仲良くなってくれればいいのだが。やがて雅彦も採点を終え、浩介に見えないように手で隠して僕にだけ見せてくれた。僕は頷いて彼の答案を裏返させた。
「おつかれさま。うん、思ったよりいいんじゃない?」
「先生それは俺らのことバカにしてません?」
「お、賢いじゃん」
「ひでー!」
「洋次郎何点だった?」
雅彦に言われ洋次郎は黙って自分の答案を押し出した。それを見て二人は「すげー!」と素直に彼を褒めた。洋次郎は当然だという顔をしていたがその頬に赤みがさしていることを僕は見逃さなかった。
「まあさ、もっかいやったら二人もこれくらいとれるっしょ?」
「えー、自信ない」
「いや自信持ってよ。結構詳しく解説したじゃん」
「今なら解けるかもしれんけど寝たら忘れるもん」
「そりゃ困ったな。どうすれば忘れないと思う?」
うーん、と浩介は少し考えて「毎日やれば」と言った途端にしまったという顔をした。僕はにっこり笑って引き出しから同じテストを取り出した。
「おー、やっぱ賢いじゃん。そうそう、毎日繰り返してたら忘れないと思うよー。ということで、同じ問題用意しといたから、また明日も解いてくれる?」
「んー、気が向いたら」
「ま、期待してるよ」
「でも他の勉強もしないといけないし」
「それも結局忘れちゃうでしょ?ならとりあえず一つしっかりとできたほうがいいんじゃない?」
んー、と顔を見合わせる二人にとりあえずテスト用紙を押し付けて時計を見た。
「うん、思ったより優秀だったからちょっと時間余ったね。どうだろ、二人はまた来てくれる?」
「まあ、そういうことになってるし」
「よし、じゃあ次からランキングつけるから」
「えー!そんなん絶対洋次郎が勝つじゃん」
「わかんないよー?問題と答えは今日あげるから、それを今度までに覚えてきたら全部解けるし」
そう言って僕は三人に新たなプリントを配った。二人はそれを受け取ってまじまじと見る。
「全然わかんね」
「解説も書いてあるからとりあえず次までにやってきてくれる?」
「うん。気が向いたら」
「洋次郎もそれでいい?」
「別になんでも」
おっけー、と彼の頭を撫でて僕はノートパソコンを開いた。
「うちのホームページのここに常時発表してるからね」
「うわ、マジじゃん。これ個人情報でしょダメだって」
「パスワード付きだから大丈夫。サイトとパス教えるからメモってー」
僕が作ったランキングページはそれぞれの名前と点数の表ともう一つ、それと連動する折れ線グラフもついていた。さっそく事前に聞いていた期末テストの点数の次に今回のテストの点数を追加する。点だけだったグラフは二回目の場所に合計点の平均をとった値で新たな点を打ち、線が斜めに伸びた。三人とも右肩上がり。これを維持したいものだ。
「開けた?」
三人はそれぞれのスマートフォンでサイトにアクセスし、表示された表を眺めている。一番上の黒い線が洋次郎、少し間が空いて雅弘の青線があり、そのわずかに下が浩介の赤線だった。
「次来たら抜いてやるからな」
「無理だろ、だって浩介もう答え落としてるもん」
「あ、マジじゃん」
浩介は慌ててさっき僕が渡したプリントを床から拾い上げてリュックに詰め込む。今度までにクリアファイル買っとこうと僕は思った。
二人が先に自転車で帰り、洋次郎と親の迎えを待ちながら将棋を指していた。初めはへっぽこだった彼も今じゃなかなか悩ましい手を打つようになってきて下手を打つとそろそろ負けるかもしれない。それに彼は勝ち負けなどどうでもいいというような態度を取りながら意外と負けず嫌いだということも分かってきた。いい勝負をして負けると「もう一回」と熱くなることが増えた。自分の思い通りにこちらの駒を誘い出すと顔のニヤケが抑えられないところも彼の可愛らしいところだ。まあ、まだ負けてあげないけどね。
「すみません、遅くなりました!」
扉を開けて彼の母が入ってきた。いつも通りどこか焦ったように靴を脱いで上がってくる。もう少し落ち着けばいいのに、と思うがさすがにそんなことは言えない。ただただ運転は気をつけて欲しい。
「どうでした?」
本人に訊けばいいのにと思いながら僕は同じ質問を前に座る洋次郎にふった。彼は興味なさそうに将棋の駒を片付けながら「んー」と言ったきり。
「まあ結構集中してたよな。点数もよかったし。一緒にやってけそ?」
「はい」
「ほんとですか?今日行く時いつもより用意が遅くて。やっぱり行きづらいのかなって思ったんですけど」
「そんなことない」
「そうだったじゃん!行くよって言っても漫画読んで」
「おなかすいた」
「もう。先生、ほんとに大丈夫そうでしたか?」
「大丈夫ですよ。これから競い合ってもらうんで。負けんなよ洋次郎」
「え、なんですか競い合うって。あんた大丈夫なの?」
「大丈夫。なあ、おなかすいたって」
「先生、何を競い合うんですか?」
そんなの学力くらいしかないだろうにと思いながら僕はさっさと靴を履いて待っている洋次郎に「言っていい?」と尋ねる。
「秘密」
「だそうです。夏休み明けまでちょっと待っててください」
「えー。なんで秘密なのよ。恥ずかしいの?」
「ご飯できてるの?」
「できてるできてる。すみませんね先生、それでは、またお願いします」
「はーい、帰り気をつけてくださいね」
「ありがとうございます」
静かになった部屋で僕はコーヒーを入れて一服した。さて、どうなることやら。洋次郎もやる気を出してくれるだろうか。その前に、もう少し二人と打ち解けてくれたらいいのだが。中学校というのはまだ学力で分けられていないからいろんなタイプの子供が混じってる。そんな生徒たちを教える先生は大変だろうなと素直に思う。大学の同期で中学の先生になった田辺は今休職中らしい。何かあるとすぐ胃が痛くなるタイプだったからなあ。教育実習の時も日誌とかを丁寧にやり過ぎていつも帰りはあいつ待ちだったし、行きも余裕がないと焦るからかなり早く家をでる彼に付き合わされて寝ぼけたまま自転車を漕いでいたっけ。元気になってくれればいいのだが、先日iPhoneが壊れた時に連絡先を失ってしまった。訊こうと思えば訊ける相手もいなくはないが、そこまで親しかったわけでもない。いや、訊くべきか。僕にできることがあるとは思わないけど、友達だし。
LINEの友達を遡って田辺と繋がってる知り合いを探していると着信が入った。高校の同級生で同じく自分の塾を経営している直人からだった。
「あ、大地?」
「あいよー」
「もう塾終わったやろ?銭湯行かへん?」
相変わらず唐突だなと思いながら「別にいいよ」と応えてマグカップを流しに持っていく。
「じゃあとりあえずうちの塾に来てや」
そう言うと彼はさっさと電話を切ってしまう。いつもながらなんだこいつ、としばらくiPhoneの画面を睨みつけてから僕はマグカップを洗って教室に鍵をかけ車に乗り込んだ。
暗い道を一人で運転していると余計なことばかり考えてしまう。自分の選択はこれで良かったのだろうか、とか。そんなことを考えてみても進んでしまったのだから目の前のことを一生懸命にやっていくしかないのに。教師になることを選択肢から外したのは、教育実習やその他の関わりで現在の教育というものに疑問を持ったからだ。三十人以上も生徒を抱えていればひとりひとりに対応しきれないのはもちろん理解できる。しかし型にはめてこなすだけではこぼれ落ちてしまう子が出てしまう。そんな子がとっても素敵な才能を持っているのかもしれないのに、自分は落ちこぼれだと思い込んでそれを発揮する場にたどり着けないかもしれない。そんなことは誰でもわかっている。それでもどうしようもないのだ。熱意を持って生徒のことを心から思う先生もたくさんいるだろう。けれど、もっとできることがあるんじゃないかと思ってしまうのだ。しかし一人で塾を始めてみても、出来ることなんてそんなに多くない。目の前の誰かを助けることは出来ても、目が届かなくなればどうにもできない。教育者にできることなんて、ほとんどないんじゃないかと思ってしまう。結局自分の人生は自分でなんとかしていくしかないのだ。つくづく教育とは虚しいと思う。中学校までサッカーをしていた僕は高校サッカーを見るのが好きだ。しかし高校サッカーの監督もなかなか虚しい立場ではないだろうか。どれだけ情熱を持って指導しても部員たちは三年で必ず去ってしまう。プロチームの監督からは考えられないだろう。どれだけ熱心にチーム作りをしても毎年メンバーが入れ替わっていくのだから。いや、その時間はきっと部員たちの中に残り続けるだろう。卒業すればそれで終わり、そんなことはない。そうであって欲しい。どこまでも続く財産を残せれば。
僕は塾の他に昼間、幼児向けの療育施設で働いている。そこには主に発達障害と診断された子供達が通ってくる。発達障害という言葉は最近メディアでもよく取り上げるようになり世間の認知度も上がってきた。ざっくりと発達障害と言っても自閉症スペクトラムやADHD、学習障害など様々なタイプの子供たちがいる。それを個性と捉えるのか障害と捉えるのかは難しいところだ。僕自身もなかなか自分の意見を述べづらい。ただ、小さいうちにそう診断されてうちの施設に連れてこられる子たちの多くの問題は、その親にあると思う。多くの親が共通して教育意識が高く、心配性で余裕がない。それはそうだ、わざわざ検査にいかなければそういった診断は下されないのだから。そして何より、そういう親は固定観念に囚われている。こうでないとおかしい、これができないといけないという親の思い込みに巻き込まれ圧迫されてしまい、ますます塞ぎ込んでしまう子供たちをみていると胸が苦しくなる。かといってそれが個性だからと開き直ってしまうのも良くない。こういった子供達の親は不安のせいか極端な意見に傾倒しやすい。どうしてもみんなと同じようにできなければと厳しく育てるタイプと、個性という言葉に甘えてなんだって受け入れ考えることを放棄してしまうタイプだ。丁度いい具合にというのはどうしてこうも難しいのだろう。おそらく、結果だけを見てしまうからだろう。目の前のその子が今この瞬間に何を感じ何を思っているのかということを無視して、行為の結果にしか目が向いていないから。結局、自分の視点からしか子供のことを見ていないのだ。いや、こんな愚痴を考えたって仕方がない。僕は僕にできることを考えないと。しかし僕に出来ることといえば、目の前の子供と真正面から向き合うことくらいだ。そして小学校にも上がっていない子供たちに僕が今してあげられることが、その先の長い人生の中でどれだけの価値を持つのかはわからない。そんな結果の見えない行為を信じてやり続けないといけないのだから、教育とは恐ろしく忍耐の必要な仕事なのだろう。
いっそ、直人のような進学塾なら、大学受験というわかりやすい目標があり、合否で自分の為したことの成果もはっきりとわかる。つまり僕は、子供達のためにというモチベーションだけでは続けていくことがしんどくなってきているようだ。いけない。考えるな。ただ目の前の子供にできることをやっていけばいいのに。果たしてそうだろうか。それでいったいなんになるのだろう。やめろ。ほら、さっきのところを右だった。運転に集中しなければ。
ほんの少し後ろめたさを覚えながら直人の塾の隣のコンビニに車を停めビルの階段を上った。ドアを開けると目と口の大きな女性が迎えてくれ、奥で自習室を回っている直人を呼んできてくれた。彼女は愛と呼ばれているが本名かどうかはわからない。というのも直人と彼女が出会ったのはホテルの一室であり、デリヘル嬢として来た愛と意気投合した直人は気がつけば彼女に塾の事務を手伝わせていたのだ。なんて教育的な塾なんだろう。ただ、愛がとてもいい子なのは僕も感じている。大きな口を閉じていればかなりの美人だし。
「大地ちょっとこっち来て」
顔を見せるなり挨拶もなしに僕は自習室の奥の席へ引っ張っていかれた。背中合わせで机に向かう生徒たちの背後をそっと通り抜け、僕ももっと真剣にやるならどこかテナント探さなきゃなあと思った。今の塾は家の離れで開いているので家賃はタダなのだ。
「ちょっとこいつの話聞いたげて。なあ慎吾、この人なら真剣に聞いてくれるから」
慎吾と呼ばれた少年はボサボサの髪の下から窺うように僕を見上げ、誰だこいつというようなわかりやすい反感を示した。しかし直人は「この人」というのがいったい何者なのか説明もなしにまた他の生徒の元へ行ってしまった。なんてこったと心の中で呟いて僕はため息を我慢し彼の隣に腰を下ろした。
「こんばんは。僕は直人先生の高校の同級生なんだ。森野大地っていう、冗談みたいな名前なんだけど。僕も一応塾やってる。よろしく」
慎吾は頭を軽く動かしてぼそっと「っす」と言った。洗練された僕の耳にはそれがちゃんと「よろしくお願いします」と聞こえた。
「で、なんだろ」
居心地悪そうにパラパラと参考書をめくる慎吾。僕は別に相談に乗るつもりで来たわけでもないので、直人の塾生たちを観察しながら彼が話し出すのをゆっくりと待つことにした。壁際の本棚に積まれている大量の参考書を見て、うちの塾にももっとこういうのを揃えた方がいいかなと思った。しかし中学生も通ってきているとはいえメインは小学生だし、そんなにがっつり勉強っていう感じのものがあってもどれだけ効果的かわからない。まず子供を見てどんなことを必要としているのか考えないといけないうちの塾の形態は漠然としていてやっぱりうまくいかないのかなあ。そんなことを考えていたところに直人が缶コーヒーを持って戻ってきた。受け取ったそれはキンキンに冷えていて反射的に「あつっ」と言いそうになったが、逆だと思ってなんとか堪えた。冷凍庫にでもしまっているのだろうか。
「なんかどうして勉強をしないといけないのかわかんなくなったんだよな?」
僕の隣に腰を下ろすなり慎吾が言いづらそうにしていたことをはっきりと言ってしまう直人。そういうところが経営者として成功している秘訣なのかもしれない。慎吾は一拍おいてから頷いて直人を見た。
「なんでやろう?」
「やる気がでないんです」
「高校受験の時はあんなに頑張っとったやん」
「はい。あの時は、友達と競ってたし、受験って目標が近くにあったから」
「でも言うてる間に大学受験やぜ?」
「それはわかってますけど、まだ実感もてないし」
「まあなあ、俺も真剣に勉強始めたの高三の夏頃だったしな」
「それは、ちょっと遅くないですか」
「うん遅い。だから慎吾には今からしっかりやってもらいたいんさ」
「でも、なんのために勉強するのかわかんないし、上には上がいるし、やりたいこともないし」
「うーん。だってさ。大地どう思う?」
「ここで?」
そこまで話を持っていくとあとはよろしくとでも言うように僕の肩を叩いて直人はまた他の生徒のところへ行ってしまった。まじかあいつと思いながら彼の背中から視線を戻すと慎吾がじっとこっちを見ていた。ああ、この子も何か、救いのようなものが向こうから現れるのを待ってるんだな。そんなありがたいもの、この世界のどこにもありはしないというのに。
「うーん、勉強嫌い?」
「別に。好きとか嫌いとかはないですけど」
「でもここにはちゃんと来るんだね、偉いじゃん」
「親にお金払ってもらってるし、一応」
「そういうことがちゃんと考えられるだけでも立派だよ。うちに通ってる真奈萌って中学生の女の子がいるんだけどさ、その子はほんとにやる気がなくて、月一は連絡なしに休むからこっちは待ちぼうけだよね」
「それは、ひどいですね」
「で、何で勉強しなきゃいけないかだよねえ、難しいなあ。別にしなきゃいけないわけでもないんじゃない?君がそう思い込んでるだけで」
僕は缶コーヒーのプルトップを押し上げて一口飲んだ。予想通り知覚過敏が反応し顔をしかめる。そして甘い。何が微糖だ。
「でも、それじゃあ……」
慎吾は歯がゆそうに目を伏せて押し黙った。誰も自分を理解してくれないという顔をしている。そうさ、誰も他人の心を理解することなんてできないんだ。自分自身にだってよくわからないんだから。
「昔ね、勉強の哲学って本を読んだことがあって。そこには勉強とはまるまるだって書かれてた。なんだと思う?」
彼はしばらく俯いたまま考え、ぼそっと「わかりません」と言った。当てなくていいんだからせめて何か答えて欲しいが。
「うん、その本にはね、勉強とは自己破壊だって書いてあったんだ。どういう意味だと思う?」
「自己破壊、ですか。自分を壊す、変えるってことですか?」
「お、賢いじゃん。そうそう、勉強するってことは、新しいことを知るってことでしょ?そして新しい価値観を身につけて、自分を変えていくってこと。だからさ、もし君が今の場所に、今の自分に満足してるんなら、別に勉強しなくてもいいんだよ。でもそうじゃなくて、これからもっと違う場所に行きたいなら、君が今そこにはないもっと面白いものを見つけたいなら、勉強しなきゃいけないんじゃないかな。今楽しい?」
「楽しくないです」
「なら君は勉強すべきなんじゃない?」
「でも、何がしたいのかわからないんです」
「うん、そりゃさ、何もしてないんだから、何もわかんないさ。いろんなことを経験しないと、自分は何が好きで、いったい何がしたいのかなんてわかんないんだよ。だからその前の段階で立ち止まって悩んでいてもね、向こうからは何もやってこないし、目の前をとっても素敵なものが通り過ぎてもそれに気がつかないかもしれない。だから今勉強するのはさ、そんな何かと出会う瞬間に、ちゃんとそれを掴めるようにするためなんだと思うよ。何か面白いこと起きないかなとか思ってても、準備してないとそれが起こってることに気がつかないかもしれないし、例えばある日こんな仕事したいなってのを見つけても、大学出てなきゃできなかったり、資格がなきゃできなかったりで、せっかくのときめきに飛び込めないかもしれない。それって悲しいでしょ」
「……はい」
「まあ、そんなこと言っても僕らが生きてるのは今だもんなあ。未来のためにばっかり生きるのもしんどいよね。今何か面白いもの見つけたいって、僕もずっと思ってたもん。というか、今も思ってるし、僕もまだ探してる途中で、君とそんなに変わんないよ。だから安心して、その悩みはこれからもずっと付き纏うから」
慎吾は目を伏せてちょっと笑ってくれた。僕はよくもまあこんなことを無責任にペラペラ話せるもんだと思いながらせり上がってきた嫌悪感を飲み下すために冷たい缶コーヒーを喉の奥に流し込んだ。歯には触れないように気を使ったので危うくむせ返りそうになった。それをようやく押しとどめたところで強く肩を叩かれ体がビクッと跳ね上がる。
「なるほどなあ。聞いたか慎吾。十年たってもまだ悩んどるやつがおるんやで、今からそれに負けそうになっとったらあかんやろ」
戻ってきた直人は手にアイスの棒を持っていた。生徒たちが頑張っている時に隣でアイスを貪っていたのか。なんて気に触る先生なんだ。しかし彼も親の目は気にするようで、せっかく良い車を買ったのに若いくせにどうたらとやっかみを受けたくないので自宅からここまでママチャリで通っていたりする。実に抜け目のないやつだ。
「まあ今に満足してるんなら勉強しなくていいっていうのは言い過ぎやけどな。慎吾知っとるか?飛行機やってな、まっすぐ同じ高度を飛ぶためには少し上向いて飛んどるんやで。まっすぐ飛んどるだけじゃ重力に引っ張られてどんどん高度は下がってしまうんやって。それに、お前が変わらんくても周りの環境はどんどん変わってくやろ?だから何もせんでも満足してる場所にずっとおれるわけでもない。現状維持にも少しは労力が必要なんやな」
なんだしっかり僕の話も聞いていたんだ。やっぱり直人はすごい。自分一人で家庭教師から塾を大きくしてきただけはある。僕の塾に来ている生徒はほとんどが昼間働いている療育施設からの紹介であった。それも一つの手段だが、成果を出して向こうから連絡してきてくれるだけのものを僕はまだ示すことができていない。もちろん施設からの紹介もそこでの僕を認めてくれたからこそではあるが、それでもやっぱり直人ほど塾経営というものに本気で取り組むことができていないのだろう。昼間の仕事やテナント料が必要ないことが甘えになっている。生徒に手を抜いているわけではないが、経営に手を抜いていないかと問われれば俯いてしまう。
直人が塾を閉めるのを手伝って愛に手を振りコンビニでチキンを買った。夜でもあっちーな、と言いながら僕の隣に乗り込んだ直人は勝手にエアコンの設定を二十度まで下げた。
「あー自転車どうしよ」
そうは言うが彼はゆったりとシートに身を預け、どうするつもりもなさそうだ。
「またここに戻ってこればいい?」
「いやー風呂入ってから自転車で帰るのもめんどいし置いてくわ。家まで送ってくれたらええよ」
「明日どうすんの?」
「明日休みやし、愛に運転してもらって取りに来るわ」
相変わらずの亭主関白っぷりである。直人は昔からそうだった。カッコつけなのかそういうものだと思っているのか、彼女を自分の用事に使うことに躊躇がない。そういったところが男らしく映るのか、彼は高校時代からよくモテた。でもまだ結婚する気はないみたいだ。この間も待ち合わせの時間に来ないと思って電話してみたが出てくれず、あとで聞くとけろっと「ピンサロ行っとったわ」と笑っていた。こいつは昔から僕の電話に全然出ないのだ。
疲れたのか二人ともしばらく無言で道を走っていたが、信号で停まった時に直人はポケットから煙草を取り出して火をつけた。僕は煙草を吸わないが、去年別れた彼女も煙草を吸っていたので車内で吸われることはあまり気にしていない。一声くらいあってもいいものだが。しかしそうやって横柄に甘えるところが彼の人たらしでありモテる部分であった。
「いや助かった」
「何が?」
「慎吾のこと。とりあえずしばらく頑張ってくれるみたい」
「まだ高一でしょ?そんなに深刻な悩みなんかないって。深刻にしたいお年頃ではあるけどさ」
「どうかなあ。中途半端に頭いいからなあいつも。俺らって高一の時どんなだっけ」
「お前は洋介にパジャマで学校来させたり授業中馬の被り物被らせたりしてたな」
直人は「そんなこともあったな」と笑った。僕らの通っていた高校は私服校だったので服装は自由だった。自由と言っても限度はあったはずだが。
「今思えばほとんどいじめやんなあんなの、俺ひどいな」
「まあ洋介も喜んで悪ノリしてたからなあ」
「あいつ今何しとん?」
「わかんない。大学は東京の私立行ってたと思うけど」
「あー、寛太とかにも会いたいな」
「文化祭のプロレスでお前が泡吹かせた寛太な」
「あれは焦ったよな、ギブ言わんのやもん」
「よく言うよ、言えなかったんじゃん。てかお前爆笑してたし全然焦ってなかったろ」
「でもさあ審判してた岡野先生もひどくね?ギブ言わないんですけどって俺が叫んだらさ、ならもっとやれ!って煽ってくんだもんな」
「その声で寛太意識取り戻したよな」
「まじでやばいって思ったんやろな」
「お前がイエスサー!とか応えて殺しにかかったからだろ」
「まじ岡野先生の体育軍隊だったからな。帰宅部の俺らがなんで腹筋割れてんだよって」
「球技の時とか絶対誰か血流して帰ってきてたしね」
「鼻血は常だった。燃えたねえ、懐かしい。そうやって夢中になれる時間が慎吾らにはないんだってさ」
直人はダッシュボードの灰皿でまだ長い煙草を揉み消して伸びをした。
「血流せとは言わないけどさ、もっとこう、ぶつかってもいいのにね」
「ぶつかったことがないからポキンと折れちゃうみたいよ。そんなやつばっかじゃねーけど。慎吾にしたって他の生徒にしたってみんないい子ちゃんなんだよなあ、良くも悪くも」
「いい社会なのかもしれないけどねえ」
唐突に僕は、洋次郎の力になりたいと思った。いつもつまらなそうに黙々と問題を解いている横顔が脳裏に浮かんだ。新しく入った浩介と雅彦がいい刺激になればいいが。やり過ごすだけの日々なんてもったいない。けれどあの頃の僕だって、今その瞬間の大切さに気がつくことはできなかった。青春とは奇妙なものだ。外部は赤く輝いているが、内部では何も感じられないのだ。そんなことをサルトルかだれかが言っていた。そしてゲーテは、青年は教えられることより刺激されることを欲するものである、と言っている。僕は彼らの刺激になれるだろうか。それは洋次郎の熱く生々しい部分にまで届くのだろうか。いや、届けなければならないのだ。どうしてそんなことを感じるのかはわからないが、たぶん、そんな瞬間が好きなのだろう。僕も、そんな刺激を待っていた一人だから。
街灯の少ない夜の国道。虫たちの声に何かの答えを求めるように僕らは黙ってお互いの考えに沈んでいた。こうして、どこまで行けるのだろう。どこへ行きたいのだろう。信号機の赤を見つめていると、それが迫ってくるように、世界がそこだけに焦点を合わしたかのように周囲の輪郭をにじませた。止まるな、と誰かが言った。走り続けろ。そうしないとお前は堕落する。魂にも脂肪がつく。僕はきっと、まだ自分がヒーローになれると信じ込んでいるのだろう。大人にもなりきれず、子供でもいられない。中途半端に成長した僕らはいったい、この胸の内のエネルギーをどこへぶつければいいのだろうか。とんだ詐欺師の導き手だな、と胸の内で笑い、せめて子供達にだけは真摯であろうと誓った。そして、直人が案内した銭湯は定休日だった。二人で笑いながら、僕は何を焦っているのだろうと思った。青春は波打つ水面のようなものだ。いつまでも消えないように思えるのに、少し目をそらしている間に過ぎ去ってしまう。そしてもう一度そこへ石を投げ込むのは、とてつもない労力を必要とするのだろう。その石は自分自身であったり、人生と呼ばれるようなものなのかもしれないから。けれど、ちょっとした風が吹けば波は立つ。焦ることなく、小さな波紋を感じ続ければ、きっと何かが見えてくる。そう信じたいだけなのかもしれないが。


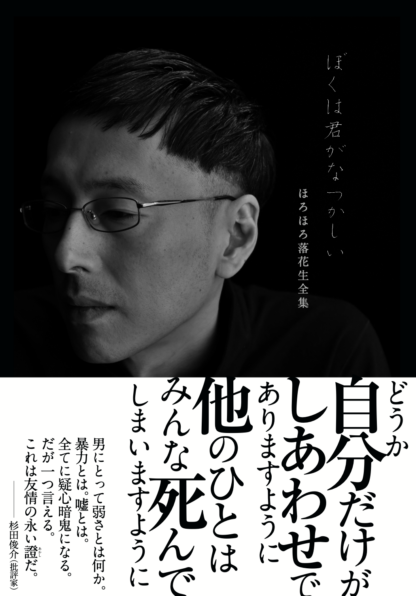
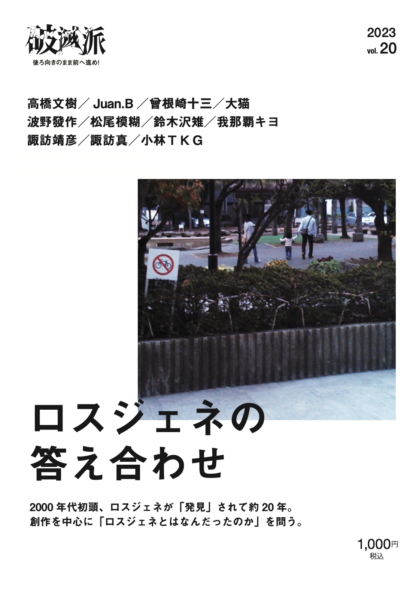
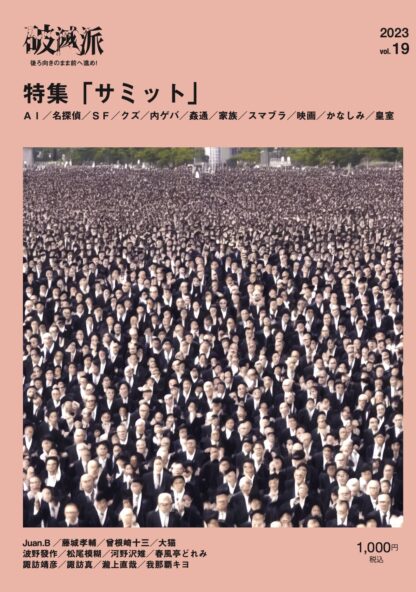
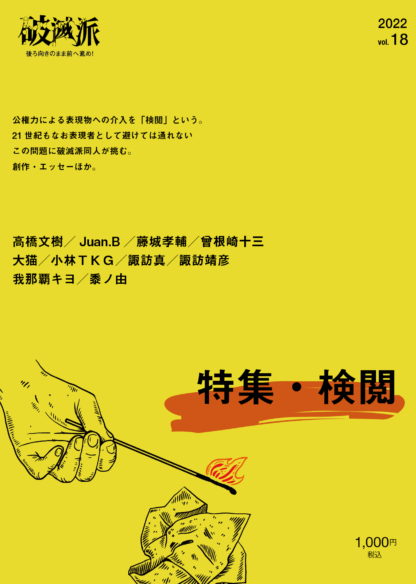
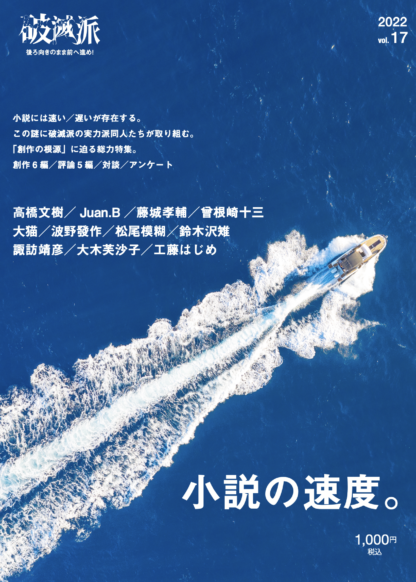













"クロスゲーム1"へのコメント 0件