小学校も中学校も、どちらもまあよろしかった。いわゆる「○○君とは遊んではいけませんよ」の、おそらく頂点に位置してはいたろうけれど。
中退した高校も非常によろしかった。よろしかったが、液体窒素で何度焼いても治らなかったイボが中退して半月も経たず嘘のように消滅した。体罰ありますと入学案内に明記された私立の男子校であった。ここの中退は中卒よりアホな高校であった。
私が受けた体罰は軽いものだったけれども、職員室じゅう引きずり回された時の教師の、例の「何やその目は」。その時私が考えていたのは、「逆の立場だったら俺はこんなことはしない」というものであった。そらシメられるものだった。
ドロップアウトの原因はただサボり過ぎて自ら転げ落ちたのに過ぎなかったけれど、恩師のなかったことももう自分のせいだ。楽しかった思い出だけ靴の裏にでも飾っておく。
さて庄原の車から中学の校舎が見える。懐かしいが、この時分の何らか作品だの記録だの残っているのならことごとく消えてなくなって欲しい。痴態の時代でしかない。ここでじっと自己表現を隠し通した輩がのちの勝者だ。ここの勝敗が死ぬまでにはひっくり返ることだけを願う。
卒業して五年ほど経った頃だったか、友人たちと訪ねたことがあった。その時でもかなり先生は異動していた。
それで今、とうに異動になっているある先生が、我々の洞窟へ訪ねて来たのであった。
皿村先生といった。あの時分からベテランに属し、なおかつ情熱家であった記憶がある。
教師への侮蔑は至るところで耳に入る。在学中これを覆す事件もとくに起こらなかった。漠然とにもせよ、どういうイメージであったろう。今の教育制度は日本の急ぎ過ぎた近代化の失敗例としてある――積極的な教師はほぼ左傾化している――第一次産業を廃れさせる――歴史を教わるによって記憶喪失となり、国語を教わるによって外国人となる――学力テストの競争に負ければ善人であろうが苦労人であろうが未来は閉ざされる――いざ社会に出る頃には疲れ果てている――学校の勉強がゆいいつ役に立つ職業は教師だけである――……等々の、こういう思惟傾向はしかしほかでもない学校教育の賜物である――云々。
かくて我々は最初から過去に対する優越感を植えつけられ、それが破綻しても傷つくことなく自嘲もできる、そんな態度を離れるべき必要もすんなり承知し得、甘い自虐はすべてを緩慢に許し続ける。
――だいたいそれら一切の責任をなすりつけらるべき人種の代表格が、訪ねて来たのであった。
しかしいざ肉体を以て眼前に現れ、面と向かって話しかけられると、我らがどうしようもなさの、どうしようもない病巣を一つずつでも、どうにかこうにか治してゆこうとむなしくも奮戦する皿村先生であると、そう映ずるのであった。
先生はリビングまで上がって来て、とつぜんの来訪を詫び、しかし教師と生徒の関係に今一度戻って欲しいと頭を下げ、それからひたぶるに自立の必要を我々へ説いた。
未来に対する失望――老人たちの孤独死、ローン地獄、過労死、リストラ、熟年離婚、いや数え上げればキリもない、そうしたものは確かに悲惨やが、いきなりそこへの憂慮に跳ぶな。直面してから悩め。じっさいはせえへんかもしれへんのやからな。可能性としてならことごとく直面し得るが、それは妄想や。妄想、上等や。してもええ。せやけど自立してからせえ。自立、経済的自立と精神的自立を分けてもええ、しかしそれは経済的自立を成してからにせえ。
我々は先生の小さな車で県道沿いのハローワークへ連れて行かれた。事の展開の速度に気づいている暇もなかった。
先生は駐車場に車を停めて、エンジンを切ると、言った。
「今日は中に入らんでええ。次に来るのもいつでもええ。一年後でもええ。でもここは、自立しとる未来への入り口や。通信教育受けるなり、重機の免許取るなり、地方に移住するなり、ほかに何ぼでもあるやろ。俺の知らん方法が何ぼでもあるやろ。でも『ここだけや』と、いったん思てみろ。入ったらあとは何とかしてくれる。聞いたら教えてくれるし、相談にも乗ってくれる。一緒に考えてくれる。そうやって動き出したら、すべてが明るいほうへ一気に動く。通信教育も、何ぞの免許も、今考えとるより遥かに身近になる。よくよく考えんでもええ。頭の片隅に置いとけ。突破口の場所はここや。ここやぞ」
我々は職安の建物を上目づかいにちらちら見ながらうつむいていた。先生の熱量に温まらぬ我々は変温動物ですらなかった。プリザーブドフラワーのごとき童心がガラスケースの中で手を差し出し叫び声をあげているのは先生には聞こえないし、聞かれるわけにはいかなかった。我々が自分で聞かねばならないのだった。
先生はたぶん実年齢以上に年寄りのにおいを発していた。気にもせずに、どんどん発し続けながら、一人々々の目を見つめて言った。負けたらあかん。逃げたらあかん。闘え。闘わんかったら、卑怯者や悪党たちに食われる。
闘わんかったら、愛すべき人たちを、お前たちが食いつぶしてしまう。
死んでもええと言うんやろ。踏んづけられても物乞いしても生きていたい人たちを笑えるんやろ。そんな自分自身のことも笑ろとんのやろ。
かまわん。でもせめて、冥途の土産をもっと持て。あの世があったらどうする。考えてもみい。もしあったらどうする。なかったらどう生きてもとんとんや。でも、あった場合のこと考えてみい。今のままやと、土産話があんまり少ないやないか……。
それからラーメンを食べさせてくれた。どこかの学校で、今もテニス部の顧問なのだろうか。試合でがんばった教え子たちにもこうしてごちそうしているのだろうか。その同じものを食べる資格が私たちの誰にあると言うのか。
好きなもん頼め、いくらでもおかわりしろ。でもビールは今度や、それはめでたい時やと言いながら、ご自身は醬油ラーメンとおにぎりを頼み、おいしそうに食べていた。
元通り一緒くたに私の家へ送ってくれて、帰って行った。
先生は誰から我々のことを聞いたのであろう。何となく、我々の親からではない気がした。
先生はまた来るだろう。忙しい身の上に鞭打って。無償で。純粋の心で。
我々が先生からいただくのは、押しつけがましいかどうかなぞ軽く吹っ飛ぶ、遠慮のない、大木のような慈悲だろう。
先生の慈悲は自費だ。こんな諧謔に遊ぶ気にもなれぬ。












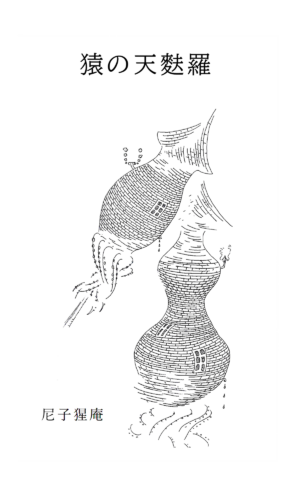
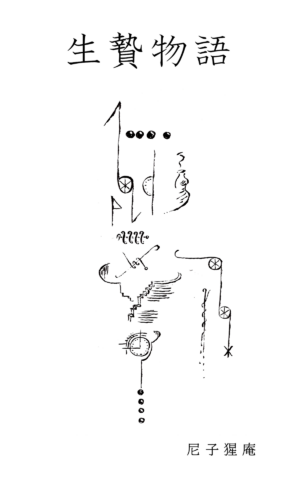










"ホルマリン・チルドレン 10"へのコメント 0件