煉瓦の壁がどんどんせり上がっていた。ネット検索の知識だけで嘘のような窓まで嵌まっていた。低過ぎて用途が不明だったけれども。私はひそかに『野のユリ』(1963)の教会を造るシーンを思い浮かべて胸中に〽エーェェメン……エーェェメン……と歌い、独り恍惚としているのであるが、誰しも負けず劣らずの夢見心地らしかった。
ずいぶん高くなり、続けるにはそろそろポールだの板だのロープだの、足場になる新しい道具を手に入れなければならなくなった頃のこと、庄原が玲衣子さんを殴った。
我々はそれを知らなかった。玲衣子さんはいつの間にか帰ったのであって、帰ることを誰にも告げなかったのだが、そんなことは別にありそうなことだった。
あとで知った貴崎さんが青くなって詰め寄って、聞き出してわかったのだった。庄原はさらりと言ったのだった。
いわく、この頃は茂みには断乎行かなかったが、ふいに近くへ寄って来て、車のロックをし忘れたからついて来てと言われ、引っ張って行かれた。迫られるのかと思ったが、そうではなく、非常に真剣な口調で以て、
「君だけは抜け出さないとあかんよ。このままやと腐ってしまう。君はまだ抜け出せる」
そう言われて、平手とはいえ、殴ったのだった。
「何か、カッとしたもんはなかった。考えてから殴った。ちゃんと覚えとう。でも、何でかはわからん。ただ、カッとはしてへんかった」
そんなことを話している庄原はぼんやりしているというのでもない、ただ感情がなかった。いつもたいがいないけれど、ここまでないのなら本当に死んでいるのかもしれなかった。
半田がつらそうだった。
私も庄原がそんな、狭い箱庭の中の火柱であることに幻滅した。みんな広い世間の片隅の、蚊取り線香のような赤い点でおったのに。さまざまなアルバイトに行っていたあいだにも、庄原は友だちができたことはないと言っていた。我々は、バイトのほうは続きやしないけれど、先々で友だちはできるのに。何もかも、断じて許されないほど強烈なものではなかったから、見逃されているものであったのに。
しかし幻滅もすぐに去った。こんなものが我々だ。優しいのでも悲しいのでもない。転んだ分だけ弱くなり、悩んだ分だけ浅くなって来たのだ。
あいまいなものはすべて醜く、確乎としたものはすべてどうでもよかった。
貴崎さんは従姉への暴行を怒っているのではなく、旦那さんからの報復を心配しているのだった。末っ子がひどい目に遭うことが怖いのだった。
川野さんも同様だった。庄原を隠すか逃がすかしようとした。
しかし庄原は、一番安全な策があると言って、諸々を振り切り、頑迷に出て行った。
それから二日のあいだみんなはうちに住み、暗鬱だった。
誰も連絡しなかったし、向こうからも来なかった。
三日目の朝に戻って来た庄原は、
「これでも腫れ引いたんやけど、よけい黒なってもうた」
彼はログハウスに行ったのだった。旦那さんが彼を痛めつけた。けれども、いまいち興が乗っていなかったと言う。殴る価値もないとはよく言うが、我々がそれであった。
そもそもその場は、旦那さんが玲衣子さんを捨てている最中だったのだそうな。口論を聞いていて、籍は入れていなかったとわかる。どころか二号さんだった。前からわかり切っていたことに、あらためて気づかされた。
それでみんな貴崎さんに玲衣子さんの現状を尋ねた。腹違いであろうが種違いであろうが玲衣子さんも我々のきょうだいだった。貴崎さんはしばらくケータイをいじっていたけれど、ダメだと言って家に帰った。
戻って来た。玲衣子さんはすがたを消したらしかった。
「わたしの将来が消えました」
半田をじっと見つめて言った。半田は何か煮えそうなのに熱が足りないようだった。
川野さんの目と私の目がずっと合っていた。けれども彼女の心がわからなかった。自暴自棄に何か刺し続けている貴崎さんをつらそうな半田から引っこ抜かなければならないと心配している。あの夜、私が外部へ隙間を開いたことを、みんなに秘めたという共犯――庄原の暴走が我々長男長女の共犯のせいかもしれないと自責している。玲衣子さんをきちんと勘定に入れ直さなければならないと訴えている。激しく咎めている。並べるほどどんどんわからなかった。












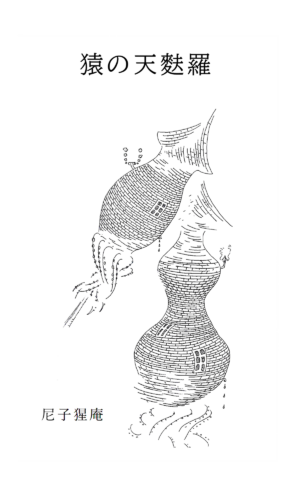
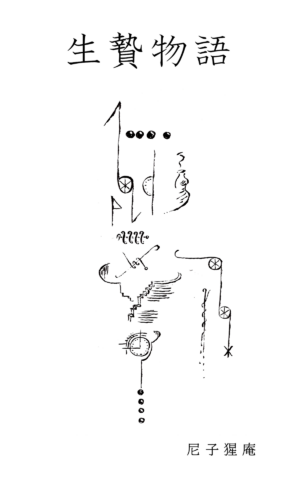










"ホルマリン・チルドレン 9"へのコメント 0件