朝から私の家にそろっていた。
夜になったら小学校へ侵入しようと話し合った。
あの時に戻ろう――しかし小学校はもう他人であろうと察しられた。精神的の問題だけではなく、窓なども、外から根気よく揺すれば鍵が外れた当時のままではなかろう。こちらもまた、侵入が見つかっても笑って済む子どもではない。当時は何度か見つかった。這いつくばって隠れおおせたことのほうが多いが、「誰や!」と発見され、「お前らか」と職員室へ連れて行かれて、冷蔵庫からソーダ水をごちそうになった。先生たちが学校で冷蔵庫など使っていることや、自分の湯飲みなど置いていることが新鮮だった。
――……ダメだ、懐かしい場所なんぞへ行ってしまったらあの頃を汚す。こんなことはどこの世界においても犯罪である。
しかし相談が進み過ぎた。途中でやめたらどこかに悪く溜まりそうだった。
違うところがいい。何が起きても嘘くさい神経鈍麻の我々は、生半可に擦り切れたがびがびの心を引きずってどこの梅園に遊ぼうが掃き溜めに遊ぼうが同じことではないかしら。いくら投げても賽は転がらぬ。転がる時は風に飛ぶ。目が外れるような期待も持たず、台無しになるような何物もない。
そうして、秘密基地とはまた別方向の山の中の小規模なでんぱた――誰かの父親がいくらか所有していた。キャベツをいただいたことがあった。洗っていると雨蛙が跳び出した――の向こうに、明らかに使われてへんグラウンドがあったやんかと私が言うと、半田があったあったと応じた。女性たちは知らなかった。
自転車で行った。みんな自転車を持っていた。私は半田に借りた。
途中、誰かの親に呼び止められたに違いなかったけれど、我々は振り返りもしなかった。
住宅街の南端から始まる山道をがたがた行ってたどり着いた。森に囲まれたグラウンドには植物が旺盛に侵略していて、もうグラウンドにも見えなかった。
かくして我々は駐輪場に自転車をとめ、校舎に入った。ランドセルを机の横にかけた。一人だけクラスの違う貴崎さんも遅れて入って来た。
我々はそれぞれの所属しているグループを離れて集合していた。グループの仲間たちが不思議そうにこちらを見ていた。
他人の恋愛の噂話をした。この時分にくっついていたちっちゃなつがいは、小学生ごときが付き合って、それでいったい何をしていたのか。県道をしばらく行けばゲームセンターだのカラオケ店だのボウリング場だのあったけれど、もさい不良ばかりだったし、知り合いが家族で来ていたりした。都会へ出るには長いこと電車かバスに乗って山々をくぐらねばならぬ。じっさいに乗ってしまえば、せいぜい一時間ちょいでくぐり終える近さではあったけれども。本当は、その程度の浅い辺境なのだったけれども。しかしそこまでやったつがいはいたのであろうか。
我々の中で小学生の頃に付き合ったことがあるのは貴崎さんだけだった。聞けば、家の電話で話したり、人の来ない階段で座ったり、交換日記をしたり、趣味を教え合ったり、同性間でしか知らない秘密を漏らしたり――けれどもけっきょく冷やかされるのがイヤで別れた。二人付き合ったがどちらもそれだけだった、誓ってキスもしなかったと言った。
先生の物真似をした。誰もうまくなかったので、とうとう出勤して来なかった。それでも授業は始まった。
付き合っていられなかった。エスケープすることに決めた。いいやエスケープどころではない、我々は一切合切やめるのだった。
先生のたぐいに見つからないよう抜け出して、帰ろう。見つかったところで、まさかそのまま本当に帰るとは思われないだろう。しかしもう二度と来ることはない。
不登校児童と呼ばれるかしら。しかしそっちがどう呼んでも、こっちは何とも呼ばれていない。
嘲笑われるかしら。しかし世間が嘲笑っているところ、憂慮するところに、私たちはいない。
抜け駆けの自由や、庇護された余裕をやっかまれるところにもいない。我々は被幽閉者だ。そうは見えないだろう。それがこんなことをしているなんて思いがけなかったんと違うか。どいつもこいつも、救いようのないアホやな。
さようなら。みんな元気で――おお、お前らも元気で。……そこのな、君たちなんか、あとで色々あるけども、くじけるな。くれぐれも踏み外さないように。逃げ癖がついたらおしまいだと、そういうふうなこと、聞いたことがあるであろう。おしまいとは具体的にどういう状態であるのか、お兄さんたちは知らないけども。
私たちは廊下に出、階段を降り、校舎を出、校門をくぐった。
山道の斜面に乗り捨てて来た自転車にまたがり、西日の射す永遠の校舎をあとにした。
やっつけだ! 何もかもがやっつけだ!
私たちは言うまでもないが、私たちだけではない、すべてがやっつけだ、そうではない一切の事物も、そうでなければないほど、何から何までやっつけだ!












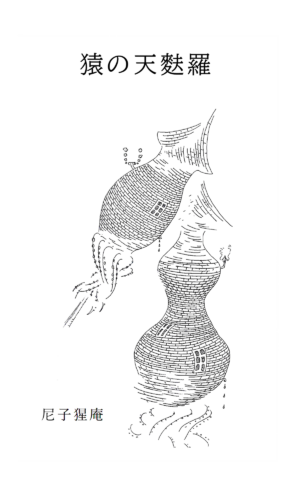
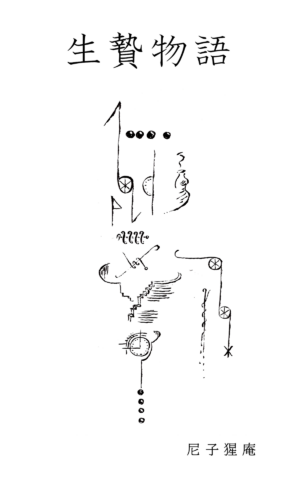










"ホルマリン・チルドレン 4"へのコメント 0件