十年ばかり前に撮ったMRIでは問題なかったけれども、もうずいぶん脳が萎縮してしまっているのに違いなかった。そうでないなら健康体ということそのものにケチがつく。眉間の奥に強い違和感が居座っていてよく揉んだ。しばしば指を突っ込んで頭蓋骨の裏側から掻きむしりたかった。
とつぜん揺り起こされたら病院のベッドか霊界の公営住宅にでもいて、ああ夢だったかと、ぼんやり思い返すというようなことにでもなれば御の字だ。しかしそこでもやがてさらなる覚醒に強制終了されて、さらなる来世からぼんやり思い返されるのだとしたら、今ここで前世をぼんやりにもせよ思い出すまでは次を起こされ得なくなって来るけれども。
川野さんのペンネームは川之三途、貴崎さんは鬼崎墓園といった。妙におどろおどろしいのはやけっぱちなのか、そこに変な色気を感ずるのは私だけであろうか。
ここではそれが常識であるかのごとく申し合わせたようにみんなまだ二つ折りケータイだった。赤外線通信で連絡先を交換し合ったら、向こうのプロフィールがまるまる来て、自分の名前をそう設定しているのが露顕したペンネームだった。
「しもた!」
「消して消して!」
「忘れて!」
と慌てていたけれど、何となく、二人そろってそんなへまをやるとも思われなかった。
このように秘密を急速に打ち明けられるのは危険に思われた。最初に早まったのは確かにこちらだが、ここで関係が崩壊したら、住宅街はもう魔界になる。もっと慎重に当たらねばならなかったか。
しかしだんだん、何の危険も漂っていなかった。二人とも、打ち明けて失うもの、穢れてしまうものが軽くなり過ぎたのか。医師か、カウンセラーか、または自分自身に、あるいは神仏や先祖の霊に、それに類した諸々に、諦め疲れているのかもしれなかった。
ペンネームの霊界ぶりにも、何だかもうユーモアも褪せ落ちていた。色気なんぞもけっきょくどこにもなかった。
半田のプロフィールはある洋画の醜悪な端役の名前だった(スロース)。その映画の話は水泳教室でも確かにしなかった。その頃には私もビデオに録ってあったのを何度も見ていたが。そしてかなり好きだったが。川野さんと貴崎さんのペンネーム露顕騒動の大きさに半田の話題は出ないかと思われたけれど、女性たちはきちんとそこにも触れた。女性たちは映画を見ていなかったが。
キャップ帽を目深にかぶって現れた貴崎さんの目元の軽い疲れも、昼からのアルコールも、濁った懐かしさにちゃんと溶けていた。変わってへん変わってへんと言い合った。
私のプロフィールの氏名そのままは一番サムく外したようだった。本名が最も懐かしさから遠かった。
川之三途と鬼崎墓園は、この世と重なり合った異世界ではとっくに玄人作家で、この世においては、新人賞に応募しては落選して暮らしているということだった。堆積した作品の分量は、感心するにも呆れるにも許容量を超えていた。「そこまでしてダメなら」という範疇の二、三十倍はある印象だった。川野さんと貴崎さんというのは、もう世を忍ぶ仮のすがたであった。
アクシデントをよそおって正体を明かしてくれたが、作品を見せてくれるまでは行かなかった。それは私にひとつの安堵だった。
しかしこれも呆気なく見せそうだった。こちらが突き破って頼めば済むことのようにも思われた。
半田が少し突っついたが、突き破る勢いではなかった。霊界の女流作家たちは、文芸誌の掲載なり単行本の出版なり、公的な活字にならないうちは見せられないと言った。
問題は私と半田の要求の弱さだった。女性たちはただただ、何かに勝利し続けているかのような余裕を持って悠々としていた。
貴崎さんが初めの氷の美女からアルコールでだんだん冗舌になる。
彼女をそれで形容したいが酒の匂いを表す単語が見当たらなかった。相談したけれど咄嗟の四人には「酒気」くらいしか出なかった。「酒匂」と私が言ってみると、それは苗字だと貴崎さんが言った。
「――わたしは、もうサナギではないな」
サナギという拙い比喩をこれほど多用されて悲しかった。また半田が言ったのだった。刷り込み的に固執しているようで。あんがい感心して、気に入っているのかもしれない。恥をかかせるための意地悪には思えなかった。
こんなことならもっと練って定義しておればよかったな。(サナギとなるにはいったん死を呈さねばならぬ、社会に出る瞬間の誰もが、頭を真っ白にして、顔を真っ青にして、人格を煮沸して、精神と感受性の小さな死を呈する、しばらく連続する小さな死だ、その後はもう別人だ、メタモルフォーゼだ、不死鳥が火に飛び込む時は、それで復活することをイデア的記憶として知ってはいるが、大脳や本能は知らず、生理現象は全力で抵抗するのではなかろうか、復活を目論みはせず、純粋な死を思いながら飛び込むのではあるまいか――云々云々とか言うて。)
幼少の頃から適当に捨てた言葉を大人に拾われてしきりにぱんぱんはたかれる恥ずかしさが過敏に嫌だった。
しかし今は恥ずかしさではない。そんな致命的なことではない。恥ずかしさそのものがおのれを恥じてすがたを消した。少しなら恥ずかしくなりたいくらいのことだった。
「わたしはサナギを終わって、背中の割れ目から、全然ちがうものがこぼれ落ちたんやわ。ぬるるっ……ぼとって。みんな『キャー!』言うてね。『逃げェ! 早よ逃げェ!』言うて。わたしは『待ってェ……待ってェ……』言うて――……あかん、おもろい」
と言って体を二つに折り、涙がにじむまで笑ったけれど、急でもあり、まったく声を出さない笑い方で、だいぶとヒドイ苦悶に見えた。
「アホばっかり言わんとき」
と川野さんが言って、肩をたたいたのやらさすったのやら、半々のようなことをした。
川之三途と鬼崎墓園の作品の開示は私と半田の度胸にゆだねられていた。それは遠そうだった。そしてしょせんそのつぼみも別の軽いキッカケで呆気なくひらきそうだった。
我々の躊躇は何であろう。現実はもう手の届かぬところに蒸発したわけであるからには何一つ重量も持たないはずが、去る際に我々の中へ茶渋を引いて、気弱な常識人の下手礼儀を強いられるわけであろうか。深刻な世間からは極めてどうでもいい葛藤だろうけれども。神々が行うのは徒然なる退屈しのぎ。鑑賞なさるのは身の入った事件より、無生産な芋葛藤であることもあり得る。
川野さんは貴崎さんの少し崩れた美貌を堅固な要塞に思っているようだった。かなり短い距離とはいえ、並んで歩く様子には以前の外出悲観が感ぜられなかった。それとも単なる同性が複数になった強さか。どこまで昇り得る強さであろう。これに類した諸証明の機会がないのがすなわち平和で、機会のなさだけが我々を生かしむるか。
我々は遂に白昼堂々住宅街の坂を長々と下り、秘密基地へと向かっていた。
誰か見ているかもしれなかったけれど、見られたとしても分不相応のローンにいまだ食われ逃れているだけな食べ残しの人々に過ぎなかった。じっさいに会えばきっと純粋な善意の直撃を受けてすべての印象はがらりと覆るのだろうけれども、会わない限りは、じっさいに会っても嫌な顔をされるのに違いなかった。
たとい私たちを噂のつむじ風で粉みじんにできても、我々の粘土をこね直す力はあろうはずもなかった。壊す力しかないものに壊されることは何の悲劇でもなかった。たといこね直し得たところでそのまま焼き上げられるほどの火があろうはずもなかった。とにかく今、すべてはあまりに涼しかった。
よく夜中に肝試しをした、誰か子どもが溺れ死んだという貯水池を過ぎ、ほのかに野焼きくさい林道を行った。やがてコンクリートの崖下に川が沿い、遥かなでんぱたが広がって、遠くの山々に雲の影が落ちる、その手前、頭上高く横切っている高速道路の真下で、人目がないか見回して、半田が私の肩を踏んで擁壁を登り、嘘のようにそのままあった、濡れた泥臭い縄梯子を垂らした。












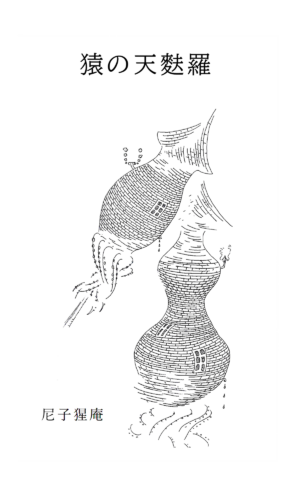
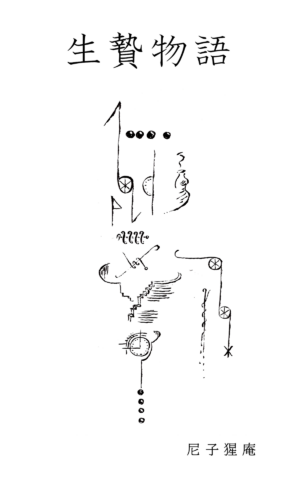










"ホルマリン・チルドレン 3"へのコメント 0件