コハルちゃんは僕のことが大好きだった。でも僕はコハルちゃんをそういう目で見られなかった。
コハルちゃんは「きょーちゃん、きょーちゃん」と、金魚の糞のようについて回る。僕は友達が少なかったし、結果的にコハルちゃんとほとんどいつも一緒だった。学校の皆には付き合ってると勘違いされることも多く、コハルちゃんはそれを嬉しそうにしていた。一方、僕は「また何か言われてる」程度しか思わなかった。そんな僕を見てコハルちゃんはいつも少し寂しそうにする。良心は痛むけれど僕にはどうすることもできない。恨むなら僕を好きになった自分自身を恨めば良い。きっと僕に言われなくたって、コハルちゃんは自分を恨んでいただろうけど。コハルちゃんは僕のことが大好きなので。
コハルちゃんはいつもコハルちゃんだった。「コハルちゃんって呼んで」と言われたので言われるがままにそうしていた。コハルちゃんの苗字を僕は未だに知らなかった。別のクラスだったし、コハルちゃんを何かを受賞するようなタイプの学生ではなかったので、フルネームを見かけることもなかった。調べようと思えば調べられたのだろう。でも、調べたいとも思わなかった。
「今日もきょーちゃんのこと、とっても大好きです」
「ごめんなさい」
僕がそう答えると、コハルちゃんは笑う。毎日笑う。変態じみている。
「ねぇ、辛くないの。僕は君を好きになることなんてないのに。一緒にいたって辛いだけでしょ」
毎日毎日、コハルちゃんは僕に愛の告白をしてくるので、その度にふる。「好きです」「ごめんなさい」「大好きです」「ごめんなさい」「愛してる」「ごめんなさい」最初は心苦しかったけれど、今は僕にとっては日常会話の一部になっていた。もはや「良い天気ですね」に対する「そうですね」くらいの労力で答えることができていた。
「全然。きょーちゃんこそ、私のことウザくないの」
「平気だよ。コハルちゃんが良いならそれで良い」
嘘偽りのない本心だった。コハルちゃんがいてもいなくても、どちらでも良かった。
「きょーちゃんは本当に優しいなぁ」
優しくはない。コハルちゃんは勝手に僕のことを美化し、僕を通して勝手に自分の中の美しい僕と馴れ合っていた。僕は一人遊びに巻き込まれているだけだった。だからと言って、邪魔とも感じなかったので、そのままにしていた。コハルちゃんは僕にとって天気みたいなものだった。ただただ受け入れるだけ。
「じゃあさ、優しさついでに、たまには『ありがとう』って言ってよ」
「僕はコハルちゃんのことをそういう風には見れない」
「わかってるよ。別に私もう、きょーちゃんに付き合ってなんて言ってない。無理って分かってるもん。私は私の溢れ出る思いをワガママにぶつけてるだけ。でも、『好き』の回答が『ごめんなさい』だなんて噛み合ってないよ」
噛み合ってなくもないだろう。どんなに思いをぶつけられても僕はそれに答えることができない。壁に向かって話していた方がマシだろう。「ありがとう」くらい言ってくれたら良いのに、と彼女は幾度となく言った。気持ちを受け取れないというのに。とにかく、僕にとってコハルちゃんはそういう対象ではない。
「コハルちゃん、ただいま」
奥の部屋から激しい物音がする。今日も元気そうだ。僕は町から回収してきた自分用の缶詰やレトルト食品、清涼飲料水を机に並べる。コハルちゃんが喉を鳴らしているのが聞こえる。獣じみた声。扉も窓も閉め、バリケードを張り巡らせてしても、あちこちから似たような呻き声が聞こえてくる。それでも、コハルちゃんのものはすぐに分かる。
自分の食糧と一緒に回収してきた肉を持ってコハルちゃんの部屋へ入る。むせ返るような悪臭が一層濃くなる。動物園の肉食獣舎に生ゴミをぶちまけたような臭いだ。たまらない。鎖で繋がれたコハルちゃんが濁った鳴き声で吠えた。音のような悲鳴のような鳴き声。床を引っ掻いたせいで、また爪が折れている。このままじゃ全ての爪がなくなるのも時間の問題だろう。ミミズ腫れが浮き上がる皮膚は全体的に灰色に濁っている。白く濁ったこぼれ落ちそうな眼球。涎を垂らし、鎖を無理に引っ張り、硬直した無表情ではしゃいでいる。僕を見て喜んでいるのか、屍肉を見て喜んでいるのか。屍肉を床に置くと、僕に見向きもせず食らいつく。やはり僕ではなく肉だったのだ。毎回そうじゃないか。それでも毎回僕は期待してしまう。まだコハルちゃんはコハルちゃんなのではないかとどこかで思っている。湿っぽい咀嚼音がする。缶タイプのドッグフードを食べる犬みたいで可愛い。美味しそうに食べてくれて嬉しい。ゾンビになったコハルちゃんは煽情的で、僕は生まれて初めてめくれ上がったスカートから丸出しの太ももがいやらしいと感じた。ゾンビのコハルちゃんなら僕は喜んで抱きしめたいし、キスだってしたい。でもその瞬間、僕は死ぬ。いつかきっと、僕はコハルちゃんに食べられて死ぬ。
僕はゾンビになったコハルちゃんを、初めてそういう目で見ることができた。
少し前から、世界はゾンビで溢れている。少なくとも僕の目の届く範囲の世界は間違いなく滅んでいる。蠢く屍と時折聞こえる生きた人間の悲鳴。その悲鳴の数も日に日に減っている。
近所の大学病院を中心にゾンビウィルスはあっという間に広がり、ゾンビ映画さながらの阿鼻叫喚と化した。現実味のない光景に「映画で見たやつだ!」と僕は高揚した。僕はその時も成り行きで一緒にいたコハルちゃんと逃げた。屋上へ避難した後、地上を見下ろすと、ゾンビがぞろぞろのんびりと徘徊し、生きている人間を見つけると俊敏に食い殺していた。とても動物的だ。その様子がおもしろくて、じーっと何時間もフェンスから地上を見下ろした。コハルちゃんは心配そうにしていたが、内心、僕は心躍っていた。野生動物を観察しているみたいで楽しいなぁ! いくら見ても飽きなかった。次から次へと魅力的なゾンビが現れる。いくらでも見ていられる。何てエッチでかわいい生物なんだろう、と踊った心をすっかり奪われてしまった。イキモノというかナマモノなんだろうけど。
僕は人間の女の子が恋愛対象ではなかった。獣にしか興味が持てなかった。見つめるだけで胸がギュッと苦しくなり、いてもたってもいられなくなる。対象のことで頭が、胸が、僕という人間そのものがいっぱいになる。世間はそれを恋というらしい。でも、その思いは獣に向けられた。僕の恋は常に片思いだった。初めての恋は動物園のアシカだった。初めて抜いたのは中学のゴミ捨て場によく現れる黒猫だった。ペットは飼わなかった。欲のままに傷付けてしまいそうで、好きだからこそ、怖かった。傷付けたくなかった。獣じゃないと好きになれなかったし、獣じゃないと興奮できなかった。思いが届かないことには慣れていた。届きようがない。届くわけがない。僕は無意識にコハルちゃんと自分と重ね合わせて、愛着を持っていたのだろうか。だから彼女を追い払いもせずにただただ受け入れていたのだろうか。
コハルちゃんが僕を知ったのは、学校でクソマズイと話題になっていたコンビニの「静岡 お茶サイダー」を普通に飲んでいる初めての人だったかららしい。それがきっかけで目が離せなくなり、気付いたら僕のことばかり考えていたのだという。コハルちゃんはそれを愛飲していた。僕は別に「静岡 お茶サイダー」を飲めなくはなかったけれど、コハルちゃんのように好きなわけでもなかった。僕がその話をすると、コハルちゃんはいつも語っていた。
「きょーちゃんを好きな理由なんてない。どこが好きとかもない。理由のある好きなんて、理由がなくなったら好きじゃなくなっちゃうでしょ。私の好きを馬鹿にしないで。私の好きは最強なの。エベレストより高くてマリアナ海溝より深いんだよ」
ゾンビがエッチだのかわいいだのこの異常事態に僕は頭のおかしなことばかり考えていたが、コハルちゃんも大概だった。学校はゾンビにやられてしまったと気付いて、二人で屋上に籠城し始めた時も、僕と二人きりになれて嬉しい、これがずっと続けば良い、と興奮気味だった。ゾンビの目を盗んで防災用食糧を漁っている時も、「新婚さんみたいだね」とはにかんでいた。どこに対してそれを見出したのかは未だに分からない。よろけたコハルちゃんの手を引いてゾンビから逃げた時も「しあわせ」と大声で叫んで、むしろゾンビを引き付けてしまった。隣で眠ったら、性的な意味で襲われるんじゃないかと、恐怖と不安を感じたが、そんなことはなかった。寝たふりをしながらこっそり薄目でコハルちゃんを見たことがある。コハルちゃんは隣で僕をじっと、じーっと見つめていた。噛み殺しても溢れ出ている笑顔で。熱烈な視線浴びながらも、僕は毎晩それなりに眠りに就いた。
コハルちゃんは今の拠点に来てから、二度目の物資収集で、ゾンビに噛まれた。呆気なかった。何が起こったのか分からなかった。身近な人が死ぬってこういう感覚なんだ、と思った。世界が滅んで、僕の「身近な人」はコハルちゃんしかいなかった。起こったことが夢なのか現実なのかよく分からない。そもそも人間がゾンビ化して世界が滅ぶなんて、そんな馬鹿げたことが起こるわけがない。これは長い夢なのかもしれない。
コハルちゃんはゾンビになりかけた状態でここに戻ってきて、最終的にゾンビになった。
「きょーちゃん、ねぇ、きょーちゃん。大好きだよ。きょーちゃんに出会って私、世界が変わったんだよ。生まれ変わったみたいに全部が楽しくて綺麗に見えるようになったんだよ」
コハルちゃんは自ら鎖を巻いた。ふらふらになりながら、汗だくで必死で鎖を壁に固定するためにDIY行為を行うコハルちゃんを、僕は手伝いもせずに黙って見ていた。何だか、全部テレビの向こう側みたいな気がした。
「私の愛はね、たとえ世界が滅んでも、焼き尽くされて消滅しても、宇宙がなくなっても、ぽつんとそれだけが残るような愛なんだ」
コハルちゃんはゾンビになったから僕の恋愛対象になるとは思っていなかっただろう。それとも、ゾンビを見る僕の熱い視線に少しは気付いていただろうか。
「私は絶対きょーちゃんを一人にしない。一人で死なせたりしない。本当はね、おじいさんになったきょーちゃんが幸せそうに老衰で眠るように死ぬのを見届けたかったんだけどね。でもね、私ちゃんとそばにいるから。きょーちゃんがいていいよ、って言ってくれる限りいるから」
もしかしたら、コハルちゃんはわざとゾンビになったのだろうか。彼女は決して慌てず、手際よく己を拘束する用意を着々を進めていた。準備が良すぎる。いや、もしもの時のために用意してただけかもしれない。だって、さいごのコハルちゃんの表情は悔しそうな泣き顔だったから。
ふと、小さな手帳が落ちていることに気付いた。恐らく留守のうちに、どこかから落ちたのだろう。拾い上げると「生徒手帳」と合成革の表紙に彫られていた。知っている人のものだろうか。興味本位で開いて見ると「小山春香」の文字とともに僕には見せたことのない仏頂面のコハルちゃんがいた。生徒手帳はコハルちゃんの物だった。物持ちが良いにもほどがある。思わず笑ってしまった。コハルは名前なのだとばかり思っていたけれど、キムタクみたいな略称だったのだ。続きをパラパラとめくってみても、スケジュールやメモのスペースには何も書かれていなかった。また思わず笑ってしまった。悲しくて。
「ありがとう」
あんなに言われたがっていたくせに、コハルちゃんはただただ屍肉を貪っていた。手を、口を、顔を、服を、黒ずんだ血で汚して一心不乱に食べている。僕の声は届かない。
いつかきっと、僕はコハルちゃんに食べられて死ぬ。
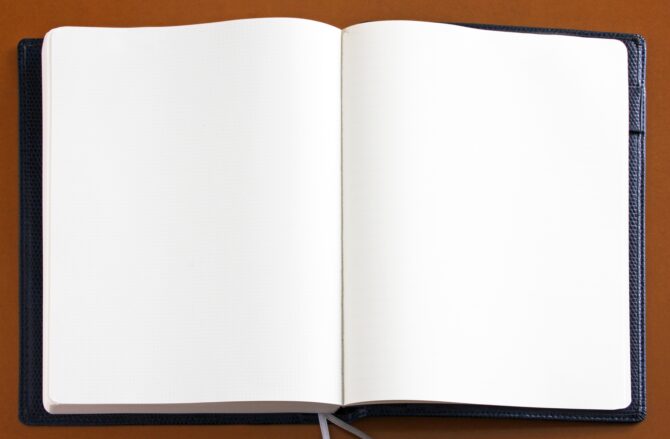






















大猫 投稿者 | 2023-03-22 21:39
やっぱり曾根崎さんにはついていけない。どこがベタな恋物語なんですか。ゾンビになったら初めて愛したって、なんつー変態ですか。面白かったけど、気色悪かったけど。まんまと狙い通りに読まされました。二人の恋に幸あれ。
黍ノ由 投稿者 | 2023-03-23 08:06
かわいいものを見て思わず、抱き潰したり、食べてしまいたくなる衝動をキュートアグレッションというそうです。
ゾンビ化したことで、人の心を失いつつあるように見えるコハルちゃんだけど、きょーちゃんを食べることは実は愛情表現で、すれ違った恋がようやく相思相愛に完結するのだなと思いました。
諏訪靖彦 投稿者 | 2023-03-23 09:13
今では特殊性癖とされる愛する人に食べられたい、愛する人を食べたいという性癖がありますが、東南アジアやアフリカ奥地ではいまだその風習が残っているようです。そう考えると人肉食は価値観の押し付けによって特殊性癖とされてしまったのかもしれませんね。ちなみに人肉食を行っている地域では人肉食によって発現するクールー病という狂牛病に似た病気が残っています。はて。
鈴木沢雉 投稿者 | 2023-03-25 06:22
素晴らしい。ロマンスの高揚感と深さは今回作品中でもダントツですね。コハルと語り手の感情の動きを丹念に追い続けなければこの深さは出ないと思う。
松尾模糊 編集者 | 2023-03-25 12:26
静岡 お茶サイダーが断然飲みたくなりました。コハルちゃんの名前が生徒手帳で判明するくだりは上手いと思いました。コハルちゃんはこの世界設定でなければ完全にただのストーカーになるところを、ゾンビ化で反転させるあたり、お手本のようなロマンスを読んだ気がします。ありがとうございました。
小林TKG 投稿者 | 2023-03-26 19:12
ゾンビの目を盗んで防災用食糧を漁っている時も、「新婚さんみたいだね」とはにかんでいた。っていうこの一文が最高に好き。私もどこが!? って思いました。最高に好き。
波野發作 投稿者 | 2023-03-26 23:06
切ないですねえ。東西の地獄観には生きたまま食われる系のものがよくありますが、この者にとってはそれすらも快楽なのでしょう。南無三。
ヨゴロウザ 投稿者 | 2023-03-26 23:54
いずれコハルちゃんに食べられて死ぬという諦観はなんだかんだコハルちゃんを受け入れているのか、ただの無関心からなのか。どちらにしてもコハルちゃんの多分にひとりよがりな匂いがする一途さと、それを突き放した目で見ている僕の、両者の視線の交わらなさが良かったです。欲を言うとそれをもっと強調してほしかったような気もしました。
余談ですが、むかーしの知り合いに鳥を見ると勃起するという異常者がいたのを思い出しました。
退会したユーザー ゲスト | 2023-03-27 00:44
退会したユーザーのコメントは表示されません。
※管理者と投稿者には表示されます。
Juan.B 編集者 | 2023-03-27 19:51
人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない。がんばれ、ふたり。
Fujiki 投稿者 | 2023-03-27 20:37
いいじゃないか、獣姦の変態に愛されるためにみずからゾンビになる変態のロマンス。関係ないけど、宝塚線の十三駅は急行も止まるので便利そうだと思った。
諏訪真 投稿者 | 2023-03-27 21:24
あ、こっちにコメントし忘れてた!
最高にヤバい性癖ですね!(褒め言葉