朝から既に容赦のない太陽の日差しと、ぬめるような湿度の中、二人を乗せた車はどこまで続くとも知れぬ未舗装の道を土埃を上げて走っていた。やがて前方に何か見えてきた。「あれは」車の列であった。どうやら渋滞しているらしかった。
※
「アキタ」
アキタが名前を呼ばれて振り向くと、そこには日本から来たジャーナリスト、その男が自らをそう言った。彼はけだるげに陽の光に目を細めていた。手を庇のようにして額にあてて立っていた。アキタにはこのジャーナリストというものがどういうものなのかいまいちよくわからなかった。
「簡単に言うと」
男の説明したところによれば、「簡単にいうと」この現状を他の人間に知らせるという仕事だそうだ。そうなのか。そういうのもあるのか。はあ。ふーん。しかしそれでも、どうも、いや、なんとなく。
「アキタ、そろそろ行けるか」
男はロペ国立公園に行きたいんだという。日本、極東から来た、わざわざこんな所まで、ガボンという国に来たそのジャーナリストはこのガボンという所にある、広大にある、広大すぎるくらいある、ありすぎるほどある、地面に落ちてる石ころ位ある、自然の、その中の、アキタがガボンの説明としてそのような話をすると、
「津原泰水の本の中にもそういう事を書いてるのがあったな、何だっけな。瀬戸内にある島の数も……なんだっけ、手を洗った時に両手に付着した水分くらいだったかな、島があるとかって……」
ぶつぶつ言いだしたジャーナリストに何の話をしているのか聞くと、
「いやいい、こっちの話だ。死んだ人間の話だよ」
「それよりも」アキタ、ガボンの森、マルミミゾウの森にはもう行けるか。ジャーナリストは気を取り直すようにして言った。
「ロペ国立公園の事だろ」
極東顔のジャーナリストはロペ国立公園の事をマルミミゾウの森と言った。
※
昨日、前日このジャーナリストを名乗るアジア人は、唐突に、突然にアキタの住んでいる集落にやってくると、流暢な、綺麗、綺麗すぎてアキタは少し怖い気がした。いつの事だったか首都リーブルヴィルに行った時に通りかかった立派な教会から聞こえてきた、多分純正の仏蘭西人の様な仏蘭西語で、
「誰かこの中に、マルミミゾウの森まで連れて行ってくれる奴はいないか」
と声を張り上げた。
「金は払う」
手にはCFAフランの紙幣を十枚くらい握っていた。それを見せびらかすようにしていた。その場にいた誰もが「あいつは、考え無し、間抜けなんだろうな」と思った。それはそう。仕方ない。極東、アジアとか他がどうだか知らない。でも、ただでもガボンでは今も昔も、昔からずっとすりやひったくりが多い。横行している。そんな環境だから、あんな風に金を見せびらかすような奴はいない。男の綺麗、怖い気がするほど綺麗な仏蘭西語と、金を見せびらかすその姿は随分とアンバランスに感じた。いや、アキタは知らないが、もしかしたら植民地時代の仏蘭西人はあんな感じだったのかもしれない。
とはいえ、基準というものがあるかどうかはわからないが、アキタはいい人間だった。何が、何をするといい人間なのかは知らない。でもとにかく、アキタはそのアジア人の元に近づいて、
「私は車を持っているので、あなたをその森まで連れて行くことが出来る」
と述べた。男は少し身を引くようにしてから、目を細めてアキタを見た。その時この男は、手に握っていたCFAフランの紙幣の束をズボンの脇に押し込めるようにして仕舞い込んでいた。それは男の体の動作や目を細めるような行為とは違って素早い動きだった。
「お前名前はなんていう」
「アキタだ」
「秋田、秋田って言ったか? ははは、ふーん」
男は少し笑うと、アキタはなんで男が笑ったのかわからなかった。その後少ししてから理由は説明してもらった。
「アキタは何の車に乗ってるんだ」
「あれだ」
アキタが指さした所には無造作にピックアップトラックが停まっていた。
「トヨタのだ。日本の車だろ。知ってるだろ」
「あれは、ハイラックスか……」
男はそれを見て、呆然としたような顔をした。トラックだからだろうか。ぼろい、ぼろく見えるからだろうか。しかしガボンにある道は、当然のことながら、ほとんどが未舗装のままだ。場所によっては穴が開いていたり酷くぬかるんでいたりする。その点あの車は大丈夫だ。とても丈夫だからだ。去年死んだ父がアキタにあの車を残した。残したというか。たまたま。父が死んだから。偶然。たまたま。アキタにあの車が残った。父がどういう経緯であの車を手に入れたのかとかは知らない。ちょっとくらい、もしくはたくさん悪い事とかをしてたのかもしれない。首都リーブルヴィルでは若者を中心にドラッグが流行っているそうだ。そうしてあの車を手に入れたのかもしれない。しかしアキタには関係なかった。アキタはドラッグもしてなかったし、悪い事もしていなかった。すりとかひたっくりとか、人を殺したりとか。そういうことはしてない。父が死んだという知らせが来て、アキタの元に車が来て、しかしその車を奪いに来るような人間もいなかった。その集落にある唯一の自動車整備工場に車を持っていって見てもらった時、整備士のオノは最後に、
「全部の隙間を見たけど、ドラッグとか金とかは隠されて無かった。よかったな」
と言った。ドラッグや得体のしれない金が無いという事はまあ、大丈夫という事なんだろう。おそらく。
「途中で停まっちまったりしないか」
「大丈夫だ」
多分。多分、大丈夫だろう。知らないけど。アキタ自身、あの車でそんなに遠出したりしたことが無い。その男はマルミミゾウの森といった。マルミミゾウ。Éléphant de forêt d’Afrique。Loxodonta cyclotis。Forest elephant。少し前にナショナルジオグラフィックという雑誌にその森、ガボンの森、マルミミゾウの森というのが載った事があるらしい。そこで間違いないとしたら、それはロペ国立公園になる。それはアキタが住んでいる所からは結構遠い。アキタの住んでる集落からは三、四時間かかる。遠かった。まあここから首都程ではないが、でもそもそもその時は、アキタが首都に行った時は鉄道で行ったのだし。
「というか、お前」
「俺はジャーナリストだ」
その極東人は自らをジャーナリストだと言った。綺麗すぎて怖い気がする仏蘭西語で。
「ジャーナリストはどうやってここまで来たんだ」
「鉄道に乗って来たよ」
ガボンにはトランスガボン鉄道というほぼ唯一の鉄道が走っている。これは首都リーブルヴィルからコンゴの近く、フランスビルまで走っている。だから、
「ロペ駅があっただろう」
ロペ国立公園はガボンの世界遺産になっている。だからなのか、いや、関係あるか知らないが、とにかく駅がある。ロペ駅という駅が。ロペ国立公園に行くならトランスガボン鉄道を使うのが一般的だったはずだ。アキタも別に国立公園には行ったことないが、それでも知ってる。車で行くのは大変だ。未舗装だからだ。
「途中で降りたんだ」
極東顔のジャーナリストは当たり前だろうというような調子で言った。
「なんでだ」
何で降りたんだ。
「大変だったんだ。途中、駅でも何でもない所で停まるし。あと暑くて。トイレも酷かったし」
「ああ……」
忘れてた。この極東顔のジャーナリストは考え無しの間抜けだったんだ。そうか、そうだった。
とにかく、そんな訳でアキタはその極東顔のジャーナリストをロペ国立公園まで車で連れて行くことになった。最初は近くの駅まで、そこまでだったらさすがにアキタも車で、ピックアップトラックを運転して行ったことがある。しかし、極東顔はそれは嫌だと、頑なに、拒否した。
「いい天気だろ。明日も多分いい天気になるだろ。だから連れていってくれ。車で」
アキタ自身も詳しくは知らないが、車で行っても難所はあると思うぞ。何か所も。酷い目にあうと思うぞ。そう思ったが、でも黙ってその提案に合意した。前金に、「前金にとかって言ってみたかったんだよ」極東顔のジャーナリストがそう言ってにやにやした。ついさっき見せびらかしていた金を全部くれたし。無事にロペ国立公園に到着したら、更に同じ額くれると言ったから。その後とても渋い表情で、苦悶の表情で、
「帰りは鉄道で仕方ないか。もう、嫌だけど仕方ないな」
と、自らに言い聞かせるように、ぶつぶつと言っていた。
アキタの住んでいる集落にはホテルが無い。だから極東顔のジャーナリストはその日、アキタの家に泊まった。夜になる前に二人で車に乗って集落を出てスーパーのある町に行った。そこで極東顔の金で、食べ物やビールを買って、ガソリンスタンドに行ってガソリンを満タンにして、帰りに集落にある自動車整備工場に行って、車の点検してもらった。
「何処も異常ないよ」
整備士のオノはそう言いつつ、助手席に乗っていた極東顔のジャーナリストをちらちらと見ていた。アキタは、
「ロペ国立公園まで無事に行って帰ってこれるかな」
と尋ねた。それでオノはなんとなく察したらしく、
「大丈夫じゃないか。最悪あいつを捨てたらいいさ」
そう言ってから、歯を見せて笑った。
「何かがあった時の為に持っていくか」
オノが助手席をちらちらと見ながら大きなパイプレンチを寄こしてきたが、アキタは断った。
「帰ってきてからでいいんだが、仕事があるんだ。運んでもらいたいものがある」
「急ぎか」
「いや、急ぎじゃない。でもまあ、だからなるべく早く帰ってきてくれ」
整備工場を出るとアキタの粗末な家に戻った。夜、家の寝床をジャーナリストに使わせて、アキタはピックアップトラックの荷台に敷物を敷いて寝た。
寝る前にジャーナリストが、
「マルミミゾウは日本では〇三三三って書くんだ」
と教えてくれた。
「それと同時にこれは0333っていう意味でもあるんだよ」
その数字には何か意味があるのか。アキタはそう聞いたが、ジャーナリストは何も答えなかった。
※
空には雲が無く、故に日陰になるような所はほとんどなかった。それに加えて湿度がひどく、窓を開けていても自然と、コカ・コーラの缶の様に汗が噴き出した。車には一応クーラーもあったが、壊れているのか殆ど効かない。道は未舗装で、場所によっては穴が開いていたり酷くぬかるんでいたりした。
「ひどいな。本当にひどい。酷いもんだ」
助手席に座った極東顔のジャーナリストがうめいた。アキタは心の中で、だから鉄道で行けばよかっただろう。そう、つぶやいた。
しかし進み続ければいつかは終わる。どんな形であってもいつかは終わる。必ず終わる。容赦のない太陽の日差しと、ぬめるような湿度の中、どこまで続くとも知れぬ未舗装の道をアキタの運転する車が走っていくと、やがて前方に何か見えてきた。
「ありゃなんだ」
ジャーナリストが言った。しかしアキタは黙っていた。アキタにもそれが何かわからなかったから。
更に車を走らせて近づいていくとそれは車の列であった。どうやら渋滞しているらしかった。こんな場所で。360度全てが。全てが自然。木々、草、空、空気、森、土、全てが自然に囲まれている。こんな場所で。
その渋滞の最後尾に車を停めると、二人は、アキタとジャーナリストは車を降りた。そして車列の間を、ほとんど適当に停めて連なっている車の間を先に向かって歩いた。『鴨ヶ谷行き』と書かれている窓ガラスも無いような小型のバスを越えた辺りで、唐突に視界が開けた。バスの先には、車の持ち主達だろう。人だかりが出来ており、皆一様に同じ方向を見ていた。ただ、黙って、何も声を発することなく、ただ、先に広がる光景を見ていた。
線路があった。トランスガボン鉄道の一部だろう。その更に先に森が広がっていた。あれが、目的地なのだろうか。「あれは」極東顔のジャーナリストが言った。あれが、ナショナルジオグラフィックに載ったという。ガボンの森。マルミミゾウの森なのだろうか。
そしてそこから、その森からゾウが排出されていた。ゾウが列をなして森、木々の間から排出されていた。森から、木々の間から。ゾウが、ずっと。あれがマルミミゾウなのだろうか。マルミミゾウ。Éléphant de forêt d’Afrique。Loxodonta cyclotis。Forest elephant。みな一様に、その、その森、木々の間から排出されて、線路を渡って、どこかに、どこに行くのか知らないが、ゾウが。列をなして。どこまでも。ずっと遠くの方まで。森から出てくるゾウ達は皆一様に元気が無く見える。見えた。辛そうだった。あばらが浮き出ているゾウも多い。鼻をあげ耳を振り、ゾウの、そのゾウの、ゾウ達の列は途切れることが無かった。アキタはロペ国立公園がどれくらいの規模なのかもよく知らない。でも、その様子は異様だった。いつまでも途切れることが無い。ゾウの群れ、列。町の電気屋にあったテレビでマジック、手品を見たことがある。何もないところから、カードやコインが出てくる。そういうのを想起させる。森の、木々の間から、ゾウ。マルミミゾウ。途切れることのないマルミミゾウの群れ。列。終わる事のない群れ。列。行軍。
アキタの隣に立っていた老人がぼそりと、アキタの脳みそ、思考を察したかのように、噛んで含めるようにして、
「もうここにはあいつらの食べるものが無いんだ」
そう言った。マルミミゾウの森にはもうマルミミゾウのエサが無い。だから夜中になると近隣の家々の菜園まで来てそこを荒らすんだという。それを住人はロケット花火などを使って追い払っていた。ロペの町は何とかゾウとの共存を、共生を、共に生きていく道を模索していたそうだが。しかし、しかしこれはつまり……。
アキタが、アキタも含めてその場にいた全員が呆然とその光景を見ていると、その中から一人、マルミミゾウの列、群れに向かって走り出した奴がいた。見慣れない肌の色。ジャーナリストだった。ここまでアキタの車の助手席に乗っていた極東顔のジャーナリストだった。
ジャーナリストは猛然とゾウの群れに向かって走っていった。周りの人間は、危ないからやめろ、よせ、と止めようとしていたが、ジャーナリストはそれらを乱暴に振り払ってゾウの列に向かって闇雲に走っていった。そうしてやがて草木に紛れ、砂埃に紛れ、ゾウの群れに、列に紛れて見えなくなった。
それっきり戻ってこなかった。極東顔のジャーナリストも。ゾウ。マルミミゾウも。行軍。あの膨大な群れも。それっきり戻ってこなかった。
※
永遠とも思えるゾウの群れ、行軍、列は、昼前に終わってしまった。アキタには永遠にも等しく思えたが、たかだか一時間弱程度の事であったらしい。もう一頭のゾウも出てこない。残っていない。気配もない。自然の、風の音だけがする。した。
ゾウが、マルミミゾウの行軍が、ゾウの気配があたりから綺麗さっぱり無くなると、そこに集まっていた人間は一人また一人となんとなく浮かない表情で車に戻って走り去っていった。ゾウの為に起きていた渋滞は解消された。
極東顔のジャーナリストは戻ってこなかった。いつまで待っても戻ってこなかった。夜になっても戻ってこなかった。仕方がないのでアキタも車に戻った。それからなんとなくカーラジオをかけた。
雑音の酷いカーラジオからは聞き慣れない曲が流れてきた。Wednesday Campanella。Mercredi Campanellaとかいうののなんとかっていう曲だそうだ。jean dupontだかJohn Doeだかって。アキタはその間ずっとフロントガラスの先を見ていた。森。ガボンの森。マルミミゾウの森。ロペ国立公園を見ていた。ゾウのいなくなった森。マルミミゾウの森。ガボンの森。
アキタはロペの町で一晩あの極東顔のジャーナリストを待った。助手席にはジャーナリストが持っていたカバンが残ったままだった。中を検めると、大量の金、CFAフランではない。が入っていた。ドル紙幣。シンガポールドルの。くしゃくしゃの50ドル紙幣が輪ゴムで括られて。大量に。何束も。カバンに詰められるだけ。仏蘭西軍のダッフルバッグみたいなのに。入れれるだけ。ギチギチに。
あとiPod。iPodtouchが出てきた。ホームボタンを押すと四ケタのパスコードを求められた。少し考えてから0333と入れると開いた。音楽をシャッフルで流すと、聞いたことがある曲が流れてきた。さっき聞いた曲だった。さっきラジオで聞いた。Wednesday Campanella。Mercredi Campanellaのjean dupont。John Doe。名無しの権兵衛が流れてきた。
次の日の朝、アキタはロペの町の電気屋に行って、iPodtouchを車で充電したいと店員に伝えた。充電コードとシガーソケットで充電できる車載充電器を昨日ジャーナリストからもらったCFAフランで購入した。
車に戻ると、店員に説明された通りにしてiPodtouchを充電した。それからまた名無しの権兵衛をかけた。あれっきりマルミミゾウも極東顔のジャーナリストも戻ってこない。一生戻ってこないような気がする。した。でも、それでも、なんでか、なんとなく、アキタにはマルミミゾウもあの極東顔のジャーナリストも大丈夫な気がする。した。救い。それが何なのかアキタは詳しくは知らない。でも、それでも救われた、救われるような気がした。する。した。なんでか。なんとなく。
目を瞑れば、アキタがピックアップトラックの運転席で目を瞑ると、一時、ガボンのこの暑さ、苛烈な陽の光も、まとわりつくような湿度も忘れる、忘れた。代わりにゾウの群れ、列、ガボンの森、マルミミゾウの森、ロペ国立公園から排出される、隊列を組んでどこかに向かうようなゾウの群れ、列が見える。見えた。その中に、その脇にはジャーナリストが居た。それからあと、父もいた。死んだはずの父。それ以外にも見ず知らずの人間が沢山いる。いた。人間だけじゃない。他の生き物もいる。沢山いる。いた。彼らはどこに行くつもりなのか。どこまで行くつもりなのか。でも、きっと、あの行軍は救われるような気がする。何が救いが、どうしたら救われるのか、よくわからないが。それでも。
それでも。
なんとなく。
アキタはいつか行った首都リーブルヴィルで見た教会の事を思い出していた。中から聞こえてきた怖いくらいの仏蘭西語。あの純度の高い。怖いくらいの。
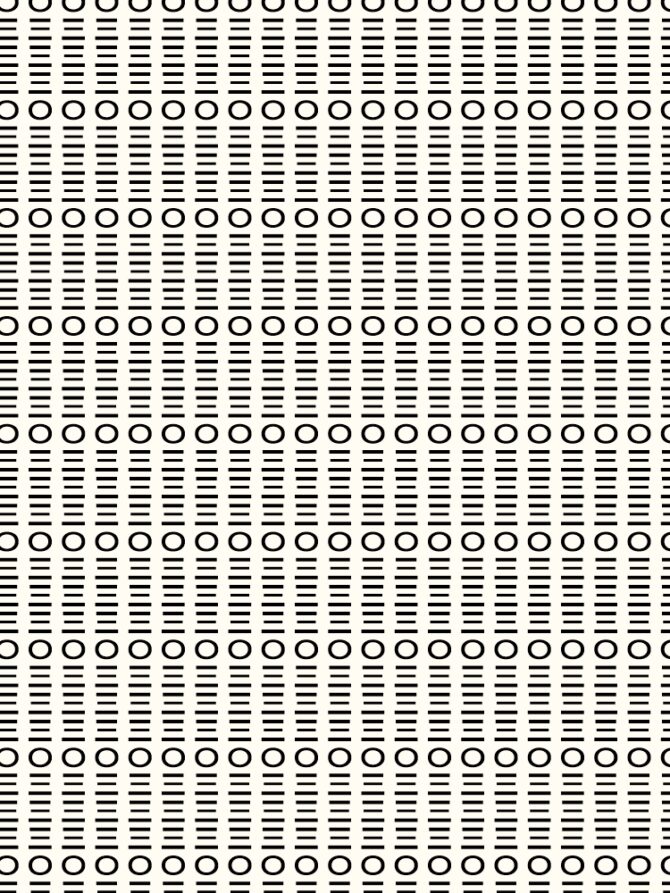






















"〇三三三の森:ディレクターズカット"へのコメント 0件