遂にドロップアウトして田舎へ帰る帰路の道々、お金は足りたけれども、心の心細さが細いから、ヒッチハイクすることにしたのであった。
高速によじ登って、親指を立てた。
すると急に世の中ちょろいもので、間もなく未開封の避妊具を唇にくわえたグラマラスなお姉さんの運転する真っ赤なスポーツカーが停まったのである。
――けれども、早い話が、お姉さんは訓戒だけ宣うて去ったのであった。
クンカイお姉さんいわく、ヒッチハイクにも然るべき作法がある。ちゃんとボードを掲げて、それから、も少し悲愴感を出すこと。もっと薄汚れて、出来るなら服も破って、血の二、三ヶ所もにじんでたらmore betterね。
ボードには目的地を読みやすい字で。そして自己PR。タダで乗せてもらって、長時間一緒に過ごすわけだから、趣味や性格が合わなければ、なかなか停まってはもらえない。じゃあ、幸運を祈る!(投げキッス、土煙。)ふたたび世の中は冷淡であった。
私はいったん地上に降りて、段ボールと太ペンを按排すると、書き始めた。《兵庫県まで》。それから、自己PRはどうしようか。一般的に望ましかろうことや、近頃流行りのことでは勝ち抜けぬ。私の得意なことだ。これなら人に負けないというものだ。
それでけっきょく、《都市の愚痴言います》と書いた。
これなら何ぼでも言える。何しろそこから逃げ帰る、怨念の塊であるからして。
ボードを高々と掲げて、誰ぞ停まってくれるまで、頭の中で噺を並べた。何を高座にかけようか。汚れタワマンだらけの歯周病地帯にいたものだから、たいがい通用するだろう。
家もヒドカッタ。上階で流す響きがすれば、便所を見に行くのである。すると果たせるかな、見覚えのない大便が漂っておるから、流すのである。そしてしばらくすると、下階でも流す音がするのであった。
淀んだ空気、濁った水、嘘くさい食事等々に体が慣れる頃には、新鮮な果物など食うと、かえって下すようになっていた。下すもの、の意から、くだものという。語源の一席。
嘘くさい食事とは何ぞや。ある日、近所の弁当屋で買った弁当で夕食を済ますと、アナフィラキシーを起こした。後日アレルギー検査をしたけれど、表記されている原材料には見当たらなかった。
ただ、私の重篤なアレルギーに、カラスやネズミが見つかった。――だいたいそういうところを淡々と話せば、そうお耳汚しにもならなかろう。
さて、いつまで経っても誰も停まってはくれなかった。けっきょく私の戦略は拙く、私の展望は甘く、私の長所は未熟で、世の中は相変わらず世の中なのであった。
日が暮れてしまう前に、《何でも聞きます。こちらは一言も発しません》と書き直して、掲げた。
間もなく一台のトラックが停まった。
*
ドライバー様による序文
私は長らく辺境へ行って来た。そこで多くの人々や現象と出会ったが、今になって考えてみれば、そこには無秩序や混沌があったばかりでなく、興味深いものも混じっていたように思われる。浅学菲才にして一個の作品にまとめることは出来ないが、散漫にべしゃるだけでも、我々の精神にとって何かしら有益な、そうでなくとも純粋に楽しみとなり得るものが潜んでいると思われるのである。以上の理由から、記憶を頼りに、ちょっと話してみることにする。
*
一 蛇
辺境の蛇は歌を歌った。
昔々の、吟遊詩人のようだった。
辺境の蛇は、高貴な人々から寵愛を受けていた。
召し抱えられた蛇たちは、美しい歌を歌った。
召し抱えられない蛇が歌を歌ったかどうか、私は知らない。召し抱えられない蛇を見ることは遂になかった。
私が聞いた歌は、哀歌だった。
自分たちの不遇な身の上を歎く歌だった。悲しい繁殖の歌だった。
時には品を欠いて、私の恍惚に水を差し、それ以降は、ありふれていて退屈だった。
蛇たちは、尻尾を噛んだ形が象徴になること、交尾の長さが象徴になること、軒下へ住み着く様が象徴になること、そのようなことも歎いた。
高貴な人々は、蛇たちの歌に耳を傾けて、涙を流していた。
二 方角
ある地域では、方角という概念が死んでいた。
方角に該当する言葉は、誰もが知っていた。しかし意味を持たない言葉だった。
そこの人々には、全ての空間が、ことごとく判然としていた。
方角を漠然と示すということはなかった。誰々の家、見果てない荒野のある箇所、大海原のある地点、地下のどこ、星のどこ、それらが方角に代わっていた。
そこの人々に、知覚出来ない場所はなかった。
誰もが生得的に知覚していた。その代償か、言語を失った人がたくさんいた。
しかし言語の有無に幸不幸はなかった。
綿毛がどこから飛んで来たのか、問えば、綿毛の飛んで来たルートはわからないが、生えていた場所はわかった。
私は判然としない場所という概念をそこで作ろうとした。そうして方角に生命を与えようとした。
しかし失敗に終わった。そこにいた時は、私もまた、全ての空間が判然としていた。
三 時間
全ての時点を把握している人々がいた。
彼らは未来や過去という概念を用いなかった。彼らには判然とした時点があるだけだった。
この完成された時間の住人は、絶望も希望も持たなかった。
私も彼らに教わり、全ての時点の把握を試みたが、失敗に終わった。
未来において発狂している自分を私は確かに見、そして彼らに連れ戻された。
その記憶だけが残った。
四 タガメ
辺境のタガメはよく石の中に潜っていた。
臀部から伸びた管で酸素を吸い、大気中の思念を吸っていた。
石から管が出ていると、そこにはタガメが潜っているしるしだった。
近寄れば、発達した前足で捕らえられ、口の針を刺し込まれ、麻酔液と消化液を流し込まれて、未整頓の記憶や腐った感傷を飲まれた。
タガメの餌食になった人は、あるいはノイローゼが治り、あるいは馬鹿が悩み始め、あるいはアトピー性皮膚炎がすべすべした。
タガメの麻酔液を精製して安楽死に用いる国があった。
タガメは空に卵を産み、雄が見張った。卵は風にも流されず、そこに付着していた。何か飛んで来て当たったり、棒で殴ったりすればこそぎ取ることは出来た。あとに残った粘液は、卵がこそげると地面に落下した。
卵からはやがて子どもが産まれたが、それはタガメには見えなかった。
辺境のタガメは自身の卵から産まれて育つのではなかった。
タガメの卵から産まれたものは風下や川下に流れて行ったが、その後どうなるのかはようとして知れなかった。
五 犬
辺境の犬は無数に枝分かれした種類が、それぞれの延長で安定と平均化を完了し、大・中・小の三種類のみに落ち着いていた。
大型犬は、大型犬病でも患わない限りたいへん頭脳優秀で、人間にはどんな相手にも完全な忍耐を見せ、忠実だった。
患った大型犬は飛行船でも襲った。
中型犬は野生に返って気楽にやっていた。森の中や草原で出くわしても、群れ全体でそそくさと逃げて行き、極めて温厚だった。
小型犬は愛玩され、飽きられて捨てられては野生化し、一匹残らず消えていた。
小型犬は、下等市民や特定の職業人からの需要しかなかった。
王族や上等市民、また蛮族は犬を嫌っていた。
六 洒落
辺境の洒落は、言葉と記憶がかかっていた。
その記憶は、個人的なものから天体的なものにまで及んだ。
どこまで高遠で、あるいは理解不能な記憶とかかっている洒落でも、洒落と成り立った瞬間に、理解することが出来た。
あんまり高度な洒落を聞き過ぎた人は廃人になった。
高度な洒落を思いつく人は、たいがい生涯に一個だけ思いつき、厳重に保護された場所で書き残して、精神病院に行くか、野に放たれた。
野に放たれた末期者は、世界を美しそうに眺め、獣や虫に食われて死んだ。
私もいくつか聞いた。しかし覚えていない。
その時私は、たいへん高度な洒落を確かに理解し、笑い転げたはずだった。
七 星座
辺境の星座はたいへんゆっくりと形を変えた。
星々は違う速さで回り、近づいては離れた。
そうしてあちこちで、それぞれの周期に従い、ふたたび同じ星座を呈していた。
何百年前の何々座はもっと細かったとか、もっと背景によく合っていたと、酒場でベニテングダケのウイスキーを奢らせてもらった老人が言っていた。
老人よりも古い人々は、星座にまつわる神話を語ったが、中でもストックが多く、また話術の巧みな語り部は、星に名前を付ける権利を持っていた。
けれども、そこまでに達した人々は必ずその権利を辞退していた。
八 イソギンチャク
辺境のイソギンチャクは無限と思われるほど種類を増やしていた。
私がじかに触れたのは、たまたま出会った孤独そうな老婆と浜辺で遊んでいた時、磯にいた個体だった。
触手を伸ばし、波に揺れながらその先端を成長させていた。
老婆が言うには、その先端は激しく分かれ、淘汰し合い、複雑になり、遊び始め、言語を持ち、謎と問答を作り、神話を作り、秩序を作り、都市になり、神話を崩壊させ、混沌として、胞子をやたらに飛ばしていた。
私と老婆が触ると、全てを引っ込めた。
九 カメレオン
ある朝、モーテルで目が覚めた時、何もかもが爽やかで、数年間悩まされていた神経不安も、数ヶ月間悩まされていた腹痛も、数週間悩まされていためまいも、数日間悩まされていた衝動的な晴れやかさも消し飛んでいた。
私はあちこちを、新たな心持ちで以て見て回った。
じつに色々と新鮮な発見や再確認をしたが、とりわけ、モーテルの裏庭の庭木にカメレオンがくっついていたのは嬉しかった。
カメレオンは体の色をたいへん薄くして、それは木の枝とは似なかったが、そこにそんなカメレオンがいることは、その木にとって完成の誉れではなかったか。
しかし彼を見つけるには、たぶん彼に起因せず、何か別の拍子で以て、物事が新たに感ぜられるような心境や体調を呈することが必要なのではなかろうか。
ェえ? ――違うか。
十 河馬
辺境の河馬は非常に大きく、異様なほど温厚で、狩られるなら狩らせ、狂わせられるなら狂った。
有史以来立ち続けているかのような最高齢の河馬は、彼方の山脈の向こうに見えていて、背中の垢に根を張った摩天楼群は、高度が高過ぎるため、地上のよりも宇宙の鳥が多く住んでいた。
鳥たちは互いに罵り合い、騙し合いながら共存していた。
小さな河馬もいた。
河馬が水の中で糞をすれば、そこへ群がって食べた魚は色鮮やかな熱帯魚になり、たいていは親のため、自ら高値で売られていた。
陸で糞をすれば、良質の煙草やコーヒーが育った。
一頭の河馬が言語を持ち、人間社会の政治家になったことがあると聞く。
彼女は、あらゆる栄枯盛衰を、笑いに変えた。
彼女が書いた書物は今でも深刻な学者たちに愛読されていた。
子どもの河馬の肉は癌を癒し、理性を狂わせた。
死んでやや経った肉は脳内に安楽な作用を及ぼし、終末医療に音楽を添えた。
十一 アブラゼミ
辺境の蝉はたいへん美しい声で鳴いた。
その声は金属音にも水音にも似ていた。
蝉の種類は極度に多様で境界があやふやだった。
ある城の塔に居候していた時、窓から入って来た蝉を見て、私の知っているアブラゼミに似ていると思った。
アブラゼミは雄でも雌でもなかった。
両性具有でもなく、生まれながらの完結、種の終着だった。
アブラゼミは死にに来たように鳴き始めた。
私はそれに詩をつけた。
その詩が合い始めた時、アブラゼミはサナギになって、翌朝背中が割れると大輪の花が咲いた。
花は強い芳香を放った。私はくらくらした。
その時女王陛下が御用聞きに現れたので、私はブランデーを頼んだ。
女王陛下は私の無礼をなじって消えた。
私はアブラゼミの花を押し花にして持ち物に加えた。
押し花にしたため、アブラゼミが花の次にも変態をしたのか、したとしたらどうなっていたのか、知る機会を失したが、私の鞄の中では押し花の放つ芳香の何かが、どうやら黴よけの効能を成していた。
十二 ミミズ
私が空腹を抱えて地平線まで続く浅い川を眺めていた時、遠く近く跳ねる魚はじつに美味そうだった。
その間は魚はどのように工夫を凝らしても捕まらなかった。
美味そうに思われなくなった頃、一尾の魚が私の前に自ら打ち上げられた。
私は魚を手のひらに乗せて、川へ投げ返した。
その時、地面から歌が聞こえた。私には高次の卑猥な文句に聞こえた。
見るとミミズが顔を出していた。
ミミズは死の覚悟を決めかねたまま、とりあえず私を讃えた。
私はミミズを餌にして釣りをした。
かぎ針に突き刺され、流れにさらされて死にゆくミミズに思いをはせた。
世界を描き損じてかえって世界に加わる芸術家たちの住む地下街や、敗死したことで成功した行動家たちの眠っている地層をミミズは耕して来たことだろう。
あんがい逃げ出して来たのだろうか。そのようなことを考えていた。
やがて魚が釣れた。さっきの魚に似ていた。
私は諸々の状況を確認せねばと思ったが、空腹に負けて、魚を即座に煮て食べた。
非常に美味しかった。
十三 トンボ
辺境のトンボは小さかった。
あまり小さいのでトンボだとは思わず、トンボに似た虫で、別物だと思っていた。
一番大きな閻魔ヤンマでも、蜂や虻に食べられていた。カゲロウと喧嘩をしても負けていた。
けれどもヤゴは大きかった。ナマズや鯉を襲っては食べていた。
人間も時々襲われて、駄目になった手足を切断する人もあった。
ヤゴはヤゴである間に生殖し、ヤゴを産んだ。そうしてヤゴのまま死んだ。
この営みの中から、時々トンボになる個体が現れるのだった。
トンボは小さく弱くなり、愚鈍になり、泣きながら空を飛んでは、世界の夢を見ていた。
自由や慈悲に向かって空しく飛び回り、そうして蜂や虻に食われた。
どこかに、トンボが産んだトンボがいるだろうか。
私はトンボが産んだトンボの存在を信じている。
十四 猫
辺境の猫はたいへん気ままだった。
神が機械的唯物論を作ったのだと主張する猫もいたし、自らを神と主張する猫もいたし、それを崇める猫もいた。
総じて不真面目だったから、何の諍いもなかった。
化ける個体もいた。
じつに様々に化けたが、人間の女に化けた猫は美しかった。
女優や歌手にもいたし、田舎の小国へ行けば女王もざらだった。
私も化け猫の女に恋をしたことがあった。極めて短期間、遊ばれただけだったが、トラック野郎の中には、向こうに惚れさせる伊達男もいた。
さんざん貢がせて逃げたり、無理心中されたりしていた。
中には粘膜の摩擦にうつつを抜かして、泌尿器科医のお世話になり、とうとう脳を犯されたのもいた。
彼が精神病棟で口走った譫言から閃かれたワクチンや発電システムがあった。
猫は男にも化けた。
騙されて子どもを産んだ人間の娘は、どうせ長生きしない仔猫に母乳をあげていた。
十五 鈴虫
辺境の鈴虫は弱いくせに飼育されるたび逃げ出しては野生化し続けた。
やがて、どれだけ淘汰されても増えた。そうしてあらゆる秋の音色を粗悪にした。
その騒音被害は相当なものだった。聞くに堪えかねて人々は大掛かりな駆除に乗り出したが、どうしても全滅出来なかった。
減らせば減らすだけかえって増え、音色はいっそう粗悪になった。
とうとう人々は屈服した。鈴虫は食物連鎖の頂点に君臨し、秋の音色は苦痛の代名詞になった。
その鈴虫が集団自決した。各地で申し合わせたように同時の出来事だった。
それで何もかもが以前に戻った。
その後も鈴虫はいたが、もう鳴かなかった。
十六 オオイノシシ
辺境の避妊具はオオイノシシの消化管で作られていた。
一般に、部位が口に近づくほど高価で、肛門に近づくほど安価だったが、品質にそう変わりはなく、たいへん薄くて頑丈だった。
オオイノシシは辺境の中央(もっとも辺境の中央は、私が知る限り三つあったが。)の、時おり星に引っかかっては地震を起こすほど高い大山を取り巻く樹海に棲息していた。
避妊具の製造過程を詳しく知っているわけではないが、最初の洗浄にはアルコール度数が三百パーセントを越える杉の荒焼酎が用いられた。
女性たちによる、パートナーだけでなく、オオイノシシにも抱かれているようだというジョークがあった。
避妊具を使い過ぎて子豚を生んだという話も各地にあった。
十七 チューリップ
辺境のチューリップの花弁の中には必ず完成された都市があった。
そこには何の破綻も葛藤もなかった。
そこに住んでいるのは小人ばかりだった。
辺境の学者の最たる人々、雲上の山腹に住む高次の大学教授たちも、小人の言葉を解せなかったので、我々は完成された都市の秘訣を吸収出来なかった。
チューリップは花弁を早く散らした。
小人たちはそのたびに何の痕跡も残さず絶滅し、また翌年季節が来ると、完全無欠に栄えるのだった。
十八 蝋燭
辺境の明かりには蝋燭が用いられていた。
街灯も何も蝋燭だった。
ある大都市では、何世紀も減らない巨大な円柱の上に、風に揺れることもない巨大な炎がとろとろと立っていた。
辺境では蝋燭が容易く取れた。畑からも川からも動物の死骸からも取れたし、その気になれば自分の排泄物からも十分な量が取れた。
火の色は蝋燭の元が何であったかによってまちまちで、光度や強度や寿命もまちまちだった。
私は枯れたサボテンから取れたものにクワガタの羽根を混ぜた蝋燭が好きだった。
ある旅籠屋にだらだらと逗留していた間、日が暮れるとその蝋燭の光で本を読み、体を洗った。
女中の少女は、「いい匂いがするのね」と言っていた。
十九 鮫
無料のガソリンスタンドを探していて、廃校に住む卒業生の老人と出会った。
老人は水田を持っていた。非常に水深のある水田で、稲は水底に揺れていた。
そこに鮫が泳いでいた。
用水路から入って来たのか、雨と一緒に落ちて来たのか、定かではないが、息子たちが見張っているので、誰かが放したのではないと、老人は言った。
モーテルで読んだ新聞に、辺境の雲の中にはしばしば鮫やエイやイルカがいて、それが雨と一緒に落ちることはよくあると載っていた。
田んぼの鮫はもうすぐ飢え死にするらしかった。
老人が入って行って、足を引っかいて血の匂いを流しても、もはや見向きもしなかった。
老人はヒルにしゃぶられながら上がって来た。
二十 主食
辺境の主食はおおむね四種類だった。
芋と、米と、パンと、うどんがそれだった。
芋は遥か上空まで葉を茂らせ、収穫の時期が近づくにつれ、その地域の空を暗くした。
そうして根を地中深く、時には遠方の海底にまで伸ばした。
収穫期が近づくと、潮の香がし、周囲の作物も塩分を孕んだ。
それで死ぬ生物もいたが、そういう生物は塩に耐えられる卵を産んで、翌年にまた生まれた。
米は炊くのに二十年かかり、二十年前から支度されていたものを我々はいただいていた。
そうして二十年後に炊ける米を支度した。
パンはおぞましい菌を味方につけて膨らんでいた。
そうしてその鮮度寿命は驚くほど長かった。
うどんは予測の立たぬ時と場所に前触れなく湧き出し、その近辺にいた人々は仕事も何も中断して駆けつけて、のびないうちに収穫した。
高貴な人々の住む地域に湧き、奴隷などがいない場合は、高貴な人々が不器用に、しかし一生懸命収穫した。
二十一 台風
辺境の台風は凄まじかった。
何もかもを洗い尽くし、国境や星の位置をも変えた。
しかし人々は気にしていなかった。
確かに国境も星も、放置していればやがて元に戻っているようだったが、より以前に戻り過ぎることもあるようだった。
台風の前日にはぎっくり腰や早産や自殺が増えるらしかった。
台風の過ぎたあとの空は澄み渡り、雲以上の雲が見えたし、星以上の星も見えた。
二十二 もやし
辺境のもやしは、豆から芽が出た形状で、そのまま砂漠に生えた。
もやしには、人間が育ち、生きて行くための栄養分が完全に詰まっていたが、そのままでは消化出来なかった。
それで人々は炒めたり、煮たり、煎じたりした。その全ての方法が、それぞれ、それが為されている地域では、最も正しいとされていた。
それで人々は各様にもやしを食べていたが、どの地域もたいへんよく効いているらしかった。
生で食べる地域もあったが、そこの人々はとりわけ健康だったし、体も大きく、頑丈で、頭脳明晰で、美しかった。
もやしを食べさせて育てた家畜の肉は香り高く、その乳は甘かった。
砂漠から遠く離れた地域には、冷凍したもの、乾燥したものしか届かなかった。
冷凍されたもやしを解凍して、あるいは乾燥されたもやしを戻して食べる人々も、やっぱり健康で美しかった。
もやしを常食している人の顔や体臭が耐えられないという人も少なからずいた。
こういう人の中にも、健康で美しく、聡明な人が多かった。
二十三 豚
辺境の豚のソーセージはまことに絶品だった。
驚くほど日持ちがしたし、古いほど味もよかった。
腐っているほど安全だったし、調理に失敗するほど美味だった。
ある地域では豚もソーセージを食べていた。その豚のソーセージはじつにほっぺが落ちた。
共食いは細胞を悪くすることがあるそうだが彼らはその危険を克服していた。
彼らには共食いは供養であったし自分へのご褒美でもあった。
いずれ食われる彼らは無数の先達を食って伝統と宿命を受け入れていた。
当人たちがそう言っていた。
一部の異端の意見ではなかった。
これから更に頭脳が高まればどうなるかわからぬと、一部の豚は言っていた。
また、こうまで頭脳の高くなった動物はもはや食えないという人が増えていた。
しかし彼らも、時々どうしようもなく、むさぼり食っていた。
二十四 本
辺境の本は、しばしば、手に取りさえすれば、内容を一瞬で観ぜられる時があった。
一瞬で観ぜられたあと、あらためて読むことはむろん可能だったが、どれだけ熱心に読んでも、作者なり時代背景なりを調べまくって読んでも、逆様から読んでも(一瞬で観ぜられたあとにはこれが出来た)、最初に観ぜられたほどには入って来なかった。
二十五 月
辺境の月は巨大だった。そこには目視し得る文明があった。
月が輪をかけて大きい夜は、沼では鯰が跳ね、海では鯨の骨が浮かび、作物は太り、動物は雌だけで出産し、思想は高まり、コメディアンは調子を上げ、酒も煙草も旨かった。
二十六 ヨシノボリ
(※ふと辺境の訛りが出てしまったのか、あるいはまるまる向こうの言語になってしまったのか、ここだけゴッソリ聞き取られず。)
二十七 歴史
辺境の歴史は嘘八百だった。
劇的で起伏に富み、人々の興味や義憤さえそそられれば、如何に出鱈目で矛盾に満ちていても歓迎され、正統の歴史として更新されていた。
歴史家は最も高尚な職業の一つで、それになるには非常な発想力と雄弁術が要り、十年に一人出現すれば回転が速いくらいで、遅い場合には数世紀も更新されなかったとある。
それも真実かどうかわからなかった。
大国の図書館には幾度も更新された累代の歴史書がずらりと並んでいた。
この中から事実を抽出出来る学者も地位がたいへん高かったが、彼ら彼女らは密教の僧侶のような扱いで、また、あまりに事実へ接近した仕事は妨害を受けた。
しかしそれも、しょせん真偽は不明だった。
何にせよ歴史家は、子どもたちに第一位の人気を誇る職業だった。
二十八 熊
辺境の熊はじつに巨大だった。
遠くにいれば空に見えた。
近ければ感じられなかった。
我々は常に熊の中にいるのかも知れなかった。
はじめは豆粒ほどから、あれほどまで大きくなったのだと聞いた。
もう生殖も出産もないらしかった。
辺境の熊は煙草を吸うらしかったが、見たことはない。
互いに食らうしかもはや食欲は満たされぬと言うが、存命中の誰もまだ見なかった。
辺境の熊は雲から水を飲む。飲み散らかされた積乱雲が憤懣やるかたなしに風を泳いで逆行するのは見た。
熊の糞が千年経って見事な空洞を得、それだけで一つの都市にもなっていた。私は短いがそこに暮らしたこともあった。
一番古い熊もまだ生きているそうだ。どうも疑わしい骨とやらは、ぞんざいに放置されていて、確かに大きかったが、やっぱり熊の骨には見えなかった。
二十九 娼婦
辺境の娼婦は王族や大女優や幽霊しかいなかった。
それはすなわち、結論として、辺境に娼婦はいないという意味らしかった。
けれど私は何も知らなかったし、その頃体調を崩していて、ひどく心細かったものだから、冥途の土産にと、買ったのだった。
彼女らは明らかに買われることが初めてである反応を見せたし、強いためらいがあったが、いざそうなった以上、拒むことは許されていなかった。
私が娼婦を買ったことは、それなりに知れ渡っていた。
しかし誰も、あまりに大きな問題につき、その話題を避けた。
私が一人の王女と、巨大宗教の本尊である幽霊の元へたびたび通うのを、止める者もなかったし、彼女らも一度も拒まなかった。
彼女らを買う金は王女からもらっていたし、買い続ける元気は幽霊からもらっていた。
しかしあまりに通い過ぎて、励み過ぎたために、ほとんど覚えていない。
王女はすぐあとでプラチナのコインに横顔が刻まれたし、幽霊は全ての信者を連れてこの世から去った。
あちこちで再会しては分かれる仲間たちは、どんなに卑猥な話になろうが、政治的な議論になろうが、この話だけはしなかった。
隣国や敵国でさえ、同様であった。
三十 楡
辺境の楡は、ある程度以上の巨木になると必ず、地下に空洞を持っていた。
空洞への入り口を見つければ懸賞金がもらえた。
懸賞金を出すのは総合国家だった。総合国家というのは、六つか七つの富裕国の戯れ言であったが、機能していないわけでもなかった。
楡の地下に住んでいる人々は、そこで生まれたから住んでいるのであり、系譜の最初は誰も知らなかった。
よそ者が長逗留してはならず、まして新たに住み着くことは許されなかった。
私は楡の国のある少女に、落下の傷を手当てされ、介抱されるうちに恋に落ち、向こうからも同じものを受けたが、結ばれようもなかった。
ただ、少女に楡の樹上へ登ることが許された日、少女と私は遥か上空まで楡を登り、そこで世界一美しい夕日を見た。
樹上生活者たちのことは、語り得る何事も経験しなかった。
三十一 モグラ
早朝の散歩をして、ホテルの酸っぱい朝食に打ち克つための空腹をこしらえていた時のこと、地面に大穴を見つけた。
穴に附属の縄梯子を踏んで下って行くと、甘い匂いがした。臭いのだが、甘いのだった。
穴が縦から横になり、進むほど匂いは濃くなった。
私はわけのわからぬ官能的の興奮に急き立てられ、胃腸の調子が優れなかったにもかかわらず、どんどん行った。
やがて急に行き止まりだった。そこではモグラが死んでいた。
モグラは仰向けだった。何だか不自然な姿勢だった。休む時にはそのようには眠らなかったろう。死ぬ時にだけ取る姿勢だった。
穴の広さに比して極端に小さいモグラだった。
ホテルの朝食には間に合わず、育ち過ぎた私の空腹は、シェフが交代する昼食の美味を、かえって薄めた。
三十二 魔女
彼女は途方もない便秘に悩まされていた。
薄青いうろこに覆われた上半身は、体調不良のためにうっすらと粉をふいていた。
二本の大蛇のような下半身を覆うふさふさした体毛も、ぱさぱさになっていた。
彼女はそれをひどく気にしていた。
彼女は、あとで後悔することを承知で食べた、ひどく雄弁な鼠のために、大便が出ないのだった。
後悔を克服する頃に出るのだと、彼女は言った。
どうしてかはわからないが、彼女は私を医者だと思って話していた。
それなので私は、彼女を安心させることに努めた。
遂に安心すると、彼女はトイレに行った。そこは酒場だった。
私たちは二階の宿に泊まっている、行きずりの旅人同士だった。
トイレから戻って来ると、彼女は私に礼を言った。
その晩私は彼女の部屋で、彼女のような民族の、脱皮するのを間近に見た。
三十三 カワムツ
非常に長い川があった。
私が聞いただけでも二十の名があり、その二十は少しも似なかったし、気に入る響きが一つもなかった。
私は小さな舟に乗って下って行った。
ずっとついて来る魚があった。その一尾は確実にずっと同じ一尾なのだった。
その一尾には何か魚を超えた、知性だとか正義だとか、そのようなものが感ぜられた。
何か私に忠告したいのか、私から何か学び取りたいのか、皆目わからなかった。
釣り糸を垂らせば必ず釣れた。いつも逃がすのだが、一度はバケツに入れてみもした。しかしすぐに放した。それでもついて来ていた。
前世で約束をしたのに現世では違う生物で邂逅した伴侶ででもあるかのようでなくもなかった。
川は下れど下れど海に注がず、地下へも潜らなかったからいつまでも続いた。
ある日、遠い岸から遥かに枝を伸ばした木陰に錨を下ろし、午睡していた時のこと、例の魚も舟のそばにいて、あちらも眠っていたのだろう、たちの悪いエビに食いつかれ、横っ腹に傷をこしらえていた。
その後も下って行くのについて来たが、やがて見えなくなった。
それ以降一度も見かけなかった。
川は、水が逆流する季節を迎えて、私を一気に元の場所まで帰した。
元の場所よりちょっと上まで行った。
三十四 玉ねぎ
私よりだいぶ先に辺境へ行っていた友人を訪ねたことがあった。
もはや住み着いているという噂だった。一個の握り飯を分け合い、眠るな死ぬぞと怒鳴り合った仲だった。
私には、その訪問は一種の帰郷であった。
友人は私を抱擁し、迎え入れてくれた。
(奥さんや子どもなんかいるかしらと思っていたが、一人暮らしらしかった。)
友人は、私を抱擁するのにたいそう屈まねばならぬほど大きくなっていた。
どうしたんだと聞くと、玉ねぎのためだと言う。なるほど友人の畑には玉ねぎがたくさんなっていた。
これを食っていたらば、こんなに大きくなったのだと言った。
玉ねぎを食って大きくなった人は、食いやめればいずれ戻ると聞いたことがあった。そして戻ったあとも、体の一部は大きいまま残るのだそうで、ある人々からは、たいそうな需要なのだとか。
私は友人のを見せてもらったが、そうまでなっちゃあ使いようがなかろうと思われた。そしてそのように言った。
すると、何、玉ねぎで大きくなった女となら大丈夫だ、しかも玉ねぎで大きくなった女には美人が多く、気立てのいいのが多く、香りもよいのだと言った。
私たちは酒を飲んで語らった。辺境の話題ではなかった。それはたいへん懐かしい時間だった。
翌日、抱擁を交わして別れた。くれると言った玉ねぎは、何となく、もらわなかった。
三十五 こうもり
辺境のこうもりは渡り鳥の中にも加わっていたし、獣の群れにも加わっていた。
空のこうもりはじつによく飛んだし、陸のこうもりはじつによく駆けた。
水中や地中にもいたろうか。知り得ぬことであった。
小さいのが私の肩にとまっていた時期があった。色々と小うるさいことを言った。
じつに諷刺的で、詩的で、哲学的だったけれど、覚えていない。
しかし覚えていなかったとしてもよいのだというようなことを言っていた気が、確かにする。
どのように別れたのだったか。
思い出せないが、何か悲惨な目に遭って別れたんであったとしても、この思い出されないということや、おぼろげには覚えているということが、彼女への供養になるであろう。
ならないわけがあろうか。
三十六 ハコベ
辺境には珍しいアスファルトの道を歩いていると、地面に書かれたチョークの人影に、覆いかぶさっている人がいた。
誰か知り合いがそこでそのような形に亡くなったのであろうか、もはや現実の時間と空間にいない人の面影を抱くように寝転んでいた。
私はそこを通り過ぎた。
前の宿で一緒になり、次の宿で別れた同行者と、飯屋に入って、その話題をしたが、しかし同行者はそのような人を見なかったと言う。一緒に通り過ぎたのに。
同行者いわく、そこには土の地面一杯に、ハコベの花が咲いていたということであった。
三十七 メダカ
池のほとりに建つ小屋を買って、しばらく住んでいた。
やがて取り壊しが決まったから、買い取った値段と住んでいた間の生活費を上回る金をもらって立ち退いた。
その短くも長くもない日々、私はひねもす池を眺めていた。
前の持ち主は、メダカの品種改良で生計を立ててでもいたのだろうか、池に放されて野生化した美麗な、そして奇形なメダカたちであった。
その中でもとりわけ大きい一尾は、前の持ち主が死んで化けたものかとも思われた。
たくさんいた。背筋に眩しい線が走るものや、暗闇で光るもの、群れの形が模様を成すものや、長い残像を引くもの等、色々だった。
しかしだんだん、失敗作だけ池に放したのだと思われてならなかった。何だかそのような哀愁が、池は無言に雄弁であった。
今頃、あの池も埋められたろうか。
それとも、先祖返りの来世を夢に見て、泳ぎにくそうに、まだ泳いでいるのであろうか。
三十八 蟻塚
たいへん大きな山があった。
山としては小さいが、そのようなものにしてはあたかも山であった。
それは蟻塚であった。中にはたくさんの人が住んでいた。
あちこちから流れて来た人々で、辺境よりも辺鄙な所から来たような人もいた。
一日に百回も大きなしゃっくりをする人や、ひねもす足がつっている人、羅列する場でもあるまいが、そこの住人は、たいてい悲しみや滑稽を持っていた。
しかし一様に軽やかであった。
その肯定の強さには、それほどまでに生きていたいかと聞きたい気持ちもないではなかったが、聞けば負けることはわかり切っていた。
蟻は、とうの昔に滅んでいた。
本当はどこかにいるのかもしれなかったが、少なくともこのような大きい蟻塚を作ることは、もうやめていた。
三十九 駝鳥
駝鳥の群れが駆け去って行くのを見た。
私がこれを、辺境へ来てすぐに見たのであれば、もうそれだけで帰ってもよかったかもしれなかった。
駝鳥の群れは、いかにも清々しかった。
駆け去って行く駝鳥たちは、死にに行くかに見えた。
突撃しているかに見えた。
その躍動美は、死体とは正反対の美ではあったろうけれど、私はその時、死だけを見ている気がした。
駝鳥は群れを成して走っていた。
単体であっても同じ美を呈したろうか。
その疑問に憑りつかれた私は単体の駝鳥の疾駆を見るまで帰れぬのか、見る前に是非とも帰らねばならぬのか。
このような疑問もあの駝鳥の群れは、清々しく吹き払っていた。
四十 ナメクジ
辺境のナメクジは発光した。
どれだけ不潔な所にいても絶対的に清潔だった。
何も浄化しなかった。
断固として湧いた。
ナメクジを食べるのはナメクジだけだった。
ナメクジを食べ過ぎたナメクジは巨大にならず、重量だけを増した。
地面の隙間にはまり込んでしまったら、どこまでもぬるぬる沈んだ。
それなので地下はしばしば光っていた。
そこはナメクジの堆積だった。
ナメクジはそこで食い合い、ひたすら重量を増して行った。
いつか重量が飽和するだろうと誰もが言っていたけれど、ちかぢかの心配ではなかった。
四十一 蜘蛛
辺境の蜘蛛は巨大だった。
空の彼方に虹があると思えば、しばしば蜘蛛の巣であった。
辺境の巨大過ぎる蜘蛛は、もはや何も食さなかった。
生物としての限界であろうか、そのようなものを突破していた。
それでも不在には至らず、この世に居残り続けさせられていた。
虚空へ張られた巣に鳥などが絡まれば、そうするのが良心ででもあるかのように、糸でぐるぐるに巻き上げていた。
しかし食さなかった。
糸に巻かれた鳥は、やがて地上に落ちた。
落ちた鳥を食料にする民族があった。
糸もほどいて、衣服や寝具を編んでいた。
その人々はさぞ蜘蛛を崇めているのであろうと思いきや、そうでもなかった。
四十二 家鴨
辺境の家鴨はたいそうな数であった。
生物の数の均衡はこれほど不真面目かと思うほどであった。
生じさせられ、育てられ、屠るを以て救われ。
屠られるに抵抗して逃げたはいいが、野生にはもはや返られず。
しかし需要を以て生ぜしめられたものは野生の苛酷にも消されず、すなわち激減しても生き残る数は甚大。
時おり集団自決を呈するも生き残りは甚大。
それでいて断固適応は出来ず、生き様死に様は醜悪そのもの。
しかしその増えかたこそ最上の適応か、味も極めて美味、栄養も豊富、捕まえやすく、そうしてまた増やされては甚大に逃げ、遂に適応し始めた個体と交わっては、遺伝子の自己強化を自ら阻み。
滅びず、他者の飢えをなくし、代わりに何かを食いつぶし、あちこちに骨を撒き散らかし……。
四十三 カモメ
海辺でカモメを見ていた。
カモメは流れて来たのか、ここで生まれたのか――
――私と一緒だった。
懐かしかった。
清々しかった。
波の音や太陽や潮の香や、遠くのタンカーやブイや、その朝食べた魚料理とジャガイモや、色々と繋がってもいるだろうが、何しろカモメだけがよかった。
関係ない絵画や、映画のシーンを思い出した。
しかし見ていたのはカモメだった。
あとでこの映像を想起する時、この時想起していた映像も思い出すだろうか。
現在の、「今ここ」の味わいかたを忘れた。
しかしそれはまるで童心に返るようだ。
あるいはその対極のもので、ぴったり間に合ったかのようだ。
四十四 クロダイ
突堤にて、釣りに没頭していた。
我が職業が空疎になり、あらゆる必要を瞬時に失して。
それで釣り糸を垂れて、偶然と生産の一致に遊んでいた。
風光明媚な入り江に突堤を作るか否かの、賛否両論に、賛成として加わり、拮抗多数決を勝たせた。
反対派だった青年が、今では一緒に糸を垂れていた。
逆に賛成派だった老人が、今では突堤の解体を提案していた。
あるいはちかぢか解体される突堤を、私と青年は愛した。
私たちはクロダイを釣った。
一連の出来事に被害者がいればクロダイであろう。
しかし餌のイソメではないだろうと、私と青年は話し合った。
辺境のクロダイは美しかった。
食うのは惜しく、放すには神々し過ぎた。
無為に殺すべきでのみあり、供養をささげるのはおこがましかった。
四十五 ひまわり
いよいよ私も終了するかと思われながら、ただただ消耗を重ね、もはや回復も見込まれず、しかしいつ死ぬともなかった。
発狂の野辺は心地よくも遠いと思われた。
代わりに私の確かな眼前には、一面のひまわりの大地があった。
あの清らかな空が降り立っても、これほど私を撃たなかったろう。
ひまわりは一輪だけではあまりに五月蠅かったが、大地一面に咲けばようやく落ち着くそれはまさしく発狂のゆくえであった。
私はひまわりと同化出来ぬ肉体を悲しむより他にすべを持たず、立ちすくんでいたのか突っ伏していたのか。
泣き叫んでいたのか黙していたのか。
いつかは帰れるのだろうか。自分では帰郷とばかり思いつつ、死出の旅であるかもしれぬ。そうなら途中で死に神がヒッチハイクして来るかもしれぬ。人に化けて、甘いことを言いながら。
その時は、いっそ乗せてやろう。そうして、むしろこっちが運び去ってやろう。
ひまわりが一面に咲いていた。
私はそれをずっと見ていた。












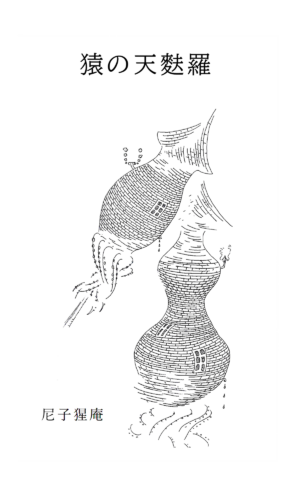
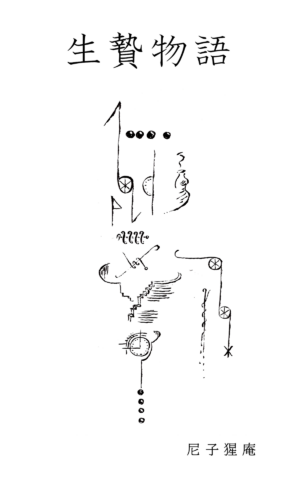









"辺境博物誌"へのコメント 0件