序
その転落死は最初マンション住人の自殺と思われたが、遺体が身元不明とわかると警察は殺人を疑って住人を調べた。
105号室・兼田さん宅からあらゆる動物の剥製を作ろうと試みて失敗したものが大量に見つかったけれども転落死とは無関係であった。
118号室・渡辺さん宅から人骨が出て来たので問うと妹で食べたと答えた。けれども転落死とは無関係だった。
302号室・川畑さんだと言い張る人は明らかに川畑さん本人ではなかったが、そのように信じていた。これも無関係だった。
615号室・宿原さん宅から出生の届出のない娘と孫娘が多数保護された。けれども無関係であった。
1017号室・大代さん宅に押し入るとドライフラワーのようになった大小三十体の縊死が全て床に落ちていた。無関係だった。
1415号室・宮野さんは質問をする巡査を見るなりお前は死んだはずだと叫びながら巡査の胸を刺した。これも無関係であった。
結局、転落死の解決に結びつくものは何もなかった。
連行されなかった住人たちがベランダに出て、帰って行くパトカーの最後の一台が角を曲がって消えるのを見つめていた。
転落死の素性が知れた。近所のアパートに住む無職の一人暮らし和田さん四十五歳、一五九センチ三十七キロ、空き巣をなりわいにしていた。
遺体に争った形跡はなく、マンションの壁をよじ登っている際に足を滑らせて転落したものと思われた。
*
一
1805号室・門谷さん宅の四兄弟は、来月行われる学芸会の劇の練習に、それぞれ熱心に取り組んでいた。
長男が食事を取らないから母親が叱ると、長男は役作りだと答えた。
「何の役なの」
「難民の役なんだ。面白くない役だけどクラスは大勢だろう。誰かがやらなきゃならないんだよ。それでくじ引きやら、『お前はあの時あんなことしたから』やら、推薦やら立候補やら名前の順やら、『一緒にやろうよ』やら『どうでもいいや』『どうでもいいならやれよ』やら、先生の指名やらジャンケンやらで色々あって、僕は結局スカを引いたわけ」
それで母親が納得し、今度は次男が入浴しないことを叱ると、次男も役作りだと言った。
「やりたくはないけど、決まってしまったことだから、こうなったら頑張らないと、劇に参加する他のみんなに迷惑がかかるから」
「あんたは何の役なの」
「ホームレスの役なんだ」
「ごはんも食べないの?」
「それは食べる。手は洗えないけど勘弁してね」
その時外から帰って来た三男が足を引きずっているから、どうしたのかと尋ねると、役作りで階段から跳んで来たと答えた。
「何の役なの」
「足の骨を折った人の役なんだ。でも大丈夫、劇の途中で魔法によって治るから」
母親は安心すると、玄関のほうを見て、
「あんたの弟はどうしたの」
「あいつは、僕が階段から何度も跳んでるのをしばらく見てたけど、さっき屋上に上がって行ったよ」
「あの子の役は何なの」
「死体だって言ってた」
二
207号室・北川さん宅に幽霊が出ると言って、北川さんが泣いていると、叔父さんが代わりに住み込んで、追い出してやると引き受けてくれた。
数日後に会うと叔父さんは、心配御無用と言った。
「幽霊なんて馬鹿々々しい、ナンニモいないよあの部屋には。――けれども、もう少し住んでみるからね。ではもう帰るよサヨナラ」
「お急ぎでなければお茶でも――」
「急いではいないんだけど、寂しがっちゃいけないしするから。お茶はまた今度」
三
902号室・中村さん宅の秀則君は考え込んでいた。
けれどもある時、このまま考え込んでいては気がフレテしまうと直感した。
それで秀則君は勉強机から跳び離れると、運動をしてノイローゼを回避するために、言いやすい言葉を力の限り叫びつつ、両腕を思い切り振り回し、裸足のまま外へ飛び出して行った。
廊下や階段で大いに運動した。
風を通すためであろうか、玄関扉を少し開けているお宅があったので、突撃して、中にいたお爺さんと枕投げをして汗を流した。
枕投げの勝負で秀則君は圧勝したけれど、どこまで勝てば正式な勝利なのかわかりかねたので、明らかな勝利になるまで勝ち続けた。
四
ベランダの手すりから透明な中に踊り出ると、急流に飛ばされて、水の流れは速く、壁や電線にぶつかってはなりませなんだ。
沈むも浮かぶも目まぐるしい速さ! 浮沈おおらかに自由自在、それでいて常に流される気楽。見晴るかす限り何もない所は透明でありました。
上はどこから水が終えるのかわからない、上がるのは一番速い。上がり出すと急流の気配はぴたりとなくなります。マッタク、静かな透明をのぼる、とうとうそれと知らず水から出ると、体に浮力ははたらかなくなり、飛び上がり、止まり、落ちる――ばしゃんと透明の中に落ち込むと、嗚呼魚の跳ねるわけがわかります。
透明な濁流の上に立つようになってしまいますと、もう自由自在の飛行ではなく、歩いていると割れ目です。
薄い割れ目は手探りでもってその存在と、薄いという特性を知るのです。それは私の足を股までくわえ込んでもなお深々と続くらしいのでした。
全て夜なのによく見えることは清麗透徹、体を横にして割れ目に滑り落ちます。途中で何ですか恥ずかしかったことがチラホラと思い返される……修学旅行、私はたまたま傍にいた生徒を誰彼構わず笑わせる時もあれば、集団で歩きながら隣に居合わせた親友にも黙りこくる。それをいちいち何か考えごとや、心境事件と思われては困るのです。
さて彼らがみんな来たおかげでまた透明な中に沈むというと踊り出る自由自在、私の気ままな急降下や急上昇を同時に散らかった生徒たちも等間隔に行うのはみんな、私に訓練したように合わせているのかそれとも全て自由自在と思っていた降下上昇は私が最初からそう導かれている出来事だったのか。
急上昇する空。どんどん浮いて行く空は水中があまり透明なものでどこから水が終わっているのかわかりません。
上昇時には流れの気配はなくなり、歯止めの効かなくなった、何ですかもう一つ大きな世界の大自然の甚大な力はこちらでは浮力に相成り、浮力は私を光るほど速くぐんぐん上げる、飛ぶ、魚が跳ねる。上昇し、止まり、落ちる。
ばしゃんと着水し、でんぐり返るとまた濁流に立ちます。誰もいません。全て透き通っておりました。
むろん透き通っているのは先に透き通らないものがあってわかります。それは地面、彼方の突起、そうして頭上のあれは流れ星ではない、小さい円を描いて回りながらいつまでも流れている星ら。
小さな円の連鎖の残像です。見渡す限り透き通った水中に私の他泳ぐ者とて無く。恥ずかしいことが思い返されないとみんなも二度とふたたび現れないので思い出しましょう、見ようによってはたいへん冒涜的な行為ではありましょうが……嗚呼恥ずかしき哉!
やっ、誰かが花火を上げています。夕食後にカラオケのマイクが回ります。星らがたくさん回りながら流れてゆく小さな円の連鎖の残像。それは私の寝室の天井に、回りながらいつまでも流れている星ら。脳が死ぬまで遊ぶのです。
心臓が500/分~550/分に痙攣して光ります。罹患して私から独立したこの臓器。よく頑張ったね。おめでとう。こうして分離して他人になったら、私はお前に接吻する。
嗚呼お前の働きを世界中に教えたい。世界は前方の画面に小さくなってゆく走行中の自動二輪のミラーのようだ。いいやそんなものにお前を渡すものか。お前は突然私に復讐し始めたけれども、それほど愛してくれているのだから。
よく思い返せばヨーグルトか何かを食べて、歯を磨き、隠れて煙草を吸い、アチコチの電気を消し、床に入った。
しかしそれらは私の行動だろうか。それをやったのは私ではない。覚えているけれど、私とは違う私に相違ない。
前の私がやった。今の私が覚えている。入れ代わるのは睡眠時だけではないらしい。私は今、前の私なのか。次の私もかように自分がわかっていない私であろうか。
明晰な覚醒時に入れ代わり、前の私はまるで水中のごとき透明な空気に溶けた煙のようにあとかたもない。いいやソチコチにある。私よりも他人的ではない。かすかに回りながら小さな円の連鎖の残像と、どこまで水が続いているのかわからない。
同級生は私に予期せず消え、たまに目覚めれば私のおしめをかえる姉がいる。その生徒らも今までの生徒らではない。彼が言うには、
「あいつ屋根を亀たんだぜ」
ガタンという音がして視野がズレた。ななめにこけた額縁の中に、この世の映像がくっついて、本来の視野景色の右上と左下は、枠からはみ出して様相はようとして知れない。
左上と右下は角となり、上と下はななめに黒く切れて、彼の言ったのを思い出し、
「屋根たんだぜ」
と私も口に出してみると、昼間に一回だけ、吸ったのに出て来なかった煙草の煙が今になって出た。古びて黄ばんだ煙であった。湿気ているため地面に落ちた。
誰か生徒の一人が、どこか上の階で、便座から立ち上がり、いくらかの所作のあと、潮騒がする、この建物の血管を、危険な血栓が流れてゆく。
こんな血栓、何が何でも、私の心臓には届かせまい。
五
1213号室・平畑さんが管理人室に行って、
「ベランダにいると、ずっと両隣がうかがって来て、気味が悪いのです」
と訴えると、管理人さんは、両隣の住人が以前から何度か、
「ベランダにいると平畑さんにうかがわれているようで気味が悪い」
と訴えていたことを思い出し、窓口のシャッターを下ろして扉の鍵をかけた。管理人さんは、やがて平畑さんがうなだれて帰って行った後も、パイプ椅子を構えて扉の傍に立ち、脂汗をかいてじっとしていた。
もう一人の管理人さんが点検から戻って来ると、扉に鍵がかかっているので、首をひねり、鍵を開けて中へ入った。
六
1605号室・益田さんはしばしばマンション内を散歩する。
故障して十六階と最上階にしか止まらない中央のエレベーターで最上階へ行って、そこから全ての廊下を塗り潰すように降りて行き、一階の郵便受けを見て、その頃には体が温まるので、階段を一直線に上って戻るのだった。
廊下を歩いている際、どこかのお宅で食事の支度がされていると、料理の匂いが廊下へたちこめた。誰かが入浴していると、湯気と石鹸の匂いが廊下へたちこめた。益田さんは時おり何かの思い出や、淡い印象へ連絡する匂いに遭遇すると、じっくりと胸中に味わいながら歩いて行った。
益田さんは散歩から帰ると煙草がのみたい。けれども奥さんが喘息なので、ベランダでのみたいが、隣人の1606号室・金原さんが嫌煙家らしく、ベランダで一服吸っていると、荒々しく窓を閉めるのだった。
数秒後にまた開き、また力一杯閉めるというのが繰り返されるのだった。
その憎しみの気配が侵略するのか、益田さん宅のベランダでは鉢植えがすぐに枯れるし、金魚がすぐに死ぬのだった。
それなのでこの頃ではベランダでのむのをやめて、台所で換気扇を回してのむのだった。
禁煙する選択肢はなかった。益田さんの考えでは、煙草をのむ習慣を一度でも逃してしまうと、その時発散されなかった何かが、のちに、先天的の喘息を患うによって自分の喫煙行為を罪と成した妻への清算という形で現れるに違いないのだった。
それで益田さんは換気扇を回し、台所で一服吸い始めた。
その頃廊下では金原さんが趣味の散歩から戻って来る。故障したエレベーターで最上階まで上り、全ての廊下を塗り潰すように下りて郵便受けを確認し、階段を直線に上がって来て、遠くの景色を眺めながら最後の深呼吸をしていると、隣家の換気扇から煙草の煙が廊下へたちこめる。
金原さんは胸一杯吸い込んでしまった。金原さんの考えでは、これで寿命が数分間短くなってしまった。最後の最後に何か話している死に際の金原さんは、数分間の時間が足りなかったせいで、重要な言葉を言い漏らしてしまうに相違なかった。
それを言うことによって全ては清算され、極楽往生したはずのところが、ふと一過性な罪悪感を自覚したちょうどその瞬間に事切れてしまい、地獄におちるに相違なかった。
金原さんは益田さん宅の扉をじっと見つめた。
七
屋上や幾部屋かのベランダで、鳩の巣作りと糞害が著しいために、管理人さんはアチコチに薬を散布した。けれども被害は減らなかった。
卵が孵化したら爆発的に増えるのではなかろうかと思われて、躍起になって何羽か殴り殺したけれど、鳩は頑として出て行かなかった。
住人たちが怒り狂う管理人さんをなだめた。管理人さんは納得して鳩を放置することにした。
かつてスズメバチが住み着いたことも、ゴキブリが住み着いたこともあったけれど、どちらも数がどんどん増えて、人々が我慢ならなくなる頃に、突如として姿を消し始め、最後には根絶やしになったので、放置が最もよいという結論だった。
八
日が暮れて少しした頃停電になった。住人たちが廊下に溢れ出し、興奮して上ずった声で話しまくっていた。
一人、大きな声で無関係なことを喚く人のために会話があちこちで中断されて、情報がよく伝わらなかった。
誰かエレベーターに閉じ込められていないかどうか、停電はいつ直るのか、管理人はとうに帰宅して居ないけれども、どこへ連絡するべきなのか、そうしたことを聞き合い、何か答え合う声をかき消して、誰かが大声で繰り返し叫ぶのだった。
人々は叫び声から出来るだけ離れ、事態の対処について話し合った。すなわち、
「停電の時には流れない秘密のラジオ番組に出会う確率と、停電になって初めてラジオをつけて当たり前のラジオ番組に出会う確率とは、停電の時には流れない秘密のラジオ番組が現実に存在する確率よりも高いのか低いのか? 相関関係が前提とならない因果関係において?」
「それよりも、停電の時には流れない秘密のラジオ番組に出会う確率と、停電になって初めてラジオをつけて当たり前のラジオ番組に出会う確率とは、停電の時には流れない秘密のラジオ番組が現実に存在する確率よりも高いのか低いのか? 相関関係が前提とならない因果関係において?」
人々は突然の闇に酔ってたいへん浮かれ、アチコチで急速に仲良くなって行った。空は雲が垂れこめていて、停電になったのはこのマンションだけらしく、町の明かりはついているようだったが、廊下は暗くてほとんど何も見えない。
住人たちはお互いの顔の判別出来ない中でいつもと違う声を出し、和気あいあいと話していた。
突然廊下の明かりが点くと、人々は叫び声を上げて散り散りに駆け出し、それぞれの部屋へと帰って行った。
裸で立っていた一人のおじさんは、しばらく階段の踊り場から身を乗り出していた。エレベーターに誰か閉じ込められていたのかどうかだけ、確かめておきたかったので。
九
507号室・大守さんは夜中に目が覚めた。
しばらく体を通過して行くニュートリノの数を数えていたが、やがて起き上がり、洗面所に立って鏡を見ると、爪による傷跡が網目に走ってメロンのような顔だった。
台所に行くと奥さんが鍋を覗き込み、蓋を持ってくわん、くわん、とかすかな響きを立てていた。大守さんは
「何をしているんだい」
と尋ねた。奥さんは振り向いた。その顔を見て大守さんは
(こいつは俺を組み敷かせた不審な奇ッ怪している、茂みから遠くへ弾けて逃げた早鐘を押さえて、かっと見開いた目で俺を見るんだ。)
「あなたお願い、落ち着いてください! 今、救急車を呼びましたから! もうすぐ来ますから!」
(嗚呼……この女がまた散らかっちまった。何度片付けたってこうなんだから。しかし俺は何度でも片付けようじゃァないか……)
十
1011号室・田村さん宅に811号室・柳川さんが訪ねて来た。初対面の柳川さんはすこぶる顔色の悪い人でケーキを持参していた。
お裾分けだということだった。ケーキは五つだった。田村さん宅は田村さんと奥さんと長女と次女の四人だった。田村さんは少し断ったけれど、受け取ってお礼を言った。
柳川さんは親戚が始めたケーキ屋を支援するためにたくさん買ったのですと話すと帰って行った。
田村さん一家は一人一つずつ、次女が二つ食べた。田村さんはケーキに詳しくないけれど、それなりに美味しいケーキだと思った。
翌日柳川さんが洗濯物を持って訪ねて来た。風で落ちたんでしょう、一軒ずつ当たって行こうかと思ってとりあえず真上に二軒目ですと言った。
田村さんはそれが自分の洗濯物だったので受け取ってお礼を言った。
数日後柳川さんがケーキを持ってやって来た。ケーキはまた五つだったので田村さんは家に入ってもらって一緒にお茶を飲んでもらった。
柳川さんの話は芸能人のように花やかで面白く、二人の娘も柳川さんをたいへん好いた。
上の1111号室の住人の名前を田村さんは知らないが、ある日からその騒音が始まった。
跳び上がっては踏み鳴らしている地響きだった。数分間から時には数時間続き、いつ始まるのかわからなかった。
ある日柳川さんとエレベーターで一緒になると、顔色がお悪いようですよと言われた。
えェそれが、近頃は何だか上の住人が異常にうるさくてと答えた。柳川さんは気の毒そうな顔をして、
「管理人には言いましたか」
「言いましたけれど、どうも何だか変な目つきでじろじろ見られるようで、適当にあしらわれたような気がします」
「夜もですか」
「いや夜はないようなんですが、とにかくすごい音なんで、うちの者はみんな神経が駄目になりました」
「警察に通報されましたか」
「考えてはいます。――えェはい、それではまた」
柳川さんが八階で降りると、田村さんはそのまま十二階まで乗って行った。そうして1211号室・坪口さん宅を訪ねた。ケーキは隣町で買って来たものだった。坪口さん宅の人数分と自分の分とで四つだった。坪口さんはお礼を言ってケーキを受け取ったけれどお茶には招かれなかった。
夜中に樋をよじ登って坪口さんの洗濯物を取り、翌日に持って行った。後日またケーキを持って行くとお茶に招かれた。
田村さんは柳川さんに聞いた話を喋りまくった。坪口さん夫妻と出戻りの娘さんはけらけら笑った。
坪口さん宅はあまり外出しない一家らしかったけれど娘さんを操作して頻繁に出かけてもらった。
娘さんは強く命じられると喜ぶのだった。何か考え始めたなと思うと即座に頬を引っ叩けばたいへん従順になるし、そのままベッドに連れて行くと目がくらむように燃えるらしかった。あまり強く殴って両親に発覚してはいけないし弱いと喜ばないので力加減が重要だった。
田村さんは誰もいない坪口さん宅に入ると思い切り跳び上がって踏み鳴らした。1111号室の住人は名前を確認すると林さんだった。田村さんは何度も跳び上がっては踏み鳴らして騒音の復讐をした。
ある日田村さんがエレベーターで坪口さんと鉢合せになると久々に見る坪口さんはひどい顔色をしていた。手に提げているのはケーキか何からしかった。
十一
1213号室・平畑さんが管理人室の窓を激しく叩き、隣人に殺されると訴えた。
管理人さんはシャッターを閉めた。平畑さんは道路に飛び出して行った。
数分後、管理人さんと巡査が話しているところへ帰って来た平畑さんは、とっさに全ての事情を察した。
今から新聞記者とテレビカメラが来て、自分の顔と名前が日本中に流れるのだとわかった。
巡査が平畑さんに拳銃を向けると、写真や映像を撮られてしまう前に隠れさせて欲しくて、平畑さんは合掌しながら、巡査に向かって駆け出した。
十二
朝、通勤電車の座席に座り、弾みをつけて跳ねている102号室・中広さんについて、若い女性の二人組が、
「ああいう人は人殺しをしそうだ」
と話しているのが聞こえて、中広さんは非常に悔しい。突然跳ねやめて、じっと宙を見つめ始めたので、若い女性の二人組は別の車両へと移って行った。
自分は人殺しなんてしないと、証明するにはどうすればよいのか? 何かをしない人物であると証明するためには、何をしたらよいのか。
何かをしないと証明された状態とは何か? 何かをしないと証明された状態、それは、その人物に対して、何かをしそうだと考える人がいない状態である。
そう中広さんは気がついた。中広さんが人を殺しそうだと考える人が、この世にいなくなれば、中広さんは人を殺さない人物であると証明されるとわかった。
十三
真夜中に、205号室・倉多さん宅のチャイムが鳴った。
画面を見ると、エントランスからで、若い美しい女性が立っていた。鍵を無くしてしまったのでロックを開けて欲しいということだった。
倉多さんがボタンを押すと、ビーッと錠の開く音が聞こえた。女性は何度も謝りながら画面から消えた。
後日女性がお礼を持って挨拶に来た。先日は真夜中に失礼いたしました、おかげさまでたいへん助かりましたと言った。
それから品物を差し出すのを、倉多さんは断った。それでも差し出して来るのを、倉多さんはたいへん素っ気なくまた断った。
途方にくれた女性を、倉多さんが睨みつけるので、女性はドギマギして謝罪し、何度も頭を下げて帰って行った。
真夜中にチャイムが鳴った。画面を見ると同じ女性が立っていた。倉多さんは鍵を開けた。
後日お礼に来た。倉多さんは差し出される品物を断って睨みつけた。途方にくれた女性はドギマギして帰って行った。
真夜中にチャイムが鳴った。
十四
603号室・藤並さんが裸になってベッドに座り、全身を掻きむしっていると、全開にしている窓から中庭で遊ぶ子どもたちの声が聞こえて来る。
もういいかい、まあだだよと繰り返している。藤並さんは首の後ろから胸、わき腹からお尻と、執拗に掻き続ける。
いきなり乱暴に掻きむしったと思うと、また柔らかく掻いて行く。
子どもの声が聞こえている。もういいかい、まあだだよと繰り返す声が響いている。
藤並さんは優しく体を掻いている。もういいかいの後に、数人の声がもういいよに変わって来た。
すると藤並さんは強く掻きむしる。まだいく人かはまあだだよと答えている。
藤並さんはまた優しく掻く。それから少しずつ、もういいよと答える声が増えて行く。藤並さんは優しく掻くことが少なくなって行く。
もういいよが増えるごとに、だんだん強く掻きむしる。しばらくもういいかいが途絶えた時、藤並さんはばりばりと全身を掻いている。
そうしてもういいかい、と聞こえた後に、子どもたち全員の声が、もういいよと答えた瞬間、藤並さんはベッドから跳ね起き、服を着て部屋を飛び出して行った。
職場がどこであるかはわからなかったけれど、仕事に行かなくてはならなかったので。
十五
1106号室・橋田さんは、拘束具の中で暴れていたが、注射を打たれて眠った。
明るい寝具売り場に寝台が並んでいた。一つ一つ見てゆき、決めた。ステッキで叩くと、店員は頷いてどこかへ行った。
橋田さんは見渡した。売り場の壁の隅に隙間があり、奥にまた売り場が続いていた。隙間は狭く、固い壁の間を橋田さんは体を横にして入った。
狭い売り場に子ども用の寝台が一つだけ展示されていた。電燈が消えていて薄暗かった。寝台は勉強机を兼ねていた。今は勉強机の形状で子どもが二人並んで腰かけられる形状だった。机の板を引いて縦にするとベッドの壁になるらしかった。
ここには幽霊がいる! 突然わかった橋田さんは総毛立って元の広い売り場にごりごりと出た。
売り場は電気が落とされていた。向こうの横並びの四角い窓から淡い白い光が天井に射している――街灯だ。夜だ――誰もいない。――幽霊がいる!
橋田さんは走り出した。何であろうか若い日々にも到達し得なかった力強い健康だと思った。
老化に伴う臓器や関節の尽きせぬ不快な発言が一斉に沈黙して飛ぶようだと思った。天まで届く波しぶきだと思った。百年生きる雷だと思った。
売り場の端に壁が四角く切り取られて階段がある。下の踊り場へ飛び降り飛び降りする、玄関が開いている。屋外へ飛び出す。
広い芝生に街灯の白い光が落ちて草に反射している。向こうにシェパードを連れた男が歩いている。探されている。建物の中に戻る。
踊り場へ跳び上がると幽霊がいた。建物じゅう一帯に仲間が点在する気配を感じた。姿がぼやけているが女性だった。
橋田さんを見て逃げかけたのを捕まえた。首から上はぼんやりとして顔がわからなかった。向こうを向かせ、なかば持ち上げて、服の上から入れた。
三十年ぶりだった。硬過ぎる大きな胸をつかみ、少し上に持ち上げただけで女性は浮く軽さだった。ぼやけていると思ったけれど、後頭部がはっきり見えていた。若くはないと思った。
建物の外を男女が二人歩いているのがガラス張りな踊り場の壁を通して見下ろされた。橋田さんは目を伏せたが橋田さんに揺さぶられている女性が外の女性と目が合ったのがわかった。
外の女性は傍らの背の高い太った外国人をけしかけた。外国人は走り出したらしい。橋田さんは途中だったけれど引き抜いて投げ捨てた。
外国人と入れ違いに外へ出て芝生の上を飛ぶように走った。白い街灯が運転手のいないトラックやフォークリフトの影を伸ばしていた。
夜空に星一つなかった。雲もなかった。遠くの町明かりが赤くにじんでいる夜空だった。
四つ足の獣が追いかけて来る。梟になったのはいいけれど飛び立つのに時間がかかった。
けれどもやがて舞い上がった。橋田さんは見下ろした。広い芝生にばらばらに乗り捨てられたトラックやフォークリフトの長い影が落ちている。獣の姿はない。鳩と鳶が追いかけて来る。
鳩と鳶は梟を見失っている。空に停止した梟の少し下で相談事をしている。梟は羽音が立たない。梟は息をひそめている。
「夜空にカラスは見えないね」
と、鳩か鳶がそう言うのが聞こえた。
「奴が梟でよかったけれども、カラスだったらまず逃げられていたろうな」
しめたと思って、カラスは暗い空に舞い上がり、夜に溶け込んで羽ばたいた。しかし振り返ると、鳩と鳶はこちらに向かって真っすぐに飛んで来た。ハメられたとわかった。まんまと乗せられてしまった。カラスは一心不乱に逃げた。
いっぽう橋田さんは直立の姿勢からかすかに胸を逸らせて、水平になって飛んでいる。
町の上空を飛んでいた。放物線を描いて落ち始めると、更にぐっと胸を逸らして浮き上がった。
建物がたくさんあった。向こうに橋田さんの高さにちょうどよい屋上がある。けれどもそちらへは向かわない。あそこには郷愁がない。
橋田さんは自宅に向かって日の当たるアスファルトの細道を歩いている。誰もいなかった。右は山々だった。山々までの間に谷があった。谷には木が茂っていた。貯水池があった。左には高いマンションがあった。小学生の橋田さんは静かな細道を独りで歩いた。
細道が下り階段になって終わった。階段の下は自宅のある住宅街だった。階段を下りた。
ぞっとして振り返ると階段の上に猪がいた。たいへん巨大な猪だった。牙が四本、口から伸びて曲がりくねり、顔に突き刺さっていた。目がないようだった。ワゴン車程大きかった。
小学生の橋田さんは住宅街の坂を上った。猪は追いかけて来なかった。坂の上に中学校が見えた。中学校は岸壁の上で日に当たっていた。
橋田さんは曲がった。その筋からは中学校が見えなかった。橋田さんは自宅の門扉を開けた。緑色の鉄の門扉だった。
自宅の中に入った。誰もいなかった。吹き抜けの天井付近の窓から外光が射し込んで白い壁が明るかった。ポール・シャバスの絵がかかっていた。九月の朝という題のはずだった。
小学生は自分の部屋のある二階に行こうとしたが、リビングに透明な宇宙人がいると直感し、仏間へ駆け込んで襖を閉めた。
耳を澄ませているとリビングから気配が消えた。同時に母と父が帰って来た。小学生を呼んだ。返事をしないでいると苛立ったように大きな声で呼ぶ。小学生は追っ手かもしれないと思って返事をしなかった。
小学生は仏間の窓から庭へ出た。巡査は家に入り込んだ頃だろうと思われた。
サンルームの壁を蛙のように這いのぼった。隣家のツツジの生け垣を飛び越して住宅街の坂を下った。谷に下りるアスファルトの道だった。その先は森の中のグラウンドだった。グラウンドの先にも道は続いていた。その先は貯水池だった。
夜のグラウンドに友人たちが集まって待っていた。食料を用意してくれていた。小学生はこれからホトボリが冷めるまで森に潜伏するのだった。
森の中には確か道が何本もあって、沼の傍の旅館や、少女の浮浪児の住んでいる木の上の小屋があったはずだった。そんな夢を昔見たはずだった。
グラウンドから見上げる空は非常に澄んでいた。宇宙は七色に光っていて、土星か木星がたいへん大きかった。森には地雷があるから気をつけろと友人が言った。
森の中に道があった。森は薄明るかった。途中に黒い沼があった。長い生き物の背中が出ていた。それは進んでいた。次々とぎざぎざの背びれが現れてはもぐって行くけれど尾はいつまで経っても現れなかった。橋田さんとガールフレンドは手をつないで見つめていた。
森が切れた。地平線まで湿地だった。大きな水たまりのさざ波が太陽に銀色に反射していた。右の遠くに西洋風の城があった。城は太陽に白く光っていた。ガールフレンドはいなくなっていた。小学生は温かい柔らかい感触の残った手が寂しかった。
追っ手を振り切ってマンホールから這い出た。そのL字型な三十階建てのマンションの最上階の内角に美人の転校生の部屋があるのだった。
友人と訪ねに行くのだった。小学生と友人は最上階でエレベーターを降りた。見下ろすと中庭はイギリスのお城の庭のような庭園だった。
L字型の縦と横の連結する箇所は少し間があいて渡り廊下が渡されていた。マンションがゆっくりと風の音を立てて倒れる。小学生と友人は手すりにつかまってどんどん傾きながら総毛立っている。
美人の転校生と会わずに終わって小学生も友人も切なかった。谷の貯水池を見下ろすと白いクジラのようなものが沈んで行って見えなくなった。
小学生と友人は黙って住宅街の坂を上った。小学生の家はもうすぐだった。友人の家は中学校の前の県道を更に上った向こうにあった。
友人が隠れた。小学生が振り返ると下り坂に誰もいなかった。友人が隠れた可能性のある列は二つだった。友人はあまり切なくてこのようにフザケルのだろうと思って、小学生は探しに行った。
天井にホタルブクロの花房のシャンデリアがついている。電気は消えている。小さな窓から射し込む昼間の外光が当たって薄明るい壁には九月の朝が非常にたくさん、壁がそういう柄であるようにかけられている。
飴色のテーブルのアセビの花房のライトが日の暮れた室内を黄色く照らしている。高く切り立った絶壁のてっぺんあたりに穿たれた部屋だとわかった。室内の類人猿の一頭は他の四頭と違って明らかに苛立っていた。
橋田さんにリーダーの座を明け渡すよう要求して威嚇していた。橋田さんは部屋の隅のうず高い本の上に登った。類人猿がいつ登って来るか知れなかった。
夜明けに橋田さんはとうとうパラグライダーを編み終えた。リーダーの座を狙うゴリラはそのことに気づいた。
その時部屋の向こうの扉から少女が入って来た。そばかすのある白人の少女だった。橋田さんの乗っている棚の近くに来ていたゴリラが仲間のもとへ戻った。少女はそれを目で追って、こちらに来た。
橋田さんは棚に乗ったまま高い方の窓を開けた。顔を出すと風で薄い髪の毛がばらけた。下は遥かに高い絶壁と南に見果てない海だった。視野の果てまで雲が垂れこめ、その先に日が射していた。そこでゆっくり移動する飛行機がずっと反射していた。
「どちらに行けばいいかね」
と橋田さんが尋ねると、少女は本の山を登って来た。隣に並んで窓から顔を出した。風にばらける少女の髪が橋田さんの目に入りそうだった。
「西に行ってください」
と答えた。橋田さんは少女の頭越しに西の海を見た。少女は腕をまっすぐ伸ばして指さすと、
「あのあたりに、海に出る帆船があるから、そこで受け取って、神社の公園の隅に持って行って埋めたら、全ては終わりです」
「ありがとう」
橋田さんは窓から足を垂らした。パラグライダーを先に出すと上に張りつめて広がった。
外に出ると浮かんだ。座ったまま右の紐を引くと右へ、左を引くと左へ傾いた。両方を同時に引くと上昇し、紐を強く握ると下降した。何もしないでいるとそこに浮いたままだった。
右の手を前へ、左手を後ろへひねると左向きに回転した。振り返ると少女が見ているので、橋田さんは口をすぼめ、寄り目をしてみせた。少女は意外なほど強く笑った。
紐を両方強く引く。空に上昇する。紐を前に押すと前進した。
橋田さんは西に向かって、ゆっくりと進んで行った。
十六
401号室・藤野さんは、拘束具の中で暴れていたが、注射を打たれて眠った。
明るい寝具売り場に寝台が並んでいた。一つ一つ見てゆき、決めた。ステッキで叩くと、店員は頷いてどこかへ行った。
藤野さんは見渡した。売り場の壁の隅に隙間があり、奥にまた売り場が続いていた。隙間は狭く、固い壁の間を藤野さんは体を横にして入った。
狭い売り場に子ども用の寝台が一つだけ展示されていた。電燈が消えていて薄暗かった。
寝台は勉強机を兼ねていた。今は勉強机の形状で子どもが二人並んで腰かけられる形状だった。机の板を引いて縦にするとベッドの壁になるらしかった――
十七
太陽が今日もコンセントを探し求めて出歩いている。同じ所を初めてのような顔して探し歩いている可哀相な奴だ。
ははあ。前からアンダーテイカーが歩いて来たな。戦わねばならない。我々warriorは完全な世界のために秘密警察から消されるが、しかし消す側として送り込まれて来る奴らもwarriorだ。そうでなければ勝てないからだ。
このアンダーテイカーもそうだ。あまり強いので秘密警察に雇われたのだ。こうして送り込まれて来る刺客を倒し、生き残り続ければ僕も雇ってもらえる。
そしてお金をもらったら、引っ越すのだ。もっと大きなマンションに引っ越したらもっと鍛えることが出来る。そうしたら更に強くなって、大きな仕事をもらえるようになったら、更に大きなマンションに引っ越すのだ。
しかし今度のアンダーテイカーは弱そうだ。まるでただのお婆さんだ。いや見かけに騙されてはならない。この間のカールゴッチは子どものような姿をしていたが驚くほど大きな声が出たし、シュガーレイロビンソンは車椅子のくせになかなか倒れなかった。
ははあ。向こうからたこ八郎がアンダーテイカーの加勢に来た。警察官のような身なりだが騙されない……
……そうかwarriorはこれまで秘密警察から送り込まれて仲間をやっつけていると考えていたが、実は仲間を集めていたのかも知れない。ひそやかに、次の秘密警察を組織しているのだ。
それでwarriorたちが安心して暮らせるもう一つの世界を作るつもりなのだ。
じゃあ抵抗はすまい。たこ八郎はこれまでのwarriorの中で一番強そうだが、そういうことではない。ハタから見れば僕はたこ八郎に負けて連れて行かれるふうに見えるだろう。これで秘密警察も騙されるだろう。
僕はたこ八郎に、warriorの新組織の存在に気付いていることをそれとなく示そう。戦闘力だけではなくて知能も高いことを知ってもらえたらwarriorの世界で大きな仕事がもらえるだろう。
そうすればもっと大きなマンションに引っ越そう。それでもっと勉強したら、もっと大きな仕事がもらえて、更に大きなマンションに引っ越すのだ。
十八
609号室・百田さんがしきりに綺麗な髪の毛を梳いていたところがとうとう居ても立っても居られなくなり、隣家を訪ねると留守番の五歳児が出て来た。
百田さんは中に入れてもらうと五歳児の手を取って、しゃがみ込んで瞳を覗き込み
「私は独りきりの独りきりの思弁的な思弁的な思弁的ィィィな瞑想により、人間は大いなる宇宙生命の、すなわち時間という生物の――いいえ時間という生物と表現するにはたいへんな過程がいるので忘れてください――皮下細胞の一箇所なのだとわかったんです。
一人一人の生まれては死んでゆくのが末端組織の新陳代謝なのだと。広範な新陳代謝では人間が人気で、動物がどんどん減り、こぞって人間になっていると。家やビルディングが人気で、樹木が減り、こぞって家やビルディングになっていると。
ところが市場では激増により価格が暴落していると。しかし市場は今のところ売り買いする人は誰も訪れないのだと。遺伝子の微細な変貌による局所の増加を、わかりやすく拡大すると末端組織の箇所が例えば毛髪ならばゆくゆくは毛の塊が歩いているでしょう。皮膚なら皮の玉が転がる。皮の玉が転がるその天体に、水とミトコンドリアの発生であると。
天体がもう一つ次の段階に行くために、または休息するために例えば脱皮するところを我々は杭を打ち込み垢まみれの窮屈な殻を脱がれないようにしているのだと。思考と外界現象の連鎖性により、個体と全体は混和しているということが。
選択を迫られ続ける宿命をより能動的に支配出来るということが。そうこれはある本を読んで覚えていた文章が、本当にそうだと気が付いたことです。わかったんです。ふと頭の中で流れた歌が、ふとつけたラジオでも流れたりすることの理由が。噂をしている当人が、そこに現れる理由が。ただ記憶の印象を濃厚にするだけな偶然の確率から、爆発肥大して脱出したこれに類するあらゆる現象の。
その連鎖性をひっくり返して、外界現象を思考して個体の近辺に望むまま引き寄せる祈念。混和箇所の照射の執拗による具現、実現。私の思考を大いなる宇宙生命がある時思考したのがすなわち私なのだと。
そういうわけで自身のどこかの生命力の源泉へ正確に依頼を出して、強靭な健康と自己自身の円満な操縦が果たされるということを。
膨張する宇宙は要するに呼吸の息を吸い込む状態で次には縮小が起こることに納得しました。そしてまた膨張、縮小、膨張縮小膨張縮小、呼吸、満ち引き、宇宙に発生はなかったと。消滅もないと。無の不在だと。この世にあるのは維持だけなのだとわかりました。
白目を剥いた主観視野は永遠存在を見つめているが近くて何も見えないのだと。眼球天体に宇宙の暗闇だと。時間という生物に経過という状態はなくまた循環もなく、在りながらたゆたいながら、永遠の微細な変貌だけが状態するということを痛感しました。
そして私は全体に混和しているということが。あなたもそうですよ。私の認識はすなわち全体がふと自覚した瞬間なのだということが。あなたはとても愛くるしいですけれど、それは世界が愛くるしさを欲したのだということが。誰か主観的な性格をして愛くるしいと感じさせようと決心したということが。それで私が派遣されました。
ただ時間という生物が今度は何の末端組織であるのか、また私の末端組織が微細な無数世界に沈殿して私のようにハッとした個体が今何を考えているのかが、よくわかりません。
他の世界はどういう形状の生物なのか。生物でないものは何なのか。私の好奇心は誰なのか。
最終的に理想なものをどこまでも連鎖させてゆけば、ぐっすり休まれる日が来るんじゃないか。近所の不在らの動向は、私の目に映っているどの無生物なのか。その混和箇所は、遥か遠方で沈黙している……」
十九
1605号室・田中さん宅の猫が、料理をするたびにコンロの火を舐めに来るので、田中さんはたいへん困っている。困りごとは重なってやって来るものだと考えてはため息をついている。
それというのも田中さんには元々重大な問題があったので。
ある日突然気になって徹底的に調べてみたところ、自宅の中には一台の隠しカメラもなく、盗聴器もなかったので、田中さんは世俗の支配者たちの誰にも見られていないという不安なのだった。
しかし目下のところは、猫がコンロの火を舐める事実が、最も先決問題だ。
窓を開ければどこかの廊下で交わされている専業主婦たちの会話が聞こえる。いい加減食べ飽きた鳩の肉と卵をどのように調理するかと話し合っている。
掲示板では、「近ごろ東棟内にストックホルム症候群が流行している」というようなものよりも「鳩の大発生に抗する対処法」のほうが重要だった。
また鳩への倦怠の不満も、安泰の感謝に戻さなければならない、スズメバチやゴキブリの頃と比較するによってではなく、もっと最終的に。
その時廊下の向こうからゴキブリが一匹飛んで来て、台所の床にピチッと落ちた。
田中さんは猫がこれをどうかする前に羽子板で叩き潰した。三度潰してようやく死んだ。白い体液が出ていた。
どこから侵入したのでもないのだと田中さんはわかっていた。この世に存在する全ての物の卵は全ての空間にあるのだった。生まれるかどうか、育つかどうか、発見されるかどうかだけである。
虫に限ったことではなく、病気もそうだし、知恵なんかもそうだし。このマンションのどこかに日本語の通じないモナコ人の老人が住んでいるという噂は、きっと本当だし。
グレース・ケリーとはきっと、何らかの関係のある人だし。
二十
あたしの人格の、遮断や変質を食い止めて、常に統合させようと踏ん張るこの力は何?
神仏からも先祖代々からも未来の自己からも監視されてはいないと断言するこの声は?
あたしの人格は一つで、あたしはどこまでも一人の人間なのだと撫でてくれる手のひらは?
その存在をあたしに悟らせまいとし続けて、しかし気づかれたからには、いっそおどけてみせるこの温もりは何?
そうして結局、最後にはこれに対する一切の考えをやめさせるこの匂いは?……
同僚の尾和さんはいつも優しくてステキだけれど、どうもマンションに住んでいる或る男の子が、尾和さんの昔なのではないかと思われるのだ。
これには証拠があって、……もうその証拠はどこかへ行ってしまったみたいだけれど。
過去の尾和さんにあたしを印象づけるにはどうすればよかろうか。
過去の尾和さんにはガールフレンドがいるけれど、あれは昔のあたしではないので尾和さんは間違いを犯している。
出勤する道々に、時々すれ違うお婆さんがいるが、あれはこのガールフレンドの未来だと思われる。マッタク世界はたいへん入り組んでいる。
しかしそう、つまり大丈夫なのだ、あのガールフレンドは例え突き落とされても死なないで、ちゃんと老婆になるまで生きるし、後遺症だって残らないということだ。
あのお婆さんは今朝も、元気そうに歩いていたから。
二十一
209号室・馬場さんは、筋肉の異常で腹の一部分が陥没していて、その穴に拳銃を埋め込むことによりボディチェックをのがれられるから、極道生活や戦場ではいつも活躍して来たのだと、孫娘が後ろの席の友人に話している。
友人は何度も聞いた話だけれども初めてのように聞きながら、その老人が今も道路でよく何かと戦っている姿を思い出している。
老人は子どもと目が合うと追いかけて来て、架空の手榴弾を投げて来る。
捕まると、シャツの襟を開いて、架空の入れ墨を見せながら脅迫して来る。
またゴミステーションに上半身裸の太った老婆がいて石を投げて来るが、この夫婦は一緒にいる時には凶暴性はないのだった。
孫娘も、話を静かに聞いているうちは鉛筆で刺して来ないので、手の甲にいくつか黒い穴の開いている友人は、静かに耳を傾けている。
二十二
508号室・出水さん宅の出無精の朱音ちゃんの独白。
――もう毎日のあたりまえのこととして、ひとりでいやらしいことをするようになってしまった。
いろんなものにいやらしい美しさを感じるようになった。
それはやがてわたしの中に入って、どこかへ行ってしまうので、わたしの指が一生懸命さがすのだった。
お母さんに怒られるから、隠れてする。お母さんはものすごく怒る。でも体がもっとものすごく、美しくなりたがるので、どうしてもやめられないのだった。
ずっとがまんした時は、血のおしっこが出たし、世界がくらくらして、頭がずっと夢の中のようになった。
それでがまんしないことにした。指はいつも体を、けっきょく美しくしないけれど、美しくしようとし続けるのだった。
そうして、気がつくと、嫌われてしまったのだった。
世界中が、わたしを嫌っているのだった。
嫌々で、わたしを加えているのだった。
ベランダに出ると、太陽が嫌々わたしにさすのだった。
部屋の中に入っても、物が嫌々わたしに見られているのだった。
服も嫌々わたしに着られているのだった。
それは下着とか上着とか、役割ぶんたんによって強まったり弱まったりする嫌々ではなかった。
鼻に入ってくる空気も嫌々、耳に入ってくる音も嫌々、食べ物も嫌々で、おしっことうんこは嬉しそうに出て行った。
それから、自分のことを嫌々考える人が、頭の中にいた。
その人は、世界から嫌々で加えてもらうのがつらいので、わたしの中に隠れているし、その人がなにかしても、みんなはわたしがしたと考えるのだった。
わたしを嫌がるものを無くすことがいいと、頭の中の人は言う。
無くさなければならないのは、世界中にちょうど世界中と同じだけあるから、最初に無くすのならわたしの頭の中にいる人と、その人が隠れている頭の持ち主、つまりわたしだと言う。
話の最中だったけれど、待ってもらった。
わたしも、色々のもののことが嫌々でしようがないのだった。
わたしの中の汚いものが嫌いでしようがない。じっとしていても汚いものはわたしからいつも出ている。あかとか、あぶらとか。おなかの中でうんこが動いている。ぽたりぽたりとおしっこがたくわえられていく。わたしは汚いものの入れ物のようだった。
でもしようがない。嫌々で、わたしの中に加えるしかない。
わたしは美しくなろうとして指を動かすけれど、美しくならない。ならないけれど、その最中はたしかに汚いもののことを忘れられるし、終わったあとは、世界はきれいだ。
このきれいな世界の中にわたしも頭の中の人も入っているのだから、もしもわたしたちが死んでも、消えるわけじゃあないから、世界はわたしのところだけ汚いままだ。
わたしたちは死んで、わたしたちではなくなっても、元々わたしたちだったものが、いつまでも残るはずだった。
どこまでも小さくなって、あちこちに飛ばされて、なにかに吸い取られたり、別のもののために使われたりするかもしれないけれど、でもわたしたちだったものは、絶対に消えないのではないでしょうか。
嫌々加えてもらっているわたしたちのまま、いつまでも残っているのでは。
するとその時、嫌われ者はひとりでいるからいけない、二人いて、おたがいが嫌っていなければ、好き合っていれば、きれいでいられるのだと、マンションは言ってくれたのだった。
でも、わたしたちはもう、作戦を開始していた。
つまり、死んでもしかたがないから、わたしたちが嫌われてしまった元々の原因を、無くして、嫌われていることがそのうち少しずつうすらいで行くかどうか、実験するのだ。
一晩中しめつけて、氷で冷やしていた右手の中指を、お父さんの葉巻カッターで切って、それから、これを捨ててもいつまでも消えないから、きれいなものに変えなければいけない。切った部分を、包丁でもう一度ななめに――やさしく一日中さわってくる、このいやらしい指を――切って、土にそっと植える。
温かい季節だから、すぐに根ざすはずだった。
短くなった元々の指は、しめつけていた夜中のあいだが一番かゆかったけれど、もう痛くないし、血はとろとろ糸を引いていた。
それにしてもやがて植木鉢の中で、ぴょこんと出てきて、土から足をひっこ抜いて、足の裏の根っこをぷちぷちちぎって、わたしと目が合うと笑うもう一人のわたしは、土の中で育って全身がまるまる全部あるのに、わたしは中指の先がないのは、不公平だ。
そう言うと、マンションは笑っていた。
頭の中の人は、いやそんなことはない、植木鉢の中では君ほど大きくならないから、小さい君になって、一本の指先だけ大きいバランスになるはずだと言った。
それで私たちとマンションは、どうなるだろうと楽しみにしながら、植木鉢をながめた。
植木鉢はわたしたちに向かって、中指を立てていた。
二十三
1307号室・佐藤さんが包み紙の貼り付いてなかなかはがれない古くてべちゃべちゃするチューインガムを噛んだらパイナップル味だった。
佐藤さんはこれほど美味しいものは知らないと思った。近頃はもっぱら辛くて臭くて飲み込むと喉を焼くものばかりだったので。
また食べ物が落ちていないか見回したら向こうに何か落ちているので這って行った。
それは鈴だった。佐藤さんは思い出していることに自分で気づいていなかったけれど、それは奥さんの鈴だった。
奥さんが財布のファスナーにつけている鈴だった。奥さんが家にいて、鳩の煮物を作ってくれていた間は、食べ物は実に美味しかった。
――彼女はあの頃、財布を取り出すたびに鈴の音がすると言って恐れていた。
彼女の考えでは、強盗か引ったくりがいつも尾行していて、その人が鈴をつけているから、財布を出すたびに鳴るのに違いないのだというのだった。
その時佐藤さんがふと数年前の佐藤さんの続きになって、その鈴の音は財布につけている鈴の音なのではないかと指摘したら、奥さんはたいへん不機嫌になった。
そうしてある朝いきなり飛び出して行って、そのままだった。
鈴だけ置いて行っていた。
その鈴は金属のひどい味だったために、佐藤さんはあまり噛むのはやめて早々に飲み込んだ。
それからまた、食べ物がないか探し始めた。
今は無くても、探し続けていればそのうちに必ずあることは、わかっているので。
二十四
416号室・竹内さんは、もうすぐ旦那さんが帰って来る頃なので玄関の鍵を開けた。それからポーチの明かりをつけた。
1605号室・益田さんが暮れ方の散歩で全ての廊下を塗り潰すように歩いていると、ちょうど前を通りかかったお宅の扉の鍵が開くガチャリという音がした。
立ち止まって見ていると、ポーチに灯がともり、Welcomeと書かれた玄関マットが照らし出された。
益田さんが扉を開けると、向こうから若い女性の声で、
「あら、お帰りなさい。早かったのね」と言われた。
益田さんはしばらく立ち尽くしていたが、靴を脱いで入って行った。
数十分後、帰って来た竹内さんの旦那さんに、益田さんは手荒く追い出された。もうこの部屋の前の廊下は通ってくれるなと言われた。
それで益田さんが必死になって、何も悪意があって侵入したわけではなく、ただ真実の世界から受け入れられて、真実の伴侶にただいまと言っただけなのだと、熱心に説明したけれど、竹内さんの旦那さんは怒り狂い、今度現れたら殺すと言って扉を閉めた。
ガックリとうなだれた益田さんが帰宅すると、隣人で嫌煙家の金原さんが侵入していて、喘息の奥さんの首を絞めていた。
益田さんは竹内さんの旦那さんを呼びに駆け戻った。
二十五
ようやく新しい管理人さんが来た。
行方不明の前任者のつけていた記録帳やメモを見ると、全く判読出来なかった。
二十六
406号室・所沢さんは狂喜した。そうしてテープの入っていないラジカセの録音ボタンを押して
「2013年3月13日、私は大いなる発見をした。
全ての占星術はここを目指して、わずかに逸れ続けていたのだ。
数学が逸れなければとっくの昔に人間はいくつかの恐ろしい法則を理解していたし、宗教が逸れなければあらゆる理解欲を超越していたのと同じように。
医学が逸れなければ人は死を恐れなかったし、芸術が逸れなければ人類はもう現在の諸状態から退室していたはずなのと同じように。
この発見を肉体化する手段はまだ不明だが、どう考えてもたいへん近い将来において判明するだろう。いともたやすくである。来週や来月のレヴェルで、近い将来にである。大いなる座標そのものは、私が計算して導き出してあるのだから。
しかし私はこの座標を誰に伝えればいいだろう。
文化水準が高く、豊かさ等々の物的利益からも、尊厳等々の精神的尊厳からも無縁で、努力家でありながらユーモラスな国に渡したとしても、どう考えても、以後の計算が少しずつズレ込んでしまうのは明らかだ。
私の計算は、その座標は、初めての出現ではないと如実に物語っているからだ。それなのに今まで、これを耳にしたことが一度もなかったからだ。
……これまで普及しなかったことは警鐘だ。よくよく考えるに、彼らがこの座標を知らないはずはないからである。
それに計算によれば、このまま行けば、私のことを血眼になって探し始める人々がいる。私はこの発見を、未発表にすると決め込んでしまうが無難であろう。
ところで計算によれば、同じマンションに、私とは違う形でたいへんな発見をしている人物がいるが、その人の発見は無益な錯覚に過ぎない。地下駐車場の壁にラクガキしてあった。《神経症患者の夢を捕まえて文芸作品に編み込むことにより、いつでも自由に治療を行われるようにすることは出来まいか。少数の病人が夢において必死に癒やそうとしているものは、多数の健康な人々をも大分量蝕んでおりましょうけれども?》――阿呆。
――どうやら計算によれば、私を探し出すはずの人々は、もはや私を見つけているようだ。
そして嗚呼、計算によれば、私はあと数分で座標を見失うだろう。
記録しておくことは出来ない。記録するには、不可欠なのに発見されていない記号が、あまりにも多く不足しているのだ……。
二十七
複数のお宅に知り合いがいて、様々の手法でマンションの外から遊びに来る服山少年は、いよいよ自分とマンションとが一体化する兆しが現れ始めたのではないかと思っている。
たった今、いつもは454段ある階段を、434段数えただけで登り切ることが出来たので。
次には廊下が何メートルであるか調べねばならないと思った。
仮に二十メートルだとしたら、十メートルで横断出来るようにいずれはなるのを目標にして。
二十八
生存の次の状態がわかった。これにより生存に閉じ込められている我々の、本当の席順が自然と判明する。
さあもうこれでつらいことは何も起こらない。しかもそれが、何らの反作用的障害にもならずに。
我々は次の状態へ移行する際には、自身の全ての体験の中でしばらく繰り返すから、これまでの人類はみんな可哀相だったが、これからの人類はたいへん楽しい。何度も楽しい。全ては俺を分岐点として。
ただ結論として、これは《万能なる自我》もしくは《神の自我》の外部、すなわち我々の理性では考えるべきではない。
なぜというに、あとで恥ずかしい目に遭うから。
このような事実に気づいた人物の放つ電波が毒ガスのように周りの人々を病ますので、全員がこれに気づかなければならない。そうすれば誰も病まない。
太陽は生前三階、水星は生前二階、金星は生前一階、地球は現世、現世は罪深いので人によっては月で服役したのち、火星は死後一階、木星は死後二階、土星は死後三階、天王星は死後四階、海王星と冥王星は選択可能。
(詳しくは芝生を練り歩くデモ隊のプラカードを見よ。隊員への質問は厳禁。)
時は来た。いざ、このスイッチを押そう。厳かに開いたこの扉を、颯爽とくぐろう!
――こうして1707号室・梶田さんは、買い物袋をぶら下げて、エレベーターに乗り込んで行った。
二十八・五
どこまでも性的ではない、無尽蔵にエネルギッシュな清々しい嬉しさを、その強烈な柔和な透徹な全体境地を、人類文化は我知らず目指していたのだ。
それはついに正しく発見され、そこへ到達したら、新たな西暦の始まる分岐点だ。
しかし徐々に到達するにはむつかし過ぎる。双葉の如雨露のような形態だ。そのまま当たり前に時間が過ぎても木は生えない。このような木への到着を想定して何らの迂回も試みようがない。
浸透しようのない先史時代の水槽で泳ぐ我々は、この可能性を無視し続けなければならない。
我々からは、新しい世界の到来に際して踏み越える境界が、集団自決とほとんど変わらぬようにしか思えないから。
これを不用意に未到達の時代で発見してしまった俺は、誰にも明かさぬ分別を持っていて本当によかった。危ない所だった……
――こうして梶田さんは一七階に到着し、エレベーターから降りて行った。
二十九
その土曜日、市税事務所に勤める709号室・原島さんが同僚を二人家に招いた。
招待客の一人、北條さんは二年前に建った新しいマンションに住んでいたが、この二年間であたりの風景が変わったと話し始めた。
「僕はよく家内と散歩をするのですが、越して来た頃にはあった田んぼや畑や山林がなくなりどんどんどんどん、なんだかおもちゃを拡大したようなチープな家やマンションが建って行きますよ。マッタク、消えたものはどんなものに変わってしまい、現れたものはどんなものから変わって来たんでしょうか」
すると次に原島さんが
「このマンションに越して来て九年だけれど、九年前とは周辺の様子は激しく違う。もっと田畑や山林や古い建物や、散歩していて楽しい見晴らしの良い地域だった」
するともう一人の招待客、築六十年の日本家屋にお住まいの増森さんが
「昔はマンションなんかなかった」
と言った。それからいつもの癖で、視野に浮かぶ眼球のゴミが中央付近に漂って来るのを、目をくるくる回して視界のわきへのけた。
景観とは住人の魂の容器だ、と意見が一致した。
では我々は地域の景観を守るため、侵略者をこれ以上増やさないようにしようという話になると、お茶を持ってやって来た原島さんの奥さんも加わって一同は熱狂した。
翌日にまた集うと北條さんがしばらく来られないと言うからどうしてと聞くと、
「侵略者を増やさない作戦に、さっそく取り掛かりましてね。あっちに、半年前に建ったマンションがあるんですが、そこから出て来た侵略者をね」
「乱暴だね。早まったね」と増森さんが言った。「だってその人はもう半年間住んでいる人なんだろう」
「いやいや駄目ですよ。とにかく侵略者ですから」
「しかし君だって二年前に来たんじゃないか」
と原島さんが言うと、
「ええ、そう言う原島さんは九年前です。厳密に言えばここにいる中で侵略者ではないのは増森さんだけですよ。しかしねえ、この厳密さに囚われてはいけないですよ。私は或る厳密さに従いますけれど、同時にいくつかの厳密さを放棄しなければならないんですよ。
ええ、わかってます。重要なのはこれから先の侵略者であって、すでに住んでいる人ではなかった。しかし本当に押さえるべきこれから先の侵略者は、今はまだいないからどうしようもない。
でも考えてみればわかりませんか。今いる侵略者を押さえることで、その子々孫々は現れようがないということが」
この言葉に、原島さんと増森さんは目から鱗が落ちるというふうだった。
言い置いて出て行こうとする北條さんの肩に原島さんが後ろから手をかけると、北條さんは振り返って
「何ですか」と尋ねた。
原島さんは包丁で以て、今いる侵略者を押さえた。北條さんは最期に一瞬間、何か重要なことを思い出したような顔をして、事切れた。
遺体を見下ろしている原島さんの肩に増森さんが後ろから手をかけたから、原島さんは振り返って
「どうしました」と尋ねた。
増森さんはその場に座って、
「どうしてこんなことになったんでしょうなあ」
と言った。増森さんは包丁を持っていたのだが、背中を原島さんの奥さんに刺されていた。
「私もまた、何かの厳密さでは侵略者でしょうがなあ。……これじゃあ腑に落ちませんですなあ」
三十
九時五十分に火災警報が鳴った。十五階から火が出たという放送が流れた。
1006号室・田山さんが廊下に出ると非常に騒がしかった。住人たちがぞろぞろ階段を下りて行くのだった。
廊下の手すりに手をかけて見下ろすと、中庭の向こうのロビーに住人が集まりつつあった。やがて中庭に出て来た住人たちが新米の管理人さんから消火器の使い方を教わり始めた。
避難訓練なのだった。新米の管理人さんはシッカリしていた。避難訓練もこれで七日間連続になるので。しかしみんな初めてのように熱心に話を聞いていた。
田山さんがその上に落ちてやろうと思って手すりから身を乗り出すと、ちょうど上から落ちて来たものが直撃し、もつれ合って落ちた。
「……私の後ろ頭に落ちたのは君かね」
「あなたこそ邪魔をしてくれて」
「私はただみんなの上に落ちてやろうと」
「僕がまさにそれをやったんですよ。そしたらあなたがひょっこり乗り出して来たんだ。男同士で心中と思われたら胸糞悪いじゃないですか」
「みんなぽつぽつ帰ってゆくね」
「ええ、どうしたことでしょうね。我々が見えないのかな」
「やッ、君と私の体がないよ」
「……しまったなあ、それでは廊下に落ちたんだ。あなた何階ですか」
「私は1006――田山です」
「じゃあ十階の廊下に落ちたかな。僕は1806の下川です」
「下川君見たまえあそこ、三階かな。ピンク色の煙が出ているよ」
「アハァ、さっき使い方を聞いたんで、小僧がさっそくやらかしましたナ」
「ンほほほ。――ありゃ、あそこも。いちにいさん、しい――十一階かな」
「あれは黒いぞ。本物の火事ですよあれは」
「凄い勢いだ。ありゃ自殺だよガソリンをまいたんだよ。炎はしかし落ちて来ないね、あんなに廊下から飛び出しているがね」
「自殺ですねあれは。……あァ出て来ましたね、おおい! おおい!」
「来るかな?」
「来ましたよ。来た来た。……やァやァここですよ」
「いかがです?」
「はァ。よござんすかね」
「よござんすとも。ね?」
「よござんすよござんす」
「それではお言葉に甘えてちょっと。嗚呼やれやれ」
「どこなのォ――」
「おや? ――ッハハハハ、ころっと忘れていました。すみませんが、家内も、ゥ……」
「いやァよござんすとも。ね?」
「よござんすよござんす」
「どうもそれでは。――おおい! おい!」
「あっ! そこだったの――アレどうも、こんにちは」
「こんにちは」
「こんにちは」
「このかたたちがね、御一緒にどうぞって。どうだい御一緒させてもらおうか」
「……どうして?」
「どうしてって、イヤどうもナ」
「だってあなたそれじゃ、約束が違うじゃないですか」
「あのう横からすみませんが」
「はい」
「私たちは構いませんから、どうぞお二人で。ねえ?」
「そうですとも。どうぞお二人で」
「ェェでは、ハイ。何ともすみませんです。じゃあおい行こうか」
「うん。あのう、それでは失礼いたします。どうもありがとうございました」
「いやいや」
「サヨナラ。……あァあ、いやしかし、ナンですね。お羨ましいもんですねェ」
「そうですなあ。もう気楽なもんだが、独りで気楽なのも寂しいものがありますよ」
「ただこうなると、あれが怖いですねえ我々も」
「あれですか? 怖いねェ」
「――あッ、来た! 来ましたよほら、あっちの空から!」
「嗚呼ほんとだ。あれさっきの二人は捕まるよ。こっちから向かってってんだもの」
「かわいそうに。しかし本当、イヤ我々はもう少しここで隠れましょうか」
「あれ……指さしてるよあの二人が。……教えやがったんだ!」
「来たぞ! 逃げろ!」
デュデュデュデュ。
「いやだ! いやだ!」
デュデュデュデュ。
「嗚呼!……ああ……デュデュデュデュ」
「デュデュデュデュ」
「デュデュデュデュ」
――おおいここにも呼んでくれ! トビオリだ二人! 風に吹かれて廊下に落ちたらしい!
あれ、こちらのかたは、ここの部屋のかたですよ田山さんだ。何か言っていますよしきりに。
いや、うわごと言ってるんだ。うわごとですよただの。管理人さんまだかなあ。
でもこれはもう駄目ですよ。
ええ、これはもう駄目だよ。
三十一
廊下で712号室・江口さん宅の文昭君が青いボールをセィンセィンとドリブルしている音がよく響く。
手近の階段まで左右どちらも三軒ずつあるが、どの窓からも包丁の先端が突き出ている。
包丁は長い棒にくくりつけてあるものと思われる。前を通れば突き刺される道理である。
騒音を出す者の宿命である。
文昭君はセィンセィンとドリブルしながら立ち往生している。
三十二
1506号室・阿野さんが喋りながら目を覚ました。喋りながらトイレに行き、洗面所へ行った。
顔を洗うためにいったん沈黙して、それからは黙り込んだ。黙り込んでからは頭の中で喋り続けた。
――おれはノイロ税をたくさん払ったから、もう晩年まで、死ぬまで安心だ。
でも人には喋らない。世間はたった一振りで誰をも負かせてしまうから。負かされた者は虫のように葬られるから。
良否はどうでもいい。おれはただ現象が怖いだけだ。仕組みに興味はない。
可愛い従妹は何を感じているのだろう。たくさんの人がいっぺんに亡くなったニュースを見てからテレビ画面を見続けている。目を離さない。
目に悪いし、電気代もかかるので、少しペテンにかけて、今では段ボール箱を見つめ続けている。
おしめを換えられている間も体を拭かれている間も、見つめ続けている。
綺麗な体は若々しく再生し続けていてちっとも崩れない。お尻まで届く髪の毛も綺麗だ。
あまり食欲のない、かすかに開いた口。細い鼻。
まばたきしない真っ赤な目。
三十三
408号室・本多さん宅の奥さんが、ハム肉のステーキを焼いている。
肉をフライパンに押し付けると、豚の絞められる最期の「ピィ! ピィィィ!」という声がする。
いっぽう旦那さんが玄関扉の覗き窓から外をうかがっていると、407号室の木村さんが忍び足で前に来た。こちらを見て何かぶつぶつ言い始めた。
木村さんは扉の前でビニール袋や自転車のタイヤを燃やして行くことがある。本多さんはうかがい続けた。
木村さんは本多さん宅の扉をぼんやり見つめて何かぶつぶつ言っていた。手を胸の前で変なふうに組んでいる。やがて白目をむき始めた。呪詛らしい。
それで本多さんが、扉を強めにこんとノックすると、木村さんは驚いて白目が戻らないのか、そのまま眉間にしわを寄せ、後ずさりして上り階段へひっくり返って頭を打った。
木村さんは白目のまま硬直した。そうして流れ出た血が階段をキャアキャア上って行ったよと奥さんに話しながら本多さんは食卓についた。
奥さんが疑って見に行き、扉の覗き窓をしばらく見て戻って来ると、何か言いかけたが、食卓の上を小さな羽虫が飛んでいて、叩こうとするとくるくる螺旋状に飛び出したから噴射型の殺虫剤とライターを取りに行った。
本多さんは食事の皿を持って向こうのソファに避難した。
三十四
わたしは待っている。あの日、夜中にベランダへ出て星を見ていると、魔女が数人、箒にまたがって飛んでるのを見つけて、わたしに気づいてくださいと念じていると、一人が降りて来て――たいへんな美女だった――ひそひそ声で
「あなたは秘密が守れますか」
と尋ねるので、頷くと、魔女は
「また連絡します」
と言って、行ってしまった。
わたしは待っている。おそらく連絡は試験も兼ねていて、すごく遠回しな方法で訪れるだろうから、どんな些細な兆候も見逃すまいと、心を開き、目を皿のようにして。
三十五
朝起きたら誰もいなかった。マンション中、どの部屋も空っぽだった。テレビもつかなかった。電話も通じなかった。ベランダに出て見下ろすと、誰も歩いていなかった。太陽が燦々と照らしていた。慌ててもう一度寝ようとするけれど、いつまで経っても寝つけなかった。そのまま長い月日が経った。どうしてか空腹にはならなかった。
三十六
もう私の能力や性質の範疇で手に入り得る書物を全て読み終えた。
ぎゃていぎゃていはらぎゃていはらそうぎゃていぼじそわか――鸚鵡が覚えてしまって口にしている。幸せな奴である。
幸せな奴であるが、マンションから嫌われてしまったのか、すぐに死んでしまった。
私もたいへん病気らしい。
オウムになんぞ唱えさせてはいけなかったのか、そういう呵責が事を荒立てたのか、あるいは天罰によって室内の水質が悪化したとか、全ては隅々まで理由も目的もない偶然なのか、あるいは誰かから誰かへの呪詛の線上に居たとか、云々云々、真相は無数の説得力だけを残して謎のままである。
それではさようなら。
三十七
803号室・原田さんが帰宅中、赤信号だったけれど後ろに救急車が停まるので前進した。急患を搬送することが先決だったので。
そういう理由で赤信号の前進を繰り返していると、もう一つサイレンが鳴り、メガホン越しの声で停車を命じられた。
言われた通りに停車すると、パトカーから降りて来た巡査に原田さんは
「急患を搬送することが先決でした」
と答えた。何、と問い返されたから、
「後ろに救急車が停まるのです」
と答えると、救急車なんかいなかったよと言われ、パトカーの後部座席に連れて行かれた。
通行人がチラチラ見ていた。飲食店のネオンが光っていた。その光を見た途端、原田さんは声を荒げて、運転席に座っている巡査に、
「急患を放っておくのか」
と言った。何、と問い返されたから、頭をかきむしり、
「救急車のサイレンがうるさくてたまらないんです。気が変になるから、急患を早く搬送してやってくれ」
と言った。具合が悪いのかと聞かれると、それからは
「急患を搬送してくれ」
の一点張りだった。巡査たちは顔を見合わせ、原田さんにかかりつけの医者はあるかと尋ねた。
それからパトカーは原田さんの指示するほうへ向かった。そうしてマンションに到着すると、帰ろうとする原田さんを巡査は取り押さえた。
ハッとした原田さんが、
「私の車を返せ。置き去りにして来ただろう」
と怒鳴っていると、子どもの運動会から帰って来た209号室・金平さん一家が駆けつけて、巡査二人を石や煉瓦でしこたま殴った。
三十八
その晩、一人の泥棒がマンションの壁をよじ登っていたところ、突然笑いながらジャンプした。
それはそれとして、701号室・岡塚さん宅の峰弘君が、宿題の日記を書いている。
――このマンションの水道水にとけた金属の影響で、住人はみんな発狂しています。でもほんとうは水道水は無関係なので、結局は、マンションもそうだし、最後もそうです。
最後というのは、メガホンを持っている警察官に、住人たちが石を投げているのです。
大いに戦っていました。数日後、トラックやダンプやクレーン車が現れて、更に数日後に、鉄球がうちつけられました。
うちつけられる瞬間、壁と鉄球の間に、上から落ちて来た住人がちょうどはさまるのでした。鉄球は風船を割るような音を立てて壁にちょっとめり込み、また振れて戻って来ると、壁には穴があいていて、クッションになった住人は、中に入りこんでいて見えません。
上のほうの窓からは、住人たちが次の鉄球にそなえて、クッションになるため、間にはさまる頃合いを見計らい、体を乗り出しています。
新たな警察官たちが要請をうけて駆けつけると、先に包囲していた警察官たちの姿はありません。クレーン車が大きく首を振り、鉄球が振れて、新たに駆けつけたパトカーが三台、まとまって飛んで行きました。
また次の警察官たちが要請をうけて駆けつけると、横向けにひっくり返ったパトカーの向こうから、先に駆けつけていた全ての警察官たちがのぞいていました。新たにとまったパトカーを、鉄球がねらって、クレーン車がのろのろと接近します。
クレーン車の運転席に駆けつける警察官たちを、バリケードに隠れる警察官たちが拳銃で撃ちます。女の住人たちがお茶やおにぎりを持って、味方の警察官たちにくばります。
しばらく飛び回っていたテレビ局かなにかのヘリコプターが、高度を落として、乗っている人は上から、なにか機材を投げ落としています。
水道やガスや電気をとめられてしまうと、マンションは七秒間ほど、ぐるぐると揺れました。そのために、屋上で踊っていた1702号室の間山さんが落ちました。
間山さんの死体は、奥さんの願いが聞き届けられて、中庭の、名誉ある戦死者墓地に入れてもらいました。
真夜中に休戦しました。その時、包囲している自衛隊員の中から、バリケードを超えて爆薬を仕掛けるエキスパートが出発しました。
エキスパートは数分後に、対策本部のテントに戻って来ました。そうしてスイッチを押すと、エキスパートがコッソリ持ち帰っていた爆薬は爆発しました。
対策本部のテントが空に浮き上がり、がらがら、ボトボト、びしゃびしゃと降りました。
窓という窓から顔を出して見守る住人たちが、歌っています。くり返しくり返し歌っているために、もう全員が歌詞を覚えました。
その頃、少し離れた高速道路で、一人の警察官が裸足で走っていたところ、よけきれなかった車にひかれて、病院に運ばれました。
同僚が最後に彼を見たのは、彼がこのマンションに関する報告書を、熱心に書いている姿でした。
同僚はその報告書を読んでみましたが、やがて裸足で走り出しました。
虫の救急車は静かです。人間の救急車はどうしてあれほどうるさいのでしょう。天の救急車に至ってはもう、先生、夜空いっぱいに響き渡りますよ!……












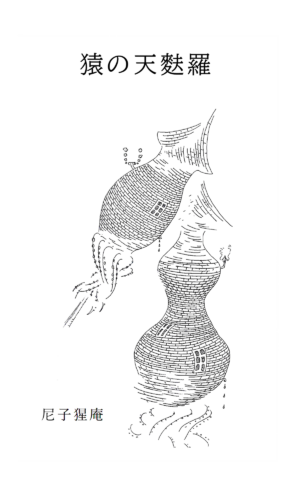
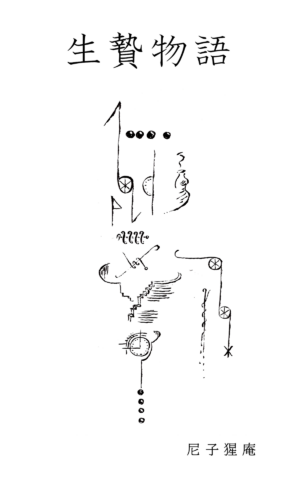









"発狂マンション"へのコメント 0件