其の壱
女体山、桃尻山、柔乳山の三山は女体三連峰と呼ばれ、はるか平安の昔から、近在の村人たちの尊崇を集め続けている。中でも女体山は標高こそ690mと低いものの、夢幻観音菩薩の化身と言われており、三山の中心霊場の地位にある。熟女の腰の線を思わせるなだらかにふくよかな稜線はまさに「女体」の名にふさわしい。しかしこの名の本当の由来は、麓から山頂に縦に走っている巨大な岩の割れ目である。割れ目の周囲は白い岩盤がむき出しになっており、ところどころしだれ柳が風にそよいでいて、いかな謹厳実直な石部金吉といえども、ついあらぬ妄想を抱いてしまうと言われるほどの絶景なのであった。
聖興宗因覚寺はこの女体山の山頂にある。開山は鎌倉時代と記録には伝えられるが、それ以前からすでに女体山の聖地だったらしい。夢幻観音菩薩信仰は今も連綿と続いており、参詣参籠の信者は絶えることがない。古刹らしく車両の乗り入れは禁止なので、寺へは例の割れ目の参道を伝って登るしかない。
朝の参道は秋景色であった。深山の暗緑色の中にも時折、華やかな黄や赤が交じり、岩道のせせらぎにはブナや銀杏や楓の落葉が流れる。岸辺には桔梗や竜胆が咲き乱れ、赤とんぼがつがいで飛んでいる。どこからか雉の鳴く声も聞こえてくる。
小説家・青柳優人氏は、片手に土産の一升瓶を下げ、傾斜の険しい山道をヒイコラ登っていた。まだ三十前のくせに早くも足腰が萎えている青柳氏を尻目に、四十代のおふくはスタスタ先に登って行く。健脚である。ピンと伸ばした背筋にも少しの乱れもない。長年に亘って広い青柳家の家事を一手に引き受けているだけのことはある。
「先生、大丈夫ですか? 少し休憩なさいますか?」
おふくの言葉が終わらぬ先に、青柳氏はその場にヘナヘナ座りこんでいた。
「あとどのくらいある?」
「半分ほどは上りましたかしらね」
「まだ半分もあるのか! 困ったな。ここまで来てしまった以上、もう引き返すこともできないし」
愚痴っぽくため息をついた青柳氏を、おふくはいつもの優しい目線で見つつ、襟足の後れ毛を整えながら、さりげない様子でこう尋ねた。
「それにしても先生、ここの住職様の御用というのはどういうことなんでございましょうね? なぜ私などをお供にお連れくださったのですか?」
呼吸も整わないうちに質問攻めか、と青柳氏は苛立たしげな目をしたがすぐに思い直して、
「この手紙だよ。まあいい、お前にも見せてあげよう」
と古ぼけた檀紙に書かれた書状を手渡した。
「どれどれ…一筆啓上仕り候。過年当寺へお立ち寄り下されし以来、多年に亘り音信これ無く候あいだ、この度、旧交を温めたく存知おり候。御依頼したき儀も候ほどに、必ず必ずお出まし願いたく候。尚、眉目秀麗にて聡明なる女子一人、御同伴願いたく候。因覚寺住職 厳岩頓首」
「ずいぶん昔、ここの寺の世話になったことがあってね。まだ学生の頃のことだよ。賀状を出すくらいで、連絡をしたこともなかったし、向こうからも音沙汰がなかったのに」
言いさして暗い表情になった青柳氏を見て、何かいわくがあるのだろうと察したおふくは、それ以上は聞かないことにした。「眉目秀麗にて聡明なる女子」に自分が選ばれたうれしさもある。もっともそれも当然であると思わないでもない。売れない小説家で収入などほとんどないくせに、親の遺産でのらりくらり暮らしている世間知らずの青柳氏を陰で支えているのはおふくであった。
「では先生、参りましょう。あまり遅くなってもいけません」
そう言って、おふくは先に立って歩き始めた。青柳氏もしぶしぶ立ち上がった。
今朝のおふくはいつもの割烹着ではなく、銀鼠の紬を着ている。値の張る衣装を着せたのは単に青柳氏の見栄だが、おふくは品よく着こなしている。こうして下から見上げると、まだまだ張りのある尻がよく動いている。秋の花を散らした裾模様からチラと白い脛が見えると、もう青柳氏はたまらなくなり、おふくを呼び止めて背後から抱きついた。お太鼓の下へ顔を埋めつつ前へ手を回そうとするがおふくは抗う。
「先生、いけません、こんなところで」
「こんなところだからこそ、その気になるんだ。ここの景色を見るだけでムラムラ来てしまう。お前は感じないか? 山全体にみなぎるこの淫猥な湿気を。風までがこころなしか生温かくて甘酸っぱい匂いがする」
「でも先生、ここの山の神様は女神様だというじゃありませんか。こんなところでナニしたらきっとお怒りになって、焼き殺されてしまうかもしれません。それにまだ頂上まで先が長いのに、ここで精をお漏らしになったら後が大変ですよ」
山の神の怒りはともかく、青柳氏は物書きにふさわしく体力にはあまり自信がない。それもそうだと手を放し、再び山頂目指して歩き始めたのであった。
其の弐
山頂・因覚寺のお湯殿では春香尼が湯浴みをしている。万事が質実剛健なこの寺にあって、唯一贅美を尽くした総桧造りの蒸し風呂である。湯船はない。白木の板の間の床下に竈で焼いた大石をいくつも置き、それに水をかけて蒸気を充満させる。蒸気の中に十分もいると、体中から汗が噴き出て、肌の老廃物が浮き出してくる。これを木綿の糠袋でこすり落として上がり湯の代わりに井戸水を浴びる。四季寒暖問わず、春香尼の日課となっていた。
糠袋で春香尼の背中を流しているのは桜子という在家の修行女である。粗末な木綿の作務衣をたすきがけにして、頭にはてぬぐいを巻いているが、すでに汗もしとどになっている。
「桜子はん、そなたもお脱ぎ。ついでに洗てしまえばよい」
春香尼の言葉に桜子は有り難く衣服を脱いだ。はだけた襟元から薄紅色の乳房が弾け、締まった腰とむっちりした尻と伸び伸びと長い脚が現れた。
「うちが流してあげまひょ」
「そんな、春香尼さま、もったいない」
「ええのよ、さ、糠袋貸し」
春香尼がこちらへ向き直った。湯煙の中でも玲瓏と涼しげな目元だ。全身白く光る肌を持っている。ただ白いだけではない、雪白というのとも違う、純白の陶磁器の白さとでも言おうか、白玉の壷とでも言おうか。桜子も美しい肌をしているが、春香尼の完全無比の白さには叶わないと思っていた。
ところでこの春香尼には毛がない。尼さんだから髪の毛がないのは当たり前だが、下の毛もない。幼女のようにツルツルの一本線である。それどころかこの尼さん、体中ムダ毛はおろか産毛の類にいたるまで、毛という毛は一本もない。さすがに睫毛と眉毛はあるが、鼻毛はもしかしてないかもしれないと桜子は疑っている。
ほっそりした腕が伸びてきて、桜子の豊かな胸元を糠袋でこすり始めた。ゆで卵みたいに小さな頭がすぐそこにある。作り物のような薄い耳とすっきりしたうなじから甘やかな芳香が立ち昇ってきた。少年のように華奢な体つきの尼さんなのに、そばに寄るとなんともいえぬ切なさに襲われて、冷静でいられなくなってしまう。
糠袋を持った手が乳首に触れた時、とうとうたまらなくなって、桜子は春香尼に抱きついた。
「ああ、もう我慢ができません。春香尼さま! どうかあたしにもお慈悲を」
「まあ、何を…」
構わず桜子は尼の小さな顔に自分の顔を重ねてしたたかに唇を吸った。肉付きのいい桜子に抱きつかれて春香尼は板の間に仰向けに倒れてしまった。桜子も一緒になって倒れこんで、春香尼の薄い耳たぶを噛みながら毛の無い丘へと手をやった。中指が割れ目の内部に沈むようにすっと入りこむと、ふわふわとろけそうな感触にいよいよ正気をなくしそうになる。すると尼の小さな手も桜子の毛に覆われた場所を探ってくる。
「まあ、桜子はん……あんたのここ、ええ形したはるなあ。ええ具合や。ふっくらして締りがようて、うちの指に吸い付いてきよる。見込んだ通りや。素質は十分」
囁きながら、尼の細い手指が桜子の一番敏感な部分にそっと触れ、巧みに撫で回し、揉みしだいて、トロトロのなめこ汁みたいにしてしまった。桜子も負けじと尼を攻め立てる。蒸気に混じって快楽の香りがムンムン立ち上り、二人はひしと抱き合い欲情した裸の肌をピッタリと合わせた。互いの乳房が柔らかく圧迫し合って、固くなった二つの乳首が擦れ合う。
それから尼は桜子を仰向けに倒すと、自分の脚をするすると桜子の脚の間へ滑らせた。淡く毛で覆われたピンクの秘所と真っ白な無毛の秘所とが合わさり合い、うねうねと動き始める。
「貝合わせ…いにしえからの雅やかなお遊びどすえ」
「あ、ああっ、春香尼さま!」
喘ぐ桜子にねっとりした笑みを向けながら、尼は両脚を締めて貝合わせの密着度を強めて行く。
「ほう…柔こいなあ、桜子はんの貝柱はこれか?」
「あ、あっ、そんなことしたら、あたし、イッて、ああっ!」
「ふふふ…イきよしぃ…」
「ぬおおおお、もうたまらん!」
突如、湯殿に野太い声が響き渡り、目隠しに置いてあった衣桁がガッシャンと音を立てて倒れた。驚いて振り返ると、衣桁のそばに引っくり返っているのは褌一丁の大入道である。
「御前!」
厳岩和尚はむっくりと起き上がった。見上げるような偉丈夫である。顔デカく目はギョロリ、耳も鼻も大きく、全身、熊のように毛深い。若い頃、熊野三山、出羽三山をはじめとする全国の霊山で山伏の修行を修め、極寒の山中での滝行、不眠不休の回峰修業、断食断水断眠での真言念誦など、数々の荒行を積んだ後、雲水として全国行脚の旅をしたと言う。そのかいあって六十の声を聞いた今もたくましい体つきは衰えない。
「御前、待っとくれやす、今日は願ほどきの大切な日どす、明日になったらまたゆっくり」
「願ほどきがなんじゃ! もう千人斬りは達成したのであろうが!」
厳岩和尚は割れ鐘のような声で答えた。
「達成はいたしましたが、観音様へご報告をして願をほどかぬことには終わったことにはならしまへんのどす」
「もう待てん。あんたが童貞千人斬りの願を立ててから十年、とにかく目標を達成するまではと我慢を重ねておったが、もう限界じゃ。さ、参るぞ」
言う間ももどかしげに厳岩和尚、すでに突っ張り切っていた越中褌を毟り取ると、異常成長して規格外になってしまった巨大マツタケのようなシロモノが飛び出した。長年に亘る両刀使いに鍛え上げられて、赤銅色にテカテカ光りつつ、行く手を阻むものを威圧せんばかりに反っくり返っている。
「桜子や、お前は外へ行っておれ。後はワシが引き受ける」
不満げな桜子を湯殿の外に追い出し、厳岩和尚は猛然と春香尼に襲いかかった。そうしていきなり尼の無毛の丘に顔を埋め、鼻先で肉襞をこじ開けると、鼻息も荒荒しく音を立てて吸い始めた。春香尼は思わず甲高い声を上げたが、かろうじて理性を取り戻した。
「あきまへん! 今日だけはなりませぬ。あの日、必ず世の童貞さんを千人盗んでみせます、それまでは他の男とは決して臥所を共にいたしませんと観音様にお誓いしてから苦節十年、雨の日も嵐の夜もせっせせっせと男を探し、寄る年波に内心怯えつつ、顔で笑って心で泣いて、ようよう守り通したこの誓い、今日の今日でなんで破れましょうか」
「桜子はよくて拙僧はいかんのか?」
「桜子はんはおなごやさかい」
「拙僧とて観音様にお仕えしておる。あんたとはいわば同志。拙僧ならばお目こぼしくださろうて」
「堪忍しとくれやす。こればっかりは」
物柔らかだがきっぱりした尼の威厳ある声音に厳岩和尚もややたじろいだが、股間の巨大マツタケはいっかな承知をしない。
「それではあまりに殺生じゃ。ここまできたら引っ込みがつかんではないか」
泣かんばかりになってかきくどく和尚に、春香尼も心動かされたか、
「ほうやなあ、このままでは可哀相おすなあ」
と言って、おもむろに和尚の股間へ屈み込んだ。そしてこんなおちょぼ口がどうやってと思う間に、スルスルと例の巨大マツタケをくわえ込んでしまった。
「モゴモゴモゴ(このくらいなら観音様もお許しくださいますやろ)」
「ああっ、そ、そんなに強く吸ってはいかん!」
湯殿の外で衣服を整える桜子に、日頃の鍛錬にも似合わぬ和尚の狼狽した声が聞こえてきた。そっと中を覗いてみると、尼のしなやかな体が和尚のごつい胴の上に乗り、ゆで卵のような頭が腰の上で激しく上下しているところだった。
「おおっ、あんた、いつの間にこんな技を習得しておったのじゃ」
「モゴモゴ、モゴモゴモゴ(うちかて伊達に年はくってまへん)」
「むむ、なんのこれしき」
「モゴモゴモゴ、モゴモゴ?(これでどないどす?)」
「おおっ! もういかん、おおお、うおおおおおお!」
獰猛な巨大ヒグマもかくやと思わせる咆哮が轟き渡り、その後マツタケが萎れると共に、和尚の態度も急にしおらしくなった。
「いや、済まんかったな。危うくあんたの願を破るところじゃった」
「それも今宵で決着がつきます」
「童貞斬りも好きで始めたとはいえ、あんたも並大抵の苦労ではなかったじゃろう。それもこれもあの青柳めのせいで」
「青柳さんは今夜は?」
「うむ、来るぞよ」
「よろしゅうおした…これでお膳立てがすべて整いましたなあ」
春香尼は艶然と微笑んだ。それにしてもこの尼が五十を過ぎていると信じる人がいるだろうか。
桜子は中途半端なまま放置された欲情をもてあましながら裏庭へ行った。
好色の名高い厳岩和尚も桜子にだけは手を掛けない。桜子は和尚の血を分けた娘なのである。去年まで歌舞伎町のソープランドで働いていて、界隈では名を知らぬものもないほどの売れっ子だったのだが、ある日、突然父和尚に呼ばれて寺へ入り、髪は下ろさぬままで仏道修行をすることになった。ソープでの源氏名はプッシー・キャットと言う。和尚に似て両刀使いであるが、どちらかというと男の方がいい。
裏庭の畑で肥を担いだ男を見つけると、桜子は作蔵、と呼んだ。作蔵は桜子を認めると肥桶を地面に置き、ヘラヘラ笑いながらやってきた。作蔵は住込みの作男である。麦藁帽子に汚い手ぬぐいを顔に巻いた背丈の低い男だが、風俗にいた桜子は男の風采にはこだわらない。肥溜の傍らに敷いた筵まで行くと、桜子はおもむろに作務衣を脱ぎ捨て、作蔵のツギハギだらけのズボンを引きずり下ろした。
この男は父の和尚のような巨根は持ち合わせていないが、野良仕事で鍛えた体力にものを言わせた荒っぽさが桜子の気に入っていた。寺に百人はいる美少年の稚児に手を出すことは固く禁じられている。和尚と尼が仲良く共有しているのだ。そのかわり、作蔵などの下男や出入りの商人や檀家の男をつまみ食いすることは大目に見てもらっている。
前戯の類は一切省略し、作蔵はいきなり彼の商売道具を取り出すと桜子に乗っかった。畑を耕すのが専門の作蔵の鍬使いはさすがに堂に入ったもので、どっこんどっこんと打ちつけたと思うと、ざっくざっくと掘り返し、またどっこんどっこん打って、と言った具合で、肥溜にたかる蝿も作蔵の尻には停まるヒマもない。畑の大根を両手で握り締め、肥の匂いを吸いこみながら、桜子は歓喜の声を上げ続けた。
其の参
「あれから十年にもなるのですな」
金襴の袈裟をまとった厳岩和尚は青柳氏に抹茶を勧めながら闊達な口を開いた。湯殿での出来事などなかったかのように、いかにも高僧らしい威儀を整えて座っている。一方、春香尼もさきほどの狂態はどこへやら、端然とした墨染めの法衣姿で、目元に涼しげな笑みを浮かべながらしみじみ、
「青柳さんも…御立派にならはりましたなあ」
と言った。
青柳氏は我知らずドギマギしてしまい、それをごまかすかのように手土産の銘酒「若竹女ころし」を和尚に手渡した。和尚はかたじけないと言って受け取りながら、後ろで控えているおふくに目を留めた。
「青柳さん、その女性が?」
「青柳家の女中頭、ふくと申します」
青柳氏が口を開く前におふくが自分で三つ指をついて挨拶をした。厳岩和尚はギョロ目を見開いて、なんともいえぬ好色の目線でおふくの全身を舐めまわした。
「ふむ、器量といい、年の頃といい、品のよさといい、まさにうってつけではないか、どうじゃな、春香尼どの」
「へえ、よろしおすな」
「いったい何のことで…」
尋ねる間もなくおふくは厳岩和尚の頑丈な手で畳に転がされた。和尚は目にも止まらぬ早業で女の裾に毛むくじゃらの手を突っ込むと、秘所に指を滑り入らせた。
「あれっ! 何をなさいます、御無体な」
「わ、和尚、いくらなんでも気が早すぎるのでは…」
「まあまあ慌てるな。ちょっと具合を確かめただけじゃ。うむ、思った通りの名器じゃな」
と、和尚は指をチュパチュパしゃぶりながら満足した表情になった。
「どうじゃな、おふくどの、ひとつそこもとを女と見込んで頼みがあるのじゃが」
おふくは侠気のある女である。女と見込まれたからには承知せずにはいられない。
「いったいどんなことなのでしょう」
「他でもない、十年ぶりに青柳さんにお越しいただいたのはな、今夜の秘仏開帳の手伝いをお願いしたいからなのじゃ」
「待ってください、秘仏開帳ですって?」
「うむ、今宵はちょうど三十年に一度の夢幻観音御開帳の日に当たっておっての、近在の村から信者が観音様を一目拝もうと集まって来るのじゃ。当寺にとっても一大イベントであるからして、荘厳に厳粛に行いたいと思っておる。それと、そこの春香尼どのの十年来の宿願が叶ったので、御開帳に合わせてその願ほどきの儀式も併せて行う予定じゃ」
「それが私と何か?」
当惑するばかりの青柳氏に、春香尼がにこやかに口を挟んだ。
「青柳さんは有名な小説家にならはったそうどすな」
「はあ、いや、その小説家などというほどのものでは」
「ご謙遜はよろしい。お頼みというのは、今宵の御開帳の様子を、ぜひとも青柳さんのお筆で、後世に伝えていただきたいのどす」
「私ごときにそんな大切な儀式は…」
「青柳さんに書いていただきます」
ためらう青柳氏に引導を渡すかのようにきっぱり春香尼が言った。
「それで、おふくどのへのお願いというのは…」
女体山に伝わる観音伝説は数多いが、一番有名でかつ今も人々の生活に根付いているものは「観音降臨」であろう。麓の集落で、十五、六歳になった少年がいる家に、ある夜、人間の美女に姿をやつした観音菩薩が訪れて、性の手ほどきをしてくれるという。夢のようなひとときを過ごした後、観音は静かに去って行く。それから若者は決まって眠りこけてしまい、日が高くなってからやっと気がつく。目覚めた頃にはせっかくの観音様との交情の様子さえおぼろにしか覚えていない有様なのだが、夢ではなかった証拠が体に残っている。すなわち男性自身に梵語で観音の真言が刻まれているのである。
観音に選ばれた若者は「観音童子」と呼ばれて村中の羨望を集めたものだが、戦後になってからは民主主義の世の中を反映してか、急にその数が増えた。特にここ十年ほどは、村で生まれたほとんどの若者のもとに観音が訪れるようになった。
「近頃の観音さんは男が好きなのじゃな」
などと村人は言い合ってはいたが、ともかく観音童子を出した家には、商売繁盛、無病息災、悪霊退散、家内安全、夫婦円満、子孫繁栄、等々、観音様の有り難い御霊験が雨あられと降り注ぐのだから、否やのあろうはずもない。逆にいまだに観音様のご降臨のない若者はいつまでも一人前扱いしてもらえず、あれは不吉な家だということになり、嫁のきてもない有様である。
したがって年頃の息子を持つ親たちはこぞって観音の御座所であるこの寺へ参詣し、若者の在所、氏名、年齢と顔かたちの特徴を記した願文を奉納し、多額ではないが、つましい生活から捻出した喜捨を伏し拝むようにして厳岩和尚に差出すのである。
おかげで厳岩和尚は大好きな酒と百人の食べ盛りの稚児を養うのには事欠かないという寸法だ。願文を収めた奉納箱は春香尼だけが開けることができる。
「なるほど」
そこまで聞いた青柳氏は深く得心して頷いた。
「なるほどね」
おふくも頷いて、青柳氏の耳元でこうささやいた。
「つまりあの尼さんが死んでしまったら、観音様の御降臨もなくなるということですか」
「そういうことだ」
「そのご心配なら御無用どす」
なぜ聞こえたのだと驚く青柳氏らに、春香尼はにっこりと笑いかけ、
「ちゃあんと跡継ぎは探してあります。まだまだ修行と覚悟が足りひんけどな。私利私欲やのうて民百姓の幸せのために、観音様の名代として死んだつもりで尽くすんやいう心がけがのうては、勤まらんお役目ですさかいなあ」
と言って、尼は障子の向こうへ声をかけた。
「桜子はん、お茶のおかわりを」
ほどなく障子が音もなく開いて、法衣をまとった若い女がしとやかに入ってきた。
「プッシー・キャットじゃないか!」
かつて通いつめたソープ嬢の顔を認めた青柳氏は驚愕して叫んだ。
「ああら、青柳さん、お久しぶりね」
プッシー・キャットこと桜子は店にいたころと変らぬキャピキャピ声を上げた。
(下へ続く)
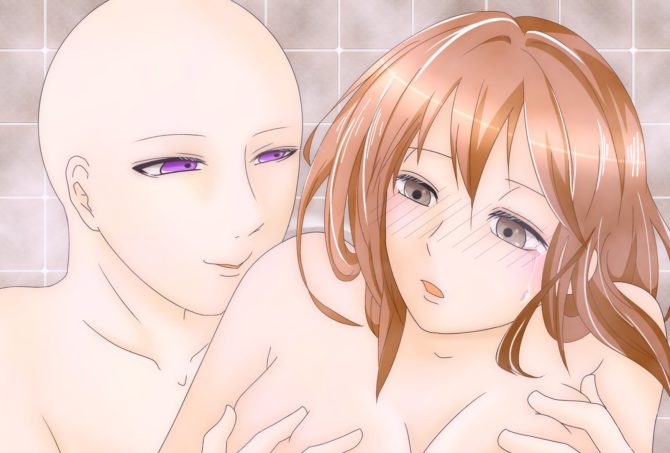























"女体山夢幻観音開帳縁起・上"へのコメント 0件