同級生の理沙ちゃんが大好きだった。趣味や好きなテレビ番組が同じで、おしゃべりしていると楽しかった。おっとりしていて優しくてめったに怒らなかったから、内気な私でも安心して何でも話せた。
いつもいつも、理沙ちゃんと一緒にいたかった。幸い同じクラスだったから、休み時間や放課後もべったりくっついていた。学校帰りには互いの家のどちらかへ立ち寄って遊ぶこともあった。私の家が多かったように思う。
理沙ちゃんが来てくれた日は、嬉しくて嬉しくて、来客用の高級菓子を勝手に出したり、マンガや雑誌をある限り広げたり、居間の大型テレビを占拠してアニメや映画を一緒に見たりした。嬉しい気持ちが昂じた時は、理沙ちゃんと無理に腕を組んだり、横から抱きついたりもした。
どのくらいの間、そんな楽しい時間が続いていたのか覚えていないけれど、理沙ちゃんの足は次第に私の家から遠のいていった。放課後や休日前に遊びにこないかと誘っても、ダメというばかりだった。理由を尋ねても返ってくるのは要領を得ない返事ばかりだった。
それでも教室では相変わらず「仲良し友達」のままでいたから、私はそれほど気にしなかった。家で遊べなくなった分、余計に理沙ちゃんとくっついていようとした。
その年、県の合唱祭へ私たちの学校も参加することになり、低学年、高学年でそれぞれ合唱チームが選抜された。
私は高学年の代表に選ばれた。理沙ちゃんも選ばれた。一クラスから選ばれるのはせいぜい数人だから、選ばれた子たちは誰もが晴れがましい顔をしていた。
その日の五時間目の自習時間、急に担任の先生が入ってきて、合唱の代表に選ばれた者は自習しなくていいから、音楽室に行くようにと言った。私も理沙ちゃんも席を立った。いいなあと、からかい混じりの他の子たちの声が聞こえた。
私はすっかり嬉しくなっていた。だってみんなは自習で教室に残るのに、私と理沙ちゃんは合唱団の練習で音楽室へ呼ばれてゆく。私たちは特別扱いで教室を出て、他のみんなは教室へ残る。大得意だった。それで私は見境なく理沙ちゃんに抱きついた。それしかこの途方もない嬉しさを発散する術がなかった。教室から廊下へ出るまでの間、ずっと抱きついたままでいた。
私に抱きつかれたまま、理沙ちゃんはずっと無言でいた。けれども廊下へ出てしばらくすると、突然こう言った。
「やめてよ」
理沙ちゃんは体を固くして私の腕を振りほどいた。
「こういうの、気持ち悪いからやめて」
廊下を先に歩いて行った理沙ちゃんの後姿を眺めながら、私はしばらくその場に立ちすくんでいた。実際、体が動かなかったのだった。
やっと気を取り直して音楽室へ入って行ったら、合唱の説明会はもう始まっていた。机や椅子を後ろに下げて、全員が立って説明を聞いていた。クラス別に並ばされていたから、理沙ちゃんの隣が私の並ぶべき場所だった。そっとその場所へ立った時、理沙ちゃんがちょっと体を離したように思えた。
二十分ほどの説明会を、私は立って聞いていることができず、途中で気分が悪くなって保健室へ行った。翌日から始まった練習でも、やっぱり途中で気分が悪くなった。音楽の先生から、体の弱い者は合唱に出なくてよいと言われた。一人音楽室を去ってゆく私を理沙ちゃんは振り向きもしなかった。
それでも私は理沙ちゃんが戻ってきてくれるのではないかと期待していた。「気持ち悪い」と言われたことはショックだったけれど、あんまりベタベタしなければいいんじゃないか、普通にしていればまた友達付き合いができるのではないかと希望をつないでいた。でも放課後、一緒に帰ろうと誘った私に、理沙ちゃんは口ごもりながらもハッキリとこう言った。
「私、これからは田中さんと帰るから」
耳の奥でけたたましい音が鳴った。例えば黒板を両手でひっかいたような、屠殺寸前の豚の悲鳴のような、背筋に震えが走るほどの不快な音だった。
すべてがダメになった。理沙ちゃんはもう帰ってこない。あの優しい理沙ちゃんがここまで言うなんて。嫌だったのに言いかねていたのに違いない。それほど私は嫌われていたのか。溢れる感情をそのまま垂れ流していたのだけど、理沙ちゃんには迷惑だった。迷惑だった。
その時以来、私は親しい友達との間にも、適度な距離を保つべきであることを覚えた。
恋をした。生涯に一度だけの恋のはずだった。
私はその人を心の底から愛していた。この人にめぐり合うために生まれてきたのだと本気で思っていた。その人も私を愛してくれた。ただし魂というよりは十代の若い体の方を愛していたようだった。
私にしても無防備に体を委ねることにためらいはなかった。実際、二人きりでいる時間は楽しかった。濃密な肌の触れ合い、深く交わる体、それらから得られる激しい快楽に私は酔った。同じ快楽に彼も酔っていると思った。
生きていることそのものが彼への愛の証で、日常のちょっとした動作も会話も、すべて彼を愛するがゆえのものとなった。私がこんなに愛していることをのべつまくなしに伝え続けたかった。彼にもそれに応えてもらいたかった。その期待はしばしば裏切られたのだけれど、恋で盲目になった私はそれを認めようとせず、彼は応えてくれているんだ、表現方法が違うだけなんだと思い込もうとしていた。
ある夜、彼はこう言った。
「こういうのはあんまりよくないよ。大人なんだから、自分をもっとしっかり持たなくちゃ。僕らは大人同士で楽しんでいるだけなんだから」
目の前が真っ白になり、ひとことも口がきけなかった。
前に一度聞いた不愉快な音が耳の奥で鳴った。そしてすべてを理解した。彼が正しい。のぼせ上がって舞い上がっていた私を、彼は冷静に観察していた。そしてこれでは危ないと思って忠告をした。それだけのことだった。
その夜も彼は私を抱いた。こんなことがあっても、体はきちんと快楽を覚えていた。一生に一度の恋なんてそんなものか、と思った。
とは言え、それは生まれ持った癇の虫のようなもので、一、二度、やられたくらいでは懲りることもなく、その後も何度か同じことを繰り返した。
ある人は繊細で豊かな感情に恵まれていて、私のことも本気で愛おしんでくれた。熱烈な愛情に熱烈な愛情で応えてくれた。私の感情はまたしても幸せな暴走を始めた。
けれどもその人は、私と一緒になって暴走するには、体力が足りなかったようで、最後には疲れ果ててしまっていた。日に日に生気を失っていく彼を見て、狼狽し動揺し罪悪感に駆られ、なんとか疲れさせないようにと気遣っているうちに、私の方も疲れてしまった。砂の城が壊れてゆくように、ゆっくりと確実に心が離れて行くのを、二人して無気力に眺めているほかはなかった。
またある人は、恋愛感情と利害の計算との区別がつかない性質の人だった。その人が私を選んだのは、私の存在がその人にとって利益があるからだった。そしてその利益イコール恋愛感情だと素直に信じ込んでいた。私はそれに抵抗し反抗し、利害を抜き去った私だけを見てくれるよう要求した。でも彼にはその意味が分からなかった。怒鳴ったり、叫んだり、身悶えしながら泣いたりする私を、途方に暮れて見ているだけだった。
何度かあの豚の断末魔を聞いた。あれは外から聞こえた音ではなく、実は自分が発した絶叫なのだった。不細工で浅ましいその声を、声を嗄らすまでがなり立てわめき散らして、精神が崩落するのをかろうじて堪えていた。
独りよがりの激しい感情など他人には迷惑なだけ、過剰な愛情など邪魔にはなっても何の役にも立たない、感情はオブラートに包んで小出しにするものだと、幾つかの経験から手痛く思い知った。
そうして私は、他人をあまり必要としていなさそうな人、他人からの激しい感情にも平気でいられそうな人と結婚した。結婚当初はそれに戸惑ったのだけど、慣れてしまえば楽な生活だった。
そのうちに子供に恵まれた。男の子だった。
可愛かった。赤ん坊にはどれだけ愛情を注ぎ込んでも少しも嫌がることがない。可愛がれば可愛がるほど、小さな体で喜びを一杯に表現した。その可愛らしい姿が私への最上の返礼だった。愛し愛される蜜月時代に満足して、子供の成長に一喜一憂する生活に没入した。
ある年、子供たちと母親が集まってクリスマスパーティを開いた。場所は近所のカラオケ屋のパーティールームだった。広い部屋に子供たちを勝手に遊ばせて、日ごろ家庭と職場で忙しく働いている母親たちが、多少は開放された気分になって思い思いに喋ったり歌ったり酒を飲んだりしていた。
大人の集まりの場へ連れて来られて、子供たちも有頂天だった。大人に混じって上手にカラオケを歌う子もいれば、そこらで転げ回って遊んでいる子もいた。唐揚や焼き鳥に食いついている子もいた。
息子も楽しそうに遊んでいた。いつもはあまり遊んだことのない友達と、今夜はカラオケルームで一緒にいることが、とてつもない楽しみに思えているようだった。テーブルに並んだごちそう、賑やかな歌声、笑い声、それらがいちいち嬉しくてたまらない様子で、あちこち飛び回ってはケラケラ笑っていた。
テーブル席で座って飲んでいる大人たちの後ろでぴょんぴょん飛びはねていると、ヒロ君がやってきた。ヒロ君は息子の前で足を止めた。目の前に立っていられると通り抜けられないからだ。息子はヒロ君に気がつくと、満面に笑みを浮かべて正面からぎゅっと抱きしめた。
ヒロ君は顔を強張らせ、邪険に息子を突き飛ばして、さっさと通り抜けて行った。 息子の上気して真っ赤だった頬がスーッと白くなった。そしてしばらくその場につっ立ったまま動かなかった。
しばらくして気を取り直したのか、再び遊びに行ってしまった息子を、私はただ見つめていた。見ていることしかできなかった。
この子もあの声を聞いたのか。これから幾度となく痛烈に思い知らされることになるのか。
だとしても、やっぱり見ているしかできないのだろう。だってそれは教えてやることのできないことだから。
突然、はっきりと意識した。それは私の中でも決して消えてはいなかったのだった。処世術に隠した埋火が、じわじわと頭をもたげてくるのを感じた。これからも何度も、あの絶叫を聞くのだろう。枯れ果てて朽ち果てるまで。
聞き続けるよりほかにないのだ。
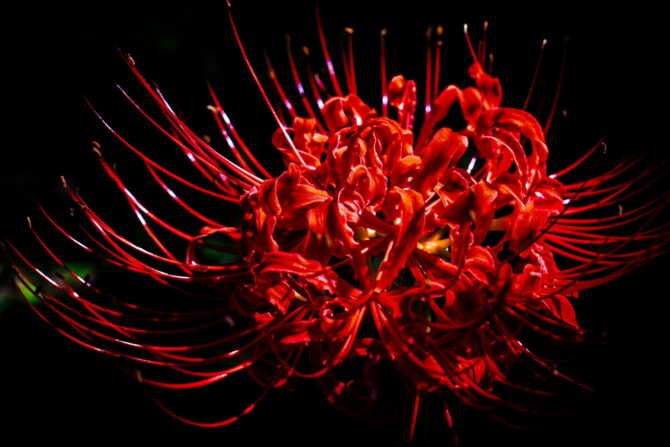






















眞山大知 投稿者 | 2025-11-14 13:48
太宰の『トカトントン』のような話だと思って読んだのですがトカトントンのように幻聴が聞こえる主人公に作者が救いの手を差し出すわけでもなく、オチが絶望的で気分が重くなる作品でした。たしかに感情的な女性と感情が揺れ動かない男性とのカップルは結構安定していて長続きするんですよね……
河野沢雉 投稿者 | 2025-11-15 10:19
人はみな社会に適合するために大なり小なり感情を抑えこむことを覚えるのですが、それをいつどうやって学ぶかというのは、誰が教えてくれるわけでも、マニュアルがあるわけでもないので、人によっては怪我をしたり、とんでもないトラウマを残しながら覚えることになってしまう。
抑えこむ以外にもやりようはあるんだよ、というのを提示するのが文学の役割の一つだと思うのですが、こっちは真逆のベクトルで辛い。救いがない。豚の悲鳴が耳に残りそうです。
曾根崎十三 投稿者 | 2025-11-16 11:32
語り尽くすには尺が足りない内容ですね。
絶叫じゃなくても良い気はしますが、好きです。人生を感じました。傑作というのはいかに「ああこれは自分のことだ」と思わせられる作品か、とも言いますが、そういう点で傑作だなと思いました。私はここまで奔放ではないですが! 世間一般の価値観としてはどうか分からないのですが、私ウケが良い作品です。曾根崎賞があったら出せます。
今はその激情が身近な他人には向かなくなっただけで、消えたわけではない、というのも良い。現実ですね。人生。
持野キナ子 投稿者 | 2025-11-16 18:34
誰しも共感できる内容な気がして、とても面白かったです!
本作は薄暗い後味で終わっていますが、主人公と子供が人生経験を積んで少しでも生きやすい世の中になることを願いました。
佐藤 相平 投稿者 | 2025-11-17 15:47
淡々としているようで、奥底に強い熱を隠しているような文章が良かったです。僕も小さなころから人との距離感がわからないので共感できます。「理沙ちゃん」との話、恋愛の話、子どもの話、と3つの部分から成り立っている作品ですが、それぞれが独立しておもしろく、しかも相互にうまく結びついているのが上手いです。技巧的になり過ぎず、さらりと書かれているのが好みです。曾根崎さんがコメントしているように、人生を感じます。私たちは年齢を重なるごとに変化していくのか、しないのか。そんなことを考えました。
諏訪真 投稿者 | 2025-11-27 21:59
既にコメントでありますが、これは自分の話かなと思わされて、非常になんか羞恥心を刺激されるなと。
そんなところを晒さないでくれと。