鏡に、濡れた生白い体が映っている。我ながら脆弱そうな細い腕の右の二の腕には繋ぎ目がある。雑に縫い合わせ、真っ赤な肉が糸のあいだから痛々しく覗いていた。
シャワーの音が響く。当然、伝う湯に血が混じることはない。なかなかリアリティーはあるが、これは昔彫り師に掘らせてやるかわりに格安で彫ってもらったデザインだ。
「内側の部分はちょっと痛いぜ」と言いながら彫り師はボクの腕に針を刺していったが、ボクはしれっとしていたと思う。確かに切られるような痛みを感じたが、普段スッキリしたいときボクは左手を刻んでいる。慣れていた。なにも切られるだけではなく、痛みそのものにも。
鏡には煙草を押しつけられたり、ぶたれたりしてできた古傷はハッキリとは映らない。切れ味の悪い果物ナイフで刺されたこともある。彫り師は「カワイソウな体しているな」と言葉とは裏腹にニヤニヤ下品に笑いながら、ボクを抱いた。
彫るのは繊細なのに、掘るのは雑すぎてがっかりしつつ適当に合わせて喘いでやった。タトゥーで埋め尽くされた彫り師の体に手を回して、肩に綴られた古代ギリシア語の〝神は愛です〟という意味らしい聖書の一文に爪を立てた。
コックをひねってシャワーをとめる。バスルームを出て、水滴を拭い、ボクサーパンツを穿くと髪を乾かす。ドライヤーを洗面台に置いて、M字にカットしている前髪をワックスで軽く整える。そのまま洗面台の鏡を見ながら、ワックスの隣に並べていたアイライナーで垂れ目を黒く囲む。途中、マニキュアが一部剥げていることに気づいた。あとで黒く塗りなおそう。
好きなバンドのバンドマンはだいたいこんな感じのビジュアルだった。モテるから、という理由もあいまってエモファッションは趣味。「女もオネェも嫌いなんだろう? なのに化粧なんかして女みたいだ」と男娼にからかわれたときは相手がたじろいだくらいキレたけど、あとからふとボクは男でありたいわけでもないのかなと思った。
あくまで男は愛されたい対象なだけだ。マッチョなボトムがモテないわけじゃないけど、なれそうにないし、なんとなくなりたいとも思わない。できるかぎり、中性的でいたいな。鏡の中のまだ少年と呼んでもいい顔をしばらく見つめてから、部屋に戻る。
なんとなく窓へ近寄って、マルガリータ街8番通りを見おろす。深夜だけどネオンでビカビカしているから、行き交う男たちの姿がよく見えた。カップルは寄り添うようにして歩いている。
住んでいるアパートメントのすぐ前、ビカビカに加わっているバー《New★World》ではボクの恋人、コスタが働いていた。新世界でもなんでもないだろう、ここじゃ。
「はやく、朝にならないかなあ……」
思わず、独りごちる。バーに行きたいけど、ボクはコスタの仕事の邪魔をしてしまうだろう。コスタが仕事に行って、まだそんなに経っていない。なのにもうキスしてほしいし、抱いてほしかった。
窓から離れて、ベッドに寝転がる。ベッドサイドテーブルのように使っている椅子から爪ヤスリと黒のマニキュアの瓶を取って、あちこち剥げて爪に汚く残っているマニキュアを削り落とし、塗装しなおす。照明を受けて黒く艶めく爪は、まるまると太ったコックローチの体を思い出した。
乾いていない爪に触れないように仰向く。天井をぼーっと眺めていると、女の豚みたいな鳴き声も浮かんできた。
日が落ちているときは下品に賑わっているのに、日が出ると嘘のように閑散とするマルガリータ街と同じく、夜はボクも忙しかったはずなのに、今は寂しくて、暇で仕方がない。幸せなことだ。けど、暇を潰そうとする無意識がそうさせるのか、いろいろなことを回想してしまう。
幼いボクは膝を抱えて、囲まれているゴミ袋のあいだから、黒光りするコックローチがさっと通る様を覗いていた。寝室のほうから、母親――以後、女と呼ぶ――が男とセックスしている声が響いていた。豚の鳴き声に似ているなと思った。
ようやく鳴き声がやむ。それから女がボクがいるリビングルームの隅っこへやってくる。
「エディ、お腹空いたでしょ?」と、スナック菓子の袋を投げてきた。無言で受け取った次の瞬間、平手が顔に飛んでくる。視界の端で、女の爪のラメが煌めいた。
「なにシケたツラしてんのよ、お礼は?」
ゴメンナサイ、アリガトウ。と熱い頬をさすりながら呟くように言う。
「おおい、腹減ったからはやく行こうぜ」
「ああ、はあい。じゃ、いい子にお留守番しててね」
玄関のほうから聞こえてきた男の声に応じ、そのまま女は男と一緒に食事しにいった。女は男と遊びに出かけると、だいたい翌日になるまで帰ってこない。二、三日帰ってこないこともある。その間、家にある食べ物を勝手に食べたら、制裁を受けるから我慢した。制裁にはおもしろがった男も加わることがある。
でもこのヒステリー持ちの女は機嫌がいいときはたまにボクを抱きしめて、頭を撫でて、キスしてくれることがあった。だから、好きに思っていた頃もあった。
「エディ、こっちおいで」
微笑む女の手招きは優しげで、惹かれたボクは近寄る。寝室で女はボクの服を脱がし、ピンクのベビードールを着せて、化粧をした。「んー、かわいい!」と女は笑ってボクを抱きしめて、キスをした。どうしてこんなことをするのか意味はわからなかったけど、嬉しくなってボクも笑った。
直後、寝室に入ってきた男がボクをベッドへ放り、犯した。十歳の肛門じゃローションを塗っても鮮血が溢れ、元々シミだらけの汚いシーツをさらに汚した。狭くて痛いくらいだ、と男が呻く。ボクはまともに声も出せない。
女が煙草を吸いながら凌辱を眺め、言った。
「エディ、あなたはなかなか可愛いんだし、そのうち男娼にでもなってあたしを養ってよ」
まだ男娼の意味はわからなかったけど、この豚女に対して薄く残っていた愛は潰えた。
「あたしもねえ、街娼やってママを支えたもの……」
――ウン、血を吐くような暴力を振るってくる男より、とにかくあの女が嫌いだ。もう爪はちょっとくらい触れても平気だろう。仰向いたまま手を伸ばし、煙草に火を点けた。夜はまだまだ明けそうにない。
誰が父親に該当したのかわからないくらい頻繁に変わった情夫の中には、優しい人もいたしね。とくに、ジョージお兄さん。
「なんだって、こんな汚い部屋に子供を放っておいているんだ!? 学校にも行かせていないなんてっ……君はそれでも母親か!?」
と、女を怒っていた。
「知らないわよ、母親なんて!」
と、女は目に涙を浮かべて激昂していた。男と喧嘩になっても、野蛮な女は激しく対抗して泣くことなんてなかったから、めずらしい光景だった。
女が怒ったまま出ていくと、ジョージお兄さんはうってかわってあたふたと女を追いかけようとしたけど、膝を抱えているボクを見て、微笑みかけてくれた。そしてリビングルームをせっせと掃除してから、冷蔵庫を開けて「本当ひどいな」とため息まじりに呟くと、ボクをレストランへ連れ出した。
外は少し怖い。あまり出されたことがなかったし、女とめずらしく外出したときはぐれて迷子になって、賑やかな人ごみにめまいを覚えたことがある。保護されたあと、制裁だと女に車のドアで指を思いっきり挟まれた。たぶん骨イッてたけど、バンドエイドを巻いて耐えた。そのあとなぜか女がキャンディー買ってくれたことを、ジョージお兄さんの車の窓から流れていく夜景を眺めつつ、思い出していた。
「僕がパパになったら、必ず幸せにしてあげるからね」
ジョージお兄さんがハンバーグステーキとサラダ、スープを食べさせてくれる。それから女のヒステリーはいつにもましてひどくなったけど、ジョージお兄さんがいる間ボクは幸せだった。
しかしジョージお兄さん、いい人だったけどどうしてあんな女と結婚したがったんだろう? 紫煙をため息と一緒に吐き出す。残念だ。初恋の人であるだけに、よけいに。
物心ついた頃から自覚していた。床に散らばったまま、片づけられることのないポルノ雑誌。興味がわいて捲ってみる。裸の男女が絡んでいる表紙だったが、ボクはマッチョな男のほうに興味を持ったのだ。引き締まった体、たくましいペニス。熱くなっていく自分の股間に戸惑った。
日課のようにジョージお兄さんと喧嘩して、女はテーブルをひっくり返すほど怒り狂ったあと寝室へジョージお兄さんを連れ込む。ヒステリーによる興奮をジョージお兄さんの肉体で鎮めてもらっているのだ。ジョージお兄さんが女に喘がないように頼んでいるのか鳴き声はあまり聞こえないけど、容易にわかる。
羨ましい。ポルノ雑誌はもうジョージお兄さんが片づけてしまった。責任とってボクも鎮めてほしい。ムラムラする……精通はまだだったけど早熟なガキだったボクは、女に快楽を与えているであろうジョージお兄さんのすらっと背の高い体や、指や唇、抱きあげてもらったときに記憶した匂いを思い浮かべながら、小さなペニスを慰めた。
でも、ボクの幸せは長くなかった。喧嘩してから寝室へ行く一連の様子は思い出すと、そういうプレイのようだった。しかし〝知らない〟ことを責められつづけるのは相当のストレスだったんだろう。元々、女の情夫は入れかわりが激しい。女は熊みたいな男を連れて、家に帰ってきた。それからフラれたジョージお兄さんが泣きそうな顔で家に来た。
「ジェシカ! 僕が悪かった!」と、悲痛な声が響く。けど
「なんだテメェは!」と、ジョージお兄さんは熊男に殴られて泣いて出ていった。追いかけたかったけど、女に手首を掴まれる。女は笑っていた。そのまま熊男にフェラチオするように命じてくる。熊男と女がセックスするための前戯らしい。
熊と豚が寝室に引っ込んでからボクは口をすすぎ、久々に泣いた。
紫煙をまた、ため息と一緒に吐き出す。ウン、ジョージお兄さん好きだったけどやっぱりダメ男だ。ボクも人のこと言えない部分あるけど、見る目なさすぎ。あんな豚女放って、ボクをさらっていってほしかった。短くなった煙草を椅子の上の灰皿に潰す。
それから数日が経って、再びゴミで散らかりつつあるリビングルームの床から起きる。テーブルにブルーやピンクのクリームでデコレーションされたカップケーキが並べられていることに気づく。メモが添えられていた。《エディ、十二歳おめでとう。好きに食べていいわよ》そういえば誕生日だった。
熊と豚が居る気配はない。甘ったるいケーキを食べて、また床に寝た。しばらく帰ってこないだろう。
ずっと帰ってこなかった。
制裁の恐怖を乗り越え、家にある少ない食料を貪り尽くし、飢えを癒やす。しかし、ボクに罰を与えにくる鬼畜はいつまで経ってもやってこない。薄れる意識にジョージお兄さんの顔が浮かぶ。次に、不本意にも豚女の顔が浮かぶ。いったいどういうつもりだったんだ、あのケーキ。誕生日にケーキが用意されているだなんて、なかった……わけじゃないけど、思い出すのに苦労するくらい、めったにないことだ。
壁に手をつき、なんとか立ちあがる。足元を何回か口にしようか迷ったコックローチが通る。そのまま倒れそうになりながら部屋を出て、玄関に向かい、うすら恐怖を覚えつつドアを開けた。日の眩しさに目を細める。生存本能に任せて歩く。犬の散歩をしている老人が訝しげな視線を投げてくる。
また愛が欲しい。ああ、その欲求にあの女は別に関係ない。……見つけたコンビニエンスストアに食べ物を盗むつもりで入った瞬間、気を失った。
ボクは保護されて、施設に入った。豚女は捜されたようだけど、見つからなかった。もう、どこかで死んでくれていることを願う。
ベッドから起きあがり、キッチンへ向かうと冷凍ピザを一切れ電子レンジに突っ込む。食費もなにも払えていないけどコスタは怒らず、ほとんど煙草とキャンディーだけで生きていることもあるボクにむしろもっとちゃんと食べろと叱る。愛してくれるのなら、この生存本能には従おう。
通いはじめた学校とやらでボクは六、七歳くらいの子が教わるようなことから勉強をはじめたけど、なかなか呑み込めない。まわりの能天気な奴らはムカつくという事実はすぐに理解できたのだけれど。
まず、奴らは十分愛をもらえていて、幸せらしい。休日は家族とどこそこへ出かけただの、そんな会話が耳に入ってくるたびカルチャーショックを受け、そして腸が煮え繰り返った。ほかなんて知らなかったし、どこのガキもボクと同じように育てられているものだと思っていた。馴れ合えるわけがない。
そして幸せな奴らは異質なものをバカにしたがる。バカだのアホだの捨て子だの、そんなからかい取るに足りなかったけど、一年経って学校のマドンナらしい年上の女から告白されて、フッたらからかいはイジメに変化した。
確かに綺麗な娘だった。でも、女に興味はない。
「ゴメン、ボク男の人のほうが好きだから」
ほかなんて知らなかったし、男が男を好きになることがそんなに変なことだなんて思わなかった。
「近寄んな、ホモが伝染っちまうよ!」と、罵られ、避けられ、暴力を振るわれる日々のはじまり。わざとぶつけるように投げられたボールが顔に当たって鼻血を出してうずくまったとき、様子を見ていたマドンナが笑っていた。きっと告白なんてジョークだったんだろう。もう、あの豚女だけじゃない。女という生き物自体クソだ。
手当てしてくれたキリスト教徒の教師はいじめっ子を叱るより、ボクに同性愛について「地獄に堕ちる」と説教してきた。学校もクソだ。
……クソでも我慢してマジメに勉強していたら、人生違っていたかな? や、そうしていたらコスタにたぶん出会えていない。プラマイゼロだ、人生。レンジで温まってチーズの溶けたピザをさっさと食べて、戻るとまたベッドに寝転がる。
クソみたいな学校に通いはじめてさらに一年経とうとしていた頃、一方施設でははじめてのロマンスを経験した。
男しかいない施設はボクと同じように傷や痣だらけだったり、それぞれ独自の負のオーラを発している奴ばっかだ。もちろんいじめっ子もいて、断じて居心地がいいわけではない。そんななか、ひとつ年上のポーイという男は陽気にボクに話しかけてきた。頭をコーンロウにした黒白混血のその男はなかなかカッコよくて、悪い気はしなかった。
ボクがホモ野郎と罵倒されに学校へ行って、帰ったあと、ポーイにCDを貸してくれるという口実で自室に連れ込まれた。差し出してきたCDを受け取ろうと伸ばした手を掴まれる。男らしく整った顔を寄せられて、胸が高鳴ってしまう。
「やっぱりお前、男が好きなんだろう?」
ポーイが学校へ通っている様子はほとんどないが、どこからか噂を聞いたのか。それとも、挙動で見抜かれたのか。
「俺、どっちもイケるんだ。お前、可愛いし好きだよ。楽しもうぜ」
口づけられて、入ってくる舌。絡めることで返事をした。そのまま二人してベッドへ倒れる。服を脱がし合いながら、何度もキスをする。体が熱くなる。ポーイはボクが初体験だとでも思っているのか、いきなり突っ込んできたりせずに優しくしてくれる。
「や、ぁ……」
や、初体験だと言ってもいいかもしれない。レイプはただただ苦痛を覚えるだけだった。後ろからうなじや耳を舐められながら扱かれ、他人の手で触られる気持ちよさに喘ぐ。「声、女みたいで可愛い」と言われたときはしらけそうになったけど、肉体はそのまま達した。
もう精通しているペニスから出したものをポーイがキレイに拭ってくれる。「今度は俺もよくしてくれよ」と突きつけられたたくましい肉塊を口に含んでいると、また自分の股間が熱くなってくる。……とりあえずペッティングだけで済ませたあとベッドの中でいちゃついていたら、耳元でポーイに「愛しているよ、エディ」と囁かれて、ボクは悲しいわけでなく泣いた。
それから、ボクはポーイと同じく学校にまともに通わなくなった。一緒に遊び呆け、ポーイと付き合いのあるギャングからもらったマリファナを吸った。ハイになりながら体を求め合い、愛し合った。
「アアッ……ポーイ、それ気持ちいい」
路地裏の壁に手をつき、経験豊富な彼の手でバックは解され、溶かされ、涎を垂らしてしまうほどよがる。求められれば施設の部屋だけではなく、どこでも抱かれた。
たとえば、案内されたマルガリータ街8番通り。男しかおらず、街中でも誰もが平気で絡み合っている。しかし、この街に感動することができないのは、どいつも愛し合いながら死んだ魚のような目をしているせいか。周りに倣って路上に膝をつき、ポーイをくわえる。口笛が聞こえた。
そしてここなら、稼げるということを教わった。
「知り合いから借金してんだけどさ、返せそうにねえ……このままじゃ殺されちまう」
と、友達にガラの悪いのが多いポーイに泣きつかれてしまっては仕方がない。ボクは男娼の意味を知ることとなった。街角で、公衆便所で、ポーイに開発された体を使って客を取る。
ポーイを失わないためとはいえ、自分がひどく淫乱に思えた。セックスする前に済ませる浣腸と排泄を目の前でしてほしいとか、ボクを猫に見立てて皿に注いだミルクを四つん這いで舐めてほしいだとか、そういう気持ち悪い変態の客は嫌だ。けど、優しく愛してくれる客相手ならまあまあ楽しめてしまう。
だから、ポーイがどんなに浮気していてもなにも言えない。一回、女と浮気していたことがわかったときは問い詰めた。逆ギレされて、殴られた。そのあとしばらく口きかなかったけど、キスされて仲直り。
我ながらちょろい。こんなこともあった。ポーイの友達らしい男が住んでいるアパートメントの部屋に連れられて、その男と二人きりにされた瞬間ボクはレイプされた。ポーイはボクに「悪かった。キツく懲らしめてやったから、許してくれ。あんなのでも大切な友達なんだ……」とキスをして、優しく慰めてくれた。
ウン、思い出すとボクは最高にアホだった。ポーイはあとでその友達から金でも受け取っていただろう。借金とやらも疑わしい。煙草に火を点ける。
十八になって先に施設を出たポーイからいっさい音沙汰がなくなってからやっと、あ、別に求め合っていない、ボクってただの銀行兼肉便器だったんだな、と悟った。
それからボクも十八になって施設を出て、ほかに行き場なんてないからマルガリータ街8番通りに居着いた。
レオパード柄のソファーに座って、指と指を絡ませる。相手はボクと同じ、爪を黒く塗った男の子。ピアスをした口で、ボクのピアスをした口を塞ぐ。差し込まれた舌にも金属を感じた。
キスをしながら、指を解いて互いの体を弄り合う。Tシャツとジーンズ越しに刺激し合って、高まってきたら脱ぐ。勃ったペニス同士を擦り合わせて、わざとらしいくらいに喘ぐ。ソファーに倒れて、ボクは相手の、相手はボクのをくわえる体位になる。
ピアスの感触が気持ちよくて、素で息が震えた。ボクも舌開けよう。十分前戯をしたらボクは四つん這いに、相手は膝立ちになる。尻にローションが垂らされた。
「ああ、イイッ、イイッ……」
激しい抽送に合わせて鳴く。そのまま中に出された。監督がOKサインをする。コンドームをせず、フェイクでなく中へ出すだなんてよくないけど、ボクは精液を体内で受けとめるこの行為が好きだった。病気で死ぬことになっても、相手を殺すことになっても、別にどうでもいい。
トイレで惜しみつつ搔き出してくると、ボクを抱いた男優が仏頂面で煙草を吸っていた。射精したあと男は冷淡になるものだけど、挙動でわかる。この人実はストレートだ。撮影中のみの恋人に愚かしくも切なくなる。
マルガリータ街8番通りは排他的で、女とストレートの立ち入りは禁止しているような空気を醸し出している。観光スポット化する気はないらしい。おかげで居心地がよかった。でも、貧しさからか、ドラッグ欲しさからか、ストレートが働いていることもある。男優の腕にはうすらと針の痕があった。イバラのタトゥーもあった。ボクもそろそろタトゥー入れよう。
ネットに安値で配信されるであろうポルノムービー出演のバイトをおえると、安宿を出て街の雑踏に紛れた。
約二年間、ボクはとにかくいろんな男と交わった。ギャングの男。うさんくさい金持ちの男。無職の男。ボクと同じ男娼。商売や遊びの範囲も、懲りずにたびたび超えた。
アプローチしたけど白髪のパパ好きらしく、フラれた男娼に男娼失格だと笑われた。その男娼、恋人の老人に無理心中を図って捕まったと後で聞いた。
偽りでも抱きしめてくれて、頭を撫でてくれて、キスしてくれれば幸せな気持ちになれる。一夜がおわったり、関係がおわったりして、去ろうと向けられる背中を見ると幸せな気持ちはバラバラに壊れて地面に落ちる。
愛は、マリファナよりタチが悪いんじゃないか? と、ドラッグが切れて錯乱した客に頭を殴られ、血を滴らせつつ逃げながら思った。その客がやってたのはヘロインだけど。
痛い。めまいがする。路上に膝をつく。唯一好きになれる男もクソかもしれない、と絶望しながら倒れた。
日が昇りつつあるマルガリータ街8番通りに人通りはない。あっても無視されるだろう。や、助けられたところで困る。8番通りで血を流して倒れていた少年なんて、きっと病院でいろいろ調べられる。
意識が途切れる直前、甲高い、しかし男だとわかる声が響いた。
「キャーッ! どうしたのこの子!?」
目覚めると、そこは、そう……ボクが今、いろいろ思い出しながら寝ているベッド。そばにはコスタがいた。
「大丈夫かい?」
声は気絶する前に聞いた、オネェのものではない。初対面、コスタのルックスは別にタイプじゃなかったから、ボクは冷淡な態度を取っていたような気がする。コスタは苦笑して「僕もちょっと前までそうだったけれど……8番通りの男娼は君みたいな病んだやつばかりだ。嫌になるね」と、言った。
嫌になるね、はボクに対した言葉だと思っていた。
「頭のケガは、後が危ない。でも病院はどうせ嫌なんだろう? とりあえずはウチで安静にしてな」
ボクの頭に巻かれているのであろう包帯を指して、コスタが言う。下心だと思った。でも、求められたら応じるつもりだ。なんだかんだ言いつつ、愛してくれる男なら誰だっていいんだ、ボクは。
「元気になっても、しばらく居ていい? もうちょっと楽になったら好きなときにさせてあげるし……宿代も欲しければさっと稼いでくるから」
「別にいいけど、いらないそんなもの」
んだよ、ムッツリスケベ。ボクがタイプじゃないとか、向こうも完全にボトムとかだったらボクを置いておく意味がわからない。ケガが治るのを待たずに襲いかかってくるに決まっている。
が、なかなか手出ししてこなかった。もう取ってもいいだろう、包帯。
いろんな男の家を寝床にしてきたけど、こんなことははじめてだ。インポテンツだったのかペニスは挿入してこないけど、尻尾のついた玩具を挿れてくる男ならいた。玩具を挿れたまま四つん這いで、首輪もつけて一週間生活するよう命令してきた。たくさんお金くれたから耐えた。
「調子はどうだい?」
「包帯を替えよう。ママみたいに綺麗に巻けないけど」
「ちゃんと食べな」
こんなことは、マルガリータ街8番通りに来てからははじめてだ。ジョージお兄さんを思い出す。コスタはジョージお兄さんほどハンサムじゃないけど。
なにかを試したくなってシャワーで中を清め、中身のいっぱい残っているローションを見つけて拝借する。裸になって、ベッドに寝た。
「ただいまー……うわっ、なにしてるんだ!?」
「ワオ。いきなり入ってこないでよ」
股間にローションを垂らしてオナニーに耽っているボクを見て、コスタが目を丸くした。
「溜まってるんだよ。キミ、なかなか手を出してこないし……ウ、ン、はぁ、気持ちいい」
セックス漬けのボクだ。実際、溜まっていた。濡れたペニスをぬるぬる扱きながらアナルを穿る。
「ああ、でも、ひとりは寂しいな。……ボク、もう元気だよ。準備はできてる」
掻き回して水音を立てたあと、散々ブチ込まれてきて荒廃しきった肉壁を見せるようなつもりで拡げてみる。ローションがとろりと流れ出すのがわかる。シーツにシミ、できてるだろうな。
コスタがふらふら寄ってきて、ベッドにあがった。さすがにこれで喰わないのはありえないよね。ボクに被さって、優しく愛撫とキスを施してくれる。体の中心に堪らなくなるほどの熱が集まる。
「あんっ……準備、できてるって。はやく欲しい」
ズボン越しに撫でてみたら、コスタも硬い。やや身震いしてから、コスタは裸になった。結構立派なそれに期待する。けどすぐに突っ込まずベッドサイドの椅子からなにやら小箱を取った。
「ああ、ゴムしちゃうの? 中に出してほしいよ」
「ダメだ、衛生上よくない」
「まじめだね」
「当たり前のことだ」
当たり前、ねえ。コンドームを被せたペニスが宛てがわられる。背中に手を回し、そういえば伝えていなかったことを伝えた。
「エディっていうんだ。名前、呼んでっ……んあっ、あ、あああ」
ゴム越しなのが不満だけど、熱くトロけたバックを貫かれて、もうこのまま死にたくなる。
優しくて丁寧だけど、激しくてよかったな。思い出していると、体が火照ってしまう。や、テクニックを気に入ったから今まで二、三年もつづけているわけではないけど。や、ボクがフラれない限りおわるだなんてありえない。
二、三年から今までコスタはボクの隙間を〝当たり前〟で埋めてくれた。この当たり前を知らないままだったら、ボクはいったいどうなっていたんだろう? そしてまた失ってしまったら……いけない、手首切りたくなってしまう。
窓から朝日が射していた。灰皿の中は吸い殻で山盛りだ。ベッドからのろのろ起きあがる。細いダメージジーンズを穿いて、黒のタンクトップと星柄の袖なしパーカーを着る。レザーのリストバンドで、赤いリストカットの痕を隠す。あとちょっと待っていれば帰ってくると思うけど、ダメだ。
ベッドのそばに転がっているコンバースを履いて、部屋を出る。するとちょうど、隣の304号室からスーツを着た老紳士が二人出てきた。片方はゴミ袋を片手にさげて、お互い手を繋いでいる。この二人は結婚しているらしい。遠ざかっていく、仲睦まじげな二人の背中を見送ってからアパートメントの階段をおりた。
ひっそりとした道の向こう側にはもうネオンの消えている《New★World》扉を開けると、ゴリラのような体をミニのワンピースで包んだママが笑顔を向けてくれた。ママの隣では上半身裸なのに蝶ネクタイをしたバーテンがカウンターを拭いたりしている。
「コスタ! 愛しのエディちゃんが来たわよ!」
ママが、コスタが変なコスプレから私服に着替えているであろう控え室のほうへ大声を出した。つづいて
『愛しのエディ! 愛しのエディ!』
ギンガムチェック柄のエプロンをたくましい裸体に着けて、親指を立てて笑っている男のポスターの横、カゴの中のオウムが騒ぐ。長生きする種類らしく、五十歳近い。こんなところで飼われているものだから卑猥な単語ばかり覚えてしまっているが、今はボクになにやら求愛してくれている。
倒れているボクをコスタと見つけてくれたあの日以来、オネェは苦手だけどママとは普通に仲良しだ。ママも当たり前を知っている人間。やや呆れている様子のコスタを迎えて、朝食に軽い食事を出すというママの厚意を断り、ボクたちの部屋に帰る。途中、そっとコスタの手を握った。
「抱いて、コスタ」
部屋に入るなり、コスタに抱きつく。まずなにをするよりも、体を求めてしまうボクにコスタは黙って応じてくれる。
「ああ、もう、できることならずっと、キミとセックスしてたい……」
深くキスしてもらってから、そのままコスタの首筋、胸元に唇をつけていき、床に膝をつく。コスタのズボンのチャックをくわえた。
舐めて、たくましくなったペニスをゴム越しにだけど受け入れて、出ていかないでと懇願するようコスタの腰に脚を絡ませる。前立腺を突かれてイクと、やはりこのまま死にたくなる。
事がおわったあとベッドの上、コスタはボクの隣で浅く寝息を立てていた。いつもの寝る時間より早い。疲れているんだろう。しかし、構ってほしい。顔のバランスを崩してしまっている、コスタの鷲鼻をつまむ。
必死に探していたときは見つからなかったモノ。いざ手に入ったら、不安になるモノ。ボクのもとから去ろうと家を出ていくジョージお兄さんの姿、施設を出ていくポーイの姿が目の前をちらつく。一瞬、あの豚女も浮かんだけど、すぐに掻き消す。
あるゲイの殺人鬼は去られるのが嫌で、相手を殺したんだっけ。それで、食べたんだっけ。ボクなら食べられたいけどなぁ。……コスタが手足をバタつかせて、飛び起きた。
「な、なにするんだっ!」
「アハハ、起きた!」
いつも言っていることを唐突に発してみる。
「コスタ、ボク、キミに捨てられたら死ぬね」
せっかく得られた幸せを素直に享受しきれない。コスタはこんなボクにウンザリしているんじゃないか。でも怖いんだ、いつか去られるかもしれない幸せが。コスタが言うから男娼はやめた。けどもしもコスタから捨てられたら、また愛を探しまわる虚しい日々がはじまるだろう。
あまり依存していなかったし、マリファナもやめた。リストカットは無理にとめてこない。けど男娼生活に戻ったら虚しさからの逃避に、ヘロインにまで手を出すかもしれない。
コスタはため息をつくと、どこか悲しそうに微笑んで、ボクを抱き寄せる。硬い胸板、汗のにおい。
「どうやったら、君は安息できるのかな?」
聞き取りづらいほどの小声。つづいて、
「エディ、いつも言っているけど、君のその病気みたいなものは君が悪いんじゃない。環境が悪かったんだ。ゆっくりでいいから、飽きるまで愛してやるから、抜け出して……楽になろう」
大きな手がボクの頭を撫でる。
「……ウン」
ああ、ボクは、コスタを愛せているのか。これはただ隙間を埋めてもらいたいだけのエゴなのか、よくわかっていない。
ああ、でも、コスタ。
愛して、愛して、愛して、愛して。
ボクのなかの欠けているものを満たして。
「ちゃんと食べて、運動もしな。君は抱くのが怖くなるくらい細い。僕の可愛い黒猫ちゃん」
「コスタ、それさすがにサムい」
「……」
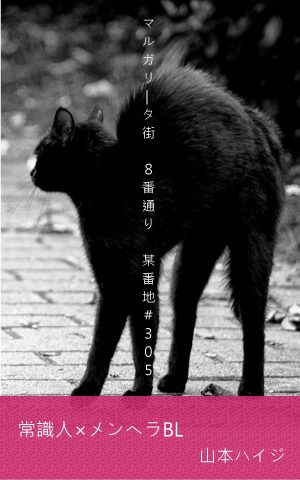










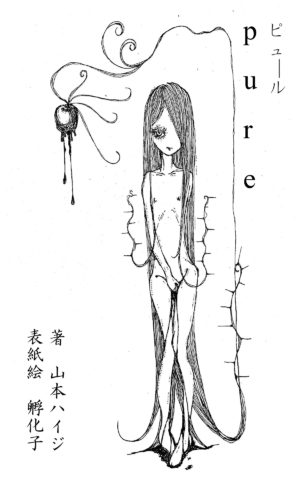











"マルガリータ街 8番通り 某番地#305"へのコメント 0件