乳首が見たい。桃色の乳首、褐色の乳首、黒い乳首、幅広の乳輪、幅狭の乳輪、小粒の乳頭、肥大した乳頭、陥没した乳頭、ひとりひとり違うそれをいちいちこの目で確かめたい。無論、乳房としての多少の膨らみがあってこその乳首であるからして、この内に子供や男子(相撲取りも含む)の乳首は入らない。また、見たいのはあくまでも人間女の乳首であり、女は女でもボノボの乳首は見たくない。後々変な揚げ足を取られても遣り切れぬから、予めこの辺りの線引きははっきりとさせておく。
そんな訳で、いま道の反対側で信号待ちをしている女、早速あの女の乳首が見たい。グレーのニットコートに黒いナップサックを背負い、両手をポケットに入れている。痩せ型の体型、年の頃は二十代後半。若干、猫背。彼女の乳首はどのような塩梅か。そしていま現在、それはブラジャーの中でどのように収まっているのか。寒さにかたく勃起してやいまいか。あるいは暖かい布生地に守られ、首を曲げてやわらかく埋もれているのか。見たところ、あの女は自分の乳首の具合を気にしている風ではない。まっすぐに前を向いて、ただ信号が変わるのを待っている。すなわち、あそこの乳首はいま彼女に放っとかれている。もったいない。乳首はもっと四六時中気にかけられて然るべきである。だのにあの女が平然としているのは、乳首がいつでもしっかりと己のものとして装着され、あまつさえその見てくれを毎日鏡の前で観察し塩梅を十分に知り尽くしているからであろう。慣れとは恐ろしいものである。いずれにせよ、あの女は自分の乳首に関してどのような所感を持っているのか。視認は叶わぬにせよ、それだけでも良いから知りたい。色、形、大きさをおおよそでもお伝え頂ければ、あとは私の方でなんとかする。
信号が青になり、乳首が近づいてくる。ニットコートの中に格納された乳首が近づいてくる。暗黒物質じゃあるまいし、確実にそこに在りながらどうしてほんの少しの視認さえ叶わないのか。それはあの女自身がブローカーとして立ちはだかっているからである。すなわち、たった数枚の布切れに隠された乳首でも、拝見するためにはあの女を介さなければならない。ブローカー類との交渉は私にとって最も不得手とするところである。すれ違いさま、とりもなおさず乳首との距離が最も近づいたとき、私はその軟禁された乳首に向かって(やぁ調子はどうだい、うまくやってるかい)と心中で呼びかける。ブローカーは変わらずまっすぐ前を向き、こちらの視線に気づいておきながらつんと澄ましているが、私には乳首がブラジャーという檻の中で声にならぬ呻きを発しているのが聞こえる様だ。嗚呼、ここはちょうど十字路。もしも私がロバート・ジョンソンだったなら、ギターなどすぐさま叩き壊して、迷うことなく透視の能力を頂戴するであろう。私はぐっと歯を食いしばり、乳首を後にする。
横断歩道を渡りきると、すぐさま次の乳首がやってくる。そう、世の中は乳首で溢れている。その持ち主は男にぴったりと寄り添い、絡ませた腕に乳房を押しつけている。あの男はあの女の乳首を知っている。平生からあんなに密着しておきながら知らぬとは言わせない。乳首の塩梅を知られている女と知っている男の二人組。女からはうまくブローキングを果たした充足と、男からはそれを我が物とした余裕が窺える。であれば、あの乳首は通常よりも意識される機会が多いはずだ。それは乳首にとっても本望であろう。しかし、乳首はもっと公に開かれた存在であるべきに思う。ひとつの乳首にひとりのブローカー。いくら価値を有するとはいえ、あまりにもこまごましく管理されすぎではないか。せめてその様子だけでもディスクローズされるべきである。あのモナ・リザでさえ実物こそなかなか見ることはできないが、様子だけは嫌というほど全世界に公開され知られている。それでもモナ・リザの価値は変わらないではないか。各乳首もそういう風に在るべきである。とまれ、あの男は密着している女の乳首に関してどのような所感を持っているのか。満ち足りているのか、いないのか。それだけでも知りたい。あとは私の方でなんとかする。すれ違いざまには二人から視線を外す。こちらの渇望を悟られては、男はきっと下目遣いをし、隣の女の乳首を知っていることの優越をここぞとばかりに醸し出すから。これをまともに喰らうのはなかなかに辛いことだ。なんせ私は背が高いのだ。
限界まで首を捻ってそっぽを向き、二人を視界から完全に葬った先、古い一軒家の二階のベランダでは、老婆がひとり洗濯物を取り込んでいる。老婆はこれでもかと服を重ね着しているので毬のように着膨れしている。ざんばらの白髪、物干し竿に引っ掛けた襦袢を取るべく、ヨイショと弾みをつけて曲がった腰を懸命に伸ばしている。あの老婆の乳首が見たい。もう何十年も乳房の先についている、とうの昔に無用の長物となっているはずのそれはどのような塩梅か。しなだれて弾力を失った乳房についた乳首は、やはり太く長く肥大化し黒ずんでいるのだろうか。否、こればかりは現物を確認してみなければわからない。桃色の小さな乳首をした老婆だっているはずなのだ。なぜならば、これは出産の経験やメラニン色素とやらの多寡を孕んだ複合的な事案なのだから。
仮にいまあの老婆のところへ行って「すみません、一寸乳首を見せてくれませんか」と言ってみたならば、不穏に首を傾げながらも案外家に招き入れてもらえ、ホイと躊躇うことなく見せてくれそうな気がする。老婆とはそういうものだ。彼女はあの厚着の中にランジェリーをつけているのか、いないのか。また、積年のそれを露わにする瞬間にはどのような表情をするのか。その辺も併せて確認したい。無論、目的はあくまでも乳首の観賞なのだから、塩梅さえ確かめられたら、あとはこたつでみかんでも頂戴しお暇すればよい。もしもそこに老年のハズがいたならば、時とともに老婆の乳首がどのように変容してきたか、その初見の日の思い出からじっくりと語ってもらうのもよい。きっと「また遊びに来なさいね」と見送られるだろう。
せっかくの休日。こうなってしまわぬために、私は本日昼過ぎに起床するやいなやすぐに手淫をしたのだった。そうして、平日のうちに散らかった部屋の片づけをし、溜まったゴミを捨て、洗濯をし、小便ついでに便器も磨いた。ゆっくりと風呂にも浸かり心身を整えた私は、本を片手にアパートを出た。すれ違うブローカーたちへは目もくれず、この世の不条理、あるいは儚さ、仮に無駄な抵抗だとしても芸術は運命を悔しがらせるためにあるのだ(芸術は女だが、女は芸術ではない。自分は大きな石像に噛みつく蟻のようなものだ)、そういうことを考えながら歩いた。町角の写真館に飾られた家族写真、幼児の手を引いて歩く仲睦まじき若夫婦、後部座席ではしゃぐ子供を乗せて走るミニバン、同じ面をした建売住宅、そこかしこの駐輪場に並ぶチャイルドシートを装着した自転車、押し付けがましく迫り来るそれらは軽やかに撥ね除けて。欺瞞に満ちた、形式ばかりのモノガミー。結婚なんざ、凡俗の凡俗による凡俗のために拵え上げられた実に馬鹿げたシステムである。
健やかな自己肯定により、出だしはよかった。行きつけのバーガーショップにてホットコーヒーを注文し、私は十九世紀オーストリアの哲学者オットォ・ワイニンゲルが命を賭して物した『性と性格』を開いた。この、女という存在に対する絶望的な論考。何度読み返したか分からぬこの本を開けば、藁にもすがる思いで手に取ったかつての懊悩がたちどころに蘇ってくる。平日に失われた精神性というもの、すなわち性的以上のなにかは、働かなければ食えぬ以上休日に取り戻すしかない。ゴッホが耳を削ぎ落としてまで向日葵を描き掴まんとしたもの、ニーチェがツァラトゥストラを以て発狂しながら掴まんとしたもの、宮沢賢治が雨ニモマケズのメモ書きを密かにトランクへ忍ばせ掴まんとしたもの、人間の成しうる仕事の内で最も尊く重要なものは芸術であり、それ以外の活動は単に目先の退屈と生活の不安に蓋をかぶせるためだけの凡夫専用のまやかしであるからして、そのようなものに忙殺され一度きりの人生を終えてしまっては、徹底的に無関心を貫き、いつまでも意地汚く沈黙し続ける創造主とやらの思うつぼである。いわんや恋愛・結婚をや。
視界の端に、三人組の女が座っていることには気づいていた。そのうちのひとりは赤ん坊を抱いていた。その女は膝上の赤ん坊を覗き込み、しきりにまだその生え揃わぬ薄い髪の毛を整えたり鼻水や涎を拭ったりし、時折自分のストローに口を近づけるときにだけ向かいの二人を見ておざなりに相槌を打っては、また赤ん坊をあやしていた。母親が熱心に背を丸めている分、向かいの二人が変に姿勢正しく見え、それがため彼女らが余計に手持ち無沙汰に見えた。とまれ、女たちの興味はすべて赤ん坊に集約され、交互に抱いてみては重さや匂いについて感想を述べあうなど姦しくしていたが、やがて赤ん坊がむずかりだした。
「おっぱいじゃない?」と向かいの二人のうちの一人が言った。
「うん、たぶんおっぱいだよそれ」ともう一人が言った。
「おっぱいあげちゃいなよ」
「うん、おっぱいあげちゃいなよ」
女らのおっぱいの連呼に、すぐさま周囲の者の反応が窺い知れた。たとえば、それまでしかつめらしく新聞を読んでいた初老の男は、明らかに文字を追うことをやめ、内容に集中できなくなっていた。ケータイゲームに興じていた青年はおっぱいというパワーワードが聞こえるたびにスリの目つきで女らの方を盗み見た。余談だが、私は駅の階段などでミニスカートの女が前を行くとき、そのものよりもまず周囲の人間の視線や動向の方を観察する質である(更に言えば、その際に近くの女らを見れば、やはり彼女らもまたミニスカートの女よりも男らの視線の行方を確認していることの方が多い。私はそうした女らとよく目が合う)。
とまれ、私はこういうこともあろうかと思い、手淫をしてきたのだった。余計な動物的渇望に苛まれずとも済むように。しかし女らは一向におっぱいの連呼をやめようとしなかった。あまつさえ若い母親はなにやらバッグの中からポンチョのようなものを取り出し、それを服の上からすっぽりと被り、あろうことかその場で授乳を開始した。見れば、母親よりも向かいの女二人の方が周囲を気にし、とくに新聞を読んでいるふりの初老の男を尻目に警戒しては、ポンチョの中でどれだけ服を捲ろうとも背中や脇腹も一切見えていないということを感心し合った。
私は努めてその方を見ぬようにした。見て、そのことに気づかれてしまっては、自らの存在が性的以外の何ものでもないが故に、男を渇望させることについてまるで呵責なきブローカーらの思うつぼであり、なによりもその問題にこそ絶望し、ベートーヴェン終焉の館にて拳銃自殺したワイニンゲル先達への申し訳が立たない。が、母親といえど年の頃はまだ二十代半ばほど。斯様な女が公衆の場で乳房を露出し(無論ポンチョによって隠れているが)、それこそたった一枚の薄い布切れの向こう側では今まさに乳首がお目見えしているという空間的事実。うら若き母親はポンチョの胸元をつまんで自らの乳を飲む赤ん坊の様子を窺い、向かいの二人はしゃぶっているところを見たいと興味本位に身を乗り出し、これが我らブローカー同志の特権とばかりテーブル越しに堂々とポンチョの中を覗いた(当然その際も、彼女らは自分らに便乗してしれっと覗いてくるフリーライダーが周囲にいないかを細目にて十分に確かめた)。
殊更に警戒してみせながら、なお「乳首」や「おっぱい」を聞こえよがしに連呼する浅ましきブローカー共を視界の端に、私は梃子でも顔を上げるまいと強引に手元の『性と性格』に集中せんと努めたけれども、女が動植物と同等の存在であることを大真面目に論ずるワイニンゲル先達の考察が俄然頼りなく思えてくると同時に、あの女らの眼球になりたい、あるいは原子レベルに小さくなってポンチョをすり抜けたいという如何ともしがたい妄念が突き上がってくるにつれ、儚くも手淫の効果が掻き消えてしまったことを自覚した。
女らは暫時授乳をテーマに話し合った。しかし―――カントが「女はその秘密を漏らさない」と言ったごとく、またニーチェが「女から女に関して何ごとも学ぶことは出来ない」と言ったごとく、つまりワイニンゲル先達の論に従えば「女の最も深い欲望、女が意味する一切、女の在るべきすべては、無精神かつ単に性的であるだけの彼女に拠って認識されることがない」となるが―――、そのどれもがあくまでも地上生活に根ざした内容(一日の授乳の回数や、必要な栄養素など)に終始しており、たとえば男にしゃぶられる時と赤ん坊にしゃぶられる時との違いといったような肝要の部分には一切触れられず、一見あけすけな様でいて結局はすべて上滑りに完結するブローカーらのそのどこまでも平板な現実性に、コーヒーはまだ半分ほど残っていたけれども、寄る辺なき自意識を引きずりその場を去る以外にやるせがなくなった。
席を立ち、女らの傍を通る際、若い母親は私に覗かれぬようポンチョの胸元を素早く片手で押さえた。会話は続けつつ、視線も私ではなく向かいの二人に向けたまま。このノールックによる徹底したディフェンス。一時、油断を見せていたのは確かだった。彼女はその少し前から乳をやりつつ何度かストローへ口を近づけようと試みており、しかし体勢的になかなか難しく、その試行のたびにポンチョの胸元に少しの隙間があいていた。事実、私はそのタイミングを見計らい席を立ったのだった。首尾よくいけば絶好の角度でそこを覗き込めたはずだった。なんせ私は背が高いのだ。
目論見を完全に見透かされ、あまつさえノールックという無下の仕打ちを喰らい、乳首との邂逅を期待した目は間抜けにも見開いたまま、私の顔面は瞬く間に膨れ上がった。取り返しのつかぬ愚行をしでかした羞恥により、たちどころに瓦解する自尊心。あらわになる誤魔化しようのない剥き出しの我。我といえど、それは意見のまるでそり合わぬ無職の肥った居候のごとき正体不明の黒い塊であり、ここぞとばかりにふてぶてしく質量を増してくる。放っておけば前頭葉あたりでインフレーションが生じ、なにか軽薄なパラレルワールドでも形成されかねない。そうなればもう統合性を保ったひとりの人間としては存在できなくなる。―――そう、かつて私は暗い暗い階段を下りた。しばらく下りたらドアがあり、開けるとまた階段が暗闇に伸びていた。どんどんと深く下りて行き、何枚目かのドアノブに手をかけたとき、不図ここを開けたら最後、もう二度とは戻って来られぬことを察した。
「行けば楽になる」と、黒い塊は言った。「もうだれへ気兼ねする必要はないし、生活のために働かなくてもよいし、自分の思うまま、なにをしても許され、好きなことだけをして生きていける」
暫時、私は暗いドアの前に立ちすくんだ。はたしてそこは狂人世界への入口であった。また、それは女体の魅惑なんぞとはまるで比較にならぬ、人生最大の誘惑であった。しかし私は踵を返した。なぜならば、近しい人たち(とりわけ母や無償の愛を注いでくれた祖父母)を裏切り、悲しませることになると思ったから。悄然と引き返す中、永遠と一瞬が同義であることを突然に理解したことを忘れない。宇宙と己とが完全に調和し、一体化したような恍惚が全身を貫いた。事実「なんだ、そういうことだったのか」とつぶやいた。つぶやいたといってもツイッターではない。だれからのアテンションも予期しない真実の独白である。あの法悦は、世間に迎合せず、正気を保ったままやせ我慢と孤独を貫いた者だけに贈られる最高のギフトだったと思っている。我が切なるねがいは、あの法悦をふたたび体験すること。そうして、できうることなら不断にそれを身に纏って生きること。創造主とやらは、人間のそうした殊勝な志を悉く握りつぶしにかかる。黒い塊は、大方自我に巣食ったその手先だろう。古今東西、偉大なる人物たちの自殺や発狂は、それ以上踏み込んでくるなという絶対者からの暗黙のメッセージの気がしてならない。己に似せて人間を作っておきながら相当にケツの穴の小さな奴と思われる。連戦連勝に胡坐をかいた、ふてぶてしき黒い塊。ただほくそ笑むだけのそれをせめて少しでも悔しがらせることができたなら、一度きりの我が人生に於いて、一片の悔いなしである。
とまれ、この刹那にひとりの男の中でこのようなスーパーノヴァ的苦悩が展開されていることなど、ブローカー共にはきっと想像もつかぬこと。むしろ彼女らにとってこうしたことは日常茶飯事であり、仮にここいらで女らのテーブルにコーヒーカップを叩きつけ「目的は乳首であって、おまえら介在になど微塵も用はないのだ」と訴えたとて、乳首の威を借る狐にはなにも響かぬだろう。まずは割れたコーヒーカップについて騒ぎ立て、衣服に飛び散ったコーヒーの染み、なによりもまず赤ん坊の安全確認、異常者の出現という一大イベント、すなわち満点の被害者意識を以てギャーギャーと喚き散らすのだろう。たかが地上生活の維持者、男を性的状態に留まらしめることを唯一の目的とした肉の奴隷どもに精神性を説いたとて馬の耳に念仏、まったくもっての無意味である。ビバ、ワイニンゲル先達。ただちに帰宅しなければならない。そう、ただちに帰宅しなければならない。床に散らばった自尊心はそのままに、私はそそくさとその場をあとにした。
絞め殺したように狭苦しい、うなぎの寝床のようなアパートの自室にて、帰宅するなりワイニンゲル先達の本をベッドに打っ遣り、ズボンとボクサーパンツを同時に下ろす。それらを膝に引っ掛けたまま床に跪き、すでに起立しているペニスを右手に握る。射出してしまえばこっちのものである。かつて弄んだ乳首を思い浮かべ、飽きもせず吸い続けたりひねったりしたことを回想しながら大急ぎでこする。
これは、私だけの乳首か。
そうよ、これはあなただけの乳首よ。
そうか、これは私だけしか見てはいけない乳首なのだな。
そうよ、これはあなただけしか見たらいけない乳首よ。
そうか、それでは一寸写真に収めさせてもらおうか。
いいえ、それはだめよ。ちょっとなら良いけれど。いいえ、やっぱりだめよ。ぜったいにだめ。
懐かしきブローカーとの戯れ。吐精してしまえば用はない。
はたして人間はうまく出来すぎている。私が創造主だかなんだかわからぬ存在を意識するのは、いつもこの丸めたティッシュをゴミ箱へ放り投げるときである。どうにも弄ばれている気がしてならない。あれだけ精神を参らせておきながら、物理的射出後におけるこの興味の失われ様といったら唐突であり、解決としてあまりにも粗略が過ぎている。もしも私が創造主だったならば、射出前の懊悩へもキチンと寄り添い、なにかしらの慰めと立つ瀬を与えるだろう。とまれ、もう乳首に用はない。なんだ、あんなものは。ただの肉片である。バッハの無伴奏チェロ組曲のCDをプレーヤーに挿し入れ、煙草に火を点ける。俗に賢者タイムと呼ばれるこのひととき(だれが名づけたか知らぬが、このネーミングセンスは秀逸である)。すなわち、真理への肉薄はこの限られた時間を如何に過ごすかにもかかっている。バッハもこの間をうまく利用して作曲をしたにちがいないのだ。重厚なるチェロの調べ。第一番プレリュード。ベッドに腰かけ、眼を瞑る。動物的運命には逆らえぬにせよ、芸術はそこへ爪痕を遺すことのできる唯一の術である。過去に戦いを挑み、悉く敗れてきた先人達の超人的な努力を鑑みれば、じぶん風情がその高みへ到達できるとは思わぬが、仮に死んでその魂がカテゴリー分けされるとするならば、レベルは如何にせよ〈抵抗者〉として振り分けられたらそれでよし。魂の行列を歩きながら、閻魔の傍を通るときには胸を張り、精一杯の哄笑を以て闊歩してみせる。『性と性格』を手に取り、パラフィン紙に包まれた表紙を指先で撫でる。
「すみません」
ベッド上とはいえ、さきほどぞんざいに放り投げてしまったことを声に出して詫びる。ワイニンゲル先達へはもちろん、書物という物自体への詫びでもある。大正十四年発行の四六判。いったいにこれまで何人の間を経巡ってきたのか、経年劣化は激しく、黄ばみや焼けたようなシミはもちろん、インクは掠れ(実に文字の消えてしまっている箇所もある)、紙は枯れ葉よろしく少し力を込めればパラパラと砕け散りそうなほど水気を失っている。私はこの真実の書を、森鴎外の小説にて知った。其処にはこう書かれてあった。
『恋愛の希望を前途に持っている君なんぞのためには、ワイニンゲルの論は残酷を極めているのです。女には恋愛というようなものはない。娼妓の型には色欲がある。母の型には繁殖の欲があるに過ぎない。恋愛の対象というものは、すべて男子の構成した幻影だというのです。それがワイニンゲルのためには非常に真面目な話で、当人が自殺したのも、その辺に根ざしているらしいのです』
当時私は、過去に遭った二度にわたる強姦被害を、常より沈鬱な(人間存在の哀しみを一身に背負ったような)面持ちで語り「もうあなた以外の男とのセックスは気持ち悪くて考えられない」などと言いながら、その実隠れて夜な夜な他の男と情交を結んでいた女と別れたばかりであり、果たしてこのあべこべの事案をどう呑み込むべきか頭を悩ませていた。マノン・レスコーを初めとする古今東西の“女”を描いた小説を手当り次第に読み漁り、どうにかその意を突き止めんと試みたけれども、知り得たのは斯様な女がとくに珍しくもなく、今となってはあべこべどころか小説の題材にすらならぬほどありふれているということであり、ではそのような莫連についての考察がどこまで為されているのかといえば甚だあやしく、つまりは“そういうもんだ”と了解するに甘んじている人類の怠慢に、じつにやりきれぬ日々だった。そんな最中、私にとりワイニンゲル先達との邂逅は、たとえばドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟(とりわけその大審問官の章)に於ける、所謂“ドストエフスキー体験”を遥かに凌ぐものだった。脳ミソがぐるぐると回転し、何度叫び出したい衝動に駆られたかわからない。「じゃあ、叫べばいいじゃん」とおっぱいパブ嬢は言ったけれども、そのような芝居じみた行為は性にあわぬし、仮に叫んだとて喉を詰まらせ発声をしくじれば歓喜そのものが台無しとなる。すなわち、ムンクに叫んでみろと言うも同じである。ほぼすべての頁の端を折り、あらゆる箇所に色分けした傍線が引いてある。単に読み返すだけでは飽き足らず、殊に重要と思われる部分はノート三冊分に書き写した。
あれから六年。ご多分に洩れず、私の月日にも関守はなかった。齢三十八、このところは顔面にばかり肉がつき、毛穴も開く一方である。薄暗に煙混じりの細長いため息を吐く―――坂口安吾は「孤独は人のふるさと、恋愛は人生の花」と書いた。この説に倣うなら、己はかれこれ六年間も里帰りをしていることになる。通常は三日も帰省すれば垂乳根とはすぐさま諍いになり、一刻も早く都会の巣穴へ戻りたくなる故、これは異常の事態である。室生犀星が「ふるさとは遠きにありて思ふもの」と詠ったのもこのためだ。が、ワイニンゲル先達の示す如く、恋愛の概念が女の裡になく、それが男の勝手に作り出した幻影であるならば、存在せぬ花を愛でる理由もない。ふるさとへは居られず花への情も喪ったとなれば、もう出家のほかに道はない気もするが、そうして俗世から離れたとて俗世は俗世のまま平然と存在し続けるわけだし(それが気になるし)、また当方の出家に至ったまでの苦悩など彼らに理解されるはずもなく(それに腹が立つし)、況してや単に変人扱いされるのもたまらんから(悲劇である)、煩に耐え、閑に耐え、サルトル的嘔気にも耐え、なんとか正気を保ちながら生活していく以外に道はない―――。
すっかり日が暮れてしまっている。本日、バーガーショップでコーヒー片手に有意義な時間を過ごせたならば、帰りしなに駅前のスーパーへ寄ってなにか美味しいお惣菜を購う予定だった。食に執着のない私にとり、スーパーのお惣菜はこの上ないご馳走である。各種唐揚げにポテトサラダ、焼き鳥、めんたいフランスパン、お好み焼き、ナポリタンに海鮮丼と無上の品揃え。その中からそのときのフィーリングに合うものを選び、己の胃袋満タンの量を購う。満腹になってしまえば、もう眠るまで食欲に気を取られずに済むからである。殊に貴重な休日とあっては、食にうつつを抜かすなどまるで飼い慣らされた畜生のそれと同じであるからして、夕刻一度にまとめて手早く済ます。さりとて楽しみであることには違いなく、お惣菜を卓袱台に並べ、いざ掻き込まんとする際には毎度悦びに箸を割る手が震える。残念ながら、乳首に翻弄されすごすごと帰宅してしまった今宵については、当座近くのコンビニなどで購うしかない。あの若い母親も家へ帰り、今頃は家族のために夕餉の支度をしている頃だろう。まさかじぶんの乳首が中年チョンガーの胃袋ひとつ分のスーパーの利益を減らし、コンビニを儲けさせようとは夢にも思うまい。乳首覗けばコンビニ儲かるこのバタフライ効果を、いったいにだれが注視し、認めてくれようか。それともそのような因果はなく、本日の私がスーパーではなくコンビニで食を購うことは予め定められし運命だったとでもいうのか。
煙草を揉み消し、スーパーへ行くことにする。駅前までの道のりは億劫だが仕方がない。もうお惣菜も粗方売れてしまっているだろう。しかし、これ以上乳首の影響下に甘んじ、夕餉のイニシアティブまで剥ぎ取られては敵わない。そもそもあの乳首はまったく覗けてもいないのだ。ちらつく黒い塊。なにかべつのことに気を取られている風を装いながら、チラチラといやらしくこちらの動向を窺っている。私は努めてなんでもない素振りをする。このスーパー行きの痩せ我慢を彼奴に悟られては癪である。なにかちょっとした想定外(たとえば喫茶店でカフェラテを頼んだらカフェオレが出てきたくらい)に捉えさせなければならない。すなわち、看過の可能な微細なエラーとして認識させ、その全知全能の傲りにチクリと不穏を突き刺す。そのため、ぼんやりと虚空の一点を見つめ、口を半開きにし、なにも考えちゃいないとわかる間抜け面を以てアパートを出る。果たしてこのタクティックスがどれほどの効果を生むかわからない。実はこうした密かな抵抗さえも彼奴らにとってはお見通しであり、すべてが織り込み済みの可能性もある。が、如何にせよ私は己の億劫に打ち克ち、すでに近くのコンビニではなく遠くのスーパーへと歩き出している。この作為的不可逆性こそが我がレゾンデートル、徒労に終わろうともこれが私の生きる道である。冷たい空気に強張る頬。最愛の休日が恋人の如き憂いを湛えて去って行く。
満員電車の人いきれ。とめどなき押し競。肩先の鍔迫り合い。捻じれる胴。置きどころを奪われた片足。鼻先をくすぐる目前のつむじ毛に思わず仰け反れば、背中に頑固な肘鉄がめり込む。もしも私がにきびなら、ブツリと弾けて根こそぎ膿を噴き出すだろう。結露のべっとりと貼りついた窓。捏ね回された生ぬるい人間の臭気。ときに耐え難き屁のような臭いも漂ってくる。私は常々「満員電車の中で屁をひる者がいる限り世界平和は訪れない」と言っているけども、思わず漏れひる他意なき屁というのもあるから、一先ず息を止め、口の端から断続的にヒッヒと細い息を吹いて臭気を紛らす。かにかくに、嫌と思えば途方もなく嫌になる。せり上がる不快は喉元に留め、目前のつむじ毛と向き合い凝然とす。土台、不快を表明したとてどこへ汲み取られるわけでもないのだ。見れば、女がどぶに嵌ったような苦悶の形相を浮かべている。なるほど、女は左右からの強かな圧迫により、両腕をだらりとクロスさせ、壁の割れ目から上半身だけ抜け出たごとく、前屈の体勢で身動きが取れなくなっている。形よくくっきりと描かれた眉、オレンジ色を帯びた明るめの口紅、しっかりとカールされた睫毛にはたっぷりとマスカラが塗られている。ファンデーションの馴染み具合から察するに、三十代半ば辺りと窺える。めっぽう顔色が悪い。キャメル色の厚手のコートは片方の襟が肩口まで捲れ上がり、そこへトートバッグの細い持ち手が祭りのたすきのように食い込んでいる。本来、乳首の庇護者たるところの女はもっと丁重に扱われ、尊ばれるべきである。斯様な存在がこのような憂き目に遭うのを見ると、なにやら情愛の念が湧くことしきりである。が、この同情こそが陥穽、すなわち命取りとなるわけである。ブローカーに心の取引は通用しない。女に感じるこうした切なさもまた我々男子の構成した幻影であり、乳首と女はどこまでも切り離して捉えなければならない。繋がっているが故に混同されがちだが、仮に乳首をチワワとするならば、女はブリーダーである。チワワが瞳を潤ませているからといって、なにもブリーダーごと慈しむ必要はない。みるみると青ざめていく女は視野の外に葬り、私は私のタスクである、鼻先をくすぐるつむじ毛と対峙する。寝癖混じりのそれは、弓なりかつ先端がフックの形に折れており、ともすれば私の鼻孔をかき回すから。鼻息でいくら吹き払おうにも雑草よろしく立ち直ってくる。先方は私のことをよほど鼻息の荒いやつと思ったか、頭皮にかかる鼻風を払い落とすみたく大袈裟に頭を振り、いかにも迷惑そうにゆっくりと首を捻って睨めつけてくる。一重瞼の三白眼である。下膨れの顔面は茹で餅のように白く、はみ出たジャムを連想させる唇がぐしゃりと重なっている。この相貌のタイプの男とは昔から相性が悪い。で、この種は往々にして頭髪が乏しい上に、毛色をライトブラウンに染めている。生理的に合わぬとはこのことをいうのだろう。ひとつには私の相貌がそれと正反対というのもあるかもしれない。私はぱっちりとした二重瞼であり、顔面は黒糖ふ菓子のようにガサガサと色黒く、あとはもうすべてが濃い。相貌が気にくわないのは先方にとっても同じであるらしく、私を一瞥すると、鼻に皺を寄せ、今度は後頭部を押し付けるようにわざと仰け反ってくる。危うく、私の高い鼻先がつむじ毛をかきわけ、先方の頭皮まで到達しそうになる。強い脂臭が鼻奥に突き刺さり、一寸目が回る。臭いからも徹底的に相容れぬなにかを感じる。ヤァ、ここで一発頭突きを喰らわせ、頭髪を掴んでブチブチと引き千切り、八往復ほどのビンタをお見舞いし、顔面に唾を吐きかけ、力の限り罵声を浴びせることができたならどんなにか胸がすくであろう。俄かに額や背中から脂汗が滲み出し、あらゆる毛穴からプツプツとじんましんのような痒みが生じる。目を瞑ってやり過ごそうとすればクラクラと意識が遠退き、堪えようとすれば嘔気が込み上げる。先方の私への苛立ちはまったくもってお門違いなのである。私は決して鼻息の荒い人間ではない。むしろ、平生の私は車内ではほぼ息を止めている方のデリケートな質であるからして、呼吸といっても、酸素の切れ端をほんの少しかじらせてもらうくらいの至極遠慮がちなものとして行っている。周囲との比率でいえば、事実人間とハムスターくらいの差があるであろう。つまり、いまの私の鼻息は、このいかんともしがたい男により、意に反して過剰に荒くさせられているのである。先方は腹を立てる前に、まず、なぜにこうまで己の後頭部に鼻息をかけられているのかを考えてみなければならない。直線的な満点の被害者意識を以て阿呆みたく頭を振るんではなく、吹きかけられている箇所を自ら触ってみるなどし、そうして己の寝癖が人様の鼻孔をかき回すほどひどいことに気付かなければならない。然すれば、私とてドントマインドといった風のふやけた微笑を浮かべて彼を許容するであろう。はっきりと申し上げて、この問題は彼の想像力の欠如に起因しているのである。彼が少しでも己を疑ってみることをすれば、この無駄な啀み合いも発生せず、互いに余計な不快を覚えずとも電車を降りられたのだ。ジョン・レノンがイマジンを歌ったのはこのためである。この下膨れの男も、無邪気な子供時分にはイマジンを合唱したことくらいあるはずだ(「いや、おれんとこはヘイ・ジュードだったよ」などというどうでもよい訂正は受けつけない)。いったいに彼はこの名曲をどう捉えているのか。きっと「いまじおーらっぴっぽー」とかいう、わけのわからぬ呪文くらいにしか思っていないのであろう。なぜならば、彼は大袈裟に仰け反り、私の顔面に後頭部を押し付けることをいつまでもやめないから。ジョンが言っても伝わらぬのだから、もう世界平和など望むべくもない。下膨れは、周囲に圧し流され立ち位置が変わっても、一度掴んだ吊り革を意地でも他に譲るまいと、短い腕を懸命に伸ばし、指先を輪っかに引っかけては利己的に安全を確保している。沈没船に於て、真っ先に救命ボートに飛び乗るのは彼のようなタイプであろう。肉づいた薬指には指輪がめり込んでいる。こんなさもしき男にも伴侶がいるのである。この世の不条理は、こうしたところにも現れている。そしてなによりも、そのぐしゃりと潰れた唇で吸いつかれる乳首を思えば気の毒で仕方がない。乳首はなんにも言わないけれど、私には乳首の気持ちがよくわかる。
凝縮すれば、強大な爆弾でも作れそうなほどのストレス・エネルギーを充満させた満員電車は、一触即発のテンションのままターミナル駅へ到着する。のろのろと完全に停止するまでの十数秒間、焦らされる乗客たちは不快は、トイレ到達直前の逼迫した便意のごとく限界に達し、ようやくドアが開くと、我先と押し合い圧し合い、巨大な溜め息の塊となって一気に吐き出されていく。下膨れも、やはり露骨に身を捩り、周囲に体当たりしながらせっせと独善的に降りていく。まるで背後を棄て去るように。彼の掴んでいた吊り革が揺れている。私は思う。なぜ私はかくも賢明なのかと。
ホームに降り立ち、お次はフン詰まりの改札へとなだれ込む、重くグルーミーな人波の渦と化す。一群は黙し、一様に俯いている。漫画ならば、顔は皆のっぺらぼうにされ、草臥れた暗い群衆としてぼんやりと描かれるところだろう。註釈として「満員電車が我が人生」などと揶揄い文句がつくかもしれない。自由人気取りの職業作家類には好きに表現していただいて構わないが、私が俯くのは単に悄げているからではないことだけははっきりと申し上げておきたい。ちょうど我らが蟻を見下ろすように、いま現在、もしも天上より何者かに人間世界がウォッチされているならばと想像し、観察される側として少々気恥ずかしさを覚えているのである。群衆に埋没しているときほど無力を感じるときはない。ただ、いつまでも選ばれずあることの不安と微かな期待、ふたつがここにあるだけである。先ほど車内で身悶えていた女が、一群から外れ、壁に向かって蹲っている。キャメル色のコートの裾が汚れた地面に擦れ、脇にトートバッグが無造作に転がっている。満員電車に慣れていないのか、それとも本日は元々具合が悪かったのか。単に気分が悪いだけでなく、よもや命に係る事態の可能性もあるから、行って無事を確認しなければならぬ気がするけども、ここは素通りを決め込む。先方の乳首を意識せず、無邪気に声をかけることが不可能だからである。ブローカーはどのような状況下に於いても、当方にそうした欲望が僅かでも潜んでいる限りそれを素早く読み取るから、近づいた途端に叫ばれ、痴漢に仕立て上げられぬとも限らない。となれば、実際にはなにもしておらぬとはいえ、後ろめたさのある以上、恥辱の炎に包まれた顔面を晒すことになり、それを見た群衆からは(あー、あいつは下衆な行いをしたのだな。残念な奴だ。)と後ろ指をさされるであろう。これではまるで思想犯、いや夢想犯である。すなわち、女は夢想警察とパラフレーズされてもよい。瓜田李下、君子危うきに近寄らずである。
こうして通勤戦線を抜け、会社へ着く頃には、もう一日の体力の大半を遣い果たしているといってもよい。つまるところ、サラリーマンの仕事の半分は通勤である。すぐには入らず、コンビニで購ったホットカフェラテを片手に、ビル陰にて一服する。これより、生活費用と引き換えに夕刻まで自由を売り渡す。すなわち、物理的世界の単なる反応薬と成り下がるまでのカウントダウン。一秒でも多く差し出しては癪だから、決められた時刻ちょうどに出社する。己を忘れ、己を誤解し、己を小さくし、狭くし、凡庸な人間としてとことん愛想よく振る舞いながら。なぜならば、そうした無私の姿勢が理性そのものとなり、いつしか己の能力のすべてとなって、ある日突然成熟し、予想されぬところから究極的に完成したものとして飛び出してくると、ニーチェが言っているからである。生活は、謂わば私にとり実存をかけた実験であり、ここが穀つぶしの標本たる自称芸術家や、自我を肥大させわけのわからぬ抽象画を描いてみせる美大生などとは一線を画するところである。
デスクにつけば、今日も向かいの席でヒロカズが虚空を見つめ、顔面を強張らせている。会社勤めが嫌でたまらぬという情念が、ボサボサ頭の脳天からポンポンと間欠泉よろしく噴き出している。
「おっす」私はヒロカズを極力刺激せぬよう声をかける。
「うぐ」ヒロカズが挨拶とも呻きともつかぬ声を出し、片手を上げる。
ヒロカズはパンクロックバンド『美酢魔流苦(ビスマルク)』のボーカルであり「己が人生の拠り所はライブハウスに在り」と決しているために、それ以外の味気なき日常を不倶戴天の敵のごとく考えているのである。生活のための仕事に、難しさなどなにもない。難しい仕事とは、耳たぶを削ぎ落してまで絵を描いたり、相対性理論を思いつくなど、精神性をフルに活かした取り組みのことをいうのであり、パンクロックは、どちらかと言えば難しい仕事の内に入るのだから、だれにでもできる生活仕事にマウントを取られている場合ではないと常々言い聞かせているのだが、彼はなかなかそれを受け入れない。ただ顔面を土気色にし、小刻みに震えながら凝然と耐えている。故に、隣席の持田という中年女に徹底的に馬鹿にされており、時に彼がエクセル作業などに手こずっていると、彼女は背伸びをするふりをして横目でヒロカズのデスクトップを覗き、関数を使わず電卓片手にいちいち手打ちでセルに数字を打ち込むのを確認してはほくそ笑んでいる。持田は末っ子で、猫好きで、地元好きであり、私が最も信頼に値せぬと思う人間の三条件をすべて満たしている。公務員の家庭に育ち、いまは引退した両親とともに実家で暮らしている。見た目はおおよそ一九七〇年代前半頃のオノ・ヨーコである。ナントカという年下の自称サウンドクリエイターと交際しており、思うに彼はただの無職のボンなのだが、彼女は彼が印税収入で暮らしていると信じ込んでいる。毎週金曜日は大荷物を抱えて出勤し、終わればいそいそと彼の元へ直行する。普段は四十がらみらしく目尻にカラスの足跡をつけ、ゴルゴンゾーラのごときくすんだ肌は直視できぬほどだが、月曜の朝だけは妙にハリツヤが良い。首から提げたイルカのネックレスは、先週彼とナイト水族館へ行った際に購入したものであり、本日身体から匂わせているのは、元アイドルのナントカという女がプロデュースしたナントカという、このところ売り切れ続出のボディミストである。巷ではアイドルから実業家へ華麗に転身などと持て囃され、持田は自分より遥かに歳下のこの女をアラーのごとく崇めているが、どうということはない、単にブローカーが店を構えただけの話である。とまれかくまれ、なぜにこうまで私が持田について詳しいのかというと、持田のツイッターを見ているからである。彼女のツイッターには、どういうわけか一万五千人ものフォロワーがいる。今朝のツイートは「ねむいにゃん(=^・^=)」だが、すでに百三十件のイイね!がついている。なにが良いのかダークマターの謎ほどわからない。いったいに一万五千人はこの干柿女の思想のどこに共鳴しているのか。昨今の写真加工の精度は凄まじいから、自撮りの持田が別人であることは確かである。年齢にもうまく触れぬようにしている。趣味は映画鑑賞と美術館巡りということになっているが、以前なにかの折にアッバス・キアロスタミについて話してみた際にはまるで知らなかったし、最も好きな画家がゴッホで「展覧会は欠かしたことがない」という割には弟テオとの書簡のことも知らぬし、是非とも読みたいというから渋々愛蔵のものを貸し出すと「ちょっと文字が多すぎる」という理由で翌日には返却された。しかし、ツイッターには広げた書簡集とバナナ豆乳ラテが、どこぞのカフェのカウンターから街の雑踏を背景にアップされており、ハッシュタグは#わたしの大切な時間♪であった。どういうことなのかきちんと説明してほしい。おそらく彼女にとっての映画とは、死んだ恋人がひょいひょいと蘇ってくるやつとか、異星人やゾンビがわけもわからず急に脅かしてくるやつとか、猫がかわいいやつとか、アニメを露骨に実写化したやつなどを指すのであり、芸術もちょっと高級な手仕事くらいにしか考えていないのであろう。持田は私がツイッターを見ていることを知らない。なぜならば、私は常日頃からSNSなど低俗千万と公言して憚らず、極度の否定派として知られているからである。しかし、ほんとうは私もやっている。主にワイニンゲル先達の言葉を抜粋してツイートしているのだが、フォロワーは登録した六年前と同じ八人のままである。そのうちの二人は母と叔母(母方)で、あとの六人は個人ではないなにかあやしげな広告のようなやつである。持田のツイートであれだけの反響があるのだから、当初はほんの少しエスプリを効かせて呟けば、軽く数万人にはフォローされるであろうと踏んでいた。一先ず十万人ほどフォロワーがついたところで「あのアカウント、実は私なのだよ」と公表し、持田の鼻を明かすつもりだった。あまりのアテンションのなさに、私のツイートだけなにかしらのエラーにより非公開になっているのではないかと疑い本社へ問い合わせなどもしてみたが、今のところ返答はない。ただ、母と叔母はほぼ必ずイイね!をしてくるし、ごく稀にではあるがハードフェミニストらしき者から悪鬼台詞のダイレクト・メールが送られてくる。ワイニンゲル先達も生前は黙殺され、いつの世も偽物が持て囃され本物は不遇なのだから、私はこの否認を甘んじて受けとめる所存である。
始業から一時間と経たずして、ヒロカズはすでに生気を失い、落ち窪んだ眼を三重にして、定まらぬ焦点とひとり格闘している。昨夜もどこかでライブをし、朝まで飲んでいたのだろう。持田が真っ赤に塗った口をへの字に曲げて、ヌイッと顎をしゃくり、私に変な合図を送ってくる。ヒロカズのことを言いたいらしいが、わからぬふりをする。するともう一度、今度は少しヒロカズの方に顎先を向けてヌイッとしゃくり、(ねえねえ、この人ったら月曜からこんなんでいったいどうしたもんかしらね?と言いたげな)同意を求める風の呆れ顔をする。その際に彼女の鼻の穴が黒々と膨らんだのにつと胸糞の悪さを覚えた私は「え、なに、ちゃんと言ってくれないとわからないんだけど、なに?」と、わざと大きめの声を出す。持田は、うわ馬鹿!という風にさっとそっぽを向き、そしてしばらくすると、再びモニターの陰から非難がましく私に顔面だけでなにかを伝えようとしてくるが、もう私は一切気づかぬふりをする。私と簡単にアイコンタクトを取れると思う方が間違っているのである。
ヒロカズがビクリと脇腹を小突かれたような動きをし、つと顔面を歪ませる。当初、私はこれを一種のチック症だと思っていた。しかし観察の結果、このところ漸く原因が判明した。持田のくしゃみである。持田はなんのつもりかすぐにくしゃみをするが、「クチュ」と雀が握り潰される瞬間のような声を出す。一般的にくしゃみは「ハクション」または「ヘクション」であり、「クチュ」とはやらない。これだけでも十分にくしゃみの体を成していないのだが、持田の場合は「クチュ」のあとに「にゃむ」と妙なオノマトペが追加される。すなわち、ヒロカズはこの「クチュ、にゃむ」をひどく嫌っており、彼の曲に「猫又のくさめ」というものがあるけども、これはまさしくこのことを唄ったものである。ほぼ絶叫しているために歌詞は聞き取れないが、声明としては「おまえのくしゃみ一回につき、おれの命が一秒縮まっている」といった風なことだと理解している。『美酢魔流苦(ビスマルク)』のライブへは、これまで何度か足を運んだ。終始目玉をギョロつかせ、涎を垂らし、時には全裸となってフロアへダイブし、そのまま客の上に立って力の限り「プロシア!」と咆哮するアナクロ感の強いものであるが、言うまでもなく、客に女の姿はほとんどない。たまに居ても、壁際につまらなそうに寄りかかり、へっぽこペニスなど露出されてもなんともありませんという、あの精一杯にすました顔をしている。私などはペニスのひょこひょことした不器用な揺れかたにとてもエロスを感じるから、毎度直視してよいものかどぎまぎする。それは、女の走るときの乳房の揺れかたに注目するのと似ている。本人の意思とは関係なく揺動することの、この如何ともし難きいやらしさ。人前で生殖器を露出することに抵抗はないのかと聞くと、ヒロカズは「そうでもないよ」と言い、続けて「おれは隠したいから出すんだ」と、折れた前歯を気まずそうに覗かせニンマリと笑う(前歯は、いつかのライブの際にフロアではなくあやまってドラムセットにダイブし、シンバルに激突して折れたとのことである)。本来、ヒロカズのようなアウトサイダーは、つまらぬ社会経済システムの歯車に組み込ませてはならない。その可能性を信じ、蜘蛛の糸をよじのぼるのを黙って見送るべきである(実際、彼の目には、何度それをよじのぼろうとしたかわからぬ奮闘の過去が見て取れる)。しかし、キリストでも磔にしてしまう凡庸人の桎梏は、黒い塊に通じたスパイ集団かのごとく、平然と徹底しているから遣る方ない。
たとえば、私の隣のデスクには小柴剛という男が座っている。既婚者で、四歳の娘がいる。このところ何十年ローンだかで郊外に家を買い、毎日二時間をかけて通勤してきては、得意げにキーボードを叩いている。とくにエンターキーを小指で弾く際には、息巻いたピアニストのラスト一音のごとき激しさで打ち叩くから、その振動により、都度私のデスクのモニターがぐらつく。持田の「クチュ」に苦しむヒロカズ同様、私もこの小柴剛のキーボードさばきには日々うんざりしているが、問題はそれよりもその無為にシャカリキな態度である。繰り返しとなるが、生活のための仕事に難しさなどなにもない。キーボードを強打することで、人類になにか相当な貢献でもしているつもりか知らぬが、はっきりと申し上げて、どれだけ小柴剛が張り切ってエンターキーを叩こうが、ブッダが寝そべっている方がすごいのである。そうした無邪気さだけならまだ良い。面倒なのは、小柴剛は以前長らくどこかの小劇団で役者をしていた過去があり、それをまるで万に一人とてない特異な経歴かのごとく誇りにしていることである。「いまは卒業してカタギになった俺だけど」との枕詞で、かつての自分がいかに“芸術分野”にコミットしていたかを語る。売れる要素のまるでないバンドを続けるヒロカズに対しては「一応、元芸能の世界に生きてた立場から言わせてもらうと、売れるか売れないかはまず運だね」と宣い、本当かウソか(どちらでも良いが)、名の知られた俳優から芸能界のあらゆる闇の話を聞いたと嘯く。本人曰く、それを知ったらとてもじゃないが“芸能”を続ける気にはなれなくなったらしく、四十を目前にきっぱりと引退し、いまは家族三人、普通であることの幸福を噛み締めているとのこと。何をかいわんやとはこのことだが、つまり、この男にはブッダもバッタも同じに見えているのである。もしくは、ヒロカズのような才能に恵まれず、結局は夫や父になる以外にはなにもなかった自分を認めたくないのである。蜘蛛の糸を断ち切るのは、主にこうした手合いである。
すでに昨日の休日が遥か昔のようである。あれこれと業務に取り組むうち、半ば諦めのような気分から徐々に我が遠退き、気づけば今週も社会と接続している。愉しさは微塵もないが、其の実ほっとする瞬間ではある。今週も、ニーチェからの宿題である「本来の任務とは無関係の任務に真剣に骨を折ってみること」が見込めるからである。もしも己を丸ごと抱えて此処に在るとなれば、数分ともたずして発狂するであろう。ヒロカズは大方常にそうした状態なのであり、その煩悶は計り知れない。しかし、サラリーマンなど恐れるに足らず、人間が溢れるほどいっぱいいて仕方がないから、なんとなくみんなで一緒に退屈を紛らすべく、いろいろな会社を作り、ぐるぐるぐると金銭を回し合っているだけである。たまたまA社と繋がりがあるだけで、B社とはないだけである。鹿爪らしくあれこれと送り合うメールは、単に繋がっていることの確認であり、印象良ければそのまま繋がるし、悪ければ他社と繋がる。これのどこに難しさがあるか。そこに誠実さのスパイスを少し加えれば、繋がりはより強固なものになり、なにも言わずとも突然C社から繋がりを求められたりもする。したがって、会社の利益を上げるなど造作無いことである。
そうして請負った業務は、すべてヒロカズと分担する。パンクロッカーは正直であり、なにをするにも誤魔化さないからである。たまにD社やE社とも繋がってしまい、作業が追いつかず一部を持田に頼むこともあるが、最終チェックは必ずヒロカズに託す。すると必ず彼女がおざなりに済ました箇所やミスが見つかる。事実、他社からの信頼は、そうしたヒロカズの力に拠るところが大きい。以前ヒロカズはアルバイトとしてたまにくるだけであったが、三年ほど前に彼をなんとか説得し、私が社長へ直談判して正社員になってもらったのである。しかし、いま目前で白目を剥き、ぐわんぐわんと船を漕ぐ彼を見ていると、引き込んでしまったことになんとも申し訳なさを覚えるのである。
「いやいやいや、月曜から草臥れすぎだろ」
案の定、小柴剛がヒロカズを見ながら半笑いで茶化し出す。
「だよね、ヤバいよね」
すかさず持田が反応する。なにもヤバくはないし、だよねとはなんだ。先ほど私にあしらわれたことへの当て擦りと取れなくもないが、その手には乗らない。突然「ぐはっ」と奇声を喉に詰まらせ、惚けて目を覚ますヒロカズを、二人は別のデスクの者も巻き込みケラケラと笑っている。絶望的につまらぬひとときである。しかし、ヒロカズを見れば平然としている。というよりも、ほぼ他人の話を聞いていない。彼は会社勤めとパンクロックを糞とカレーほど明確に区別しているのである。彼がまともに耳を傾けるのは、私の知る限りジョン・ライドンか町田町蔵のふたりのみである。その態度はたしかに潔い。翻って私は、なんとしてでも糞とカレーの混合だけは避けたく思っている。いずれも同じ意に取られがちだが、私の場合は糞を一切含ませないという点で異なっている。週に五日も糞に浸かっていれば、いくらカレーを頭上に持ち上げていても、油断すればその小片や飛沫が混入する可能性がある。少しの混入ならば、なるほど気づかぬかもしれぬ。ヒロカズにそうした鈍感さがあるのは確かである(現に、私はヒロカズが陰で「腰かけパンク」なんぞと揶揄されているのを知っている)。しかし、より高次な生を求む私にとり、斯様なエントロピーの増大は許されない。すなわち、私は糞にまみれながら、まっさらのカレーを食すのである。糞まみれなど、余程の変態でない限り地獄であり、いみじくも「地獄とは他人のことだ」と言ったのはサルトルである。
したがって、私は身近な持田や小柴剛をはじめ、生活仕事に係る人間すべての動向に、常に神経を尖らせている。私は持田が数時間で片づくような作業を三日がかりに引き延ばしていることを知っているし、となりのヒロカズが気づかぬのを良いことに、しかつめ顔でこそこそと牧場シミュレーションゲームに興じているのも知っている(そのスコアがユーザー内でレジェンドと称されるほどに高いことも)。また、キーボードを絶え間なく打ち叩く小柴剛が、実はだれも必要としていない無意味な資料を作り続けているのを知っている。これは、かつて役者をやりながらアルバイトとして来ていた時分、ハキハキと受け応えも良く、なにやらいつも自信たっぷりの様子を見せていたために、本人の社長へのたゆまぬ自己アピールの甲斐あって(どうもヒロカズが正社員になれたなら自分もなれると踏んだらしい)、役者をやめた際におめでたく正社員登用となったのだが、流石役者だったというべきか、瞬く間に中身が空洞であることが露呈し、あまつさえ、もうどこにも演出家はおらぬというのに日々役付けを待つような有様だったから、(皆がこの遅ればせのルーキー社員をどう扱ってよいものかわからずしばらく放置していたところ)見るに見兼ねた社長が直々に「職業訓練」をオファーしたのである。すでに存在する資料と同じものを最初から作り直すという、会社にはまったく無益な作業だが、本人は社長直々ということで、主演舞台が決まったかのごとく雀躍と取り組んでいる。そうして出来上がった資料の表紙には、必ず「作成者・小柴剛」と記し「ほんとうはⒸにしたいとこだけどね」と、満足そうに煙草に火をつける。
私は想像する。小柴剛の片道二時間の通勤を。私は想像する。帰宅して妻と娘に迎えられる姿を。そこは、小さな庭付きの一戸建て。キッチンは狭いが機能的。無理して買った新型の冷蔵庫。正社員となった夫のために、妻はいつでもビールを冷やしている。「以前は発泡酒だったけどね」が、晩酌時のお決まりの台詞。股座に纏わりつく娘(名前は夢と書いてウタ、呼び名はウー)。本日の保育園での出来事を脈絡なく話し出す。垂れ流しのアニメ映画。娘は時折話すことを突然やめ、テレビ画面に全意識を集中させる。片手にそれとは関係のない玩具を持ったまま。
「ウー、好きな男の子がいるんだよね」と母からの余計なアシスト。
「なんだって!」と大袈裟に驚く父。
すでに聞こえぬふりを覚えている娘。
「芸能関係の彼氏だけはやめてくれよ」と笑いながら父。
「とくに役者志望ね!」とふざけて母。
「いやいやいや、それをいうならバンドマンだろ」ややムッとして父。
俄然、両親の話すことに興味を持ち始める娘。それはどういう意味かとしつこく食い下がる。
私は想像する。娘を寝かしつけ「この寝顔を見れば、疲れもストレスも吹き飛ぶね」と、開闢以来億万人の父親が言い古した台詞を恥ずかし気もなく妻にささやく夫を。
「会社はどう?」
「うん、社長に直接資料作成を頼まれたりしてるね」
「社長さんから直接?」
「だね」
「期待されてるってことだよそれ!」
「だね」
私は想像する。夫が妻の胸元に手を滑り込ますのを。私は想像する。妻の乳首を。役者という夢を諦め、夢(ウタ)のために家庭人となることを決めさせた乳首はどんな塩梅か。さぞかし夜空に向かってピンコ勃ちを決め込んでいることだろう。妻は思わずアハンと声を漏らす。夫は娘の起きぬことを確認し、口唇を尖らせチューチューとしゃぶりつく。そこは、小さな庭付きの一戸建て。寝室は風水に従ってどっちか向き。奮発して買ったクイーンサイズのベッド。三人はいつも川の字で眠る。私は想像する。第二級の恒星である太陽、これもいつかは寿命が尽きることを。私は想像する。然すれば第三惑星の我らが地球も光をうしない、単なる土塊と化すことを。
そこは小柴のローンのお家でせうか
そこに小柴の立ってゐる
そこに妻子の笑ってゐる
そこは小柴のローンのお家でせうか
いいえ、昨日はどこにもありません
そこに小柴の立ってゐた
そこに妻子の笑ってゐた
昨日はどこにもありません
と、三好達治を捩ってみても如何にもならない。こうした無意味な想像は己の毒にしかならぬから、かぶりを振って業務に戻ろうとしたところ、オフィス電話が鳴る。いつもの如く、ワンコールの刹那に私は視野全体でぐるりを確認する。まずは持田が反応し、続いてヒロカズも意識を取り戻し、緩慢ながら電話機に手を伸ばす。両者からは取ろうとする意思が窺える。しかし、小柴剛はキーボードを叩く手を止めず、その方を見もしない。実際に取るのは、それらを確認し終えても時間の余るせっかちな私である。快活に応対し、そして、相手が切るのを待ってそっと受話器を置く。
「いやいやいや、テレクラかよ」
小柴剛が入社したての頃、私の電話の取り方を見て彼はそう言った。
「マァ、電話取り競争みたいで見てておもろいけどね」
爾来、私はこの男とはまともに口を利くことをやめた。彼の方でももう自分は電話を取らずに済むものと思っている。地獄に気狂いである。今週も糞の波がざぶりと押し寄せてくる。私は股を開いて大きく踏ん張り、嘔気を堪え、カレーを頭上高く掲げる。
さて、あなたは不穏を覚えてきた頃かと思う。この『乳首が見たい』と題した独白が、このまま読み進めるに値するか否かの判断に揺れているのではあるまいか。かくいう私も詰まらなくなってきた。わかっている。此処らで、独善的な私を圧倒的に否定する展開があれば良いのだろう。あるいは、もっと私に間抜けな振舞いをさせれば良いのだろう。然すれば、この独白もある種キュートなものになり、書いても楽しく、読み手にも安心を与えられるに違いない。しかし、そうしたことを起こす予定はない。何故ならば、私は正しいのである。どう転んでみせたとて、結果的に私が正しくなってしまうのである。むしろ、私は己の正しさについてこそ辟易しているのであって、この先も私はその証明に終始するであろう。つまり、一般的な一人称の独白としてはすでに退屈な結果が見えてきたわけである。しかし、わざわざ道化を演じ、間抜けな己を強引に創造し、読み手を一時的な優越に浸らせたとてなんになる。このあと、シーンは正午となり、私は昼食をとりにいくが、お望みならばそこに突如として地球外生命体を登場させてもよい。大地震を起こしてみてもよいし、可愛い猫を抱いてファンタージエンへ飛んで行ってもよい。しかし、アドラーの言ったごとく「すべての問題は人間関係に通ずる」のであり、なにか派手な事件が起きたところで、物事の結局は素朴な人間関係に収斂されるのである。宇宙の果てまでの壮大な旅をしながら、最終的に乗組員同士の人間関係に悩んで帰ってくるならば、わざわざ宇宙へ旅立つなど時間の浪費であり、ならば近所の煙草屋へ行くだけで十分だ。以上を踏まえ、私は以下を書き進める。含羞を滅却し、地球の平和に一縷の望みをかけて。
正午。小柴剛はこれ見よがしに愛妻弁当を広げ、持田はタブレット端末を片手にピンク色をした棒状の謎の物体をかじり出す。ヒロカズはデスクに突っ伏しているが、これは今日に限らずいつものことであり、彼は会食恐怖症なのである。彼の曲に「暴食一代男」というものがあるけれども、これは人知れずビル陰で菓子パンを胃袋に詰め込む己の姿を自虐的に唄ったものである。かくいう私は、中原中也がその「正午」で表したごとく、オフィスビルの真っ黒い小ッちゃな出口から、ぞろぞろぞろと、月給取としてぶらりぶらりと手を振りながら外へ出る。
今日も今日とて、其処彼処の店に行列ができている。私には、並んでまでものを喰らわんとする者らの気が知れない。すぐに入れる店は他にいくらでもあるのに(店内でなくても、弁当ならば其処ら中に積み上がっている)、どうせ糞として捻り出すものを、摂取時にわざわざ人気店にて取り繕わんとするそのマインドには甚だ嫌悪を催す。なにやら男も女も澄まし顔で並んでいるけども、私からすれば、列をなす彼らの口はもう肛門である。肛門が口々に、否、門々に「我々一同はこれから此処の店のものを喰い、それを糞に変えてみせます」と臆面もなく宣言しているも同じである。二人組の若い女がいて、ひとりは洒落っ気のない黒いダウンジャンバーで着膨れているが、もうひとりはピンク色のニットセーターだけであり、乳首を摘んでブンブンと揺らし甲斐のありそうな胸がこんもりと盛り上がっている。同僚らしきうしろの男二人が、女たちに被さるようにして親しげに話しかけている。ニットの女の方は前を向いたまま、両手を袖の中に入れていかにも寒そうに(且つ、可愛らしげに)足踏みをし、主に着膨れた方が振り返って男たちの相手をしている。男は二人とも細身のジャケットを着てカッコつけている。ただし、ひとりはちょっと禿げかかっている。彼処でニットの女がヒロインなのは一目瞭然である。なんでもよいが、とりあえず四人とも肛門が丸出しである。たしかにAVなどを見ても肛門にはモザイク処理が施されていないことが多いから、私が思うほど世間では肛門に対する羞らいが薄いのかもしれない。しかし、ヒロインまでが公衆に肛門をさらすというのは、いくら恋愛が幻想とはいえ、源氏物語からシェイクスピアから過去の偉人たちの大仕事をすべて台無しとする身勝手極まる所業であり、畢竟、乳首隠して菊門隠さぬ彼らは、我利我利根性の染みついた浅ましき餓鬼も同然である。この観点からすれば、ヒロカズの会食恐怖も至極真っ当な反応として腑に落ちる。ヒロカズは、喰らうことが排泄と同義であることを人よりも強く意識してしまっているのである。したがって、人間の区分けの男女に次ぐ下位分類は、列に並ぶか並ばぬかで決定されてもよいだろう(食に限らず、そもそも並んででもモノを入手せんとする執着そのものがさもしい。仮にワイニンゲル先達が現世に甦り、サイン会を開いたとしても、一人でも並ぶのであれば私は行かない。握手券付きでもだ)。いつか私はこの分類を表にまとめたく思っている。
とまれ、並ばぬ私は、いつものカレー店に入る。本場のインド人らしき者がやっているこの店は、テイクアウトの客が外に並ぶことはあっても、中にはだれも座っていない。理由ははっきりとしており、店内に強めの下水臭が充満しているのである。持田に言わせれば公園の公衆トイレレベルであり、たしかにどうしてこうまで臭うのか、配管が壊れているとしか思えぬが、インド人らしきは気にしていない風であるし、実際に入ってしまえば数分も経たぬうちに慣れてくる。人間の嗅覚はうまいことできているのである。そう持田に言えば、真っ赤に塗りたくった口を丸々と開けてとても信じられないという顔をする。持田は以前入った折にはすぐさま嘔気を催し、そのまま店を出たとのことで、以後はテイクアウトでもあの店のものを食す気になれないと言うが、彼女のごときは昨今の潔癖無臭文化に毒されているのである。己ははらわたに糞をさんざ溜めておきながら、臭いも糞もない。そして、いったいにブローカー風情は尾籠話に耳を塞ぎたがるけども、なにも私は好んで糞話をしているのではない。メメント・クソ、すなわち糞を忘れるなと言っているのである。とまれかくまれ、奥の四人用テーブルに一人で広々と腰かけ、日替わりカレーとナンを注文する。インド人らしきは、これにいつもプレーンラッシーのサービスをつけてくれる。あまり好きではないが、有難く頂戴する。
と、ポケットで端末が振動し、見ると安椰夏からメッセージが届いている。
「はろはろー!今日よかったら会いたいニャー♡ムチュムチュポーン!」
一旦、端末をポケットにしまい、煙草に火をつける。世の中は意外と軽薄に回っている。想像以上に場当たり的であり、想像以上に不真面目である。「人間は、物理的世界の偶然的事象の奴隷である」とサルトルの言ったように、奴隷は奴隷としての調和を乱さぬこともひとつ忘れてはならないことである。
「ムチュムチュポーン!」
安椰夏に返信する。すぐにウサギが飛び跳ねて喜ぶモーションイラストが返ってくる。
裡に秘めたかったるさは誰よりも負けぬ自信がある。が、それを表明したとてだれが慰めてくれるわけでもない。したがって、オフィスへは元気よく戻る。それでなくても、皆が胃袋にものを詰め込み、部屋全体が重くなったように感じられる。社長なんぞは、私のことを単純明快な男として認識しているだろう。小さな会社であるから、社長とは常に顔を合わせている。私が「ただいま戻ってまいりました!」と潑剌に言えば、やれやれ能天気な奴だといった風な顔をして、それでも嬉しそうに、太鼓腹の上で難しげに組む腕をひょいと片方挙げる。他の者はすでにデスクについて業務を開始しているが、私はすぐには向かわない。まずは時間をかけてコーヒーをドリップする。そうして応接セットに腰掛け、のんびりと食後の一服をする。私の売上成績はナンバーワンであるからして、せめてこれくらいの安らぎは得られて当然なのである。小柴剛などは、まるで昼休みなどなかったかのようにキーボードをけたたましく打ち叩いているが、あれはあれで私と同等に張り合っているつもりなのだから世話がない。
ところで、遠目にヒロカズを見遣れば、午前と変わらずやはり半死半生の様相を呈している。いよいよもう限界なのかもしれぬ。しばらく観察していると、となりの持田が自分が見られていると勘違いしてチラチラとこちらを意識し、あまつさえタンバリンを片手に奇声を発する直前のオノ・ヨーコのような顔をして振り向いたので、小蝿を払う仕草で否定し、打ち合わせと称してヒロカズを呼ぶ。
「今日はまた随分とだるそうだな」
「うむ」
「ちょっとはなにか食った方がいいんじゃないか」
「いや、いま食ったら吐いちまう」
「昨日もけっこう飲んだな」
「うむ、やっちまった」
「今週はそんなに忙しくないから、まぁなんとか気楽にいこう」
「うむ、すまねぇ」
そう言って煙草に火をつけるヒロカズは、泣き笑いのような顔をしている。これまで、ヒロカズは何度か退社しようとした。その都度、私は芸術と生活の両立など到底不可能なのだから、極力生活に煩わされないための会社勤めだと思い留まらせてきた。つまり、生活はとかく生きることの邪魔をする。生活には宇宙の真理もなにも関係ない。ただ地上にべったりと貼りつき、いかれたロボットのごとくどこまでも執拗に纏わりついてくる。心も通じぬからなにを訴えても無駄であり、古今東西の芸術家たちもこの桎梏には悉く翼をへし折られてきた。生活がなければ、人類はもっと飛躍していたに違いない。私は、生活にストーカー規制法が適用されることを強く望んでいる。故に、最も近づきたくない場所は役所であり、私は彼処へ行かなければならぬ用事ができると三ヶ月前から毎日憂鬱になる。一週間前には頭痛が始まり、三日前からは下痢が止まらない。前日は一睡もできず、いざ当日となると凄まじい嘔気に見舞われ、それでも行かなければいつまでもいつまでもいらぬ手紙を送りつけてくるから、どうにか気力を振り絞り出向いていく。そうして建物に入った瞬間には脂汗が噴き出し、じんましんにより顔面を凸凹に腫らしながら息も絶え絶え各課を回る。一秒でも早く立ち去りたいから、なにを言われても食い気味に御意と答え、いろいろと渡される紙はそのまま急いでバッグの中へ捻じ込む。どうして好きに生きさせてくれないのかと、毎度涙の出る思いがする。そして、この思いを極力せずに済む方法が、心ならずも会社員である。会社員になってしまえば、こうした苦行のような生活手続きは知らぬうちに会社がすべてやってくれる。平日五日を取られはするが、そこさえ凌げば生活は驚くほど大人しくなる。ヒロカズは、辞めて気楽なアルバイトに戻り、ぎりぎりの費用を稼いで己の時間を増やしたいのだろうが、生活は特にそうした者を標的とするため(交通違反の取り締まりにおいて原付バイクがターゲットにされやすいのと同じく)、結局はあらゆる支払いに追い立てられ、アルバイトにばかり精を出す羽目となりかねない。フリーターは、実のところまったくフリーではないのである(ここで言うフリーとは精神の自由のことを指すのであって、生活と苦もなく手を繋ぎ、嬉々として立ち回る自由を履き違えた我利我利のフリーランサーとは似て非なるものである)。つまり私の言いたいことは、生活に面従腹背せよということであり、とりあえず見せかけだけでも会社員という隠れ蓑を纏っておけばその監視からは免れられるのだから、終業後もしくは土日を遣って、何も気にすることなく、存分に己の本来の仕事に励むのが賢明且つ最善だろうということである。
二本目の煙草に手をつけてよいものか躊躇うヒロカズに、まだ休んでも構わぬことを伝えるべく、私が先に火をつける。―――とは言え、ヒロカズのことはりんごの気持ちほどよくわかる。小柴剛や持田のように、社会がオーダーメイドのごとくしっくりと身につく者ならいざ知らず、ヒロカズにとってのそれは、体格の良い小学生が穿く半ズボンよろしくつんつるてんである。そして、これが当人には見かけ以上に深刻なのである。もしも私が王であったなら、ヒロカズへは毎日が夏休みの特権を与える。無論、国民の義務とやらについてはすべて免除である。とにかく日々を好き勝手に過ごしてもらう。生活費は持田や小柴剛からたっぷりと徴収した税金から支給すればよい。最初の三日間はぐうたらと寝てばかりかもしれない。否、一週間はそうかもしれない。仮に一ヶ月間や一年間そうだったとしても、周囲は社会的ジレンマを乗り越え、黙ってその堕落を見守らなければならない。芸術家が往々にして堕落の先に光を見出すことくらい、庶民はいい加減に理解しなければならない。酒浸りとなっても仕方がない。桃色に狂っても仕方がない。あやしげな薬に手を出したとしても、遺憾だがやむを得ない。挙句なにも達成することなく死んでしまっても、それはそれとして手厚く弔う。だって、彼は人類の大いなる希望に殉じたのだから。人間が性的以上の存在たりうるか、奴隷から抜け出せるか、我々は彼の精神性に一縷の望みをかけたのである。彼が駄目なら次の可能性のある男に託す。とりもなおさず、下手な鉄砲数撃ちゃ当たるの詮術である。宝くじも買わなければ当たらぬように。ただし、罷り間違っても小柴剛のような男を選出してはいけない。こうした者に斯様な特権を与えると、姑息にも己の家庭の運営だけに邁進するに決まっている。太宰の示した如く、家庭の幸福は諸悪の根源なのである。
「おいおいおい、君らちょいと休みすぎじゃないのかい」
噂をすれば、小柴剛がマグカップを片手にやってくる。にやにやと薄笑いを浮かべながら、ちゃっかり御相伴にあずからんとするその魂胆がたまらぬ不愉快である。
「打ち合わせだ」
「いやいやいや、煙草吸ってサボってるだけだね。でもわかる。そういうのって、けっこう大事だよーん」
みなまで言うなという風に人差し指を立て、恰も自分が一枚上手であるかのような顔をしてヒロカズの隣にどっかと腰かけ、己も胸ポケットから煙草を取り出す。小柴剛のマグカップには娘の写真がプリントされている。ある日揚々とバッグから取り出した際には我が目を疑った。我が目を疑うなど、生きていてそうそうあることではない。小柴剛が煙草に火をつけたタイミングで、ヒロカズを促して席を立つ。
「あれ、打ち合わせ終わっちゃう感じ?」
「終わった」
「なんか手伝えることあったら言って。おれには遠慮しなくていいから。だってほら、おれって社員としては一応後輩じゃん?いまならちょっとだけ、手空いてるよん」
私は小柴剛の白けたジャック・オー・ランタンのような顔面をどうしても直視することができない。そして、なにか言おうにも、相対すると失語症のごとく言葉が出なくなる。なにをどう伝えようと、彼はきっと頓珍漢に解釈するだろうし、下手に言葉を発すると、己を大いに誤解せられる危険がある。つまり、田舎育ちの私は些かお人好しではあるけれども、話せばわかるというようなナイーブさはもう疾うに持ち合わせていないということである。ただ、デスクに戻りしな、なんとはなしに振り返れば、ひとり応接セットに残った小柴剛の背中がいくらか寂しそうに見えなくもない。あれはあれで彼なりに当方と関係を築こうとしているつもりなのだろうと思えば、にべもなく席を立ったことにやや後ろめたさを覚える。では、こうした惻隠の情に従い、親しく歩み寄る義務が私にあるのかといえば、たぶんない。会社での立場や人間関係がどうあれ、彼はきっとこれからもしゃあしゃあと生きていく。所詮、ビールを飲んで娘の寝顔さえ見られたら、その日のことはぜんぶ忘れ去るのだろうから。そうして人生のすべては小さな家庭の中に収斂されていくのだろうから。関係すべき人間は、たとえば異星人が突然地球を襲って来た場合に、すぐに立ち向かう心構えができているか否かである。小柴剛は一旦マイホームへと帰り、妻と娘の安全の確保に励まんとするに決まっている。そうに決まっている。おおよそ交通は麻痺しているというのにご苦労なことである。これは地元好きの持田にも言えることである。地元好きを公言する者はどういうつもりか年中祭りばかりやっているけども、それはともかくとして、その排他精神といったら取り付く島がない。彼らもまた地元を守るためだけに集合し、粗野に立ち上がるのだろう。男はふんどし一丁、女は後方にて握り飯、血気盛んでなによりだが、たまたま地元への襲撃がなかったらどうするつもりか。地酒で乾杯して解散か。地産地消だから、きっとそうに決まっている。異星人が攻めてきたなら、守るべきは我らが宇宙船地球号である。国籍も人種もおのが村も関係なく、乗組員としてなにがなんでも直ちに立ち向かうのである。私には、小柴剛や持田がせっせと家路を辿る間に、ヒロカズが徒手空拳でエイリアンに猪突していく姿が目に浮かぶ。パンクロック精神とはそういうものである。わけのわからぬビームで一瞬にして丸焦げにされたとしても、これを犬死と笑うことなかれ。では、お前はどうなんだと問われたら、むろん私もヒロカズ同様直ちに突撃する所存だが、その前にヒロカズの勇姿を写真に撮り、SNSに拡散希望をアップしてから出撃させて頂きたい。こうしたアンサング・ヒーローは、戦場カメラマン同様第三者がフォローし、伝えなければならないのである。さういうものに私はなりたい。ちなみに、家族(地元)も地球も両方救えるようにやればいいじゃんという戯言は、ハリウッド映画の影響を受け過ぎているので論外である。それは、ゴッホが画家をやりながらウォール街でバリバリと働くというくらいあり得ぬことである。
昼下がり。ヒロカズは漸く宿酔が抜けたような顔をしている。小柴剛はトリップしたボンゴ奏者のごとく一心不乱にキーボードを叩き、持田は向こうで別部署の女となにやら愉しそうに立ち話をしている。社長はといえば、やはり太鼓腹の上で腕を組み、ぐぅぐぅと昼寝をしている。窓の外は冬日和。瓶覗の空が、沈殿したビル群の上澄みのごとく冴え渡っている。つまるところ、サラリーマンの仕事の半分は、ただ居るだけである。なにやら胸の詰まるような焦燥が込み上げるのは、こうした場当たり的な午後のひとときである。他人との関係に気を取られ、物事に筋道をつける頭の働きが鈍り、現在だけに意識が限定されている。シモーヌ・ヴェイユが『労働と人生についての考察』の中で「考えないために給料が支払われている」と述べた通りである。私は此処にいる。此のオフィス街の片隅に佇んでいる。二十代に試みた様々な自己表現の蹉跌の末、生活への無駄な抵抗をやめ、則天去私とまではいかないが、四の五の言わずこうして歯車に組み込まれて早六年。私はまだあきらめていない。能動的道草、即ち、無私へ己を溶かし込む絶対矛盾的自己同一の実践。これで駄目なら観念の、自己実現最後の試みである。未だ天啓の兆候なし。かの宮沢賢治でさえ「いまにどこからかじぶんを所謂社会の高みへ引き上げに来るものがあるやうに思ひ」ながら死んでいったというから、ときに我が人生もこのままおそろしくへっぽこにフィニッシュしてしまうのではないかとの不安が頭を擡げるが、それでも運命は私に好意的なのだと信じている。否、せめて信じていなければ、ただ行屎走尿にまつろうのみでは侘しくって仕方がない。実のところ、だれかが自殺したというニュースを聞くたびに、私は第一に羨望を覚えるのである。モームが「人生が苦悩と不幸以外に何も与えないとき、自分の意志で自分の命を絶つ人を私は是認するのみである」と言ったのを、私も是認するのみである。
持田が別部署の女と話しながら戻ってくる。そうして、ふと私を見るなりギョッとした顔をする。
「え、顔色悪いよ、大丈夫?」
「ほんとだ、大丈夫ですか?」
鮫島という別部署の女もそう言って気遣わしげに覗き込んでくる。わざわざ二人がそうして言うことで、俄かに周囲の視線が私に集まる。たとえば気分が悪くなりトイレで嘔吐などをしている際、外からドンドンとドアを叩かれ「大丈夫ですか」と言われると邪魔臭くて仕方がないように、間に合わせの同情など一切いらないのである。大体、私の顔色はいつも悪いのである。そして、こちとらの秘めた懊悩などおまえらニョショウに理解できる次元のものではないのである。ワイニンゲル先達が「女は隣人の悲哀を沈黙を以て尊敬することをしない」と言った通りである。
「ダイジョブです」
軽く手を挙げて答える。が、素っ気なく「大丈夫だ」と言おうとしたところ、我にもなく一瞬怯み、カタコトの丁寧語になってしまったのは、ちょうど視線を上げたところに思いがけず鮫島の胸の膨らみがあったからである。この女は痩せてるくせにボインであり、アイドル顔負けのルックスをしている。学生時分から交際していたラグビー選手と二十代半ばで結婚し出産したまでは良かったが、その後なにやら夫の借金と浮気が発覚したとかで、子供を実家に預け、離婚を視野に仕方なく働き出したという。いつかそれを部署の飲み会で涙ながらに語っていたらしいけども、この手の女は、大学を出て一旦は世間体のために就職こそするものの、二、三年経ったところでとりあえず鬱病的なものを発症してみせ、散々乳首を舐めさせたステディをそそのかし寿退社、せかせかと三十までに子どもを二人くらい産み、無職の中でも唯一社会的に承認される誰某のお母さんという資格を得、あとは授業参観に命をかけんとする、ブローカーの中でも最も王道且つ低俗な種であるからして、泣かれたところで、ぜんぶ計算ずくとはいかずに残念でしたねと言うよりほかはない。ただひとつ、この女の乳首の塩梅を知る借金夫についてはべらぼうに羨ましい。その具合を教えてくれるなら、いくらか返済に協力してやったって構わない。巨乳を支えるためか肩幅のやや広いところから類推するに、乳輪はちょっと大きめのような気がする。どうにかしてその面積だけでも知る術はなかろうか。メモ紙に転がった鉛筆でさっと丸を描くくらいの簡単な示し方で構わない。恥ずかしければ半径の数字だけでも良い。あとは円周率を以て私の方で計算する。俯き、それ以上なにも言わぬ私を見て取ると、持田が「じゃ、そういうことで」と鮫島に向かって胸元でちょこちょこと手を振り、彼女が行きかけたところ「あ、伊香保もいいかも!」と付け加える。鮫島はオッケーの指サインをして戻っていく。そうして口元に笑みを残しながら席につく持田を、私は虚目にも見逃さない。
「なになになに、どっか行くの?」
すかさず小柴剛がパンパカとキーボードを叩きながら尋ねる。
「うん、温泉行きたいねーって話になって」
「へぇ、いいじゃん。いつ?」タンッと弾かれるエンターキー。
「たぶん、来週の土日かな」
私は努めて会話を聞いていないふりをする。なぜならば、いま私の内部には、温泉に行くならば、持田に鮫島の乳首の塩梅を確認してきてもらいたいとのデザイアが熾烈に込み上げているからである。否、はっきりと申し上げて、そういうことならば持田の乳首の塩梅も合わせて知りたい。来週の土日、持田と鮫島は冬の湯煙の中、互いの乳首を確認し合うのである。否、実際は脱衣所で脱ぐ瞬間にはもう確認できているのである。持田と鮫島はどちらが先にブラジャーを外すのか。持田にしてみても、同性とはいえアイドル顔負けの鮫島の乳首の具合が気になるところに違いない。景色だ湯感触だとなんやかんや定型のつまらぬ感想を述べ合いつつ、鮫島の裸体を隙あらば観察する持田の冷ややかな目つきが浮かぶ。鮫島は鮫島でオールドミスの裸体をある種の好奇心を以て観察するであろう。そうして互いの裸体をしっかりと確認し、しかし次にはもうなにも見なかったことにして、温泉浴衣を着てめちゃくちゃな画像加工で記念写真を撮り、ありふれた舟盛りに大袈裟に感動しながら、ただ只管に皮相の会話に終始するのだろう。私は其方の温泉宿の湯になりたい。掛け流しだって構わない。直ちに排水溝へ流される運命だとしても、須臾、乳首のまわりをゆらゆらと揺蕩い(あわよくば撫ぜながら)、そうしてアーレ―と排水されるのであれば本望である。
俄に持田へ対しての気後れが生じている。不本意ながら、彼女の乳首を渇望してしまったからである。いつか観た映画『北北西に進路を取れ』では「女の前で緊張するのは、欲望を隠そうとするからだ」という台詞があった。若かった当時は、ザッツライトと目から鱗のように思ったものだが、女への幻想を打ち遣った今では、もう隠すというよりはあえて現してみることすら癪なのであり、仮にここで「ヤァ、持田。温泉へ行くのかい。そうしたら、鮫島の乳首の具合を確かめて報告してくれまいか。ついでに君の乳首の塩梅も教えとくれ。色、形、大きさをおおよそでもお伝え頂ければ、あとはこちらでなんとかするよ」と言ってみたならば、たしかに開き直ったことでこちらの緊張は解れるけども、その際に持田の中に生じるであろう想念が鬱陶しいのであって、キモイ、ヤバイ、ウザイ等、そうしたニュースピーク的なボキャヒンの反応についてはどうでも良いが、問題は、幾分か冷静となったあとの(やっぱりそんなに見たいものなのね)と自分らの乳首の価値を再認識させてしまうところにあり、すると、ますますブローカー根性に火がつき、その結果我々と乳首との邂逅がより一層遠退くという負のスパイラルに陥る羽目となる。つまり、私はそうした墓穴を掘らぬためにむっつりスケベを決め込んでいるのであって、謂わばドン・ファンにもドン・ホセにもなりたくないのである。無闇矢鱈に乳首の価値が引き上げられぬよう、デミアン的手薬煉の詮術を以て強く願い、そしてどこまでも黙してやるのである。
と、ここで持田が背伸びをする。本日彼女が着ているのはタートルネックのタイトニットであり、そのため二つの乳房がくっきりと丸く強調される。ベージュ色をしているから、一瞬だけ裸体と錯覚されなくもない。あまりにも後ろに大きく反るので、ブラジャーを押し上げ、乳首がプクリと浮き出さないかとあらぬ期待を以て凝視する私は無意識であり、気づけば持田が両手を上に伸ばしたまま訝しげにこちらを見ている。慌てて視線を外さんとするも、時すでに遅し。投げた視線の糸は隠れた乳首に根掛かりしたごとくピンと張って引き抜けない。持田はゆっくりとその糸を目で辿り、そうして下目遣いで私を見る。もはや誤魔化し得ぬことはわかっているが、強引にラインを切断し、口を尖らせひょっとこのような顔をしてそっぽを向く。早鐘を打つ心臓。巧を弄して拙を成す。我ながらがっかりである。恐る恐る持田を確認すれば、まだこちらを見ている。真顔だが、その目には蔑みとも憐みともつかぬ色が見て取れる。ずんずんと質量を増してくる黒い塊。俄然、三蔵法師に緊箍呪を唱えられたごとく頭が締め付けられる。瞼が重くなり、気持ちが眉間の奥深くに打ち沈んで行く。逆行して迫り上がる嘔気。どっちつかずに遠退く意識。全身に噴き出す脂汗。慚愧に堪えない。このまま意識を失えたらどんなに楽であろう。しかし、私は根っからの長子気質であるからして、己が卒倒したあとの処理を他人に委ねることには強い反撥がある。反撥というよりも人様に面倒をかけることへの済まなさである。一方で、小柴剛のような人間に世話をされた暁にはどんな見返りを要求(あるいは態度を)されるかわからぬという警戒もある。ともかく、あれこれの理由から私は倒れることができぬ故、どうにか薄目を開き、うつつに意識を繋ぎ止める。
「ほんとに顔色わるいけど大丈夫?」
持田が追い討ちをかけてくる。こちらの気まずさを知りながら、意地の悪い女である。
「なになになに、どした」
小柴剛もキーボードを叩きながら暢気に割り込んでくる。というか、こいつはいつまでもいつまでもいったいなにを入力し続けることがあるのか。私は答えず、放っといてくれと片手を振る。その際にヒロカズを打ち見遣ると、明後日の方を向いてどうでもよい顔をしている。あれである、なんというか、パンクロッカーは、あんまり自分のことばかり考えず、もう少し他人にも興味を持ってみるべきである。私が君の懊悩を理解し、同情し、これまでどれだけ寄り添ってきたと思っているのか。フォローはできなくとも、私の危機を察して案ずるくらいの姿勢は見せてくれてもよいではないか。
持田は先ほどまでよりも心なしか胸を張っている。それは悦に入っているようにも見える。私は梃子でもその方を見ぬようにする。これ以上図に乗らせるわけにはいかない。なぜならば、持田はなにもしていないのである。単に乳首をつけているだけで、突如として私を精神錯乱に陥れ、不戦勝を得たのである。逆に、もしも私がペニスを持つだけで持田を同じ目に遭わせたとしたならば、私はきっと己の立場の優位さに恥じ入り、その勝利を後ろ暗いものとして受け取るだろう。そうして、すぐさま持田に歩み寄り、こう弁解するであろう。
「持田よ、君を傷つけ、苦しませ、誠に相済まなかった。私のペニスめが申し訳ないことをした。私はペニスをつけているが、決してペニスそのものではない。私はペニスであると同時に、その所有者である。したがって、私は所有するペニスについて切り離して述べることができる。だから、どうか私に敗北したと思ってくれるな。君と同様、私もペニスの悪徳には困り果てているのだ。サァ、これが私のペニスだ」
私は悄げた持田を引き寄せ、チャックをおろし、ペニスを引っ張り出す。
「見てごらん。ペニスってのは、ほんとにどうしようもない奴だ。ペニスにはなにを言っても無駄だ。この通り、ペニスはなにも考えていないからだ。ペニスはなんらの精神性も有していない。単にペニスは常にペニスとしてあるのみだ。だから、ペニスに道徳は通用しない。もしペニスにペニスがついていれば、まだペニスにもペニスの考察ができようもんだが、なにぶん自身がペニスそのものだから、ペニスには自らをペニスと認識する術がないんだ。ほら、ペニスはさっきまでてんで興味のない風にしておきながら、君に触れられたら即座に反応しただろう。こうして前後不覚となり、一瞬にしてソノ気になるのさ。ただでさえなにも考えていないペニスだが、君に優しく撫でられている間はエピキュリアンの化身となり、より一層考えなくなる。そして、終われば全部を忘れ去るのさ。つまり、ペニスには過去もなければ未来もない。記憶を持たないから、情も良心も自我さえも芽生えないんだ。だから、そうしたペニスを非難することもまた無意味なんだ。ペニスはキョトンとするか、或いはなにをムキになっているのかと笑い出すだろう。仮に怒り出したとしても、それは内容とは関係なく、単に非難されたことについて腹を立てているんだ。もしも罪悪感をどこにも滲ませず、あらゆる善良さを以てこちらを宥めすかしてきたならば、これこそペニスが自らを認識していない証左だ。さぁ、もういいかい」
私は持田の手からそっとペニスを放し、なにか出てきた先端をティッシュで拭き取り、ズボンの中へしまう。そして最後にこう述べる。
「とまれ、君のペニスへの渇望はいつだって私と共にある。君は私がペニスを所有しているからといって、私に気後れを覚える必要はない。これからは、君がペニスを望むとき、私はいつでもそれに応ずると誓おう。事実上のペニスの共有だ。嗚呼、ペニスを私から引っこ抜き、君との間にポンと置くことができたらどんなに良いかと思うよ」
とりもなおさず、私を本当に心配しているなら、持田は黙って私を物陰へ連れて行き、その乳首を露出し、私の口に含ませるべきである。そうした思いやりこそが、所有し立場的に優位な者が果たすべき道徳的義務である。しかし、持田からそうした姿勢はまったく見られない。恰も乳首の勝利を己が勝利と履き違えているかのようである。否、待たれよ。もしもほんとうにそう履き違えているならば、これは大変なことである。てっきり私は、現在の持田は乳首の所有者として、その優越にブローカーとしてただ意地悪く浸っているものとばかり思っていた。しかし、これを彼女が自身丸ごとの完全な勝利として受け止めているならば、そこには所有者としての自覚がまるで欠けている。なるほど、これはワイニンゲル先達が「女には男のように一般肉体と性的区域との間の明確な区別は存在しない」と言った通りである。となれば、先ほど私が述べた精神性なきペニスの件、悄げた持田を引き寄せ話して聞かせた部分は「ペニス」を「女」に置き換えても意味が成り立つ。そしてそこからは、女は乳首のブローカーですらなく乳首そのもの、すなわちペニス同様ただの物体であるという結論が導き出される。いみじくも、ワイニンゲル先達は「女は物質であり、無である」と書いていた。しかし、これまで私は先達の言説を支持しながらも、心のどこかでは(なにもそこまで言い切ることはなかろうに)と思っていたのである。私も口では「女など単なる肉塊」と嘯いてはいたが、これは乳首の上に胡座をかくだけの女に対して半ば憎まれ口を叩いていたのであって、まさか文字通りにただの肉塊だったとは、ワイニンゲル先達の洞察力には改めて舌を巻かざるを得ない。ただ、ここに及んでもまだひとつの引っかかりが残る。子供の頃、優しく子守唄をきかせてくれ、今でもいつも味方でいてくれるあの田舎の母もただの物体なのかというジレンマである。これについて、ワイニンゲル先達は「私の見解に対して発せられるに違いない主なる反対は、私の見解が恐らく全部の女に対して正確であり得ないと云うことであろう。(中略)私が既に女に対して述べたあらゆる誹謗に対して、母としての女の概念はたしかに対立させられるであろう」と言っている。それから先達は、女を大きく母婦型と娼婦型にわけてあれこれと理論を展開していくのだけども、決してこれら二つを明確に区別しているわけではない。結果、どちらも無道徳であることには変わりはないと述べている。先日、ぼんやりとテレビを見ていたら、サバンナで象の母子がライオンに襲われていた。ライオンは背後から小象に襲いかかったのであるが、その時母象がパオーンと鼻をぶん回し、ライオンを追い払った。母は明らかに子を守っていた。もしも象が単なる物体であったなら、そのまま喰われておしまいである。つまり、そこに精神はなくとも母は本能的に子を守るくらいはするのである。したがって、私は母の顔に免じて、人間の女を敢えて物体とまでは言い切らず、せめて動物くらいの存在意義は与えようと思う。
持田が「クチュ」とくしゃみをする。猫又は「にゃむ」を付け加えることも忘れない。ヒロカズが隣席でビクンと身体を震わせ顔を歪ませている。小柴剛のボンゴ叩きはますます激しく、もはや演芸場におけるデテケデテケのハネ太鼓のようである。皆、好きにしたらいい。
その昔、私が少女漫画を好きだったのは、登場人物たちが他人の気持ちを考えすぎなほど考えていたからだった。自分の気持ちを押し殺し、他人を慮る素朴さがあったからだった。子供の頃の記憶だから、意外とそんなこともなかったのかもしれない。今と同じく、彼らもまた自分らの居場所を世界の中心だと勘違いし、世界にひとつだけの花なのだと驕っていたのかもしれない。しかし、切ない気持ちを胸に読んだ私の記憶に、少女漫画はそういう風には映っていない。
私は小学六年生までサンタクロースを信じていたし、セックスにも二十歳くらいまではあまり関心が持てなかった。高校時代に友人からセックスをしたことを聞くと、自分もいつかはそれをすることになるんだろうかと、ぼんやりと余所事のように思った。それよりもロックバンドの格好良さに惹かれたし、自分でもバンドを結成して活動すると、こんなに楽しくて良いのだろうかと日々心が浮き立つ様だった。また、演劇をやってみようといくつかの劇団の門を叩き、練習し、台詞を覚えて、本番に舞台袖から出て行くときのゾクゾクと震えるような興奮といったらたまらなかった。それは、ひとつの完成された世界の中で自分の役割を堂々と演じられるという歓びであった。ひとりでいるときは、画用紙にいろいろと絵を描けばそれだけで食事を忘れるほど一日を満喫できたし、映画を観てはいちいち感動し、小説を読んでは詠嘆した。そのまま二十七歳くらいまでは、女とは関係なしに生きていけると思っていた。男には女よりもほかにやるべきことがたくさんあると思っていた。女なんか足を引っ張るだけの存在であるのに、絵画や小説や音楽が女を表してばかりなのが謎で仕方がなかった。私にとり、女とはこちらがなにも言わずとも勝手についてくるもの、そして勝手に離れていくもの、いつもただのお荷物であった。だから芸術の種が女の中に潜んでいることに気づいたときには本当にショックであった。うそだろと思った。創造主とかいうやつは、本当に面倒くさいところに真実を隠しやがったと思った。実際には、果たしてそれが真実かどうかもわからんというのに。せめてもの救いは、その事実に女が気づいていないということだった。世界をややこしくしている原因はこれだった。仲間はひとりまたひとりと地上の女に搦めとられていった。不思議なことに、芸術をやる以外には死ぬしかないと豪語していた者に限って早々と家庭に収まり「結局、男は家庭を持って一人前だよ」と信じられぬ言葉を吐いた。私は金を稼ぐということをまったく忘れていたから、青年期の終わりには、あれほど鬱陶しかった女も寄り付かなくなっていた。なにやら珍しく懐いてきた女も結局はただの莫連だった。そうしてひとりきりとなった私は、あのとき「サンタクロースなんかいないぞ」と隣家の大粟くんに言われたときもこんな気持ちになったなと思った。
私はもう長いこと小説を読んでいない。あんたの頭ン中なんか知らんよと思うからである。古典ならばともかく、今に紡がれるものについては尚更である。たまに魔が差し、書店で新刊本を手に取ってみることもあるが、開いて一ページ目を眺めてはすぐに閉じる。本日もつまらぬことを確認しては消すだけの、テレビのザッピングと同じである。否、はっきりと申し上げて、私はもうこれ以上細分化した人間の性格をいちいち見せつけられることに辟易しているのである。それは、女子高校生が同じ制服を着ながらスカートの短さやリボンの位置などに違いを見出し、個性と呼んでいるのと変わらない。制服は制服である。一行だって頭に入って来ず、読み続けることがまったく不可能なのである。
意識を蕩けさせ、刻々と時間を棄てていく。自覚すれば嘔気が込み上げるから。そうして終業までのカウントダウン。一秒でも多く差し出しては癪だから、決められた時刻ちょうどに退社する。
なかなか安椰夏が来ない。ボックスシートに通され、もう三十分は経っている。月曜だというのに、店内はほぼ満席らしい。ボーイは十五分くらいで案内できると言っていたが、そんな見込みが当てにならぬことくらいは想定内である。暗すぎる店内。大音量のEDM。音が割れ、まったく聞き取れぬマイクコール。時折ボーイが済まなそうに顔を出し、サイドテーブルのウーロンハイをブラックライトの中で手早く作り足していく。私は物分かりの良い客として、ヒョイと片手を上げて礼をいう。実際にも気分は悪くない。焦らされていると思えば、これもまた一興。言うなれば、時間の押したコンサートの開演前と同じ気分である。そして当然ながら、私は指名客である以上、この待たされている時間は料金に含まれないのである。ウーロンハイをちびちびと飲みながら、悠々と煙草をふかす。そうして両膝に肘をつき、はやる気持ちを抑えつつ真顔のままEDMのリズムに乗ってみたりする。思考停止にはうってつけの音楽である。
「ごめーん!来てくれるのもうちょっと遅い時間かと思ってた!ムチュムチュポーン!」
と、突然安椰夏が現れて、私にタックルするかのように勢いよく隣に座ってくる。
「おーびっくりした」
私はいかにも虚を衝かれた風に仰反り、そして舌の上に転がしスタンバイさせていたミントタブレットを噛み砕く。口臭予防は最低限のエチケットである。
「今日、お仕事終わるのはやくない?」
「いや、いつもと変わらんよ」
「えー、ほんとー?じゃあ終わってすぐ会いに来てくれたって感じ?」
「そうそう」
「えー、めっちゃうれしいんだけど!」
安椰夏はそう言ってグイと腕を絡ませ、胸を押しつけてくる。下着をつけていないから、乳房の柔らかさが直に伝わってくる。
「今日は忙しそうね」
「んーまあまあかなー。なんか出勤の女の子が少ないみたいで、私もさっき来たんだけど、すぐにフリーのお客さんにつかされたの。予約アリって言っといたのに!ごめんねー待たせちゃって。あとで店長に文句言っとく!なに飲んでんの?ウーハイ?」
「そうそう。安椰夏もなんか飲む?」
「頼んでもいい?」
「もちろんいいよ」
「ありがとう!お願いしまーす!」
安椰夏が鼻にかかった大声でボーイを呼ぶ。ボーイは直ちにやってきて、かしこまって片膝をつき「ありがとうございます、八百円です」と言う。私が千円札を渡すと、ややあってお釣りとレッドアイを持ってくる。安椰夏はいつもこれを飲んでいる。私は二百円のお釣りをそのまま安椰夏に渡す。以前、財布に戻すのが面倒くさいからと変な見栄を張って渡してからというもの、これが当たり前となってしまっている。安椰夏はこの二百円を嬉しがってすぐにポーチにしまう。その合計はもう数万円になっているだろう。
「いただきまーす!」
たった今まで他の客のところでも飲んできたろうに、安椰夏は本日初めて飲むかのようにとても美味しそうに飲む。一口飲んでは、ペロリと上唇を舐めるのである。安椰夏は、映画『砂の女』に出演した頃の岸田今日子にとても似ている。サッパリした目元とぽってりとした唇は、私の好むところである。東北の出身らしく、肌が白い。店のコンセプトが和風だから、衣装は花魁風の着物ドレスである。というか、子供の着るような丈の短いサテン生地の浴衣ドレスである。安椰夏はすでに胸元を少しはだけさせており、ふっくらとした乳房が暗闇に白く光って覗いている。角度によっては乳首も見えてしまうだろう。しかし、私はまだ見ない。ここがおっぱいパブだからといって、そう簡単に見るのは野暮である。乳首が見たい気持ちは、きちんと増幅させなければならないのである。安椰夏はそれを心得ているから、私の気持ちが決まるまでわざと見えるか見えぬかのギリギリの状況を作り出してくれる。ありがたいことである。私が彼女を指名する所以もここにある。もちろん、安椰夏の乳首はもう何度も見ている。しかし、まだ一度も見ていないとも言える。少なくとも今日はまだ見ていない。安椰夏は常に私に腕を絡ませ密着しながら、取り留めのない話をする。飼っている犬のことや、最近ハマっているお菓子のことや、昼間の仕事のことを。とりわけ私は昼間の仕事の話に耳を傾ける。ブライダルコンサルティングの会社に勤めているらしいのだが、このところ女上司との折り合いが悪いとのこと。
「職場に男はあんまりいないんだっけ」
「うん、男性社員もちょっとはいるけど、基本的には女ばっかりだよ」
私は想像する。女ばかりのオフィスを。私は想像する。それぞれの乳首を。桃色の乳首、褐色の乳首、黒い乳首、幅広の乳輪、幅狭の乳輪、小粒の乳頭、肥大した乳頭、陥没した乳頭、ひとりひとり様相の違うそれが各々オフィス内を蠢き、乳房の先端でプルプルと揺動している様を。
「その上司っていくつくらいの人?」
「んー、たしか三十五くらいだった気がする」
と、私に凭れかかったまま顎に手を当てて考えるポーズをする安椰夏の胸元が緩み、一瞬だけ乳輪が覗く。私ははっと視線を逸らす。
「あ、見えちゃった?」
「いや、うん、ちょっとだけ」
「あーあ、もう見ちゃったー」
「いや、まだ見てない。これは見たうちに入らない」
安椰夏が腕を解いて、胸元を正す。そう、まだ早いのである。
「で、その上司はどういう人なの?」
「んー、とにかく強気。シングルマザーなんだけど、男には絶対に負けたくないって感じ。で、いつも目を見開いてるの」
「目を見開いてる?」
「そ、こうやって。特に話すときはほとんど瞬きしないでずっと見開いてるの。ただでさえ目が大きい人だから、なにがこわいってそれがほんとこわい」
安椰夏が指を自分の瞼にあてて目を大きくしてみせる。よい感じである。
「いやだな、それは」
「でしょー?今日もね、お昼にめっちゃ肉うどんとか食べたかったのに、なんかパンケーキしかないお洒落な紅茶専門店に付き合わされてね、そこひとつしかお手洗いがなかったんだけど、男の人がなかなか出てこなかったんだよね、十五分くらい。そしたらさ『あの男、ぜったいトイレに盗撮カメラ仕掛けた』って言うんだよ」
「ほうほう」
「私がお腹痛かったんじゃないですかね?って言ったら『いや、ぜったい仕掛けた。私けっこうそういうのすぐにわかるから』って言うんだよ。こわくない?」
「目を見開いて」
「そう、目を見開いて!」
「いやだな、それは」
「会社のトイレにも仕掛けてあるかもしれないって、けっこう頻繁にチェックしてるみたいだし」
「大変だな、それは」
「いつも『男はみんな変態か馬鹿のどっちか』って言ってるんだけど、この間ジャーナリスト志望の女子大生が報道記者のおじさんにホテルで強姦されたみたいな事件あったでしょ?最近、その女子大生を支援する会みたいなのに入ったらしくて、テレビ観てたら女子大生が取材受けてる後ろにその人ばっちり映り込んでた」
「目を見開いて」
「うーん、たぶん見開いて。って、どうでもいいって思ってるでしょ!」
「いやいや、思ってないよ。いつも目を見開いてるのが嫌だなと思って」
「ていうか、そもそもあの人ブライダルの仕事向いてないと思うんだよね。相談にきたカップルが帰ったあと『あの男ぜったい浮気するよ。私にはわかる』とか毎回寸評するし」
「いや、天職でしょう」
「えー、なんで?ぜったいテキトーに言ったよね、いま!」
ワイニンゲル先達曰く、総ての女は媒合者(世話焼きおばさん)である。
安椰夏がグラスを両手で持ち、レッドアイを美味しそうに飲む。私もウーロンハイを一口含む。よい感じである。会話が弾み、関係性も構築され、安椰夏の乳首を見たい気持ちは十分に増幅された。ワンセット三十分。ボーイが終了を告げに来るのがその数分前。本日は待たされたぶん多少の猶予は見てくれているだろうが、気持ちの盛り上がる最中にボーイが来てしまっては興醒めである。だから、タイミング的にはそろそろである。安椰夏も、先ほど正した胸元をいつのまにか再び乳首の見えるギリギリまではだけさせている。ありがたいことである。安椰夏の乳首が見たい。ブライダルコンサルティングの会社に勤めている安椰夏の乳首が見たい。このところ上司と折り合いの悪い安椰夏の乳首が見たい。今日は肉うどんを食べたかったのにパンケーキを食べさせられた安椰夏の乳首が見たい。それはどんな塩梅か。色、形、大きさをこの目で確認したい。
「じゃあ、乳首お願いします」私は改まって安椰夏の正面に向き直る。
「かしこまりすぎ!」と笑いながら、安椰夏が姿勢をまっすぐ正し、ゆっくりと胸元を開ける。
いま、此処に露わになる乳首。私の心は打ち震え、あ!あ!あ!と切羽詰まり、続けて、認識の追いつかぬなにかが私の内部を丸ごと掻っさらい、脳天へと駆け上ってくる。ムチュムチュポーン。
「あ!あ!あ!」
「ちょっと!目、見開きすぎ!」
安椰夏が笑う。私の頭部は膨張し、すでに首から下と切り離されている。妖怪、飛頭蛮である。
「ほんと、いつも初めておっぱい見る人みたいな反応するよね」
そう、私はたったいま安椰夏の乳首を、否、女の乳首というもの自体を、初めて見ているのである。是即ち、西田幾多郎の謂うところの純粋経験である。また、これは私がまだ恋愛というものを信じていた頃、ステディの乳首に厭きてしまわぬよう、謂わば慣れぬための工夫として自ら編み出した感覚的手法でもある。
徐々に認識が追いついてくる。安椰夏の乳房は釣鐘型であり、滴のように美しく撓んでいる。そのいただきに、淡い桜色をしたやや幅広の乳輪が冠雪のごとく被さり、同色の練り消しを指先で気まぐれに捏ねて作ったような乳首が昂然と上向きについている。なるほど、これが安椰夏の乳首である。たしかに先週も此処に来て見た記憶のある乳首である。私は顔を近づけ、目を凝らして見る。この場所が暗がりであることがなんとも惜しい。乳首を凝視する私を、安椰夏が下目で面白そうに凝視している。が、そんなことにかまっちゃいられない。いま、此処に在る乳首。美術品同様、ぼんやりと見るだけではなにも残らぬから、様々に視点角度を変え、殊更に見ていることを意識して見る。意外とこれの効果はあるのだ。すなわち、私は安椰夏の乳首を観照しながら、乳首のイデアを思考するのである。これもまた、私がまだプラトニック・ラブというものを素朴に信じていた頃、ステディ以外の乳首を見たい気持ちを押し殺すべく、謂わば目移りせぬための工夫として自ら編み出した実践的手法でもある。これにより、ひとつの乳首にあらゆる乳首が収斂されるのである。いま、目前に在るのは安椰夏の乳首だが、此処には鮫島の乳首も、持田の乳首も、昨日のバーガーショップの若妻の乳首も、あの人この人の乳首も、すべて内包されている。とりもなおさず、わたしはいま、世界中の女の乳首を目の当たりにしているのである。もはや色、形、大きさなどの違いは存在しない。乳首のイデアはひとつである。
乳首とコンサートは似ている。私はコンサートへ行くと、演者の登場の瞬間こそ目を奪われるが、二、三曲も聴くともう十分であり、以降は只管時間を持て余す。外へ煙草を吸いに行くこともあれば、そのまま帰ることもある。かにかくに、オープニングが気持ちの高鳴りのピークという意味に於いては乳首も同じである。
浮遊していた私の頭が、すとんと身体に返ってくる。安椰夏は、尚も私の観照になにか趣きを加えようと、乳房を両手でプルプルと揺らすなぞしてくれている。ありがたいことである。しかし、もう満足である。最後に、私の方でも乳房に軽く触れさせていただき、乳首もペロとひと舐めさせていただく。これにて終了。ありがたいことである。
「満足した?」
「はい、ありがとうございます」
「なんで丁寧語なの」
笑いながら、安椰夏が乳房を仕舞う。俯き、口元に笑みを残しながら衿元を正す安椰夏の横顔には、諦めに似た憂いのようなものが浮かんでいる。おぉ、女よ、できるものなら、きっときっと愛していたものを。この芸術の露顕する瞬間を、ワイニンゲル先達は「娼婦性の根本的起源は、何人も入ることの出来ない深い神秘である」と言った。先達がその『性と性格』の中に於いて、唯一わからぬとしている部分である。
「そろそろお時間です」
絶妙のタイミングでボーイがやってくる。見計った通りである。
「ご延長はいかがいたしましょう?」
ボーイは、胡麻擂りのごとく手を捏ね、膝をついてかしこまっている。しかし、そう遜って言われなくともこちとらの気持ちは決まっているのである。
「はい、延長をばお願いします」
これまでのことは一旦忘れ、純粋経験からイデアの認識と、もう一度最初から繰り返す。アンコールである。安椰夏は一度化粧直しに立ち、その間に私はミントタブレットを口に放り込む。
地中深くから階段を上がり、地上へと出れば、暗闇に慣れた目の奥に毳毳しいLEDネオンが突き刺さる。人工的な光にギラギラとどきつく照らされた大通り。人々が賑やかに行き交っている。すでに出来上がり、なにやら大声を発しながら肩を組んで歩く中年のサラリーマン。シンバル猿のごとく手を叩き、横並びにはしゃいで歩く若い女たち。地味な大学サークルと思しきおどおどした垢抜けぬ集団と、そこへぬりかべよろしく立ちはだかるカラオケ店のサンドウィッチマン。その次に彼らを眈々と待ち伏せするは、居酒屋のメニューをプラプラと片手に携えたいかにも軽薄そうな数人のキャッチ。肩で風を切り、邪魔臭そうな顔をして歩くホスト。ロングコートでドレスを隠し、急ぎ足でどこかへ向かうホステス。べったりと密着して歩くあやしげな歳の差カップル。道の真ん中で腕を組み、仁王立ちで品定めをする女衒、等々。とまれかくまれ、のそのそとおっぱいパブから出てきた中年男に気を留める者など誰もいない。
勢いづいた夜の街を縫い歩きながら、脇目も振らず駅へと向かう。私がこの街に求めるものは、まったく乳首だけである。一刻も早く帰宅し、安椰夏の乳首を思い出して、ひとりでアレをやるのである。我ながら、誠に素朴な中年男子である。今だ耳の奥にEDMの鳴り止まぬ中、尚も騒音の押し付けがましく迫り来る。パチンコ店からは滝の轟くような音、大型ビジョンからは早口で捲し立てるダイエットサプリメントのコマーシャル、別のビジョンには歌って踊るこましゃくれたアイドル、安さが売りの大型ディスカウントストアからは、店名を連呼するだけのふざけたオリジナルソングが、宗教団体の洗脳音楽よろしく延々と流されている。一切を考えさせまいとする騒音の波状攻撃に、私は脇をしめ、精神のガードを固めて不乱に歩く。そうしてスクランブル交叉点に立ち止まる私の前を、大音量で珍妙なメロディ広告を流すアドトラックが、へらへらと小馬鹿にしたように悠々と通り過ぎて行く。
背後で「あれ!」と声がし、肩を叩かれて振り向くと、小柴剛が立っている。
「なにしてんの?」
それはこっちの台詞である。見れば、小柴剛の後ろに持田も鮫島も、そしてヒロカズもいる。
「ん、あぁ、ちょっと近くに用事があって」
私は無表情のまま、まったく動じぬふりをする。
「そっちはなに、なにしてんの」
「いや、仕事終わったあと、なんとなくみんなで飲みに行くかって話になってさ」
「誘おうと思ったんだよ!でも、今日体調悪そうだったし、すぐに帰っちゃったから」
持田が気まずそうにほろ酔いの顔を覗かせる。後ろで鮫島が遠慮がちに小さく頭を下げている。そのとなりのヒロカズはもう大分飲んでいるらしく、満足そうに身体を左右に揺らしながら、どうでもいいような遠い目をしている。
「あ、聞いて聞いて!鮫島さんて、パンクロックがめっちゃ好きなんだって!意外じゃない?ナントカドールズとかラモーンナントカとかそういうやつ!わたしそういうの全然ムリなんだけど、さっきヒロカズくんとめっちゃパンク談議してて、まさかの共通項にほんと笑った!今度みんなでヒロカズくんのライブ行くことになったよ!」
「へえ、そうなんだ」私は表情を変えない。気をつけなければ、まばたき一つで内奥の露見してしまうこともあるから。こうしたことを、もう何百回と繰り返してきたことか。
「これからカラオケ行くんだけど、どう?」私より少し背の低い小柴剛が、切込みのような目で凝っと私を見据えて言う。
「いや、やめとく。じゃ」
信号が変わり、私は彼等を背にしてスクランブル交叉点を渡る。渡り切ればすぐに駅である。群衆の中を、常に対向者の動きを予測しながらジグザグに進んでいく。腰掛けの二十年。いまだ慣れぬ都会の雑踏。私は、一歩一歩と打ちのめされる私を抱えて歩く。それでも私は強情である。抱えられているくせに「慣れてたまるかよ」と不敵に笑っている。私が守ってやらねば、もうどうしようもないというのに。お互いが同じ方向に避けてしまう、もどかしき連続回避本能。キャメル色のコートを着た女が苛々と舌打ちをして通り過ぎていく。
改札を抜け、ホームへの階段を上がると、いつもよりも人が溢れ、騒然としている。発車標に「人身事故」の赤い文字。
「またかよ。死ぬんだったら、どっか山奥でも行ってひとりで死ねよな」
「樹海とかな」
「飛び込みとか、まじで迷惑すぎるだろ」
「自爆テロだよな」
私も本当にそう思う。あるいは、自殺ではなく不慮の事故なのかもしれない。しかし、どうあれ、その人はもうとっくにこの世にいないのだ。すでに宇宙へエネルギーを放出し、完全なる無に帰したのだ。そのことが羨ましくて仕方がない。火、水、木、金、あと四日の辛抱である。
了
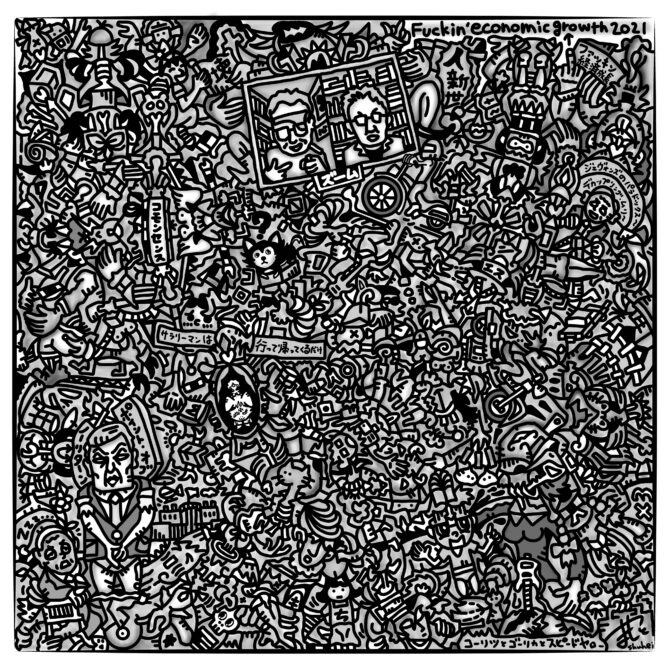






















"乳首が見たい"へのコメント 0件