今から二週間ほど前のことです。私は会社から帰宅するため、地下鉄に乗っていました。私の乗る地下鉄は上り方面のため込み合っておらず、いつもは座席に座っていても隣の方に触れるようなことはないのですが、その日は違いました。下車駅に近づく頃、私の右臀部に人の体温を感じたのです。珍しく込み合ってきたのかと思い隣の席に顔を向けると、そこにはメガネを掛けた三十代前半のサラリーマン風の男性が座っていました。そして息を荒げながら私の臀部をさすっていたのです。
私は直感しました。同胞だと。私と同じく生体改造された人間だと。
生体改造された人間は相手に何かを伝えるとき、言葉を発するのではなく、思念を送ります。思念を使えば離れた場所でも会話することが出来るのです。しかし電波状態の悪い場所では相手に触れなければ思念を送ることができません。地下鉄の中は思念通話に適した場所ではないのです。私は彼に微笑みかけ、声に出し言いました。
「大丈夫。何度も試して」
彼はぽかんと口を開けた後、私にぎこちない微笑み返し、以前にもまして激しく臀部をさすってきました。彼は必死に、熱を帯びるほど私の臀部をさすってくるのです。これは声に出すことの出来ない大事なことを伝えようとしているのではないかと思い、必死に彼の思念を汲み取ろうとしたのですが、臀部は信号の伝達には適していない部位です。私は彼の思念を捉えるため、臀部をさすっていた彼の手を取り、私の胸元へともっていきました。すると彼はガクガクと震えたかと思うと、さっと手を引っ込めました。彼はしばらく放心すると、そっと私の隣から離れていきました。きっと私が思念を受け取ったと思ったんですね。その証拠に彼は降り際、私の方に振り返ると、満足したようにニヤリと笑いました。すこし後ろめたかったのですが、私も笑顔を返しました。
このように生体改造された人間はこの国に数多くいます。是非御誌で特集を組んで頂き、国民に我々の存在を認知させて頂けないでしょうか。そうすれば公共の場所で堂々と思念のやり取りが出来るようになります。
海野優人はメールを閉じてため息をついた。ウェブサイトに情報提供フォームを作ってからというもの、こういった投稿が数多く寄せられる。優人はうんざりしながらも次の投稿メールを読み進めていく。過去に読者から寄せられた情報が大きなスクープになったこともあり、横のつながりに乏しい週間ダイヤでは、ウェブによる読者投稿は重要な情報源なのだ。
「どうだ、何か面白いネタはあったか?」
投稿メールに目を通す優人に山田太郎が後ろから声をかけてきた。山田は五年先輩の記者で、主に風俗関係の記事を書いている。彼の書く生々しい性描写は読者から好評で、週間ダイヤの人気コーナーになっている。
「八割が個人的恨みで、残り二割が陰謀とか宇宙人とか、電波がどうとか頭のおかしな人の投稿です。スクープのネタが眠っていると言うけど、掘り当てるのは並大抵のことじゃないですよ……」
優人は椅子ごと後ろに振り返り山田に愚痴る。
「そう腐るなよ。お前にいいネタをやるよ。ウチの名前を出せない取材だけど、やってみないか?」
そう言うと山田は優人の隣の席に腰を下ろした。優人は山田が座った席に椅子を回し面と向かう。
「どんな情報ですか?」
「ハプバーって知っているか?」
「知っていますよ。ハプニングバーのことですよね? 何年か前に山田さんが記事にしていましたから」
優人は思い出す。確か山田が彼女と一緒にハプニングバーに行って、仕事を忘れスワッピングを楽しんだという記事だった。自分の彼女を巻き込んだ潜入取材に読者の評価がとても高かったと記憶している。
「そうだ。けどな、最近は取り締まりが厳しくなって多くのハプバーが店を畳んだ。そんな中、地下に潜り客を選び高級化して生き残っている店がある」
「風俗取材ですか? 俺はやりませんよ。風俗なんか行って病気でもうつされたら彼女になんて言われるか」
優人はそう言ってから椅子を机側に戻そうする。すると山田にひじ掛けを掴まれた。
「俺の仕事を全否定するなよ。それにハプバーは性的サービスを受けるところじゃない。どちらかと言えば見せるところだ。ハプバーにやってくる奴らは素人だしコンドームの着用は強制だ。病気をうつされる可能性は少ない。それにそういった行為を強制されるわけでもない。見ているだけでもいいんだ。まあそれはいい。お前にやるネタとはな、銀座にある会員制ハプバーに有名女優が通っているという情報がある。そこに潜入して事の真偽を確かめるんだ」
「情報源はどこですか?」
「一時期話題になった出会い系バーに通っていた高級官僚だ。奴はそこで知り合った女に小遣いを上げただけだと言っているが、俺は売春していた事実を掴んでいる。そもそも出会い系バーとは売春交渉バーの別称だ。それをネタに取引をした」
確かその官僚は女性の貧困問題の調査で、出会い系バーに週三回も通い詰めていたとメディアで話題になっていた。
「ゆすったんですか?」
優人は山田を見据えて言った。山田の取材は強引なところがあり、週間ダイヤが告訴されている訴訟の幾つかは、直接的ではないにせよ山田が関わっていた。
「違う、取引だ。前川は女癖は悪いが優秀な官僚だ。今は停職中の身だが、これからの日本にとって必要な人間だ。女性問題で消えるのは惜しい人間なんだ。売春の事実が表に出ると政界進出を目論む彼の野望がついえる。だから売春の事実を表に出さない条件で週刊誌のネタになりそうな情報を提供してもらったわけだ」
「それをゆするって言うんですけど……」
「しつこいようだが、この業界ではそれを取引と言う。どうだ、やってみるか?」
優人は迷っていた。有名女優がハプニングバーに通っていたとなると大きなスクープになるかもしれないが、最近は警察に摘発される店が多く、運悪く潜入した時に摘発されれば、前科が付いてしまう。優人の心は摘発に対する恐れと、有名女優のセックスが見られるかもしれない期待のはざまで揺れていた。
「だけど、会員制のハプニングバーなら紹介がなければ入れないんじゃないですか?」
「そこでこれが効いてくる」
そう言うと山田は一枚の名刺を優人に差し出した。そこには「文部科学省事務次官前川喜郎」と印刷されていた。
「前川はそのハプバーの常連だ。彼からの紹介と言えば入会できる」
事務次官の名刺なんて今までお目にかかったことがない。優人は山田に尊敬に似た感情を覚える。
「でもセレブの集まる高級店なんでしょ? 俺、高い服持っていませんよ」
山田は自分の着ているTシャツをつまみながら言った。
「最近のセレブはTシャツ短パンが正装らしいぞ。奴らはそんな恰好でビジネスをしている。だからお前も同じような格好で行けばいい。それともう一度言っておくが、ハプバーは自分から行為を申し出なければ見ているだけでいい。可能性は殆どないが、もし警察の摘発があったとしても、下半身を露出していなければ捕まることは無い。見ているだけなら何の罪にも問われない」
山田は優人の不安を見抜いていた。捕まる可能性がないのであればやらないわけにはいかない。有名女優のセックスを見られるかもしれないのだ。
「分かりました。やります。それでターゲットの有名女優って誰なんですか?」
山田の言う有名女優が誰なのかで優人のやる気が変わってくる。
「能年里奈だ」
能年里奈は国営放送の連続ドラマで一躍有名になった女優だ。事務所との契約問題で一時的に芸能界から干されている状態らしいが、そのうっぷんをハプニングバーで解消しているのかもしれない。優人のやる気は最高潮に達した。












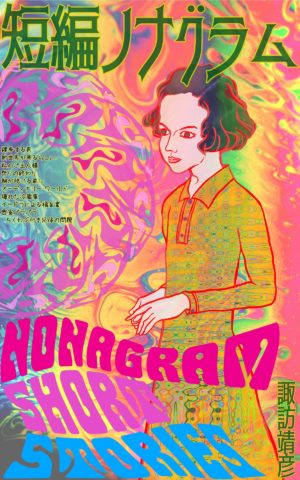










"一"へのコメント 0件