すべての人間の握りこぶしにある村、尿道村にやってきたのは初夏の暑い日でした。
お金のため。
単なるヒマつぶしのため。
「今日から働いていただく、佐々木ワンコロさんだ」
村長の右腕・ケムマキは玄関で叫びました。
「よろしくお願いします」
上がり框(かまち)で深々と頭を下げると、廊下の奥の暗がりから、
「あい」「ちきっ!」といった返事だけが聞こえました。姿は見えません。
「あの、誰もいらっしゃらないんですか?」
「貴様のようなメス犬に発言する権限は無い」
「え?」
「とにかく、人手が足りなくて困っている。ここに所属するメイドは七名いるが、平均年齢は八十歳だからな……」
ケムマキはひどく不機嫌そうに、かたわらの花瓶につばを吐きました。
居間に通された私は、驚愕の声を上げてしまいました。
 「ここが村長の部屋で、おまえの職場だ」
「ここが村長の部屋で、おまえの職場だ」
十畳ほどの居間には、尿道村を統治する村長の姿が。
なんて巨大なのでしょう。
私がおそるおそる挨拶すると、返事のつもりなのでしょうか、村長は尿を少しだけ放出しました。
あたりをウロウロする老メイドたちは、テーブルに置かれた紙パックジュースを恨めしそうに見つめるばかりでした。
「おまえの仕事は、ここで定期的に排出される村長の糞尿を掃除することだ」
ケムマキは事務的に言いました。
「それがひとつ。もうひとつ重要な仕事は、朝、昼、晩と食事をこしらえ、ここに並べること」
「あの」私はおそるおそる挙手しました。
「食事を、みんなで、ここで?」
「当たり前だ。村長はああ見えて寂しがり屋だからな」
私は荷物を置くひまもなく、食事を作らされました。
暗く、汚く、臭いキッチンで!
冷蔵庫にはだいぶ傷んだ野菜類、凍った味噌汁、メガネケースなど、使えそうにないものばかり。
老婆のメイドと組まされましたが、彼女はけん玉に夢中で役には立ちませんでした。
「あの、村長にはどれぐらいの量を?」私は老婆に聞きました。
「メシか。いらねえ。村長の顔面は屋根より高いとこにあるんだども、ケモノとか鳥とかが村長を襲ってくれっからよ」
「すいません。意味がわかりません」
「だあがら、あの大きさだべ。村長は襲ってぐるケモノどもをパクッと食っちまうんだあ」
老婆はけん玉をゴミ箱に捨て、寝そべりました。
「朝。はしごで屋根に登って、ゴミとか雑穀を口ん中に放りこんどきゃええ」
「はあ……」
私は包丁を振るいながら、窓の向こうに目をやりました。
猫背の人間のような雑木林に混じる、いくつかの朽ちた家屋。
尿道村。
昔炭鉱で栄えた村だったらしいけど……
「えいっ、やあ!」
ケムマキが竹やりの訓練に精を出していました。
私は思わず目を伏せました。
あの冷淡な顔、村に似つかわしくないブランドもののスーツ、どぎつい香水の匂い、淡々とした喋り方、すべてに嫌悪感を抱いてしまいます。
「ケムマキのやつ、若い娘っこが来たから、喜んどるんじゃ」
老婆は下品な笑顔を浮かべました。
「あの人、どういう人なんですか?」
「きちがいじゃよ」
「きちがい?」
「この村にゃきちがいしかおらんよ」
老婆。両の目の視点は定まっていませんでした。なにも見たくない、というふうに。
食事を並べ終えると、村長の男性器が活発に動きだしました。
 「ギャアアアアアア!」
「ギャアアアアアア!」
村長は私が丹精こめて作った料理に、大量の尿を放出しました。
「なにしてんだテメエはあ!」
私が怒鳴っても、すさまじい濁流にすべては流れていきました。
「これは美味そうな料理だ」縁側からケムマキがやって来、尿まみれになった野菜を手ですくい集めました。
「皆はまだ帰ってこないようだが、ひとまず先に頂こうか」
彼は、腰を抜かす私にかまわず、野菜を口に放り、じゅっくじゅっくと音を立てて噛みました。
「ちょっと塩分が効きすぎてないか? まあ初日だから大目に見てやろう」
村長の放尿はなおも激しくなりました。
 まっかな朝。
まっかな朝。
スコップを手に、二時間かけ村長のウンコ掃除を終えた私は、雑穀、鹿の生肉などをバケツに入れてハシゴを登りました。
巨大な村長は微動だにしません。
死んでいるのか、生きているか分かりません。
口の中にはケモノをおびき寄せるエサ以外に、いのししやムササビの遺骸などがあり、どれも腐食して凄まじい臭気を放っていました。
「おはようございます」
と、声をかけてみるも返答なし。
どうみても死んでいるのに、あの常軌を逸した排泄量はなんだろうか。
あまり深く考えないほうが良さそうです。
それよりも、空腹でめまいがします。
村長の糞尿にまみれた食事など摂れるはずもなく……。
「ねえ、新入りさん」
その声の主を確認すると、私は思わずハシゴから落ちそうになりました。
察するに、女性のようですが、全身に包帯を巻きつけたその姿はミイラそのものでした。
「やったあ。同じくらいの歳だ」彼女は目だけで笑いました。
私たちは森林を並んで歩きました。
腐った鳥、腐った雑草。不可解なノイズ音がこだまする暗黒の道。
彼女はメド子さんといい、私より年がふたつ上でした。
相当おしゃべりだけど、暖かい人柄で、人見知りの私でもすぐ打ち解けることができました。
「びっくりしたでしょ。村長」
「はい」
「そっかあ。おしっこだったかあ。ラッキーだったね。
あたし、物心ついたころからこの村にいたけど、初潮を迎えたあたりかな、村長のもとで働くことになって……初日はビックリしたな。お尻が、こう、こっちに向いててね。挨拶したと同時にウンコをボトボト落とすんだもん」
私は急に安心したのか、涙が溢れてきました。
朝一番の糞便撤去作業。異常な光景。他の老婆メイドたちは少しも表情を崩さず、のんびり昆布茶なんかをすすっていました。
メド子さんの暖かい励ましに、嗚咽は止まりませんでした。
彼女には子供がいて、メイドの収入だけでは食べていけず、村はずれの小屋でピンサロ店を経営しているそうです。
「色々なチンチンがやって来るからね。油断ならないよ。黒いヤツ、曲がったヤツ、油っこいやつ、バーベキュー・テイストなやつ。けど負けないよ。あたし。
自分の舌の技術に自信あるから」
「メド子さんって凄いんですね。私もひとつくらい、そういう技術が欲しいです」
「ウチで働く?」
私は首を横に振りました。とりあえず村長の糞尿に慣れるまで、油っこいものやバーベキュー・テイストのものに触れたくないのです。
メド子さんは秘密の沼地に案内してくれました。
沼を囲う葉のざわめき、心地よい緑風。汚物にまみれた心が洗われました。
メド子さんは辛いことや悲しいことがあると、ここに来るという。
 「ワンコロ、あんたイイヤツだ。本当の親友になれそう。だから頼みがあるの」
「ワンコロ、あんたイイヤツだ。本当の親友になれそう。だから頼みがあるの」
メド子さんは向き直り、声のトーンを落としました。
そして、身体じゅうの包帯を、ゆっくりと、外しました。
萎縮した私は、それでも、なるべく彼女が傷つかないような表情を作りました。
一糸まとわぬ彼女の姿態はハイレベルなグロ。裂傷、火傷、打ち身、青アザが、身体中にありました。
顔は無数のくぼみができていて、まるでゴルフボールのようです。
私は彼女から目をそらさず、平静を装いました。
「いや、これは健康対策なんだけどね。自分でやったの」
「え?」
メド子さんはあっけらかんと言いました。
「そう。針灸ってあるでしょ。ツボ押すやつ。数年前アレにはまっちゃってさ、最初は指圧棒とか、つまようじを使ってたんだけど、だんだん刺激が足りなくなってきてね。次第にバットとか木刀で自分を殴るようになっちゃって。
気持ちいいんだコレが。時間かからなかったよね。アイスピックになるまで」
「アイス、ばかなこと、やめてくださいよ! 死んじゃいますよ!」
「いや、死なないよ。あたし、チンチンしゃぶるだけが能じゃないんだから。
ツボ押しで『死なない技術』も持ってるんだから。
実際、ツボ押しをはじめてから健康だもん。病院に行く回数が増えただけで」
私のか細い抗議に耳を貸さず、彼女はリュックからガスバーナーを取り出しました。
「まだ試してないんだけど、やってくれる? 友情の証明に」
「い、いやです」
「三陰交(さんいんこう)からやって。足内側のくるぶしから指三本上の場所」
「いやです」
メド子さんは息を荒げ、ガスバーナーを手にジリジリ歩み寄ってきました。
唇の端から泡を吹き、白目を剥いて、がなりたててきました。
「ひさしぶりにやってもらいたいのしかもバーナーなんて強烈でしょうね!
じゃあ手からでいいから親指のつけ根、ここ合谷、ごうこくっていうんだけど便秘と冷えに効くの、ちょっと炙ってちょうだい炙って頼む頼みます、ワンコロさんお金も少しあげるからやってちょうだいよ炙って!」
 私が頑なに拒むと、彼女はサボデーネ、という不可解な言葉を発し、自分で自分の「ツボ」を炙りはじめました。
私が頑なに拒むと、彼女はサボデーネ、という不可解な言葉を発し、自分で自分の「ツボ」を炙りはじめました。
「あぢっ、あぢぢぢぢぢぢぢ、効くわコレ思いのほか効きますわ」
激しくのけぞり、苦悶や恍惚を顔に浮かべ、彼女は身体のあちこちに強烈な刺激を与え続けました。
健康のために。
私が逃げるより早く、「ゴルベーザ」と叫び、彼女は失禁しつつ昏倒しました。
メド子さんは病院には運ばれず、村はずれの小屋に投げ込まれました。
「いつものことだ」と、診てくれる医者はもうなかったのです。
「貴様、ツボ押しのメドに会ったのか。このスマイリー・ブス」
私はというと、さんざんケムマキにどつかれ、廊下の暗がりで鼻血を流しながらびいびい泣くだけです。台所から、老婆メイドたちのひそひそ話が聞こえました。
「会った」
「バカだねえ」
「オスッコのチンチンを吸うくらいしか能のない女が」
「新入りもそうなんじゃろ。似たもの同士仲良くなりおって」
「ジャボ嬢も不憫じゃのう」
ケムマキは壁をどん! と叩きました。
 「貴様が姿をくらましていたから、村長の糞尿を誰が片づけたと思う。私だぞ。40キロもの量をだ。明日、筋肉痛になるであろう。
「貴様が姿をくらましていたから、村長の糞尿を誰が片づけたと思う。私だぞ。40キロもの量をだ。明日、筋肉痛になるであろう。
いいか。あの女は村一番の変態だぞ。
確かに雇っていた時期はあったが、とっくの昔にクビにした。
昼はツボ押し、夜は荒くれ者たちの陰茎を吸う。ロクなもんじゃない。この村の厄介者だ。
今度、仕事をサボッてメド子と会ったら、貴様の鼻を鉛筆削りに使うぞ!」
その夜、尿道村で毎月恒例らしい「めっこん音頭」が開催されました。
めっこん音頭はその名の通り、いや、その名とは関係なく、明治の頃から伝わる伝統の踊りで、それはよそ者の私からすれば、奇妙珍妙としかいいようのないものでした。
例の居間に数十の村民が集まり、村長の尿を浴びながら踊るのですが特筆すべきはその動き。
舌を出し、目をぎょろぎょろさせ、尻を突き出し、跳躍しながら腕をデタラメに振り回すのです。さながら狂人・廃人の様相を呈していますが、村民からすれば神聖な舞いなのです。
「よっこれサッコンびちびちの米国ホッホイ!」
男衆の雄々しい声と共に、肥えた中年男が尻を振ります。
「いよっ」
「腐ったサバよっこれ!」「腐ったデニーロはっさい!」「よっこれ!」
たたたたた、と村長の巨大な陰部に触れ、男は腰を屈め、真顔で四股を踏みました。
「地引網はっさい!」「めん、むす、なんっ!」「はっさい」
踊り手を囲った村民達は真顔で拍手し、地酒を注いだ杯を時計回りでまわします。
烈火の如き動きで踊りまくる「めっこん」音頭に、私の顔面は赤く波打ちました。
「よっこれ」「サンジェルマン通りホホイ!」「はっさい!」
「ぷぷっ!」口をおさえ、こみあがる笑いをこらえました。
白い尻が凄まじい速さで左右に揺れ、頭の悪いニワトリのように跳び回るめっこん。
村長の男性器が、何かのアトラクションのように尿を放出しながら上下めっこん。
「く!」顔面の血管が切れそうになりました。
口をこすったり、まぶたに力をこめたりし誤魔化し、ひたすら終わるのを待ちました。
笑ったら殺されそうです。
「邪気を払い豊作を祈願するのだ。分かるかね」隣のケムマキが耳打ちしました。
「はい」
「村長の放尿もいつにも増して鋭い。放物線の描き方が違う。わたしには分かる」
「くっ!」私は顔をそらし、こみあがる笑いを噛み殺しました。
ぴいいいいいいいッという、村長の放屁。
「ほう。屁まで。ワンコロ。君は貴重な瞬間を耳に捕らえた。放屁などなかなか聞けるものじゃない。放屁というか、あれは村長の慟哭だ。願いだ。祈りだ。
神に語りかける神聖な……おい、おまえ、笑ってないか?」
「笑って、ません」
「腕、どかしてみろ。なぜ顔をかくす」
「いえ」
「ちょっと待て。おまえ、めっこん音頭をバカにしてないか?」
「そ、ぷぷぷ、キャ!」
「おいッ! テメエ! なに笑ってんだマジでッ!!」
ケムマキが私の髪を掴むと同時に、ひとりの少女が皆の前に躍り出ました。
 「やあ、バカだ」
「やあ、バカだ」
「ジャンプしかできないバカ」
「またやってら」
「親も親なら子も子だなあ」
「いひひひひひひひひひひ」
耳をつんざく笑い声。少女はへらへら笑いながら、元気よく跳躍を繰り返しました。
「あの娘は?」ケムマキに聞くと、彼は顔をまっかにし、「うるさい!」と俊敏に駆け、少女の襟を掴みました。
縁側から庭へ少女を放り、一升瓶を手にして一気に飲み干しました。
「くそ、うろちょろしやがって」
村民は肩をすくめ、再びめっこん音頭に集中したフリをしました。
ケムマキは忌まわしげに酒を飲み続け、祭が終わりを迎える前に酔いつぶれてしまいました。
「ジャボ嬢じゃよ」後ろの老婆メイドが、沈痛なおももちで語りかけてきました。
「ジャボ嬢……」
「メド子の子供」
私は拍手を打ちました。そういえば子供がいると言っていた。
「父親はケムマキ」
「え」
「ジャボ嬢が産まれてくるまでは仲良かったからねえ。あのふたりは」
私はいたたまれなくなり、祭の片付けもそこそこに、庭先へ向かいました。
植え込みの陰で、ジャボ嬢はへらへら笑って跳躍を続けていました。
視線の彼方には見事な満月がありました。
「ジャンプ上手だね」
私はジャボ嬢に話しかけました。
彼女は跳躍をしながら答えました。
「あたし、頭ばかでお金もないけど、ジャンプだけは負けないんだ」
「見事なジャンプだね」
「だからあたし、柿を盗むのうまいんだ。秋になったらお姉ちゃんにもあげるよ」
少しお酒が入っていたからでしょうか、私もジャンプしたくなり、
彼女にタイミングを合わせながら跳躍しました。
「へへへへ」
「きひひひ」
「危ない!」
唐突でした。
ぶうん、とうなりをあげ、地を覆うほど巨大な物体が滑空してきました。
私は彼女を抱きかかえ、地面に伏せました。
巨大なそれは私の頭をかすめ、家屋の中へ入っていきました。
「村長の腕だ」
私は叫びました。
「みんな食われるよ」ジャボ嬢は興奮して、きゃきゃと跳ねました。
「この村のみんなは村長の食べ物なんだ」
 「ぎゃああッ!」
「ぎゃああッ!」
「でいとん!」
阿鼻叫喚地獄絵図。
クレーンのアーム部分のような村長の腕は、村民に襲いかかりました。
これは後から聞いた話ですが、めっこん音頭は豊作の為の人身御供の儀式。
異常なまでに激しい踊りは、残りの生命力を燃焼し尽くすという意味があったようです。
「お姉ちゃん助かったね」
ジャボ嬢は哄笑しつつ、野良猫のように走り去って行きました。
いくら時給二千円といえども、もう堪えられません。
庭先に出ていなかったら私も握りつぶされ、殺されていたのです。
逃げよう。逃げきろう。
震える四肢に力をこめ、踵を返すと……。
竹ヤリを構えるケムマキが、そこにいました。
「どこに行く」体勢を低くし、私の鼻先にヤリの先端を押しつけました。
「ジャボ嬢がどこか行っちゃったから」
「あのガキと関わるな」
「……はい」
彼は機敏にヤリを引っ込めると、屋根の上方をアゴで示しました。
「村長の食事が済んだら吸殻を大量に投げ込んでおけ。村長は噛みタバコが好きだ」
がりがりがり、ぺき、ごきゃ。
骨と肉が噛み砕かれる音。あまりの恐怖に眩暈がしてきました。
「ご覧の通り村民が少し減った。50名ほど募集をかけておけ」
「募集を」
「キャッチフレーズは『農地無料! 家屋無料! 150歳までOKのエコライフ』……これで都会からバカが大量にやってくる」
「私みたいな」
精いっぱいの皮肉に、ケムマキは舌打ちで答えました。
 そういえば。
そういえば。
ケムマキはジャボ嬢を「食事」がはじめるまでに摘み出しました。彼なりの愛情表現だったのでしょうか。
それよりも。
明日の村長のウンコ掃除を考えると、気分が滅入ります……
なんとか逃げ出さなければ。
朝一番。子蝿が飛び交う居間。
従業員総出で村長の糞尿掃除に励みます。
臭い。苦い。ビジュアル的にディープすぎる。
嗅覚も視覚も破壊されそうでした。
昨夜、数十の村人を食したその日の糞便には、未消化の臓物や骨が混じっており、私は嘔吐と嗚咽を交互に繰り返しつつ、それでもスコップを振るいました。
 「まんず、ハァあなどれんクソじゃこと」
「まんず、ハァあなどれんクソじゃこと」
「これが現金じゃったらのう」
「わははははははははははは」
老婆メイドたちは手馴れたもので、涼しい顔で作業をこなします。
巨大な糞便によりかかり、お茶と和菓子で雑談をはじめました。
よくこんな状況でまんじゅうなど食べられるものです。
しかも、昨夜の食人騒動で同僚のメイドが二名食べられたのにも関わらず、彼女たちは平然としていました。
クソまみれの老婆のひとりがラジカセのスウィッチを押し、ジャズ・メッセンジャーズの演奏を流すと、作業が再開されました。
糞便を畑に撒き、こしらえた昼餉(ひるげ)を並べ終えると、裏庭にジャボ嬢があらわれました。
「お姉ちゃん、遊ぼうよ」
私が首を振って断ると、彼女は四つんばいで遠吠えをはじめました。
あたりをうかがいつつ首を縦に振ると、今度はバッタのように跳躍しました。
村はずれの河川敷でスイカを食べました。
河の流れも気候も穏やかで、言いようのない安堵感に包まれました。
このまま逃げてしまおうか……。
「お姉ちゃんはどこから来たの? マイルドセブン?」
ジャボ嬢の声にはっと我にかえりました。
「なにしに来たの? スターバックス?」
「私はねえ……ジャンケン屋を経営してたんだ」
スイカを川に捨て、対岸の雑木林に目をやりました。
母のジャンケンは、それはもう相当なものでした。
相手の顔の造形、仕草、言葉から、最初に何を出すのか判断し、その勝率は常に七割をキープ。
ジャンケン屋のシステムは至極シンプルなもので、まず、相手が掛け金を差し出します。
母が勝てばその掛け金は母のもの、負ければ二倍の金額を相手にさしだします。
適度に勝たせ、適度に負けさせ、満足に帰っていただく。それが母の信条でした。
その日、母は勝ちすぎました。
私の大学の入学金を稼ぐため、焦っていたのでしょう。
全力のグー。豪快なパー。先代から受け継ぎし伝説のチョキ。
もはや対戦相手は、お客ではなく金銭を運んでくる何かと化していました。
逆上したチンピラの刀で真っ二つにされ、母はこの世を去りました。
店を継いではみたものの、私には母のような才覚もなく、連日連夜負けを喫し、虚空にほえ面を刻むのみ。
金銭は尽き、野望も尽き、失意のうちにジャンケン屋の看板をたたむことになりました。
そして今。
毎日ウンコ運んでいます。
 私の話を理解したかしなかったか、ジャボ嬢は腹を抱えて笑いました。
私の話を理解したかしなかったか、ジャボ嬢は腹を抱えて笑いました。
「なあんだ。セブンスターだったのか」
胸に芽生えた殺意を押さえ、私は彼女を抱き寄せました。
「ジャンケンの才能もないし、ウンコを見ると吐いちゃうし。私って何もできないんだ」
「あたしと同じだ」
ジャボ嬢と私は、笑いあいました。
ジャボ嬢に引っ張られるまま、傾斜のきつい山道を駆けます。
ちょうど夕方まで、従業員たちのマリファナ・タイム。
私ひとりくらいいなくても支障はありません。
うっそうと繁る草むらをかきわけ、小川を越え、ひたすら奥へ、奥へ。
ジャボ嬢の家……つまり、メド子さんの住居に向かっているのです。
ピンクサロン、つまり、男性器を吸ったり揉んだりする店を経営していることを思い出し、不安な気持ちになってきました。
「ここだよ」ジャボ嬢が指で示した住居は、凶暴なビジュアルでした。
「これが……あなたのおうち」
外装には、(男性器吸い込み術・特許出願中)
(Tポイントたまります)といった文句がつづられ、常人ならば足を踏み入れるのに躊躇してしまうハードコアさです。
ジャボ嬢は私の腕をぐいぐい引きます。
 「うちの母ちゃん凄いんだ。どんなチンチンでも軽々とやっつけちゃうんだ」
「うちの母ちゃん凄いんだ。どんなチンチンでも軽々とやっつけちゃうんだ」
「そう。頼りになるね」
「もう少しすれば、すんごい行列ができるんだから」
メド子さんの眼光が、暗い室内で不穏な光を放ちました。
「なんだ。ワンコロか」彼女は布団を跳ねのけ、座りなおしました。
「へえ。うちのガキと仲良くなったんだ」
ジャボ嬢は私の腕にぶらさがり頷きました。
「具合はどうですか?」
「ああ……ガスバーナーのおかげで健康そのものだよ」
「ジャボ嬢にはツボ押し、しないんですか」
問うと、彼女は自虐的に笑いました。
「自分の子供に、そんなくだらないことできないでしょ」
「チンチン吸いは?」
「やらせるわけ……それ以上聞かないでよ。悲しくなってくる」
私はロウソクにマッチで火をつけました。
淡い光が室内を照らします。ブリキ缶に入ったしわくちゃの紙幣、ごわついた手ぬぐい、割れたカップ、あたりに散乱する吸殻……目を引くものといえば、壁に全身のツボ図面があるだけ。
生活感のない部屋でした。
もっといえば、あえて乱雑にすることによって生活臭を隠している印象をもちました。
ジャボ嬢は絶叫しながら部屋を駆け回り、転倒して後頭部を強打、その場でしくしく泣き始めました。
「まあ、親子そろってこんな感じだからさ。頼れる人がいないんだよ」
「村から出ましょう」私は毅然として言いました。
彼女は鼻で笑いました。
「どこ行っても変わらないじゃないの。赤の他人のクソを片付けて、チンチンを勃たせた男がいて、それをあざ笑う女がいて、ケムマキみたいなキチガイに頭を下げて、酒だか小便だかわからないモノをうまいうまいって飲んで……どこも一緒でしょ」
「かもしれないけど」
それ以上、先を口にすることはできませんでした。
なぜかは分かりません。
「あたしはベロさえあればどこでも食っていけるからね。余計なお世話だよ。
けど、ありがとう」
メド子さんは丁寧におじぎしました。
「母ちゃん、お客さんがたくさん来たよ」
私たち三人は、窓から外を覗きこみました。
 その団体の手には、それぞれ松明(たいまつ)がありました。
その団体の手には、それぞれ松明(たいまつ)がありました。
「あれは男衆じゃないな」メド子さんは舌打ちしました。「村の女衆だ」
ジャボ嬢は怖がって蒲団の中にもぐりこみました。
メド子さんは私をキッとにらみました。
「私が連れてきたんじゃありません」
「いや、そうじゃなくて、ジャボ嬢を連れて逃げてくれ。この村の外に」
「出て来い淫売!」
女衆は小屋を包囲しました。
「貴様は村の恥部じゃ」「亭主をたぶらかしおって」
メド子さんは窓から身を乗り出し、鋭く睨めつけました。
一同は後ずさりつつも、痛罵を繰り返しました。
 「二十五にもなるのにオスッコのチンチンばかり吸いおって。恥を知れ」
「二十五にもなるのにオスッコのチンチンばかり吸いおって。恥を知れ」
「歯がガタガタでチンチンも吸えん能無しには言われたくない」
メド子さんは怒鳴りかえしました。
「あんたらの旦那は、村長のケツ拭きする嫁より、ミイラ女のほうがいいんだってよ」
「なにを」
「燃えちまえ」
数本の松明が投げ込まれました。
メド子さんはバタフライナイフを手に、玄関ドアに手をかけました。
私はジャボ嬢を背負い、裏戸まで駆けました。
ガソリンが撒かれたのか、部屋は瞬く間に炎に包まれました。
「ババアどもなんか放って逃げましょう」私は呼びかけました。
「以前から嫌がらせを受けてたんだ。三、四人の首を掻き切らなきゃ気がすまない」
「けど」
彼女は目だけで微笑みかけ、
「すぐ追いつくから。腐れ橋で落ち合いましょう」ナイフを高々と構え、
表へ走り出ました。
腐れ橋は、他県に繋がる唯一の道。
道なき道を進み、山をみっつ越えればバス停があります。
私はジャボ嬢を背負ったまま、炎上する家屋から抜け出しました。
転がったり木に衝突したりし、ひたすらまっくらな斜面をくだりました。
家屋が密集する村の入り口。
月光に鈍く光る青銅製の男性器。
村の象徴。
人のような影を路地に落とす木製の電柱。
あたりは不自然なまでにひっそりしていました。
背中のジャボ嬢は状況が理解できていないようで、ただクスクス笑うばかり。
「お姉ちゃんどこ行くの?」
「他人のウンコ掃除しなくてもいいところ」
「そんなところ、地球にはないよ」
幅一メートルほどの腐れ橋を忍び足で進み、対岸の草むらで息を潜めました。
そこでやっと、大きな息をつくことができました。
意外に簡単に出られた……。あとはバス亭まで走って、駅まで向かえば何とかなる。
お金を持ち合わせていないけど、交番で貸してくれるかもしれない。
その後は、その後はどうすればいいのだろうか。
メド子とジャボ嬢は、この尿道村以外で生きていけるだろうか。
そもそも私も……などと考えつつ、黒々とした対岸の村に目をこらしていると、
「誰を待っているんだ?」
ケムマキがしゃがみこみ、耳元でささやいてきました。
「……」
「答えろ」
「お友達と……」
「メド子なら今、村長に食わせたよ」
「……」
食べた。
食べさせた。
元・妻であるメド子さんを。
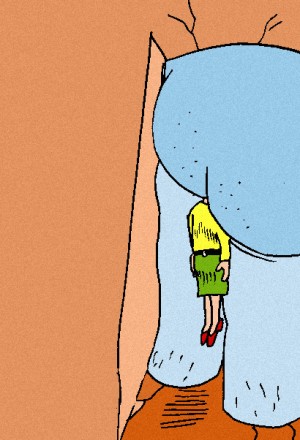 「彼女に会いたいなら、会わせてやろう」
「彼女に会いたいなら、会わせてやろう」
彼は日本刀の先端を、私の頬に当てながら言いました。
「村長の直腸でな。溶解した彼女を拝むがいい」
「どうだ。会えたか」
「いえ。まだ」
「どんな気分だ」
「ここより、ドトールのほうが快適かと」
「あそこのアイスコーヒーうまいよなあ」
「ええ」
「呼吸は?」
「苦しいです」
「タバコより身体にいいだろう。普段がんばってもらってるから私からのボーナスだ。従業員の待遇は良くしなければならん。遠慮しないで二泊三日ほどくつろいでくれ」
日本刀を鞘から抜いたり、収めたりする音。
「三日後、新しい村長の就任式がある」
「……」
「誰だと思う」
「ケムマキさんですか」
「そうだ。ジャボ嬢を連れ去られては困る。あの娘は私の唯一の失敗だ。村長就任式の際、過去を浄化するという意味で、村民たちの前でヤツを食さなければいけない」
「食すって?」
「だから、そういう儀式だよ。この村にいれば分かるだろ。ケツの穴に頭を突っ込んだまま見ていてくれ。難しいだろうが」
ケムマキは高笑いしました。
だから「めっこん音頭」の時、ジャボ嬢を助けたのか……。
もはや逃げる逃げないの問題ではなく、懲罰を終えたらこの村を破壊しよう、そう決意しました。
涙も枯れ果てた肛門の中。
私はとある恐怖に襲われていました。
いつ、村長の糞便が押しよせてくるか分からない。
そうなれば私は窒息して死んでしまいます。
人様の肛門に押し込まれ、口に糞便を詰め込まれ人生を終える。
人間としてこれ以上悲惨な死に方があるでしょうか。
来る……人智を凌駕する量の糞便が……それに呼吸が細い……酸素の量が足りない……苦しい……
村長の括約筋はけっこうなもので、いくらもがいても脱出は不可能。
体力を消耗するだけなので、暴れるのはやめました。
せめて放屁をしてくれれば、その圧力で出られるかもしれませんが。
赤ん坊がこのような気持ちなのでしょうか。生への不安……
「おい。ワンコロ。おい」
幻聴が聴こえます。
「おい。あたしだ。起きろ」
 幻聴……幻覚……違いました。
幻聴……幻覚……違いました。
「何してんだおまえ。世界広しといっても肛門で再会するなんてなあ」
メド子さんは、確かにそこにいたのです。
「た、食べられたんじゃなかったんですか?」
「うん。けどあたし、自分で自分の身体を焼いたり叩いてたりしてるじゃない。(☆第二話参照)村長の胃酸でも溶けないくらい頑丈になってたみたいだね。飲み込まれただけで、噛まれなかったのが幸いしたよ」
私は今までのことを話しました。
新村長にケムマキが就任すること、そのときにジャボ嬢が食べられてしまうこと。
メド子さんの目が怒気でみなぎりました。
「あたしの子を食うだと? さんざん人をもてあそんで、あんな山奥に押し込んで、あげく村長のエサに……。くそっ。どこに行ってもケツの穴だよ」
「あの、メド子さん。私を押せますか? とりあえずここから出られれば」
「村長の腸が蠕動して、もう少し距離が縮まればなんとか。けど、出たところで同じ結果になるだけだよ。あのババアどもスナイパーライフルまで装備してやがったし」
ふうむ、と私たちは腸の中で対策を練りました。
「……メド子さん。いいことを思いつきました」
「?」
「ツボに詳しいんですよね」
彼女は怪訝そうにまばたきしました。
「とりあえず私の手足は自由です。村長の身体の向きを回転させたいんですけど、そういう筋肉運動を促すツボってありますか?」
そして三日後、村長就任式の刻がやってきました。
村人は一同に介し、ケムマキが登場するや否や、へりくだって頭を下げました。
三日目ともなれば肛門が緩くなってきて、私は居間の様子を窺えるようになりました。
テーブルに乗せられたジャボ嬢が彼の前に運ばれてきます。
そっと頭上のメド子さんに伝えると、彼女は小声で「いい位置ね」と答えました。
 「今日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます」
「今日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます」
ケムマキは後方の村長を一瞥しました。
「ほう。ひさしぶりに村長の尻がこちらに向いている。皆様。これは吉兆です。あの時は山本さんの奥さんがご懐妊されましたな」
万雷の拍手が鳴り響きました。
「あたしが妊娠したときはバカみたいに喜んでやがったくせに」
メド子さんはひとりごちました。
「私、ケムマキは……皆様ご存知のように、かつて悪魔のような女と付き合っていました。いえ、いま思えば、悪魔そのものでした。
不貞、不埒(ふらち)、意地汚く、しかし悪魔特有の色香だけはありましたもので、当時若かったということもあり、狡猾な魔力に抗しきれず、このように歪(いびつ)な子を生誕させるに至ったのであります。村の皆様には多大な迷惑を、くっ!」
ケムマキはうそ臭い涙を流しました。
「あんたは悪くないんじゃ」「そうだ! あんたがどれだけ村に貢献してきたか!」
「そうじゃ。村長を肥料生産マシンとして考案したのもアンタじゃし」
「ありがとうございます。私は今日、忌まわしい過去の塊……つまりこのジャボ嬢を胃袋に入れることによって過去を浄化します。そして明日からはより一層、村に貢献していきたいと思います。新・村長として!」
割れんばかりの拍手。
メド子さんは声を震わせ呟きました。
「この村で、一番でかいウンコは、あいつだ……あたしはアイツと結婚するまで、他の男衆に指一本触れさせなかったのに」
ジャボ嬢は訳もわからず、台の上でまどろんでいました。
ケムマキは高潮した顔で咆哮を上げると、村人達はジャボ嬢を取り押さえました。
「今だ」私は叫びました。
メド子さんは身体をよじって、私を外へ押し出しました。
 「今だ!」
「今だ!」
それは史上空前の糞尿地獄の幕開けでした。
スポンッと肛門の外に出た私とメド子さん。
たまりにたまった村長の糞便が、激流のように溢れました。
「うわあ」「ギャアッ」
三日間。
コルクがわりだった私たち。
今、めでたい日のはなむけに、下劣きわまりないシャンパンが開け放たれたのです。
「おめでとう!」
「おめでとうございます! クソ野郎!」
私は即座にジャボ嬢を救出、巨大な固形のウンコをサーフボードがわりに濁流を滑走しました。
サーフィン経験があって良かった……
 ウンコの上でバランスをとりながらのサーフィンは非常に難易度が高いものでした。
ウンコの上でバランスをとりながらのサーフィンは非常に難易度が高いものでした。
メド子さんの安否が気になりましたが、美空ひばりの歌にもありますように、今はクソの流れに身を任せるしかありません。
 良識も常識も格式も略式もクソもなく、いや、クソだけがあり、禅道でいう「一は一切であり一切は一である」という言葉を模(も)せば、まさしくクソは一切であり一切はクソであるという、ファンク極まりない状況でした。
良識も常識も格式も略式もクソもなく、いや、クソだけがあり、禅道でいう「一は一切であり一切は一である」という言葉を模(も)せば、まさしくクソは一切であり一切はクソであるという、ファンク極まりない状況でした。
私の頭の中はWARの『ロウライダー』がけたたましく鳴り響いていました。
少なくともその場にいた村民たちは、濁流の彼方に消え去りました。
私とジャボ嬢は、「腐れ橋」のたもとまでたどり着きました。
逃げられた。
逃げ切った。
出し切った。全力を。
村長が出し切ったから、こちらも出し切れた。
ダシキラレタからダシキレタ。
「へ、へへへへへへ」
自然に笑いを発していたことに気づき、とっさに喉元を押さえました。
いけない。正常な思考が鈍磨しつつある。
はばかりなく嗚咽すると、無垢な笑みを浮かべたジャボ嬢が背中をなでてくれました。
「ありがとう」
おかしい。この村は。完全に狂っている。
今さら。本当に今さら、気づきました。
順応しつつあった自分の適応能力が恐ろしくなりました。
「おうい」
息を切らせ、全身の包帯を茶褐色に染めたメド子さんが駆け寄ってきました。
その場にへたりこみ、ジャボ嬢を抱き寄せました。
「ワンコロ、あんたもクソまみれだな」
「えっ」私は自分の髪、顔、衣類を触りました。
「川に、川に飛び込まなきゃ。あ、に逃げなきゃ。そうだ。ケムマキが追って」
錯乱する私をなだめるように、メド子さんは後方を指さしました。
「逃げるのも川に飛び込むのも後にしなよ」
 そこにはケムマキをくわえた村長が直立していました。
そこにはケムマキをくわえた村長が直立していました。
「村長が……なんで?」
「脱糞のショックかどうかは分からないけど、まだ村長の座は譲りたくないみたいね。さて。何をしでかすか」
糞尿をぶちまけた挙げ句、村長はおのれの自尊心を固守するため、めったくそに集落に殴打を見舞いました。
跳ぶ木、飛ぶ火。
家屋を裂き肉を裂き、無数の自我を田畑を踏みしだき、けたたましく咆哮をあげながら村長はコブシを振り回しました。
村人の叫喚にリビドーを感じたのか、彼の巨大な陰茎は赤黒く怒張しきっていました。
射精しては壊し、壊しては射精する。
白い花火にように拡散する精液は、妖艶な高級娼婦の如く身をくねらせる業火とともに、虚空を汚しつづけました。
 ケムマキを上下の歯ですり潰しつつ、炎を衣とし、糞とよだれをあたりに撒きちらし、彼は自らを鼓舞するように絶叫、私たちは呆として見上げるしかできませんでした。
ケムマキを上下の歯ですり潰しつつ、炎を衣とし、糞とよだれをあたりに撒きちらし、彼は自らを鼓舞するように絶叫、私たちは呆として見上げるしかできませんでした。
壊。
解。
怪。
築き上げた尿道村の歴史を蹂躙、滅殺、無垢な破壊の美に、天も地も恍惚としているようでした。
「まあ、要するにバカげた光景ってことでしょ。コレ」
メド子さんは肩をすくめました。
私は頷(うなず)きました。
派手に暴れているようだけど、自分の墓を掘っていることに変わりはない。
 案の定、村長は自らがこしらえた火炎と瓦礫に、ゆっくり身を沈めました。
案の定、村長は自らがこしらえた火炎と瓦礫に、ゆっくり身を沈めました。
「村長も大人になったなあ」
メド子さんはジャボ嬢の頭を抱き寄せました。
「自分のケツを自分で拭けるようになるなんて」
村長の姿が噴煙に消えると。
濃紺の静寂。
私たち三人は、よく訓練された兵士のように踵(きびす)をかえしました。
「腐れ橋」の対岸。
さらにその向こうの世界。
きっとクソまみれの未来が待っていることでしょう。
それは承知の上です。
新たなクソを求め、新たなクソにまみれるため、私たちはクソだらけになりながら、クソまみれの夜空の下、クソを落としつつ、それでも泰然と歩を進めます。
他の人となんら変わりはないのです。
「都会っこのチンチンはどうなんだろうなあ。手強いかなあ」
メド子さんが言いました。
「まだ吸うつもりですか」私はため息をつきました。
「母ちゃんはそれしかできないもんね」ジャボ嬢が能天気におどけました。
「ジャンケンを教えますよ」
「なんだ? ジャンケンって」
「ギャンブルの一種です。チンチンを吸うより面白いです」
「へえ……ツボ押しよりもか」メド子さんの目に生気が帯びてきました。
 私たち三人は脳みそが腐っているので、難しい稼業には縁がありませんが、少なくともグー、チョキ、パーが揃えば、ジャンケンは成立します。
私たち三人は脳みそが腐っているので、難しい稼業には縁がありませんが、少なくともグー、チョキ、パーが揃えば、ジャンケンは成立します。
頭のいい人には分からないかもしれないけど、本当に、本当に、本当に、本当に成立してしまうのです。























"尿道★ワンコロ"へのコメント 0件