1
アキラは歌手だった。その前は球体関節人形を製造するメーカーの事務員だった。
本社から振り込まれた小口現金を下ろすため、鼻歌混じりに銀行へ向かっていたときのこと。「やったんだ、俺はやったんだ」という叫び声が聞こえたので視線を向けると、メルセデスの上で飛び跳ねている何かを見つけた。それは体じゅうを金箔に包まれた全裸男で、ルーフをまるでトランポリンのように扱いながら人生を謳歌していた。彼はキース・ヘリングが描いた人間のように、大の字になったまま太腿から、肩から、あらゆる角度からルーフに落ちては跳ね返った。メルセデスのフロントドアには楷書体で「勝利」と印字されていた。
「君もあんな風に、なりたいだろう?」咄嗟に振り返ると胡桃色をしたネクタイの男が立っていた。ピンを三本も付けていたのが印象的だった。「おめでとう、何も言わなくていいからここにサインしたまえ」と、契約書を突き出された。彼はレコード会社のプロデューサーで、潮干狩りに行くと言い残したまま先月失踪した女性歌手に代わる人材を探していた。「母さん、俺はまだやれるよ」と叫び続ける金箔男に彼女が目を凝らすと、それはテレビでたまに見かける新鋭歌手だった。「君の歌声なら、メルセデスなんて目じゃない。この世界を獲れるさ」まるで他人事のように笑いながら、ネクタイの男は唐突にピンの一つを食べはじめた。それらはよく見ると、黒ゴマが練り込まれたおかきでできていた。「君も一つどうかね? おっと、ザラメ糖は残しておいてくれよ」勧められるがままにアキラはおかきを頬張りながら考える。何故私の歌声を、と尋ねようとして、少し前に自分の口から自然と旋律がこぼれていたことに気づいた。この紙切れをどうしたものかと思案しながら、彼女はプロデューサーをザラメと名付けることにした。ザラメ糖のおかきを見ていると少し甘いものが欲しくなり、鞄から好物の金平糖を彼女は取り出して舐めた。
熟練のプロデューサーの耳にも、アキラは申し分なかった。彼女の声には、幾層もの揺らぎがたたえられていた。色の違う炎を重ね合わせたような、神秘的かつ幽玄で、捉えどころがない。人間にはまず産毛があり、それから表皮、真皮、肉があり脳や心臓の向こう側に心があったりなかったりする。彼女の声はどうみても一枚岩ではなく、あまりにも有機的でそれは声自体がひとつの見えない生き物のように思えた。聴いた者を恍惚とさせるあまり、その声を鋭いメスで突き刺して透明の返り血を浴びることができたらとしばしば妄想させた。
アキラはおかきを二つ食べておいて礼を言い、再び銀行に足を向けようとした。歌は彼女のものであり、歌うのに歌手になる必要はなかったからだ。ザラメ氏は慌てて呼び止め、契約の条件にファースト・アルバムの内容については好きにして構わないという内容を加えた。彼女はグラフィティ用のスプレー缶を大量に買い漁る悪ガキの気持ちが少しわかったような気がして、契約書にサインしたのだった。
2
ザラメ氏のプロデューサーとしての手腕は確かなものだった。アキラの好きなように泳がせながらも、最低限のポップ加減は維持するように自然と誘導しつつ、ファースト・アルバムの制作を進めた。彼女は事務の仕事とレコーディングの両立が難しくなり、勤め先に辞表届を提出した。残った有給休暇を消化し、最後に保険証の返却のため事務所に顔を出した。彼女は、オフィスの隅で横たわっていたサンプル用の巨大な球体関節人形を抱え、そのまま家に持ち帰った。それは様々な人形のパーツが無秩序に組み合わされていた。一見、ばらばらに思えるシリーズのパーツ同士でも、内部的に実は規格が共有されているものも多々有り、それらの検証のために継ぎ接ぎされた残骸であった。決して社員の他意による悪戯というわけではなく、ただ悲しき資本主義的都合の成れ果てに過ぎなかった。
頭部は、カップラーメン「ぶたけつ壱番館」の蓋に描かれたイメージキャラクター「ぶたけつくん」の顔。胴体と腕は、一切薬物を使用しなかったにもかかわらず、極限までステロイドを射ち込んだ選手よりも筋肉量が上回っていたと伝えられるボディービルダー「ジ・アトラス」をフィギュア化したもの。下腹部は、雑多に色んな人形の関節が芋虫のように連なっており、最後尾に知育玩具「みるみるミルクちゃん」の下半身が取り付けられていた。それらは取り留めのないように見えたが、色合いや質感は統一感があり元からそういう製品だったかのような説得力があった。
驚くべきことに、彼はアキラの呼びかけに応じる心を持ち合わせていた。「ぶたけつくん」の頭部は元々ラジオとして設計されており、頭頂から小さなアンテナが突き出ていた。これが奇遇なことに、耳の役割を果たした。アキラの業務時間中の鼻歌を受信してしまった彼は、それがあまりに素晴らしかったため、感動するにふさわしい自我を持たざるを得なかったのだった。
その球体関節人形は食事はできないし、少なくとも外面上は笑ったり泣いたりしなかった。喜怒哀楽を放てない分、その心は繊細に出来ていた。アキラの食事中は読書の傍ら、彼女の悩み事を辛抱強く聞いた。巷の男達のように具体的な解決策は提示することなく、自分の心を彼女へ重ねるのに努めた。また詩的な一面があり、アルチュール・ランボーを好んだ。彼はアキラ自身に陶酔しきっていた。彼女の歌そのものが生命を持って自由に生きるためには何が必要とされるのかを、常日頃から意識していた。アキラの歌声を栄養としている向きさえあり、頭部のアンテナを失えば彼の自我も消滅するに違いなかった。アキラは彼をオゥ・ララと呼び、いたく気に入った。風水に良さそう、というくらいの気持ちでくすねてきたのに。こんなに私の部屋に馴染むなんて。
3
ようやくアキラのファーストアルバムは完成した。彼女の声はまたたく間に中毒者を量産し、人づてに存在が知られるようになった。彼らの興奮と汗が乾ききらぬうちに、ザラメ氏は次のアルバムで勝負を仕掛けた。万人に通じる、最大公約数的なポップ性をふんだんに散らしつつも、それらは見えないよう巧妙に隠された。「夜ってカリスマみたいだろう? 誰のものでもないはずなのに、誰もが自分だけの時間だと錯覚する。そんなアルバムに、なったらいいねぇ」自分でミキシングをやりながら、まるでお祖母ちゃんがシチューにおまじないを唱えるみたいな口ぶりでザラメ氏は呟いた。
かくして生まれたセカンド・アルバムは、ザラメ氏によりここ一番の予算が投入されたプロモーションをもって世に放たれた。渾身の作は、各誌面上にて非常に高い評価を獲得した。「声の第一印象は透き通っている。だが煤けているようでもあり、また七つ子が同時に喋っているようでもある」「本来は時系列を伴って体験すべき物語が、左手にエピローグ、右手にプロローグを引っ提げて私を抱きしめたような感覚に陥った」等々、弁舌には覚えのある批評家から絶賛が飛び交った。アキラはあっという間に歌姫として祭り上げられた。
アキラは極力、メディアには露出しなかった。彼女が必要としたのは、歌うことまさにそのものであり、世俗的な名声ではなかった。しかし世間は、彼女の異彩が際立っていくにつれ有名人としての文脈の中で消費したがるようになった。その卑近な需要を満たすため、塵一つ出やしない彼女の周辺をパパラッチが徘徊するようになった。スタジオの前で、ほんの少し挨拶しただけのエンジニアとの熱愛が報じられ、これはアキラを強く辟易させた。平穏を取り戻すため、しばし考えた末に一計を案じることを思いついた。
彼女は前触れなく、プレスに向けて一枚の写真を送りつけた。そこにはアキラのウェディングドレス姿とオゥ・ララのタキシード姿が映っており、小さく婚姻の旨がサインとともにあしらわれていた。「稀代のディーヴァ、ぶたけつクリーチャーと結婚か」という速報はあらゆるメディアを席巻し、地球の人々は思考停止した。パパラッチ達は自分がなにもわからないということがわかり、ただうなずき、やがて既婚者になったアキラに近づく芸能関係者は減っていった。
4
一週間後、アキラはオゥ・ララとの式を挙げた。彼女は近親者だけのささやかな結婚式にしたかったが、親族でもないザラメ氏によって業界関係者も巻き込んだ大掛かりな式に仕立てられてしまった。ザラメ氏は彼女を引き連れ、「これも営業の一環よ」などとうそぶきながら方々の顔役に挨拶回りをした。レトロ印刷でよく発生する「版ズレ」の技術を音像にも転用できるレコードメーカーの社長。小さな天使たちに合唱させたり、オーケストラも演奏させられる派遣会社の専務。ボイジャーのゴールデンレコードよろしく、自分だけの歌を録音したレコードを宇宙に打ち上げられるベンチャー企業の部長。数えるのが面倒になるほどの名刺交換が繰り返され、オゥ・ララは自分の結婚式が異業種交流会にすり替えられていく様をまじまじと眺めるほかなかった。寄る辺なき彼はアキラの父親に挨拶をしたが、伏し目がちな会釈をもってその存在ごと避けられた。
オゥ・ララは、妻を愛していたがその家族を好きになれなかった。父親と兄二人の四人家族。母親はアキラが四才の頃に亡くなった。内向的なアキラとは正反対に彼らは際限なく明るく、この世から月を盗まれて夜が消えてしまったとしても何ひとつ困らない。そんな屈託の無さが、余計に新郎の肩身を奪った。
彼女の父親は上場企業の商社マンで、兄二人には仕事の流儀を背中で語ってきた。一方で末っ子のアキラについてはのびのびと、悪くいえば仕事を理由に構うことがなかった。兄二人はお互い歳も近かったため、年がら年中競い合い、また親友のように近しかった。歳の離れた妹に対してはおまけのような扱いで、常に距離があった。商社マンであった父の頻繁に繰り返される転勤は、多感な時期にあった少女から友達を作る機会を奪った。彼女の歌声は、何人もの子供が合唱していると錯覚するほどに厚みがあるが、その子たちはきっと未だにアキラを放っておけないイマジナリー・フレンドなのだ。オゥ・ララはそのように分析していた。
この父親は娘を、また兄二人は妹を、確かに愛してはいるだろう。しかし彼らの関わり方をオゥ・ララが観察していると、歌手として成功した家族の名誉をしつこく称え続けており、その愛には条件が付随しているような危うさがあった。彼女の声をどこまでも深く沈んでいった奥に仄暗く幻想的な泉が広がっていることなど、家族の誰一人として知る者はいないだろう。
アキラ以外の全てから、異形の新郎は無視されていた。世間は当初、球体関節人形との結婚に面食らっていたが、次第に歌姫が結婚したという肯定的な事実のみを受け入れていった。メディア関係者は、我先にとばかりにアキラにだけマイクを向けた。新婦の父は、娘をミリオンセラーに導いた手腕に感謝しながらひたすらザラメ氏を持ち上げていた。それはまるでプロデューサーが新郎であるかのような扱いであった。本物であるはずの哀れなオートマトンは、どこまでもないがしろにされた。
散々な扱いであったが、彼はそれらを些末な取るに足らぬものとして押し殺した。オゥ・ララは、夫である以上にアキラの熱狂的な信奉者であることに誇りを持っていた。歌姫アキラと同じ空間で暮らしていることよりも、彼女の声の底にどこまでも(誰よりもね)深く沈み、その果てにある泉に触れられることが矜持であった。ボディビルダーのものである彼の腕は、丸太のようにはちきれそうだった。荒々しい印象とは打って変わり、その指先はあまりに繊細で優しかった。内気なアキラの音世界に、また心にも届きうる爪先は清潔に保たれており、彼の矜持を支えるだけの資格があるように思われた。オゥ・ララは心頭滅却の境地で耐えていたが、それでもガラスめいた心は雑音にあわせて軋みを立てた。アキラはその軋みが聞こえるたびに、厚顔無恥な連中を置いてけぼりにして夫の元へ駆け寄った。私のせいで、ごめんね。何度も耳代わりのアンテナに向けて詫びる彼女の言葉が、オゥ・ララにとって唯一の救いだった。
5
何はともあれ、これで音楽に専念できる。アキラはそう思ったが、悩みの種は尽きなかった。スタジオ・アルバムを立て続けに二枚も発売したのだから、向こう五年はじっくりと創造性の土壌を養いたいとアキラは考えていた。それに対し、いまが旬とばかりに三枚目を急ぐザラメ氏とは意見が対立した。あれこれと議論を交わし、具体的な時期については結局うやむやにはなったが、それでも彼女の望むペースで進行することは到底なさそうに思えた。
アキラは家にこもることが増えた。外では内気でも、心を許した者の前でだけはしゃぐ性格。いつもなら冗談をオゥ・ララに投げかけるアキラが、家の中でも鬱蒼としていた。彼女はうつむきながら、独りごちるように、夫にこう話しかけた。このリビングであらゆる時を過ごしてきたが、どの瞬間も、少しバツが悪い、と。いま、例えば台所の流しにもたれている自分の場面はひとつの層であり部品に過ぎない。月曜日から日曜日までの間、三日間はダイニングチェアで過ごし、二日間はカウチソファで寝転がり、一日はヨガマットで過ごし、残り一日はうろうろして過ごしたとしたらその一週間の中での揺らぎこそにこそ自分が宿る。時間は一日、一週間、一ヶ月、一年といった区切りの中を循環しているのであり、自分は今ここでなくその循環のドーナツの中心にいると彼女は確信していた。流れ星は乗り物ではなく、観測するからこそ願い事が届くのだ。オゥ・ララは三人掛けのカウチソファ──寝転がれるように彼女は三人掛けを選んだ──の一番左側に腰かけて、生真面目にアンテナを傾けていた。その場所を特等席としていた彼は、家の中ですらたゆたう妻を、どこにも行けない自分とは対称的な価値観を持った存在として認めていた。その一方で、この世に生身の人間として命を授かりながらも迷子のまま生きる妻に、何者でもない自分を重ねた。彼は、歌のみならず妻の地声をも愛していた。音源の中で流れる彼女の声よりも、その地声は低く、落ち着きがあった。多くを望まず、しかし何も見捨てはしない優しさと強かさを備えていた声。それは今や、彼を取り巻く生活の通奏低音として機能していた。あぁ、こんな日々が続けばいいのに。淡い気持ちとは裏腹に、彼はわきまえていた。一介のフランケンシュタインに過ぎない自分は、所詮は彼女の偽装結婚の相手でしかないと。
あなたは、ここにいるよ。ぶたけつくんの可愛らしい顔を妻に向けて、彼はそう囁いた。
6
異変は、その日起こった。三枚目のアルバムの打ち合わせのために、アキラはザラメ氏の事務所を訪れていた。そこに、あの金箔全裸男がメルセデスを乗りつけてやってきたのだ。曰く、最高級の金平糖が手に入ったから、アキラさんに差し上げますとのこと。それはラ・アッシュの入浴剤と見紛うほど馬鹿でかく、ほとんどザラメ氏の握りこぶしと同じくらいの大きさだった。でもアキラの大好物。これは凶悪な罠であった。金箔男は、彼女に嫉妬していた。アキラのデビュー以降、ザラメ氏は彼女に首ったけで自分に目をかけてくれなくなり、落ち目になる一方だったからだ。アキラはその金平糖を見るなり、やっと・やったぁ・やってすとと叫んだ。やったぁ三段活用。彼女はラグビーの試合中かのように突進した。金箔男の手から金平糖を奪い取り、丸呑みした。アキラの喉は爬虫類のように膨れ上がり、ザラメ氏は、アマゾン川の調査隊員が一人ずつアナコンダに飲み込まれていく怪奇映画を思い出しながら青ざめた。金平糖は、その突起により彼女の喉を傷つけながら胃に落ちた。彼女は少しえずいて味に太鼓判を捺したが、その声は明らかに光沢を失っていた。これは金箔男の思惑通りだった。「やったんだ、俺はやったんだ」金箔男は小躍りしながら勝利のVサインを作った。ザラメ氏は怒り狂い、千首観音の如くおびただしい手刀を金箔男に打ち込んだ。金箔男はぺしゃんこにつぶれた。ザラメ氏はすり鉢とすりこぎを持ってきて、メルセデスをすり胡麻に変えてしまった(いいとも、次はマセラティを狙ってやるさ)。ザラメ氏はすぐにアキラを病院に連れて行ったが、喉の傷は不可逆的なもので、もう治らないとの診断結果が降りた。
7
ポリポリポリポリ。ザラメ氏はネクタイに付けたピン、それもザラメ糖でできたとっておきをかじりながら山積みの新聞を次々と読んでいた。「歌姫アキラ、喉に大怪我か」「アキラ引退寸前」「契約終了との噂も、アキラ危機」という、本音ではさしたる関心もないくせに出歯亀根性ばかりが剥き出しになったいやらしい見出しの数々に、ザラメ氏は憤慨していた。「お里が知れるな、痴れ者どもめ。君の声がほんのちょっぴりしわがれたところで、子供がミルクレープを一枚剥がしてつまみ食いしたようなものだ。そう思わんかね?」ネクタイに二十個も付けていたピンがもう、あと三個。ポリポリ。人間は重圧がかかると食欲に逃げ道を見出してしまう癖があり、百戦錬磨のザラメ氏でさえその例外には漏れなかった。事件から二週間後、アキラは退院してザラメ氏との打ち合わせのためスタジオに来ていた。
彼女の喉の傷は癒えたが、声帯がわずかに変形しており以前の透明感は戻らなかった。しかし当の本人はというと、至って平静であった。ザラメ氏が指摘するように、自分の歌声の透明感はあくまで表皮であり第一印象でしかない。その下に無数の、どこまでも深く落ちていける層が重なっておりその厚み自体が彼女の本質なのだ。契約云々という下世話な話題はどこ吹く風で、保留となっていた三枚目のアルバムの方針について両者は討論していた。いっそのこと、二枚目でトップチャートを記録したのだから、今回はコアなファンに向けて実験作という体にしてよいのではないか。売上は望めないかもしれないが、引き出しを増やしてより深化する機会と捉えるべきではないか。アキラのそんな主張は、プロデューサーであるザラメ氏の耳には甘ったれ屋さんのどら焼き屋さんでしかなかった。
「金・金・金・オア・マニ、マニ、マニー! 我々はそんな世界に生きているのだよ。ようやく転がせる大きさに育った雪玉をまた小さくするトンチキがどこにいるね? 更なる成長こそが残された唯一の道なのだ。我々の置かれている状況を理解しているかね? 君のたわ言は商業的自殺に等しい。アキラ。君の喉の現状を逆手に取ってでも、売上を叩き出す活路を見出すんだ」ザラメ氏はまくし立てながらも、その前途は困難を極めると覚悟していた。
購買層のほとんどは、至ってライトなものだ。売上の大部分は、この人の声って透明感あるね、という反応に留まる人々に支えられているのであり、彼らはその奥にある煤けた香ばしさを知らなかった。喜怒哀楽だけでは受け止めきれず、指のすき間からもこぼれていく名前のない感情たちを彼女が代弁していたことにも気づかなかった。アキラはもう、このゲームから降りたかった。声色がほんの少し変わっただけで、別に歌いづらいわけではないのだ。ただ私が、私がいるここで歌う。それだけが変わらないのに、それ以外のすべてが過ぎ去っていく。春、夏、秋、冬の後に即、勝、殺、富みたいな狂った季節がずっと続いている。直線的で、輪になることを忘れて、まるでこの男みたいに。
ザラメ氏は、先ほど声を荒げた無礼を詫びるように、あるいは彼女の機嫌をとるかのように、大切なザラメ糖のピンを差し出した。君も一つ、どうだね?
要らない。一瞥だけくれてやり、アキラはスタジオを後にした。
帰り道がてら、アキラは父親から届いていたメールに目をやった。そこには、申し訳程度に喉の調子を労わる挨拶のあとに、今後のキャリア形成の指針について心配する内容がくどくどと続いていた。娘の健康より、そして本人の幸福よりも名誉を重んじる悪癖。この人は私をどこまで理解しているのだろう? それは少なくとも、娘の期待に応じられるほどではないのは確かだった。アキラは読むのを止めて、再び歩きはじめた。早くオゥ・ララのところへ帰りたい。そう思う気持ちについていけないかのように、足取りは重かった。
8
その夜、オゥ・ララは珍しく本棚の前にいた。妻が三人掛けカウチソファの真ん中に鎮座していたからだ。彼の特等席はカウチの左側である。ならば夫婦仲睦まじく揃って腰掛けてはいかがか? それは当然の疑問であり……ただ、彼のみならず誰でも、彼女のその時の表情を見れば……何か用事のひとつでもでっちあげて、妻に独りの時間を残してあげただろう。彼はトレント・パークの写真集を堪能するふりをしながら、アキラの一挙手一投足を見逃さぬように細心の注意を払っていた。彼女はあたかも最後の大仕事のような顔つきで、太腿の上に乗せたノートパソコンを操作していた。普段であれば、ザラメ氏からの神経質なメールに対する返信をタイプしているところだ。ただ、今日はマウス操作が中心のようであり、少し様子が変だった。一段落し、端末をカウチの片隅にやってから遠い目になった。彼女は脚を組んで、栞が挟まれた漫画本「冥王日の友達」の下巻をカウチ横のミニラックから取り出した。これは先日から読み進めていたため、終盤に差し掛かっていた。オゥ・ララは妻がじきに読み終わるのを恐れた。読書が終わる、その次に何が始まるか今宵ばかりは予測がつかなかったからだ。ぱら、ぱら、あと何ページかな、ぱらり、ヒロインと仲直りした辺りかな、ぱら、ぱら、もうあとがきまで来ちゃったんじゃないかな、ぱらり。借りてきた猫のように彼は固まったまま、愛する妻のことばかり気にしていた。アキラは最後のページにたどり着く前に、おもむろに上を向いて、開いたままの本を顔の上に乗せた。まるでいかにも寝たふりをしているみたいに。
そのときだった。三匹、いや三人と呼ぶべきか、天使が舞い降りたのだ。彼らは猫のように柔らかい金髪に小さな双翼をまとい、まるで宗教画の中から抜け出してきたかのような風采をしていた。彼らはレモンイエローにほんのり輝く輪っかを支えており、それはアキラの頭上十センチほどの宙で止まった。いわゆる天使の輪っかを、彼女はいただいた。天使たちはハープ、オルガン、コントラバスを取り出し、鎮魂歌を演奏しはじめた。彼らは手を動かしながらこの世ならざるソプラノで合唱も追従させ、それらは組み合わさりガブリエル・フォーレの第七曲「イン・パラディウム」を織り成した。
あまりの出来事に、オゥ・ララはぶたけつくんの可愛い口をぽかんとさせたまま、その光景を見つめていた。これは一体? 考えているうちに、彼の記憶の思考回路はぴしゃりと繋がった。結婚式の最中、妻は天使の派遣サービスを商品とする企業の専務とうんざりしながら名刺交換をしていたではないか。彼女は先ほど、ノートパソコンを操作して彼らに依頼していたに違いない。つまりこの天使たちは、妻が雇ったのだ。彼らはお互い、競い合うように極めて精緻に譜面を追いながら、雇い主たる女とその奇怪な夫の顔を交互にちらちらと盗み見ていた。天使たちはあまりに物欲しげで、これはチップを期待しているのだろうと嫌でも伝わった。彼らの珍しさに気を取られてはならない。僕はアキラの言わんとするところを推察せねばならない。妻を察するは夫の務め。彼女は、僕に託したのだ。この引き金を、僕が引くために。彼女が本当に必要なもの。不必要なもの。あってもいいが、枷になるもの。考えにかんがえ、オゥ・ララはひとつの結論に至った。しかし、あぁ、そんなの残酷じゃないか。妻よ、こちらに来てはいけない。我々の世界に、来てはならない。ましてや、ひとりぼっちで通り過ぎていくだなんて。誰よりも深くアキラを理解しているからこそ、その見果てぬほどの深遠な孤独を彼は感じ取っていた。
長く逡巡し、オゥ・ララは電話を手に取った。かけた先は、葬儀屋だった。
9
アキラの葬儀は、親族の意向で仏式となった。案の定というか、見栄を張りたがる父親によって、やはり近親者どころか業界関係者のみならずファンも押しかけるほど盛大な式となった。参列者は神妙な顔つきを作り、遺族たるアキラの家族に次々と頭を下げていた。ご愁傷さまです、お悔やみ申し上げます……消え入りそうな声で、聞こえるか否かというくらいの声量が演技のコツだ。歌姫アキラ、原因不明の突然死。自ら命を絶ったとの説もあり、その一因と噂されるザラメ氏は見るからにやつれていた。彼は葬儀場を出たり入ったりして、頻繁に電話をかけている様子だった。はい、大丈夫です。次こそは長く使いますから……。世間の非難もなんのその、金の卵を産む鶏を躍起になって彼はまた探すのだろう。一方で、彼女の遺族は悲しんでいた。その悲しみに偽りはなかった。一家から文化人を輩出したと浮かれていた父親も、卑しき己の振る舞いを後悔していた。ただ、何故こんなことになってしまったのかは、よくわかっていない。そして彼もまた、顧客からの電話に律儀な対応を返している。この葬儀場にいる人の誰もが、午後からの仕事のことで頭がいっぱいだった。
胸の上で組まれた手は、オゥ・ララが葬儀を手配したあの日からそのままだった。棺の中で横たわる妻へ、これでよかったんだよねと心の中で語りかけていた。彼女の棺を中心にして、生前に近しかった者が周りを囲んだ。静寂が場を支配し、やがてお坊様が見えた。アキラの顔に被せられていた打ち覆いは、厳かに取り下げられた。その顔は、死化粧の必要がないほどに艶々していた。葬儀らしく、嘘か真か小さな嗚咽が幾つか聞こえた。お坊様が読経をあげはじめ、幾ばくかの時間が流れていった。お坊様以外の全員が視線を落とし、祈りらしきものが捧げられていた。
引導が渡されていく中で、それは起こった。
突然、ブリッヒィィィィィィィアという絶叫が響き渡った。アキラの声だった。彼女は棺から起き上がって、笑っていた。口角が異常なほどに吊り上がっていた。オゥ・ララはその声にまず強く反応したし、妻のここまで激しい笑みは今まで見たこともなく、ただ恐ろしかった。彼は目をぱちくりさせたが、異常事態はこれに収まらなかった。アキラの絶叫に反応したのは、オゥ・ララを除くとザラメ氏と一部の卓越した批評家のみだった。彼らとて、一瞬周りを見渡したのちに気のせいとばかりに再び目を瞑った。遺族、その他の参列者は終始うつむいたまま、何も示さなかった。起き上がったアキラを前にして、お坊様は読経を続けていた。
「ちょっと寒いね、エアコン上げていい?」アキラは夫だけに断った上で、立ち上がって勝手に室内の空調を調整しはじめた。誰も咎めないどころか、気づいてもいなかった。「わかった、みんな喪服の下に何枚も着てるのに私だけ死装束、あはは、死装束なんか初めて着ちゃった。これ一枚だから寒いんだ。なんか探してくるね。あとトイレも」まるで家にいるときのようにけらけらと饒舌になり、アキラはどこかへ行ってしまった。
オゥ・ララは反射的に驚きさえしたが、これは計画通りだった。彼女の意思を言付かり、実行したに過ぎなかった。寝たふりでも死んだふりでもない。アキラは「死んだこと」にしてほしかったのだ。夫として、その合図を正しく受け取っただけだ。いつの間にか、故人が不在のまま弔辞の朗読が進められ、お坊様の主導で焼香をあげる段階まで来ていた。
戻ってきたアキラはよほど着るものがなかったのか、兎があしらわれたピンク色のジャージを履いていた。上には死装束が羽織られたままだ。右手にはコンビニエンスストアで買ったホットコーヒーの小サイズを持っていた。彼女は自分のための焼香を通り過ぎて棺に戻り、あぐらをかいてオゥ・ララの方へ居直った。「そのズボン、どうしたの?」オゥ・ララは咄嗟に口に出してしまい、他の参列者から怪訝な視線を向けられた。あっ、と思って、出た言葉を引っ込めるように彼はうつむきがちにアキラと目を合わせた。
「君が喋ると笑われちゃうよ。私はもう、いないんだからさ。そうそうこのジャージ、ここのお葬式屋さんの忘れ物コーナーみたいなところにあって、履けるのこれしかなかったんだよね」そう言いながら、彼女はコーヒーを一口飲んで、語りだした。「これはさ、歌手としてのアキラのお葬式であって、私のお別れ会じゃないんだよ。このとおり元気だし、お化けじゃないしね。本音を言うとさ、さっき起き上がるとき、少し緊張してた。この中のどれだけの人が私に気づいてくれるんだろうって。結局、せっかく驚かせたのに君以外ほとんど気づかなかったなぁ。あ、ザラメさんはちょっと反応してたかな?」話しながら、丁度焼香にきていたザラメ氏のおかきにアキラは手を伸ばした。とっておきのザラメ糖味を取られたのに、ザラメ氏は南無阿弥陀仏、と小声で繰り返すのに夢中だった。
「この人もね、昔は音楽やってたんだよ。偏屈すぎて、全然売れなかったって自分で言ってるけどね。今はお金のことばかり気にしてるけど、その頃の反動なのかもね、きっと。ビジネス! って感じで生きることだけが、大人になることだと勘違いしちゃったんだ。私の気持ちも本当はわかるんだけど、共感したら自分の何かが壊れてしまうんだと思う」もう一口コーヒーをすすって、少し間を置いてからアキラは三角座りになった。
「君はザラメさんがいけ好かないんだろうけど、あんまり責めないであげてね。ここにいる他の人たちも、私の声が奇麗だとしか思ってないファンの人たちも。みんな、私がいなくなっちゃったと思い込んでることは悪いことじゃない。ただ、そういう人たちっていうだけ。誰も本当の私をわからない。お父さんですらね。けどこれは、私が望んだことなんだ。私がひとりぼっちだったからこの声と歌を授かったんだ。どっちが先なのかは、もうわからないや。この話は誰も悪くなくて、ただ私が少し疲れたの。少し疲れたから、舞台から降りるだけ。ただ一人で誰のためでもなく歌う、そういう本当に大事なことが残るんだ」
オゥ・ララは、静かにうなずいていた。やがて焼香が終わり、出棺の時間になった。アキラが棺の真ん中に座ったまま、遺族はじめ近親者数人によって運ばれていった。彼女は肩の荷が下りたのがよほど嬉しいのか、棺の上で機嫌良く歌っていた。ちょっとしたお祭り気分かもしれない。
10
無人の棺は火葬場で燃えさかっていた。途中でアキラは御輿もとい、棺から降りて、オゥララと二人で自分の葬式を眺めていた。故人不在のためお骨拾いは飛ばされたが、そのことに疑問を抱く人間はいなかった。ようやく、この奇怪な葬儀は完了した。
歌姫アキラはいなくなり、歌が好きなアキラだけが残った。
昼を過ぎていたので、アキラとオゥ・ララは近くのショッピングモールに入った。以前は顔を差す、つまり歌手だとばれて収集がつかなくなることもあったが、今は平和なものだ。誰もこの奇妙な夫婦を邪魔する者はいない。フードコートの席を取ったところで、特に目ぼしいテナントがなかったため、アキラは一旦スーパーで食料品を買ってきて戻ってきた。
「じゃーん。これ食べるもんね」
「あっ、それは『ぶたけつ壱番館』じゃないか。酷いことはしないでおくれよ」
「ぶたけつくんも共食いする?」
「僕はそもそも食べられません。意地悪」
「ふふん」
「……」
「ねぇ」
「うん」
「何か言おうとしてる?」
「ちょっと考え事かな」
「何考えてるの?」
「ちょっと長くなりそう」
「またいつもの小難しい話?」
「かもしれない」
「いいよ。食べながら聞くから」
「僕は夫失格かもしれない」
「え?」
一瞬、アキラの箸が止まった。
「僕はあなたに幸せになってほしいと思っている。でも、アキラの幸せって本質的にはどういうことなんだろうと考えてしまうんだ」
「私の幸せは、今こうしていることだよ。あとは歌うことと」
「確かにそれもあるかもしれない。そう思ってくれてることが、僕はとても嬉しい。でも、それ以上にアキラはアキラでなければいけないんだ」
「どういうこと?」
「僕は、あなたの歌声に感銘を受けて自我を授かった。この頭上のアンテナで毎日拾っているあなたの声が、比喩じゃなくて本当に僕の原動力なんだ」
「うん。それは知ってるよ。ありがとうね」
「アキラ。君の幸福は『歌』そのものなんだ。歌うことだけが幸せなんだ」
「何を言ってるの? それだけじゃないよ。決めつけないで」
「厳密にいうと、孤独に歌う、それが君にふさわしいんだ」
「孤独? 独りはいやだよ。私が子供の頃からどれだけ寂しかったか知ってるでしょ?」
「わかっているよ。でもあなたの声は、ひとりぼっちだったからこそ生まれた奇跡なんだよ。僕はあなたといると幸せだ。けれどもそれ以上に、あなたの歌声が完成されることを祈ってしまうんだ。僕はあなたの夫でもあるけど、それ以前にあなたの声の敬虔な信者なんだ。そこがまず先にあらねばいけないんだ。僕とずっと一緒に過ごすと、その声は失われてしまうんだ」
「何を言ってるの? わからなくなってきた」
「僕はあなたといて、十分に幸せだった。こんな人形には過ぎた幸せだった。僕は結末を知っているんだ。その終わりに近づく日々に耐えられないから、今ここで決めてしまいたいんだ」
「お別れってこと? なんでそんな酷いことを言うの」
「さっき言ったことはそれさ。僕は夫失格なんだ。あなたに寄り添うことより、自分の美学を優先してしまったのだから。僕は、たとえあなたが孤独に生きることになっても、これからずっとさみしい気持ちで過ごしていくことになったとしても、あなたの歌声に心を捧げてしまったのだから」
二人の沈黙。
アキラは視線が定まらなかった。投げかける言葉を失ったからだった。この世で一番信頼のおける相棒の告白。繊細な、あまりに繊細な彼だからこその決断だった。ただ、アキラにはまだ別れの意味がわからなかった。オゥ・ララは何度もアキラの歌声を記憶の中で反芻していた。この歌で生まれて、この歌で終わりたかった。
「ねぇ、アキラ。あれ歌ってよ。いつも会社で歌ってた鼻歌みたいなやつ」
「え、フードコートだよ? 恥ずかしいよ」
「大丈夫だよ、みんなご飯食べながら喋ってるし」
アキラは、夫の希望通りに歌いはじめた。それはなんてことはない、ひと昔のコマーシャルソングだった。台所の油汚れを落とす、強力なハイターの宣伝歌。たった八小節を繰り返すだけだが、歌詞が一番から三番まであってなかなか起伏に富んでいる。妙な中毒性のある旋律で、心地よい。どこにでもある、ありきたりな風景。
オゥ・ララは突如、頭頂から伸びているアンテナに手をかけた。丸太のように太い腕に、彼は生まれて初めて本気の力を込めて引っこ抜いた。目の前がテレビの砂嵐のようにノイズに飲まれ、世界は無音に包まれた。何かを叫んでいるアキラが消えていく。五感が閉じていく中で、オゥ・ララは自分が泣けなかったことに、泣いた。
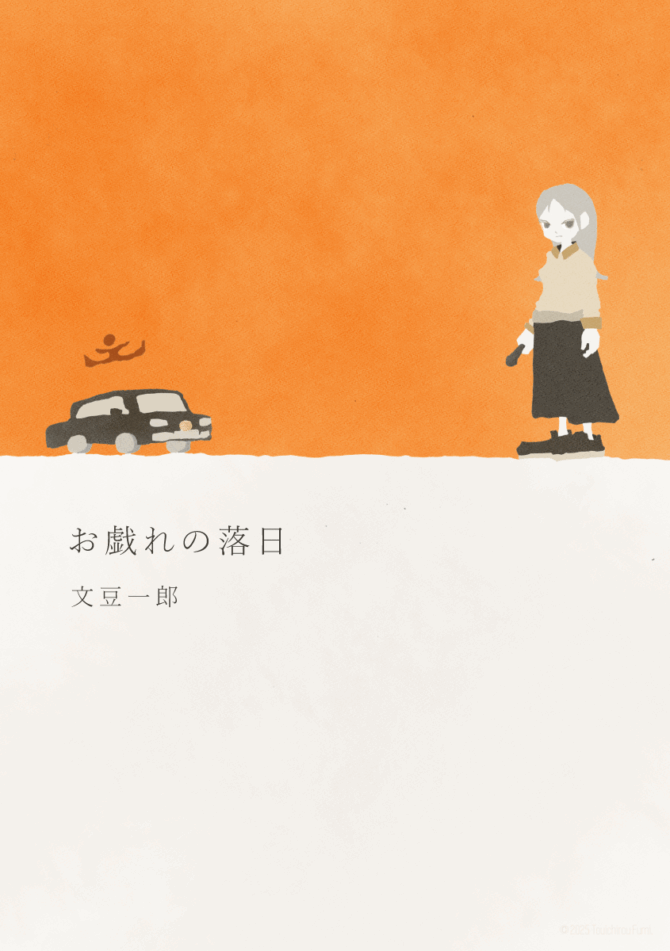






















"お戯れの落日"へのコメント 0件