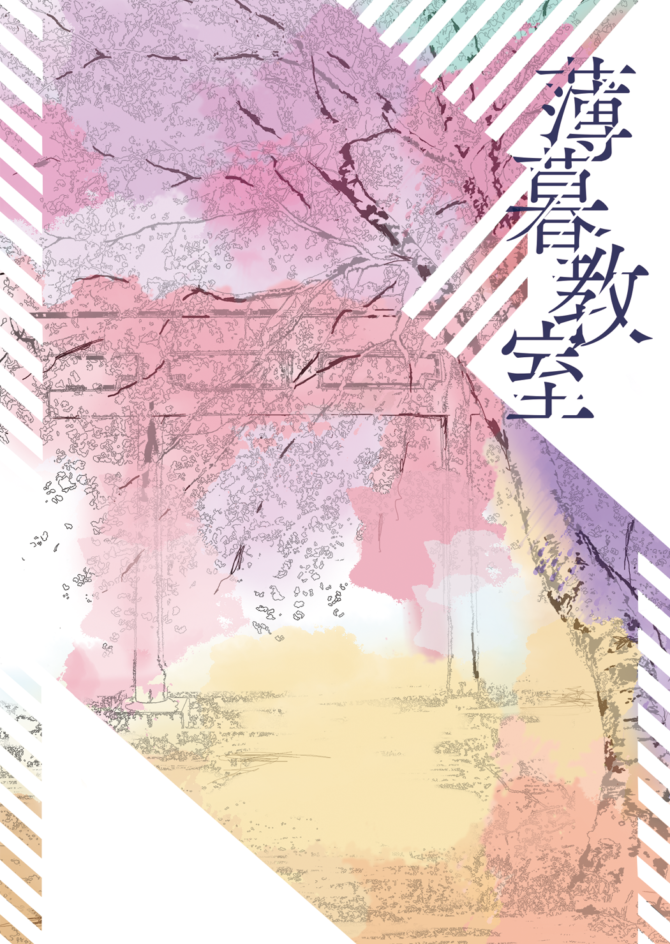Works 収録作一覧
-
- 小説
- 2,788文字
- 2021 年 4 月 5 日公開
花の下で生きると決めた日のことを思い出す。仰ぎ見た空から、彼の好きだった色が降りそそいでいた。
-
- 小説
- 7,051文字
- 2021 年 4 月 5 日公開
出会いに理由などない。それでも、その日そこにいたことがたしかに人生を変えたのだ。
-
- 小説
- 5,440文字
- 2021 年 4 月 5 日公開
たとえ身を壊すとしても、それは彼にとってなくては生きられないものなのだろう。
-
- 小説
- 13,825文字
- 2021 年 4 月 5 日公開
あの日雨が降らなければ、彷徨いこまなければ、今もここで笑っていられたか?
いいや、きっとそんな未来はあり得なかった。何があろうと、お前さんはその小さな手を離すことはなかっただろうから。 -
- 小説
- 12,094文字
- 2021 年 4 月 5 日公開
降りしきる雨の下で手繰り寄せたその身体の冷たさを、俺はきっと生涯忘れることはできないだろう。
-
- 小説
- 8,165文字
- 2021 年 4 月 5 日公開
雨の降り止んだ日に、ようやく本当に出会えた気がした。
-
- 小説
- 6,337文字
- 2021 年 4 月 6 日公開
どうかいつまでもこのままでと願うのは、彼にとって酷なことだろうか。
-
- 小説
- 7,444文字
- 2021 年 4 月 6 日公開
手の届かないものを数えて暮らすことに慣れてしまった。慣れたと、思い込みたかった。
-
- 小説
- 9,084文字
- 2021 年 4 月 6 日公開
眩いものすべてから身を遠ざけた。誰もいなくなった暗がりを愛そうとして、結局できなかった。
-
- 小説
- 6,537文字
- 2021 年 4 月 6 日公開
失いたくない、そんな思いが日増しに募っていく。終わる予感を見なければ、こんな思いには駆られまい。
-
- 小説
- 9,902文字
- 2021 年 4 月 6 日公開
ここまで来られただけで、きっともう充分すぎるほどに幸せだったのだろう。そう信じることにして、私は大切な世界に別れを告げた。
全てを失っても、貴方は隣に居てくれた。 -
- 小説
- 7,650文字
- 2021 年 4 月 9 日公開
どこにも行かないでくれと乞い願う。どうかずっとこのままでと望む。残された時間は恐らく僅かなのだろう。
-
- 小説
- 8,281文字
- 2021 年 4 月 9 日公開
拐ってやりたい。その運命からも、枷のついた身体からも。
望まないと知っていた。拐うかわりに、手のひらを重ねた。 -
- 小説
- 8,823文字
- 2021 年 4 月 9 日公開
いつの日か、君のいるところに手を伸ばす日がきたら――そのときにはまた、いつかの話の続きをしよう。
-
- 小説
- 3,836文字
- 2021 年 4 月 9 日公開
春は何度でも巡り来る。それが救いになるのだと、教えてくれたのは先生だった。
-
- 小説
- 3,237文字
- 2023 年 8 月 19 日公開
春はいつもそこで鳴っていた。さやさやと、さらさらと、遠き日の眼差しを閉じ込めて。
薄暮教室:短編 -
- 小説
- 2,454文字
- 2023 年 9 月 6 日公開
ただ春を待つことが、こんなにも残酷であろうとは。
薄暮教室:短編
How people say みんなの反応
Share This シェアする
面白かったらSNSでシェアしてください。
シェアしていただくと作者がやる気を出します。
Published eBooks
電子書籍
Books
破滅派の書籍
破滅派は同人サークルから出発していまや出版社となりました。
破滅派の書籍は書店・通販サイトでお求めいただけます。