国際図書館連盟(IFLA)は2016年10月24日(月)、公式サイトにおいて「忘れられる権利」についての見解を表明した。表現の自由とプライバシー権の対立は昔からたびたび議論を呼んできたテーマだが、インターネットの普及以降ますますこの議題は大きな論争を招いており、「知の蓄積」を至上命題とする図書館の立場からあえて声明が発表されたことの意味は小さくないのではないだろうか。
「忘れられる権利」は、比較的歴史の浅い権利であるプライバシー権のなかでもとりわけ新しい権利だ。インターネットという、一度情報がアップロードされると半永久的に保管されつづける空間が生まれたからこそ提唱されるようになった概念であり、この権利が広く検討されるようになったのは2011年からだった。
この年、あるフランス人女性がGoogleを相手に自身のヌード画像を削除するよう求めた裁判で勝訴し、それ以来EUでは「忘れられる権利」が法的に保証されるようになった。従来削除依頼があっても動こうとしなかったGoogleがスタンスを変えたのは、この判決以降のことだ。プライバシーの観点からいえば非常に意義深い判決だといえる。
しかし一方で、この権利が強く主張されることが必ずしも人類の文化にとって良いことだとはいえない点にも注目しなければならない。たとえば、重大な犯罪を犯した人物が「忘れられる権利」を主張したとしたらどうだろうか? その主張を全面的に認めてその人物に関する資料をすべて削除してしまったら、歴史はいくらでも修正可能になってしまう。「忘れられる権利」は、表現の自由のみならず、公共性にも関わってくる重要な概念なのだ。
文学的な視点からいってもこれは無視できる問題ではない。いわゆる「『宴のあと』裁判」を例に出すまでもなく、表現の自由とプライバシー権はしばしば衝突する。この点をクリアにできないかぎり図書館の自由も脅かされてしまうのだから、図書館がこの件について声明を発表するのは当然の流れといえた。
実は国際図書館連盟では、今年の2月にも声明を発表している。その際には、「公的なインターネットの情報は公共のため、また、研究者のために価値があるものであり、一般的に意図的に隠されたり削除されたり破壊されたりしてはならない」というメッセージを出したが、比較的ソフトな物言いであったこともあり、そのときはさほど話題にはならなかった。
それに対し、今回はもっと明確に「忘れられる権利」の問題点を指摘している点に注目したい。声明では、「図書館が保管できる情報には物理的な限度がある」ということを前提に、「インターネットがそれを補完し、アーカイブの情報量が指数関数的に増えた」という点の重要性を強く訴えている。そのうえで、「たしかにインターネット上の情報は個人に不当なダメージを与えることが可能だが、公共の利益も考慮しなければならない」「そのバランスを考えていかなければならない」と強調している。
メッセージの強さのわりにあまり世間では話題になっていないようだが、この提言はのちのち大きな意味をもってくる可能性がある。英文の読解を苦にしない人は、ぜひ原文でこの声明の全文をしっかりと噛みしめてほしい。
ちなみに、破滅派主幹である高橋文樹も先日、忘れられる権利についてのエントリーを記しているのであわせてチェックしてみてはいかがだろうか。





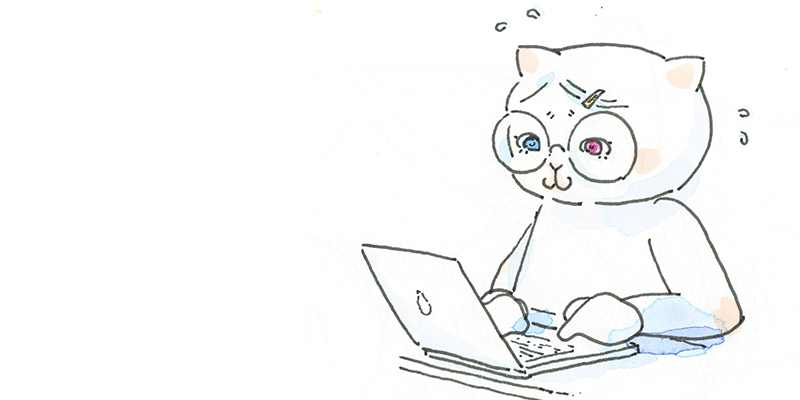


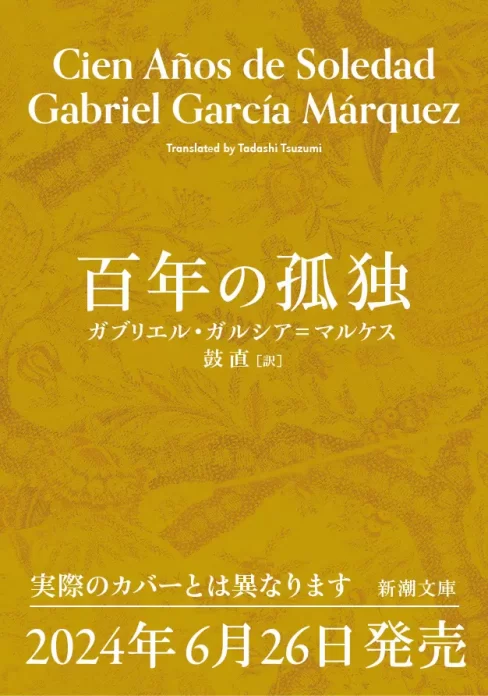
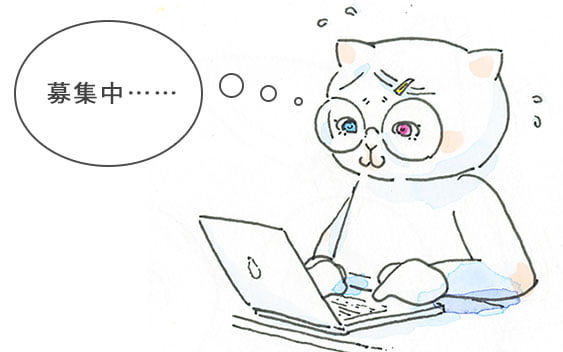












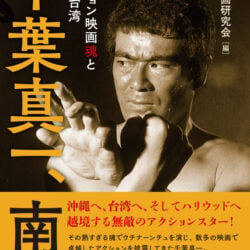
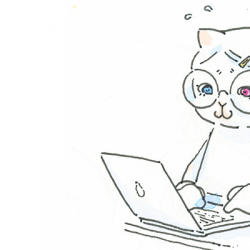














コメント Facebookコメントが利用できます