待ち合わせに現れた残波さんは僕が想像していたタイプの女性とは違って、お団子ヘアーに紺のダッフルコート、足下はもこもこのムートンブーツという素朴な少女趣味を漂わせている人だった。
この町へ越してきたばかりの僕に、この町へ帰ってきたばかりの残波さんを紹介してくれたのは、僕らの共通の友人のりんこちゃんで、東京にいるりんこちゃんを介して互いのLINEIDを交換した僕らは、少しの雑談と幾ばくかのスタンプの応酬をした後に日程を摺り合わせて映画を見に行くことにしたのだった。
駅ビルのエスカレーター前の大きな柱の所で残波さんと落ち合うと、僕らは映画館へ行き、ポップコーンの甘ったるい匂いに辟易しつつ、約二時間スクリーンの前で時間を共にした。
映画の出来は正直言って50点と言ったところだったけど、初対面の女性に作品への批判を述べるわけにもいかず僕は「いや〜よかったね」と良かった点だけのみを語り、残波さんも笑顔で僕と同じようなことを違う言葉で語っていた。
映画を見て少しコーヒーでも飲んだら、今日は帰るつもりだった。
ところが、入った店が中華料理店だったのが間違いだったのか、アルコールを頼んでしまったのが間違いだったのか、僕らの間に「じゃ、そろそろ」というフレーズは一向に出てこない。
否、この店へ入ったことは間違いではない。僕らは空腹だったのだ。唾液に胃液が混ざり始めた僕らにとって、ショーケースの中の麻婆豆腐や鶏の唐揚げは余りに魅力的過ぎた。ならば、こうなってしまったことは最早抗いようのない運命みたいなもので、僕と残波さんが延々喋り続けてしまうことは必然だったのだろう。
残波さんが杏露酒のロックを5杯ほど飲んだあたりで、ここまで来たら本格的に飲みに行った方が良かったんじゃないかということになって僕らは居酒屋に移動するが、その後も話は尽きることがなく気がつけば終電の時間が迫っていた。
何がそんなに楽しいのか、自分でもよくわからないけれど僕が自分のこと以上にわからないのはこの残波さんの方で、彼女は僕の凡庸な話に手を叩いて「おもしろーい!」と大笑いしていた。
残波さんの最寄り駅が地下鉄で、僕の最寄り駅がJR。終電はJRの方が若干遅く、僕は地下鉄を遠回りしてターミナル駅まで行くことにし、その間もう少しだけ残波さんと話すことにした。
酔いのせいもあったのかも知れないけれど、残波さんは僕のその少しばかり気持ち悪い提案も、大笑いで「うけるーうれしい〜」と言って受け入れた。残波さんは僕より年上のはずだったが、そのテンションやリアクションは幼くて僕より年下のようだ。
繁華街の中心から乗った電車は、初めが乗客のピークで駅から駅へと行く毎に少しずつ空いていく。
残波さんの駅は地下鉄の終点の郊外で、僕はその途中のJRの駅と連絡している駅で降りるつもりだった。
「へ〜そうなんだ」「えーなにそれ、すごい!」「やばい!」「ウケる!」「面白い!」「あーもうほんと、そういうところマジで好き」「素敵っ」「こういう人って、わたし大好きなんだよね」「……楽しい」
残波さんの発した言葉はだいたいこんな感じで、僕はその声を電車に乗ってからは主に左耳で受け止め続けている。
本当ならターミナル駅の羽物谷で降りるはずだったのに、気がつけば駅は疾うに過ぎていてやっぱり今夜は何かがおかしいなって、僕は思わざるを得なくなる。
「は〜今日は何か時間過ぎるの早いなあ。僕ら、何時間くらい喋ってるっけ?」
「んー、たしか飲み始めたのが5時前だっけ? っていうと……」
残波さんが左手から順に指を一本ずつ折り曲げていく。
「えっ、もう6時間は経ってるよね!?」
「マジか、すげぇな。僕まだ3時間くらいのつもりだった」
「あははは、だよねえ。ウケるよ〜」
「これ時空歪んでるわ」
「だよね、町田くんもそう思う?」
「思うよ! それ以外考えられないって」
へへ、と僕はここがネット上なら「www」と表現しちゃうような笑い声をあげる。照れてる自意識を自嘲しながら、これは楽しいことなんだ、ねえ楽しいよね? なんて確認するような、そんな笑いだ。
一方残波さんは、僕ら以外に誰もいない車内で、何かを考え込んでいるようで、顎に手を当ててひとり頷いている。
「町田くんがそういう認識でいるなら言ってもいいかなぁ」「えっ、何?」「いやいや、何かさぁ、町田くんには何でも言っちゃえそうなんだよね」「そうなんだ。まぁ僕は何でも聞くけどね!」僕が彼女を煽ると、彼女はあははと笑って、はぁと溜息を吐いた。一人で勝手に苦悩している残波さんは面白い。「あー、もうおかしいなあ。それにしたって、わたし心開くの早すぎる! お前は太陽か〜っ!」「はい?」「北風と太陽的な、そーいう」「あぁ」「わたしの心はもうブラとパンツ一枚のみですよっ!ばかっ、ばか〜っ!」とその声音にどうも上擦った色合いを感じて僕の股間にきゅんと血液が流れ始めたところで、頭を小さく横に振る。きっと気のせい、気のせい。残波さんはただノリがよく愛想がよく楽しいだけの人なんだ。
「カミングアウトタイームっ!」
「はい?」
「実はね、わたしね、魔法使いなのっ!」
「はぁ?」
にこにこしたままで、残波さんはぼくを見つめる。人の目を見るのが苦手なぼくはその圧にやられてじりり、と目を下にそらした。
すると黒タイツ越しの残波さんのくりっとした膝小僧が目に入る。
「あーもう信じてないなあ。本当なのに」
「えっと……童貞……なの?」
「違うわー! 童貞ちゃうわー! そりゃマインドは永遠に童貞だけどさっ」
残波さんの言語はめちゃくちゃだ。色々な町を転々として色々な人の方言が移った結果、とのことだけど。
「そもそもさ、何で今日、こんなに時間があっという間に過ぎてるかわかってんの?」
残波さんは深い茶色の瞳を微塵も動かさずに、僕を見つめる。
「それは、何か話が盛り上がっちゃったから」
「半分正解」
「じゃあもう半分は?」
「魔法」
「は?」
「だからわたしの魔法。魔法の力で、時間を攪拌(かくはん)しちゃった」
てへ、残波さんは片目を閉じてまるで顔文字みたいな表情をして見せた。
「だってさ〜……あ、やっぱやめとく」
「いや、言ってよ。言いかけて止めるのが一番気持ち悪いし」
「確かに」
残波さんは視線を上げて車内の電光掲示板で次の停車駅を確かめる。
「いやだってさ、もっと仲良くなりたいじゃん? 町田くん面白いし、見た目もかわいいし。正直好きな感じなんだよ」
思いがけない言葉に僕の頭は若干フリーズ。こんな時のためにテンプレ化されたリアクションも用意してないからやっぱりフリーズ。ぼくは、うっ、と動きを止めるけれどいやそれはよくないと、なるべく早く迅速に何かを言おう!
「うわ〜」
やっとの思いで外へ出た言葉はこうだった。我ながら違和感を憶える。これでは残波さんには僕の感情は伝わらないだろう。
「あーもういいいい、ごめんね。ひくよね。いやいや、ま、今後も時々一緒に映画を見に行ってくれたら、それで嬉しいので」
残波さんの身体が徐々に前傾していく。
「いやいやごめん、違うんだよ。見た目のこと褒められたのとか初めてだし、ふつーにびっくりしただけやで」
東京育ちのはずの僕に、いつの間にか彼女の言葉が移っている。
「へ〜そうなんだ。わたしは好きだけどな」
そう言うと残波さんは再びぼくの顔をじっと見る。
「うん、やっぱ、好き」
「あ、どうも……」
ちょっとどうしていいのかわからなくなった僕は、小さく俯く。
「あのね、町田くん。楽しい時間はあっという間に過ぎていく、っていうのはあれ、錯覚でも何でもなくて、実際そういうことが起きてるんだからね」
「あー相対性理論?」
「どういうこと?」
と、ここで僕はなけなしの知識で、どうやら時間は伸び縮みするらしいとかそんなことを彼女に説明する。その間、また残波さんは好奇心に目を輝かせて、うんうんと僕の話に頷いていた。
「なるほどな〜。そういうのってもう科学で立証されてるんだねぇ」
残波さんは感慨深そうに、僕ら以外に誰もいない地下鉄の車内で穏やかな笑みを浮かべる。その表情は、アルコールの中に浮いた僕の心に心地よく染みこんでいく。
「それなら話は早いな。やっぱり町田くんはすごいよ。さすがやなあ」「いや、僕は普通だから。残波さんがおかしいだけ」「うるさいわ、あほー!」僕は段々残波さんと言葉で絡み合っているような気になってくる。
「楽しかったからね、もっと色んなことが喋りたくなったんだよ。それでね、普通にしてたら時間が足りないなって思ったんだ」
残波さんは視線を斜め下に傾けて、穏やかな調子で語り始める。
「ねぇ、町田くんさ、私たち今日出逢ったばかりなのに、もうだいぶ前から知ってる友達みたいな感じしない?」
「確かに」
「少なくとも1ヶ月くらいの付き合い、みたいな」
「うん、そうだね」
「実際ね、わたしたちは今日でもう1ヶ月分くらいは喋っちゃったの」
「マジか〜」
僕はそれりに受け止めて、それなりに驚く。真実よりも今大事なのは、残波さんの真意なのだ。
「でもね、さっきからほら、30分しか話してないつもりがもう3時間くらい経ってたりするでしょ?」
「あぁ、そうだね」
「人と仲よくなるのってね、どれだけ気持ちを受け渡しし合ったかってことによって、決められるのね」
「確かに」
「それってつまりエネルギーのやりとりをしてるってことなんだ。今日のわたしたちの場合だと、つまり3時間分のエネルギーを、30分でひとっ飛び、ぴょいと渡し合ってたってことになるんだよね。えへへ。30分で3時間ペースで仲良くなって、最終的にはこの半日で1ヶ月分も仲良くなれちゃった。お得だったでしょ?」
残波さんはムートンブーツを履いた足をぶらぶら揺らして、楽しそうな調子で僕に言う。だけど僕は全然楽しくなくなった。残波さんの物言いじゃ、僕たちの楽しい気持ちが割り切られてしまうようで嫌だった。僕は割り切れない不可解な感情がばかみたく楽しかったのだ。お得だとかなんだとか、そんなコスト感覚は必要ない。効率を考えてしまえば、僕はこの楽しさが偽りだと言われている気がして、なんだか不愉快だ。
「意味わかんないかな」
黙っている僕に、違う意味を見いだしたようで残波さんはこう言った。
「わかるけど。いや、ただ……」
「こういうの嫌だった?」
「嫌っていうかさ……。お得とか、そういうこと言われちゃうと何だかね。残波さんが何か計算ずくで僕と会話してたんだなあって思っちゃって。何かね」
車窓の向こうを流れるのは闇ばかりで、窓ガラスは僕たちを映し続けている。
「楽しいって思ってたのは僕だけだったのかなって思ってさ。なんつか、ちょっと」
へへ、と僕は語尾に苦笑いを付ける。
「違うでしょ〜! ばーか、ばかっ」
残波さんは唇をへの字に結んで、僕の膝をぺちぺち叩いた。あ、ボディタッチ。僕はそう思う。
「町田くん、まだ何もわかってないっ。てか今これ、話の途中だからね!」
残波さんは僕の顔を覗き込んだ。
「わたしの魔法のエネルギーって『好き』とか『楽しい』って気持ちなんだからねっ! これがないと魔法が使えないんだからっ」
「MP的な?」
「そう! だからね……」
残波さんは少し照れたように、僕から目をそらす。
「わたしが好きとか素敵とか言うたびに、わたしたちの間の時間って流れを失うの。わかりやすくいうと、あっという間に時間が過ぎてる気がしたり、沢山一緒にいたような気がしてきちゃうのっ」
彼女は少し赤くなった頬で、えへへ〜と笑った。
「あー、町田くん、好きだぁ。好きだなあ」
残波さんは、一人呟くようにこう言う。
「マジすかー……。どうもありがと……」
「もぉ、やだなあ。ごめんね。困っちゃうよね、こんなこと言われても、さ」
「そりゃ戸惑うよ。だって僕ら、まだ今日出逢ったばかりなんだから」
「だからそういうの、もうやめよっ!? 頭で考えるんじゃなくて心で感じてよっ。そっちの方が本当のことなんだから」
「じゃ、僕たちはもう出逢って一ヶ月くらい経ったってこと?」
「その通り。ねえ、町田くん、頭で考えたって無駄なんだよ。身体の感覚にはどうしたって抗えないんだから」
残波さんは諦観を飲み込んだような笑みを浮かべる。その微笑みを見ていると、僕の身体は穏やかに脱力してく。
「確かにそうなのかもね」
そうだ、僕は分かっている。ただ戸惑っているだけなのだ。僕の感情は身体中の細胞をざわめかせて、僕の頭を置いてけぼりにして何処までも行ってしまう。
僕はまだ追いついていない。
「あれっ、そういえば次って何駅だっけ?」
たくさん喋った気がして僕は慌てて、扉の上の電光掲示板に目をやる。
「まだヨモギ北ニューポート駅だよ」「ヨモキタ?」「ううん、にゅーぽ」「どっちでもいいわ」「えへへ」
「ま、それなら鰯倉はもう次だね」
「そうだね……」
残波さんは自分のブーツの爪先に視線を落とす。
「はぁ、何だか名残惜しいなあ。わたしって欲張りだね」
困ったように眉尻を下げて、残波さんが僕に笑顔を見せる。
「ねぇ、もう。好き好き好き好きーっ!」
「うわ、ちょっともう! 酔ってるの!?」
電車が徐々に地上へと上がって、窓の向こうに街の灯と星明かりが見えてくる。
「酔ってるよぉ。酔ってないとこんなこと言えないじゃん!」
残波さんはえへらと笑った。僕はこの笑顔が嫌いじゃない。ううん、むしろ好きだ。
少しずつ車窓の向こうが電気の灯りで明るくなって、車両は駅のホームに入る。
だけど電車は速度を変えず、窓の外は同じ早さで景色が流れていった。
「あれ?」
僕は目をこらして、窓の向こうに見えるホームから、駅名を確かめようとする。
「しものせき」
残波さんが笑いを堪えたような声で読み上げるのとほとんど同時に、僕も駅名を目で捉えた。
「は? 下関っ!?」
「だね」
彼女は足をばたばたさせて、あははと大笑いする。
「何これ、あはははは。下関とかちょううけるー! ここまで移動したのなんか初めてなんだけど!」
あははは、彼女はまだ笑っている。
「ねぇ、これってマジであの下関なの? 山口県の」
「うーん、多分そう。なんか、いつの間にかものっすごい遠くまで来ちゃったみたいだね」
えへへ、と残波さんが笑った。
「あぁぁもう、こんなのどうやって帰ったらいいんだよー! 全然意味わかんねーよー!」
僕は思わず頭を抱える。何せ明日は仕事なのだから。
「だいじょーぶだよー。なんとかなるって」
「『なんとか』って」
「だって、町田くんといると楽しいから、だから何とでもなるよっ」
残波さんがにっこり笑って、その笑顔につられてぼくも笑う。何とでもなるっていうのはきっと、魔法のちからのことを指しているのだろうけど、だけど僕はもっと別のこと、この先ずっとのこと言われているように感じてしまうけど、あ、違う。それは単に僕の願望だ。その証拠に僕のちんこは軽く勃起している。僕は少しずつ、残波さんとのこの先を望むようになっている。
電車はずっと変わらないリズムで揺れ続けている。この車両は今、本当に山口県の上を走っているのだろうか? それとも僕たちが酔っ払っているだけなのか、はたまたこれは夢の中なのか。
いや、考えてもしょうがない。結局僕には本当のことなんて、わかりっこないんだ。
いま僕が、憶測で事実を仮定したとしても、仮定は仮定に過ぎず、ただの幻だ。
僕が事実にこだわるのは、己の土台を定めたい。ただそれだけの理由だ。
僕はこのふわふわした状態に不安を感じていて、落ち着いてどこかに立ちたがっているんだと思う。
「こわいー?」
「そりゃ怖いよ。だいたい僕はめちゃくちゃ慎重で臆病なんだから」
「あはは。それじゃ、楽しくは、ない?」
「うーん。……楽しい」
あははは、僕の答えに残波さんは口を大きく開けて笑った。
「ねぇ、じゃあもうそれでいいじゃん。きっと悪いようにはならないよ?」
残波さんはへへへ〜とほんのり赤らんだ顔で僕に笑いかける。それはこの非モテでいつも童貞側の僕が見ても分かるくらいにデレデレした顔だった。
僕を見て楽しそうな残波さんを見ていると、僕もなんだか楽しくなってくる。
まぁいいか。
残波さんの言う通り、このまま流れに身を任せてみようか。
列車がこの夜の中を進んでいく限り。何処まで行ってしまうのか。行けるのか。見届けてみよう。それにこの流れは不愉快じゃない。
「ねぇねぇ、下関の次ってどこだろう?」
「福岡?」
「あー、とんこつ食べたい!」
「僕は明太子ごはんー!」
僕らの声が無人の車内で脳天気に響くとすぐに、彼女が笑って僕も笑った。
進み出した電車が僕の手じゃ止められないように、僕は僕の意思で残波さんとの関係を止めることが出来ない。
車内の振動と残波さんの笑顔は、僕をどこまでも気持ち良くさせていく。
終わり。
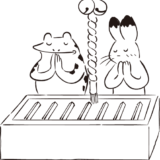





















"残波さんと僕。"へのコメント 0件