ビーアウェア株式会社のサテライトオフィスは本社より広い約五十坪、二十名程度のオフィスとしてはまあまあの広さだった。ビル自体は新しいので、はめ込み窓やエレベーターなどの備え付け設備については申し分ない。食事する場所が品川より少ないのが面倒だったが、俺はそもそも食事にこだわりがなく、チェーン店上等なので気にならなかった。大きな公園もすぐそばにあるし、なにより野球場がすぐ側だ。千葉ロッテのファンではないが、仕事終わりにナイターを見ながらビールを飲むというのもなかなか乙なものだろう。顧客の多くは渋谷区と港区に集中していたので、客先周りが面倒だが、二十分が四十分になる程度だ。
問題は通勤だった。俺は出身が山梨県で、大学進学と共に東京へ移り住んで以来、引っ越しを繰り返してきた。通学や通勤の利便性以外に優先すべきことがなかったからだ。ビーアウェアに就職する前、渋谷に勤めていた時は新代田の小さいアパートに住んでいた。電車で十五分以内というのが俺のルールだ。そうなると、自分のポリシーと照らしあわせても、やはり引っ越さざるを得ない。蒲田の家は更新まで一年ぐらいあったが、乗り換え二回で片道一時間を一年以上続ける気にはなれなかった。海浜幕張の駅付近は家賃が高く、山手線の内側とあまり変わらなかったので、少し離れた幕張本郷のあたりに居を構えた。家賃相場が少し下がったので、ファミリー向けのメゾネットだ。ペットも中型犬までなら飼えるそうだ。俺にその予定はないが。
引っ越しが一段落して一ヶ月も経つと、俺はいままでそうだったように、ずっと前からそこに住んでいたかのように感じ始めた。まだナイターにこそ行っていなかったから、新しい趣味を見つけたわけではないが、そこそこ旨いスペイン料理屋を見つけ、少し広くなった部屋の空間を埋めるためのソファも買った。そのうち、まだ見ぬ彼女といちゃつく日も来るだろう。職場まではバス通勤となったが、チャリンコを買うかもしれない。六十万ぐらいするロードレーサーなんかどうだろう。駐車場もそれほど高くないから、車を買うのもいい――などなど、新生活の楽しさに胸を膨らませていた。
引っ越したそもそもの動機についてはというと、まだ実現の恐れはなかった。世界は終わっておらず、東京もパニックになってはいなかった。少なくとも、六月の時点では。高輪署の刑事も一度新オフィスに電話をよこしたぐらいで、捜査協力を求めてくることはなかった。時折凶悪犯罪の報道を見聞きするたび、あの割烹着のことが頭をよぎったが、ゾンビめいたものの存在を匂わせる報道ではなかった。第一、あの騒動以前にも凶悪な事件は十分にあり、被害の程度だけでは素人に判断がつかない。ゾンビがいようがいまいが、人間は人間をバラバラにして食っていた。俺にできることといえば、ホームセンターで役に立ちそうなものをコツコツ買い揃えるぐらいだった。エンジン式のチェーンソーや金属バット、ロープなどを増やしては、以前整えた避難用バックパックと一緒に玄関側へ置いておいた。
カズとは週に二、三のペースで連絡を取り合っていた。それは下心でもなんでもなく、あのパニックを目撃した同志として、情報交換をする必要があったからだ。たとえば、カズに明確な異変が起きていたら、俺も危ないということになる。逆もまた然りだ。とりえずいまのところは問題なさそうだ。変化といえば、五回目ぐらいのやりとりからカズが急に打ち解けてきて、「元気だよー(^^)」というメッセージのあとに自撮り写真を送ってくるようになったぐらいだ。頬のあたりにピースサインを添えたキメ顔やらなんやらで、まあ可愛かったのだが、写真を送ってくる意味についてはわからなかった。女というのは特に意味もなく自撮り写真を送ってくるのだろう。会社に以前いたインターンの法政大学の女子もそんな感じだった。
そういうわけで、俺は二ヶ月ぐらいをかけてゆっくりと快復していった。ある意味で、あのゾンビを見たときから心に傷を負っていたのだろう。精神的外傷とはよくできた言葉だ。それは実際の傷と同じで時間をかけてゆっくりと治すに限る。その傷が果たしてあの七月までに完全に癒えたのかどうかはわからないが。
七月の湘南新宿ライン集団暴力事件――俗に言うゾンビ列車――の発生を俺はツイッターで知った。たまたまツイッターで見かけたとかそういうことではなく、知ることができるように事前に準備をしていたのである。
警察への捜査協力ののち、「東京はパニックになる」という俺の予言を信じた山本さんは、パニックを事前に検知できるシステムの開発を全社員に命じていた。俺がプロジェクトリーダーとして業務時間の半分をそれに充てるよう言われ、プロジェクトZという名前がつけられた。俺の給料は発生するわけだからタダではないのだが、極度の心配性である山本さんは心配事が金で解決するなら金に糸目をつけない。俺はちょうどその少し前に「風邪の流行をツイッターで検知する」みたいな論文に関する記事を読んでいたので、それを真似て次のような条件の監視ツールを完成させていた。
・位置情報を含むツイートで、なおかつ東京への通勤圏に含まれる
・ツイートに「ゾンビ」「喧嘩」など特定の単語を含む
・上記の条件にあてはまるツイートの量を地図上に可視化する
プログラムとしてはそれほど難しくない。機械学習や自然言語処理などの高度な技術を使っていないので、プロトタイプは二人日でできた。顧客が――この場合は山本さんだが――こだわったのは、わかりやすさだ。グーグル・マップの画面に落とし込まれたアラートはビーアウェア株式会社のオフィスに常に表示され、いざ有事となったら迅速に行動に落とし込めなければならない。幸い、俺以外のエンジニアも興味を持ち、ツイートに含まれる画像の暴力性をグーグルの画像診断APIで判定させたり、ヤバさの伝播を瞬時に計測して海浜幕張への到達予想時刻を算出したり、スマホ用アプリでプッシュ通知を作ったりと、色々な機能が追加された。こうした危機管理系のアプリケーションを作るのは、エンジニアにとって面白いものだ。実際に危機が起きたらどうすればいいのかまではわからないのが難点だったが、仮に受託案件として請け負っていたら一千万ぐらいは請求していただろう。
そんな俺達の作品は、ゾンビ列車が発生した七月三日の朝八時半、ビーアウェア株式会社の社員全員のスマホをけたたましく鳴らした。あの地震速報アプリと同じブワッブワッという音だ。俺はすぐさまチャットを開き、みんなにktkrと投げかけた。俺達の会社は十時出社で遅刻も当たり前の緩い社風だったから、その時間に電車に乗っている者は皆無だった。議論を重ねた末、東京の西側や埼玉在住のものは自宅待機、東京東部および千葉県在住の者は出社ということになった。俺たちが作った監視アプリの予測によると、このヤバさは海浜幕張まで「伝播しない」という予想だったからだ。正直に言って、俺たちはこのとき喜んでいたと思う。世の中の親どもがプログラミングを子供に教えたがる時代よりも前、けっして世の中から仰ぎ見られるような人種ではなかった。ヲタクだとか、IT土方だとか、さんざん馬鹿にされてきた人間達だ。いまでこそギークといえば格好良く響くが、社会不適合者というレッテルを肯定的な意味で引き受けた先人達の反骨心があってこそだ。俺や俺の同僚達はそうした過去を多かれ少なかれ背負っており、ヤバさを可視化できたことに恐れるよりも、まず誇らしいという感情を抱いたのだ。
しかし、そんな思いは出社してから一変した。あの日社員はみな、オイーッス、オハヨーッスという感じのテンションだった。「ITメディアとかの取材来るかもね」などという会話もされていたように思う。しかし、オフィスに備え付けられたディスプレイを見てその雰囲気は一変した。よく真冬に暖房の効いた部屋の窓を開け放ったときのように、あっという間に温度が下がっていったのをよく覚えている。
オフィスのディスプレイは、画面の小さいスマホ版と異なり、一つ一つのツイート詳細を表示することができた。その後、あの日のツイートの多くはツイッタージャパンによってほぼすべてが不適切ツイートとして非表示になるのだが、俺たちが作ったプログラムは、ツイートのすべてをコピーして保存するようになっていた。わざわざツイッターのサーバに取りに行くぐらいなら、自社のサーバに保存しておいた方が面倒がなくていいからだ。その結果、あのゾンビ列車でのツイートのほぼすべてが、ビーアウェア株式会社の手元に保存されていた。その中でもっともヤバイとシステムが診断したツイートは、肉という肉、皮という皮をほとんど噛みちぎられ、目玉が飛び出て鼻腔も丸出しになった人間の顔面写真だった。赤と白の鮮やかなコントラストからなる写真がオフィスの五十インチディスプレイに大写しにされているの見て、俺たちは言葉を失った。それは考えうる限りでもっとも残酷な画像だった。画像に添えられたテキストには「喧嘩でここまでする必要ある?」で、俺はそのツイートに「いいね」をした。
ゾンビ列車の惨劇はいまでもあまり具体的には語られていない。しかし、眼窩に指が深々と刺されて絶叫を上げる若い女の画像や、噛みちぎられた耳を抑えて苦悶の表情を浮かべるオッサン、真後ろで噛み付こうと口を挙げているヤツがいる自撮り写真など、凄惨を極める暴力が蔓延していた。日本国内でも有数の混雑率を誇る湘南新宿ラインの中で、身動き一つ取れないままパニックが発生し、すぐ隣の乗客に立ったまま顔面を食われるのだ。俺は日本のこうした労働状況が今に至る惨劇の原因の一つだと思う。
話を戻そう。その日は緊急で朝会が開かれた。俺たちはみな言葉少なだった。正直な所、どうしていいかわからなかったのだ。幾つかの画像やツイートを見てみたのだが、あの顔面剥ぎ画像よりも衝撃的なものはなかった。俺たちが朝会を開いていた十時十五分の段階で、ゾンビ列車についての有益な情報を俺たちよりも詳しくもたらしてくれるメディアは存在しなかったからだ。わかっていたのは、湘南新宿ラインで集団暴力事件が怒ったということ、犠牲者がいまのところ少なくとも三名だということ、それぐらいだ。
長いあいだ沈黙が続いた。みんなスマホやらノートパソコンやらで情報収集していたが、あいにく俺たちが作ったシステムより有益な情報をもたらしてくれるものはなかった。
「まず僕達がどうするか決めようよ」と、山本さんが切り出した。声が震えていて、二重のぱっちりとした子供っぽい目は涙で潤んでいた。しかし、代表取締役としてこれ以上ないというほど正しい言葉だった。「まず、僕の意見を言っていいかな」
俺は「どうぞ」と答えた。普段は山本さんを馬鹿にしているであろう同僚達も、なにがしさの深刻さを受け止めているようで、みな頷いていた。
「僕が言いたいのは三点。まず、僕はすべてをかけてみんなを守るということ。そして、僕はそのためなら命を捨ててもいいということ。最後に、僕たちは自分の安全を確保した上で世界を助けるために力を尽くすべきだということ」
俺たちはその言葉を完璧な響きで聞いた。ディスプレイに写っていた赤い点は、ヤバさの象徴から倒すべき敵へと姿を変えた。普段は変な色のスーツを来たスポーツ刈りの営業部最弱みたいな山本さんが、この日は反乱軍の将に見えた。俺がビーアウェアに入社してからはじめて会社が一体になった。俺たちは上場してもいない零細ソフトウェアハウスで、要するに取るに足りない存在だった。世のありとあらゆる革命の英雄の出発点がそうだったように。誰ともなく、拍手が始まった。わずか二十名のオフィスはこの上ない一体感に包まれた。
その日は退社時刻まで情報収集を続けながら、山本さんが示した方針が具体的な行動指針となった。ビーアウェアはこの非常事態において、すべての案件を停止し、監視システムの改善に注力する。海浜幕張以西に住居を持つものは駅近くの宿泊施設を会社の経費で利用することができ、家族を呼ぶことができる。監視システムの名前はvulture――ハゲワシ――とする。シンプルな目的を与えられた俺たちは、眼の色を変えてキーボードを叩き始めた。定時退社の時刻である十九時まで、余計な言葉を発する人間はいなかった。静かに、世界を書き換えるかのように、カタカタとキーボードの音が鳴り響いていた。
家に帰ると、俺はカズに連絡をした。もしかしたら、彼女の周りでも同じような事件が起こるかもしれなかったからだ。俺は知りうるすべてについてを彼女に教えた。答えはシンプルだった。
――あの、家いっていいですか 避難的な意味で
俺はそのメッセージに対して、ウサギのコニーが「OK!」という看板を掲げているスタンプを返した。俺たちは世界を助けなければいけないからだ。そのスタンプには三国志の劉備が「よろしくお願いいたす」とお辞儀をするスタンプが返ってきた。世界が終わる八日前、俺は女子高生と同居することになった。









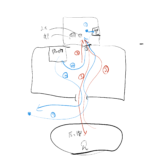
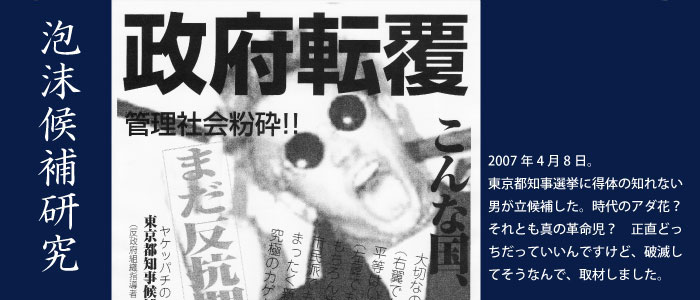



















"はつこいオブ・ザ・デッド(5)"へのコメント 0件